- 東京地裁平成16年2月27日判決 (交民集37巻1号238頁、自保ジャーナル1560号14頁は抜粋) この判決の特徴は、①非常に難解な事案で判決文も通常の3~4倍ほどの分量であること、②提訴後に被害者に有利な鑑定と加害者に有利な鑑定の2つが出されたこと、③提訴後の被害者に有利な鑑定のみがRSDと診断し、それ以前の通院先の病院ではRSDと診断されていないこと、⑤判決の採用した医学知見に疑問が多いこと、⑤判決が認定する後遺障害等級が低いこと(実質的に詐病と認定)です。
-
- 事故態様の争いについて
- 被害者は事故時31歳男性会社員です。大学を中退した後はアルバイトなどをしていて、事故の1、2年ほど前から証券会社で正社員として就労を始めたようです。被害者が正規就労の経験が浅いことは、判決が被害者の主張を否定した背景となっているようです。
- 事故は被害者が自転車で走行中に、急に開いたタクシーの左後部ドアの側面に衝突したというものです。 訴訟では、被害者側は強い衝撃があったと主張し、加害者側は軽微な事故であったと主張するのが定番です。私の経験や判例の事案では、被害者が重傷の事案や死亡の事案でも車体が派手に壊れている事件は少数で、車体のキズが小さく、修理費もそれほど高くないことの方が多いように思います。 従って、車両の損傷の度合いと被害者の受傷部位の受けた衝撃の強さは相関するわけではないと思いますが、双方が事故態様で争うと車両の損傷が小さい事故では裁判官の心象は被害者に不利に働くと思います。特にこの事件のように被害者が自転車運転の事故では、双方の物損はごく小さいことが多いのでなおさらです。 従って、被害者側が自身の記憶に従って詳細に事故態様を主張すると、それが事実であっても被害者側に不利になることの方が多くなると思います。
- 本件では判決は被害者の主張する事故態様を否定し、それが被害者の主張する後遺障害の否定にもつながっています。自転車から転倒すれば路面に全身を打ちつけるので、被害者の主張する後遺障害が生じる可能性はそれだけで肯定できることから、私は被害者側としても事故態様にはそれ以上こだわらない方がよいと思います。 被害者側は、開いたタクシーの左後部ドア側面に衝突してドアで側頭部を打って自転車から落ちて全身を打ったという程度の主張でよかったのではないかと思います。それ以上の主張をした場合、それが事実であってもそれを確実に裏付ける証拠がないため、裁判官はその認定をせず、それが被害者に不利な流れを導くことは否定できないと思います。
- 被害者の主張によれば、被害者は開いたタクシーの左後部ドアの側面に衝突して、右側に倒れてドアに右側頭部を打ち付け、ドアのエッヂ部で全体重を支えるような形で首を打ちつけたと主張します。開いたドアが、柔道の「足払い」のような形で自転車を運転していた被害者の足にあたって、被害者の上半身は右側に倒れて、頭部がドアの枠に乗り上げて宙吊りのようになったというのが被害者の主張で、被害者側は特におかしな事故態様を主張しているわけではありません。 これに対して判決では、開いた左後部ドアの側面に自転車が当れば、自転車はドアに押されて左前方に押し出されるはずであるとします。自転車とその運転者の重心部分にドアが当ればこの判決の述べるように、開くドアの勢いで左前方に押し出されるとは思いますが、自転車とその運転者の重心より下にドアが当ると被害者の主張のように、被害者は右側に倒れるのではないかと思います。 従って、判決の認定には説得力はありませんが、かといって被害者の主張を確実に裏付ける証拠もありません。このように目撃者がおらず水掛け論に持ち込まれると、被害者側に証明責任があるという感覚で被害者側に不利な認定がなされることが往々にしてあります。従って、私は被害者側としては必要以上に詳細に事故状況を主張することは得策ではないと思います。 なお判決は自転車のハンドルに曲損などがないことを不自然であるというニュアンスで述べていますが、判決が派手な事故でなければ被害者の主張する障害は生じないという方向に向かったことが気にかかります。
-
- 症状の経過
- 訴訟提起後に出された被害者に有利な鑑定をX鑑定、加害者に有利な鑑定をY鑑定とします。鑑定は裁判所の選任した鑑定人によることが通常ですが、当事者が依頼した医師が作成した書面(医学意見書)が「鑑定書」という表題で提出されたときにも「鑑定」という言葉が用いられます。
おそらくこの事件では、裁判所の選任した鑑定人による鑑定(おそらくY鑑定)に、被害者側が異議を申し立てて別の鑑定人による鑑定(X鑑定)がなされたのではないかと思いますが、判決からは詳細は不明です。
X鑑定は頚部と膝部にRSDが発症したその後遺症が鑑定時に残存しているとし、その他に脊髄に後遺障害も残存しているとしています。
これに対してY鑑定は被害者の詐病を示唆する意見を述べ、被害者の症状を否定的に述べ、事故直後からの膝の症状も主として精神的なものであるとします。以下では、両者の鑑定が症状の経過をどのように見たのかを付け加えながら述べます。
- 平成7年9月14日・・・事故発生。被害者は救急車でA病院に搬送され、「頚椎捻挫、右膝外側側副靭帯損傷、両膝・右下腿挫傷」との診断を受ける。入院はせず、通院治療を受ける。 12日後のカルテには被害者が「両手全体がしびれる、両足全体がしびれる」と訴えたのに対して、「神経学的に?」との所見が示される。 被害者は事故直後こそは救急車で搬送されていますが、その後は3日に1回くらいの頻度で通院します。両手、両足のしびれは、脊髄の損傷の可能性をうかがわせますが、この時点ではMRIなどの精密検査は受けていないようです。
- 1か月後・・・被害者は通勤の関係で転院したB病院で「頚椎捻挫、両膝捻挫、右下腿打撲」との診断を受ける。頚部牽引治療を受けるも、頚部腫脹を生じ中止となる。 頚部の腫脹(はれ)は、のちにX鑑定(被害者に有利な鑑定)でRSDの根拠とされています。Y鑑定はこの腫脹は無視します。
- 2か月半後・・・C大学病院(順天堂大学付属病院)で「外傷性頚部症候群、両膝打撲・挫傷」との診断を受ける。頚部痛、両膝痛、左右膝の伸展時の脱力、膝外側の圧痛、左手のしびれを訴える。 X鑑定は、左右膝の脱力・動揺性を脊髄障害の影響とRSDの症状が並存したとの見方をしています。Y鑑定は、膝の症状は被害者の精神的・心因的なものであると述べます。
- 4か月後・・・C大学病院の頚椎MRIで、C2~5椎体に軽度の変形性変化、C2/3からC5/6の椎間板の信号強度低下や退行変性、C3~5の脊柱管の狭窄などが認められる。 信号強度の低下は脊髄損傷の裏付とされるので、X鑑定はこれを脊髄損傷の根拠としていると思われます。Y鑑定はMRIでは明らに外傷性のものはないというスタンスです。
- 9か月後・・・D接骨院で、「頚部捻挫、腰部捻挫、右膝部捻挫、左膝部捻挫」と診断され、「頚椎の曲りにより頚部・背部の硬結強度のため、頚部回旋痛及び上腕の運動痛著しく、両膝の疼痛による歩行姿勢不良のため、平成8年9月頃(事故1年後)より、腰部体動痛著明」との所見が示される。 被害者は頚部の運動痛が強く、頚部の可動性が著しく損なわれています。X鑑定はこれをRSDの根拠としています。Y鑑定は、頚部の症状について詐病を示唆する意見を述べます。
- 13か月後・・・C大学病院の膝関節部のMRIでは右内側半月板の信号強度がやや高い、両内側半月版の変形と信号強度の増加などから軽度の損傷との所見が示される。その後も頚部痛や両膝痛が診断される。 X鑑定は、両膝の軟部組織の損傷はMRIでは軽度であるけれど、脊髄損傷による下肢への影響とともにRSDの影響が生じていると見ているようです。Y鑑定は両膝の症状は精神的な問題であるとします。
- 1年3か月後・・・平成8年12月18日にC大学病院で最初の後遺障害診断がなされ、①頚椎Ⅹ-Pで右側湾+、②頚部筋の緊張、③左側の胸鎖乳突筋の腫れ、④右僧帽筋の腫れ、⑤頚椎可動域制限、⑥同一面での前後屈が不可とされる。頚椎の可動域制限が確認される。 X鑑定は、頚部の緊張や左側の胸鎖乳突筋の腫れ、右僧帽筋の腫れをRSDによる腫れであるとして、その後に生じた筋萎縮をRSDの進行に伴う変化であると見ています。Y鑑定は、被害者の症状は詐病ないし精神的なものであることを示唆する意見を述べます。
- 1年5か月後・・・被害者が新たにE大学病院(慈恵医大)で診察を受け、「頚の可動性は正常、上下腱反射正常、左第6頚神経域に知覚鈍麻、筋力正常、膝関節MRI検査異常ない」と診断される。 一方でMRIの所見として、「左胸鎖乳突筋部の腫脹、左C6のシビレ」が記され、「右膝・左膝MRI変性あるも、断裂なし」とされる。 この時点で首の可動性は正常ということは、一時的には頚部の可動域制限がほぼ治まっていたことを意味します。腱反射は基本的に感度の低い検査(10%程度)ですので、陽性のとき以外はあまり意味はありません。膝関節MRIで異常なしとされたことから、少なくとも膝関節の器質的損傷が大きくないと言えると思います。 この時点で頚部可動域が正常と判断されたことは、判決が被害者を実質的に詐病とした判断の有力な根拠となっていると考えられます。私もこの時点で頚部の可動性が正常とされたことにやや疑問を感じ、被害者の頚部症状を詐病とする場合の最大の根拠となりうると考えますが、全体の流れのなかでこの部分のみにこだわることは良くないと思います。
- 1年半後・・・被害者は、自賠責保険の後遺障害認定手続で頚部につき14級、両膝につき非該当の判断を受け、一度目の異議申立をする。
- 1年半後・・・被害者は、両膝の関節痛により、歩行、直立姿勢等が困難であることを訴え、F大学病院(東大病院)で「両膝内障、頚椎捻挫、腰椎捻挫」の診断を受けます。 被害者は、「外傷性膝関節炎、それにともなう拘縮」という診断も受けているので、この時期に膝周囲の腫れがおさまり、筋の拘縮(萎縮)に向かっていたようです。関節炎について被害者は灼熱痛(焼けるような痛み)であることを主張したようですが、判決では「焼けるような痛み」などの表現がカルテにはないとして否定します。 X鑑定は、被害者に灼熱痛が生じて、関節拘縮や腫れに引き続く筋萎縮が生じたとしてRSDの根拠とします。X鑑定は、痛み、腫れ、灼熱痛、拘縮という変化や機能障害を頚部や膝部に確認できることから、RSDが生じていたとします。Y鑑定は、頚部につき詐病を示唆する意見を述べ、膝部につき精神的問題に起因する症状であるとし、腫れや筋萎縮が確認されたことには言及していないようです。
- 1年7か月後・・・被害者がG診療所に通院を始める。この通院はごく短期間で2回の検査のみ。
- 1年8か月後・・・後遺障害認定についての被害者の異議申立に対して、既認定のとおりとの回答があり、被害者が2度目の異議申立をする。翌月に再度既認定のとおりとの回答があり、被害者は3度目の異議申立をしたところ、頚部と両膝の双方が14級であると変更される。被害者は4度目の異議申立をするも変更されず。
- 1年10か月後・・・被害者がH整体院に通院を始める。この後2年8か月ほど通院し、中国気功整体療法を受ける。
- 2年後・・・平成9年9月3日、被害者は2回目の後遺障害診断をF大学病院で受け、田中医師より「外傷性膝関節症」の診断を受け、「両膝蓋骨下縁及び膝蓋下脂肪体の部分に圧痛がある。MRIにて靭帯、半月板などに損傷はないが、脂肪体の部分に炎症を疑わせる症状がある。膝の拘縮(とくに左)が軽度にある」とされる。 X鑑定は、膝部の炎症や拘縮をRSDによる病変であるとしますが、Y鑑定は主として精神的なものであるとします。被害者は平成10年に訴訟を起こしているので、これ以降の診断は訴訟提起後のことであると思います。
- 3年半後・・・F大学病院の同じ田中医師から再度後遺障害診断を受ける。前回は膝部のみの診断であったのが、頚部をも含めた診断となり、「僧帽筋腫脹、胸鎖乳突筋腫脹」、「頚椎にすべり、椎間板変性をみとめる以外の異常はない」とし、頚椎部に痛みのため可動域制限があるとする。
- 3年8か月後・・・F大学病院の星地医師が後遺障害診断をする。「両外傷性膝関節症、外傷性頚部症候群」と診断し、頚椎椎間板(C3/4、C4/5)の突出が、頚部、両下肢の疼痛、可動域制限の原因であるとする。頚部の筋萎縮、左大腿部の筋萎縮を確認する。頚部と膝部の可動域制限を認める。 X鑑定は頚部の腫脹がその後の頚部の筋硬縮に変化したことをRSDに整合するものと評価します。Y鑑定は頚部の症状は詐病であることを示唆する意見を述べます。
- 4年2か月後・・・F大学病院の田中医師が再度後遺障害認定をして、「両外傷性膝関節症、外傷性頚部症候群、腰痛」と診断し、「頚椎C2~6の変形による運動制限が認められる。」、「頸・肩筋肉の萎縮のため可動域制限が存在する。」などの所見を述べる。
- 訴訟提起後に出された被害者に有利な鑑定をX鑑定、加害者に有利な鑑定をY鑑定とします。鑑定は裁判所の選任した鑑定人によることが通常ですが、当事者が依頼した医師が作成した書面(医学意見書)が「鑑定書」という表題で提出されたときにも「鑑定」という言葉が用いられます。
おそらくこの事件では、裁判所の選任した鑑定人による鑑定(おそらくY鑑定)に、被害者側が異議を申し立てて別の鑑定人による鑑定(X鑑定)がなされたのではないかと思いますが、判決からは詳細は不明です。
X鑑定は頚部と膝部にRSDが発症したその後遺症が鑑定時に残存しているとし、その他に脊髄に後遺障害も残存しているとしています。
これに対してY鑑定は被害者の詐病を示唆する意見を述べ、被害者の症状を否定的に述べ、事故直後からの膝の症状も主として精神的なものであるとします。以下では、両者の鑑定が症状の経過をどのように見たのかを付け加えながら述べます。
-
- X鑑定(RSDと診断)について
- X鑑定は、膝部と頚部にRSDが生じたとします。たしかにX鑑定の前提とする事実を受け入れた場合には、膝部、頚部ともに現在のCRPSの判定指標を優に満たします。 頸部については、受傷後に痛みが治まらず、頚部から肩部にかけて著明な腫れが生じ、のちには筋萎縮に至り(この過程で灼熱痛が生じる)、X鑑定は患部が筋硬縮(拘縮ではなく硬縮というレベル)に至っているとします。また診察時に軽度の痛覚過敏があり、上肢に知覚障害や発汗の促進も確認されるとします。 膝部は受傷直後から痛みがあり、多くの病院で確認された炎症のような症状があり、患部に腫れが生じて、その後に筋萎縮が生じて、関節拘縮に至っています。MRIによればその原因は靭帯の損傷ではないということですので、RSD(CRPS)の鑑別診断の要件も満たすことになります。診察時に下肢に知覚障害が認められたようです。
- 以上のとおり、X鑑定が被害者の症状の経過をRSDで説明したことについて、現在のCRPSの判定指標からは矛盾はなく整合的であるように見えます。 しかし、このX鑑定までに3か所の大学病院を含む多くの病院で診察してきたにも関わらず、X鑑定でRSD(CRPS)が述べられるまで誰一人としてRSDの診断をしなかったという経緯があります。 CRPSでは鑑別診断で他の疾患の可能性が除外される必要があることが特に重視されます。従って、X鑑定以前の診断で被害者の症状が説明できれば、CRPS(RSD)との診断は誤りとなります。 そこで見てみると、頚部や膝部に受傷半年後に著明な腫れや炎症が認められ、その後筋や軟部組織が萎縮的変化に向った経緯や、知覚過敏や発汗異常などは、それまでの診断では説明できないことから、RSDとの診断でなければ説明できない状況が存在するといえます。
- これまで検討してきた判例には、3年以上経過してから初めてRSDと診断された事例や、4年、5年と経過してから症状固定に至った事例もあり、一方では4か月ほどで末期症状に至った事例もあります。RSDの病状の進行度合いは個人差がかなり大きいようです。このように臨床では患者の症状の進行やその出方は様々であることから、RSDについての病期説は学会では否定的に受け止める考えが趨勢のようです。 また、RSDの症状が出ていてもその診断がかなり遅くなることは、判例の事例の上でも多く確認できます。RSDの症状の経過が緩やかな場合には、その一部のみを見た医師には全体の流れが見えないため、患者が転院を繰り返すとRSDに気付きにくくなるようです。 従って、X鑑定以前の3か所の大学病院を含む各病院がRSDと診断しなかったことを格別に重視することはできないと思います。 何よりも、RSDとの鑑定が出た時点で症状の全体の流れを眺めるとRSD(CRPS)であるとの判断が当たり前のように受け入れられることは否定できません。X鑑定にはRSDという種明かしをしたに過ぎないとの印象があります。以上から、私はこのX鑑定が正しいと思います。
- このX鑑定を否定するためには、X鑑定が前提とした所見を否定するほかないのですが、Y鑑定はまさにX鑑定が前提とする所見の多くを否定して、被害者の精神的問題を強調し、詐病を強く示唆します。 しかし、Y鑑定が述べ、判決にも採用されている医学知見には疑問に感じるところが少なくありません。以下この点について述べます。
-
- 詐病を見極める視点
- Y鑑定は、被害者の詐病を示唆し、被害者の精神的問題を重視する見解を述べますが、この点については根本的な部分で疑問があります。それは本件では、詐病では作り出せない複数の症状を多くの医師が確認していることです。 実質的に詐病との判断をした裁判例の多くには、詐病により否定できる可能性のある所見にばかり目が行く傾向があり、詐病により作り出すことが不可能ないし著しく困難な症状は無視ないし軽視される傾向があります。その結果、どうしても無視できない症状を過小評価して、「この部分だけを後遺障害として認める。」という内容の判決になります。本件の判決にもこの傾向は当てはまります。
- その中には「損害の証明責任は被害者側にある」という視点から、「詐病との疑いが払拭できなければその部分の障害は否定する。」という誤った形で証明責任を運用しているニュアンスを感じるものもあります。 証明責任とは自由心象主義に基づく考察で真偽不明に陥ったときに持ち出す伝家の宝刀で、とにかく何らかの結論を出さなければならない立場にある裁判官に与えられた助け舟です。例えるならば問題の解けない受験生が持ち出すサイコロのようなものです。私も解けない問題に当たったときに五角形の鉛筆を振ったことがあります。証明責任はそれと同じです。 事実認定は、本来は訴訟に出された主張と証拠から判断されるべきであり、これらの生の事実とは無関係に定められた証明責任に頼ることは、最後の最後まで避けるべきです。証明責任とは心象形成に至ることができなかった裁判官が恥を忍んで頼るサイコロのようなものです。過度に証明責任に頼った事実認定は決してほめられることではありません。
- 従って、真偽不明となる以前から証明責任というサイコロを用いてすごろくのように前に進んで事実認定を行う感覚は理解しがたいのですが、そのようなニュアンスの判決を見かけることは少なくありません。 本件に即して述べると、詐病かどうかはまずもって自由心象主義のレベルで判断されるべきことで、真偽不明となる以前において「損害の証明は被害者の責任でなすべきである」という証明責任を持ち込んで被害者に過大な立証を求めること、この場合には「詐病ではないこと」という「ないこと」の証明を求めることは、誤りであると思います。
-
- 事前確率
- 詐病との主張が出されたときにまず検討すべきは、詐病である事前確率です。それまで事故に遭ったことがなく事故前には普通に就労していた人が事故後に重度の症状を偽装して、その偽装に心血を傾ける可能性は極めて低く、概ね1万分の1ほどと私は考えています。
- 例えば、重傷者として通院する患者のうち、詐病の患者はどれくらいの割合でいると考えるべきでしょうか。100人に1人と考えるのはあまりにも多すぎるといえます。大学病院や大規模な病院には1日に1000人から3000人ほどが入通院しますが、そのような治療機関は愛知県内だけでも10以上あります。患者の10分の1が重症患者であるとして、重症患者の100人に1人が詐病であるとすると、愛知県内だけでも1日100人ほど、月に1000人以上の詐病患者が通院することになります。従って、詐病の確率を100分の1というレベルで考えることは統計的には到底支持できません。同様にこの確率を1000分の1にすることも困難であると言えるでしょう。私は重症患者については1万分の1以下の割合で詐病の可能性があると考えています。
- これに対して、RSDのような難解な疾患が問題となる訴訟では、加害者が被害者の症状そのものを否定する対応をする割合は9割ほどであると思います。 公表された裁判例では主治医がRSD(CRPS)と診断した事例においても、加害者側は強硬にその診断が誤りであり、詐病であるとの主張をすることが定番となっています。その主張の多くは医学意見書(鑑定書)を伴うようです。医学意見書の中には華々しい経歴の医師が少なくないことは経験的に多くの法曹が知っていることであると思います。 しかし、上記の事前確率を考慮すると、加害者側の医学意見書が正しい事前確率は1万分の1ほどになります。交通事故のように賠償が絡む場合には詐病の確率が高くなると考えたとしても、重症を訴える被害者が詐病の患者である確率は1000分の1を超えないでしょう。
- 現実にもこれまで検討してきたRSDに関する裁判例で、加害者側が「RSDで必ず生じる症状は1つもない。」という初歩的な基本知識を述べる医学意見書を提出してきたものは1件たりともありません。むしろ、「RSDには必須の症状が多くある。」との誤った主張することが常態化しています。 このような外的状況が分かっていれば、訴訟で被害者の詐病を主張する医学意見書が正しい事前確率は概ね1000分の1以下であることを考慮して検討を始めるべきであるといえます。
-
- 偽装の困難な症状
- 本件では、偽装の困難な症状として、被害者の頚部や膝部の腫脹(腫れ)や、その後に生じた筋萎縮があります。この症状を被害者が意図して作り出すことは不可能と判断して差し支えないと思います。 従って、この時点で被害者が詐病である可能性はほぼ完全に排除できます。仮に万が一、被害者がRSDを偽装しようとしてこれらの症状を偽装することができたとしても(その方法は全く思いつきませんが)、なぜ訴訟を提起したあとの鑑定になるまでの長期間にわたりRSDと判断されなかったのかという問題もあります。 但し、いったんRSDにり患してもその後の治療で症状が改善する患者も一部には存在するので、症状が軽快したことを被害者が隠すという形での詐病の可能性はあります。
- RSD事案において、詐病で作り出せない症状として、このほかに骨萎縮があります。骨萎縮はCRPSの判定要素には含まれていませんが、骨萎縮が生じることは他の疾患の可能性を排除する重要な要素となります。ピンポイントに患部に骨萎縮を生じさせることは不可能ですので、軽度であっても骨萎縮が存在することは、詐病の可能性を排除する重要な根拠となります。 しかし、裁判例のなかには骨萎縮が「重度ではない」ことを理由として、被害者を実質的に詐病と認定する判決も出ています。これは加害者側が自賠責保険の3要件を引用して「重度の骨萎縮」が絶対に必要であると主張して、その旨の医学意見書を提出した場合などに、裁判官がその医学意見を妄信してしまうことにより生じます。
-
- 特別基準論
- 加害者側の医学意見書でしばしば用いられる「重度の骨萎縮」や「重度の筋萎縮」の主張は、「特別基準論」というトリックを用います。即ち、RSDの一般的基準としては重度の骨萎縮(または重度の筋萎縮)を必要としないという前提は多くの医学書の記載から否定できないことから、これを直接否定することは避けています。 その代案として、「関節拘縮によりこれだけ関節を動かせないのであれば、骨萎縮(または筋萎縮)は重度に生じているはずである。」という論理を用います。
- これはRSD(CRPS)の一般的な判定指標に骨萎縮(筋萎縮)が含まれないことは認めつつも、特別基準として重度の関節拘縮のあるRSDにおいては重度の骨萎縮(筋萎縮)が必要であるという論理です。 一般的な基準のレベルで受け入れられなかった主張を、特別基準として導入することを持ちかけるこの手法は、「重度の骨萎縮」や「重度の筋萎縮」が必要であるとする医学意見書の多くで用いられているように見受けられます。 被害者が重度の関節拘縮を訴えている場合などに、「これだけ関節が動かせないにも関わらず、筋萎縮がわずかであること(筋萎縮が確認できないこと)は医学的には説明困難なことである。」という論理により特別基準論を持ちかけられると、「たしかにそうだなあ。」という気にもなりそうです。
- もとより医学ではこの特別基準など存在しません。特別基準論を認めてしまえば、一般的な基準を導入した意味がなくなります。しかも、一般基準でRSDとされるにも関わらず、特別基準でRSDが否定されるという矛盾も生じます。従って、特別基準論は論理構造そのものからして問題があります。 特定の疾患とそれを検出するための各種の検査との間に絶対的な相関性が認められることはまずありません。このため証拠に基づく医学においては、それらの検査の感度や特異度を尤度比(ゆうどひ)などの概念を前提として検討します。有用な検査であってもその検査だけで感度が80%を超えるものはほとんどありません。ましてや100%の相関性など極めてわずかな例外のみでしょう。 関節の拘縮と筋萎縮や骨萎縮の相関性という症状相互の相関性などは、疾患への標準的な検査方法との相関性に比べるとなおさら低いと考えるのが、普通の医師の感覚ではないかと思います。 従って、特別基準論の述べる「これだけ関節が動かせないにも関わらず骨萎縮が軽度であることはありえないことである(と述べて関節拘縮が詐病であることを示唆する)」という論理は、その実体的なものの考え方からして医学的とは言いがたいものです。 このように特別基準論が論理トリックであることはすぐに分かりそうなものですが、医学的な知識が乏しい状況ではこのことに気付くことができないようです。
-
- CRPS(RSD)の診断基準
- 判決では、RSDの4主徴として①疼痛、②腫脹、③関節拘縮、④皮膚変化を列挙し、⑤末梢循環の不全、⑥発汗異常、⑦皮膚温の変動、⑧骨萎縮、⑨皮膚の栄養障害などが見られると列挙し、①の疼痛はアロディニア(少しの刺激でも強い痛みが生じる状態)であるとます。 X鑑定によれば、被害者は、①、②、③、⑥、⑦を満たし、④、⑤、⑨は不明(X鑑定は炎症のときの所見で満たすと判断したと思われます)で、⑧は満たさないようです。①は疼痛をアロディニアに限定した場合には、カルテにはそれを示す所見がないようです。いずれにしても現在の判定指標に従えば、優にCRPS(RSD)との判断ができると思われます。
- この判決は、上記のうち疼痛がアロディニアではないこと、骨萎縮を欠くことだけを取り出してRSDではないとしているので、判決は列挙された症状の全てがもれなく生じる必要があると勘違いしています。 RSD(CRPS)においては必須の症状が存在しないことは初歩的な重要知識です。国際疼痛学会やアメリカや日本におけるCRPS判定指標は、4主徴のうち2つが確認できれば良いとする指標を用いています。
- 病期について 判決は、被害者には病期説の区分に従った症状の変遷が見られないことをRSDではない根拠として述べます。しかし、すでに他のところで述べたとおり、臨床ではほとんどの患者に病期説に従った症状の変化を認めることができなかったために、現在では病期説は否定的に受け止めるのが趨勢のようです。 そもそも病期説はRSDの判定指標(判断基準)ですらないので、病期説に従った変遷を経ないことがRSDではないとする判断の根拠になるという論理は病期説からも誤りとされます。
-
- 脊柱の運動障害
- X鑑定は、背部軟部組織の器質的変化を肯定し、可動域制限の測定値が2分の1以下であるとして、脊柱に運動障害を残すとして、8級2号に該当するとします。 これに対して、判決は、「背部軟部組織の器質的変化」という言葉を骨折などのように物理的に確認できる変化であるとのニュアンスで受け止め、そのような変化はないとします。
- 被害者がRSDにり患したことと、頚関節の可動域が2分の1以下と極端に制限されていることが詐病でないとの前提に立つ場合には、その可動域制限の根拠は、背部において軟部組織が繊維化して組織の癒着が生じたために伸縮性を失ったことに求めることとなります。 被害者の頚部に著明な腫れが生じたあとに筋萎縮(X鑑定は「筋硬縮」とする)が確認されたという経緯からは、その過程において軟部組織に上記の変化が生じたことが推測できます。 X鑑定はこのような軟部組織の繊維化や組織の癒着という「器質的変化」があるはずだと述べたのに対して、判決はX鑑定の背後にある医学的な知見を理解できずに、X線やMRIで確認できないものが「器質的変化」であるはずがないというニュアンスでこれを排除したようです。訴訟において医学的知見を説明することの重要性を感じます。
- なお、Y鑑定は、被害者の頚椎がX線検査による動態撮影では可動域を越えて動いていると述べて、詐病を示唆します。X線検査による動態撮影で何ゆえそのようなことが判明しうるのか、私には意味不明ですが、判決ではY鑑定のこの部分をかなり重視しています。 判決を書いた裁判官はこのY鑑定の示唆することの具体的な意味を理解できていたとは思えません。理解できていれば、この部分を掘り下げて判決に記載したはずですが、それがなされていません。従って、判決でこの部分が重視されたのは、疑う者は疑いにあわせた証拠を重視するという確証バイアスによるものではないかと思われます。
-
- 脊髄障害について
- X鑑定は、被害者には脊髄障害(X鑑定は脊髄損傷という言葉ではなく、脊髄障害という言葉を用います)の後遺障害があり、この後遺障害は9級10号「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当するとします。 X鑑定は、被害者にはC3/4(4/5)のヘルニアを疑わせる所見が、受傷直後に見られ、半年以降退縮をみることにより、受傷時に発生した可能性も否定できない。当初脊髄障害を生じたが、徐々に改善し、現在においても、なお軽微ながら、両上肢、体幹、下肢に知覚障害を残している。実態は広範(上下肢、体幹に及ぶ)であるが、知覚異常が中心で機能障害は軽く、9級10号に該当するとの趣旨を述べます。
- これに対しては、X鑑定の述べるように頚椎椎間板ヘルニアが時間の経過とともに徐々に退縮して小さくなれば症状は良くなるはずであり、広範な後遺障害が残存するというのは、理屈として理解しにくい部分があります。 X鑑定の述べる脊髄障害を中心性脊髄損傷であるとすると、X鑑定の論理のスジが見えてきますが、判決を読む限りではX鑑定はとくに「中心性脊髄損傷」という言葉は用いていないようです。 X鑑定は、頚部の脊髄障害を9級10号とするほかに、頚部神経根不全障害はのちに頚部CRPSとなり8級2号(脊柱に運動障害を残すもの)に該当するとしています。つまり頚部の筋硬縮が生じて頚部の可動域制限が大きい状況は、頚部での神経損傷に起因したCRPSによるものであるとしています。 このことからは、X鑑定の述べる脊髄障害は、頚椎椎間板ヘルニアではなく、神経根障害など他の疾患ではないかとも思われますが、判決からははっきりしません。頚部の挫傷から頚部(から上肢にかけての部分)にRSDを発症する例は裁判例でもしばしば見られますが、頚部の挫傷の詳しい病名は大抵の場合ははっきりしないという印象を受けます。
- なお、Y鑑定は、X鑑定の指摘したC3/4(4/5)のヘルニアについて、特にC4/5の椎間で脊髄が圧迫され変形していると述べますが、判決によるとY鑑定は一貫して「椎間板ヘルニア」という言葉は用いずに、「変形性変化」という言葉を用いているようです。その上で、この「変形性変化」は事故前からの年齢性変化であるとします。 Y鑑定が椎間板ヘルニアという言葉を敢えて避けていることはちょっと奇妙な感じがします。また、椎間板ヘルニアを、頚椎の骨棘形成などと同様の年齢性変化として扱うことは、読み手に誤解を与えるのではないかという印象を受けます。さらに、受傷後にヘルニアが退縮していったとするX鑑定によると、これが事故前からの症状であるという可能性は低いように思います。しかし、判決ではこのような疑問を抱かなかったようです。
- Y鑑定は、ピンクリップテストによれば、顔面、頭部も左半分、頚部から上肢、体幹、下肢に至るまで7/10から9/10程度の痛覚鈍麻が存在するが、脊髄損傷ではありえない所見である。よって、脊髄損傷はない、と結論付けます。 X鑑定が知覚鈍麻と脊髄障害を並存させ、後者により前者が生じたとするのに対して、Y鑑定はそもそもその並存がありえないとするので、両者の立つ医学的基盤にかなりの隔たりがあります。Y鑑定がピンクリップテストにより、脊髄損傷を否定できるとする根拠は私には意味不明ですが、判決はこの部分を重視しています。
-
- 両膝の後遺障害について
- 被害者は、事故直後から両膝の痛みや圧痛を訴え、A病院では「右膝下腿副側靭帯損傷」との診断を受け、その後治療中に両膝に腫脹や炎症、両膝伸展時の脱力などが認められ、さらに大腿周の測定で筋萎縮が認められています。 膝部に拘縮が残存している(右よりも左の方が大きい)ようですが、これによる可動域制限は小さいようであり、判決や両鑑定では特に述べられていません。 被害者は、鑑定が行われた時期には両膝に不安定性を訴え、常に支柱つきのサポーターを片側に2個ずつ装着していたようです。従って、被害者の膝部の後遺障害については、「動揺関節」という後遺障害に該当するかが問題となります。 被害者の主張するとおりの障害が残存するとした場合には、硬性装具を必要としないレベルの動揺関節ですので、12級7号の「1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当することとなります。 他の部分の後遺障害と併せて検討した場合に、この動揺関節により就労に支障があるとされれば、9級10号に認定される余地があります。
- X鑑定は、頚部脊髄障害により上下肢の知覚障害が生じているとの立場で、膝部にはとくに神経の損傷はないと考えているようです。また、事故後の早期に認められた膝関節の損傷が膝部でのCRPSを誘引したとしますが、膝部には後遺障害は残存しないとします。 従って、X鑑定によれば、被害者の訴える両膝の不安定性や小さな拘縮は、独自に後遺障害として認定されるレベルには至っていないこととなります。私はこの点には疑問です。
- Y鑑定は、受傷時の両膝への打撲や、転倒時に膝関節をひねって膝靭帯を損傷した可能性があるとします。両膝の機能障害について、サポーターをつけての歩行が10分から15分くらいが限度であるとの被害者の訴えを引用し、両膝に機能障害があるとしますが、実際の不安定性は認めないものの主観的に不安定であるとし、正確には精神神経科医の判断を必要とするとします。 Y鑑定は、被害者の診断名について「心因反応の強いことから外傷性神経症と診断される」としているところ、この診断は膝部についても対象としているようです。 受傷直後から一貫して訴えていた症状が心因性のものであるという理屈はかなり奇異な感じもします。多くの医師が確認した膝の腫れまでも心因性とするのは、ちょっと無理があると思います。 しかし、判決はこのY鑑定の意見を受け入れ、さらに判決独自の補強をかなりの分量で述べます。
-
- 被害者供述の信用性
- 判決は、「原告本人供述の信用性」という項目で被害者(原告)の主張がいかに信じられないものであるのかを、とうとうと述べます。 まず、判決は、被害者は膝がガクガクすると訴えながらも、事故後いったん就労に戻っていたではないかと指摘します。また被害者が所沢市の自宅から千代田区の勤務先まで電車で通勤していたことや、各病院にも電車で通院していたことも指摘します。 しかし、硬性装具ではなく軟性装具を装着して、12級レベルの後遺障害を主張している被害者の事案で、「膝がガクガクするならば就労などできないはずだ。」、「長時間の通勤はできないはずだ。」との趣旨を述べることは的が外れていると思います。 この判決は鑑定の時に15分以上歩けないと主張していた被害者が長距離の通勤や通院をしていたことは矛盾するのではないかとします。しかし、12級レベルの動揺関節は就労不能を意味するものではなく、電車などを利用することも当然にありうることでしょう。 しかし、この判決のように障害のある人が活動的であることを、ことさら不審の目でみることを積み重ねて詐病との認定に至ることは、ある種のパターンであると言えます。
- 判決は、被害者がスポーツジムで水泳療法を受けていたことにも言及し、被害者がストレッチやバタ足やクロールの動きをしていたことが、本人の供述や大学病院のカルテからも確認できるとします。 これも被害者の主張する後遺障害とは矛盾しないのですが、判決はカルテからかなり多くの記載を引用して述べます。水泳療法を否定的に見る考えには驚きますが、判決が引用する内容について、「その時点での」被害者の症状と矛盾するかどうかを検討していないことが気に掛かります。
- 判決は、被害者が大学医学部の図書館に出向いて独自に医学文献を調べていたことや、被害者が大部にわたる陳述書を作成したことについて、懐疑的な評価を述べます。 しかし、被害者の症状がどの病院でも良くならなかったという経過からは、被告が独自に医学的なことを調べるのはむしろ当然ではないかとも思います。本件では裁判になって初めてCRPSという判断が下されたという事実からも、被害者が独自に調べた医学知識に従って症状を偽装してきたというのは無理があると思います。被害者が大学病院で医学文献を調べる以前からCRPSの症状が出ています。
- 判決は被害者が2、3回シンガポールに1人で行ったことがあるとして、これも懐疑的に述べますが、この行動のどの部分がどの後遺障害と矛盾するのか全く不明です。 治療中であるという立場からは、被害者が生活を楽しむことは望ましくないという考えが背景にあるようで、あたかも喪に服さない遺族を非難するようなニュアンスが感じられます。 しかし、私の知人のなかには、重い病気があるにも関わらず、「今行かなかったら一生行けない。」と言って海外旅行に行く人もいます。このように病状が進行すれば海外旅行に行けなくなるかも知れないという考えから海外旅行に行く人もいるので、このことを否定的に捉えることはできないと思います。ましてや、海外旅行に行ったことが詐病と認定する根拠になるとは思えません。 (2011年5月14日掲載)
 提訴後の鑑定で初めて診断されたRSD(16.2.27)
提訴後の鑑定で初めて診断されたRSD(16.2.27)

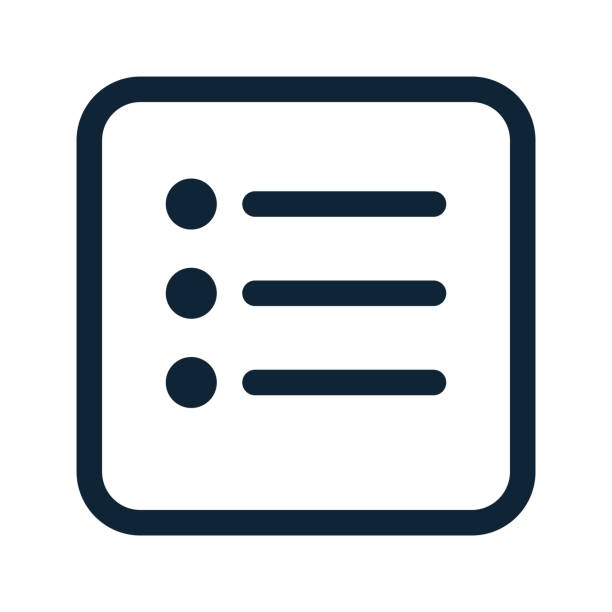 目次へ
目次へ