- 札幌地裁平成18年1月24日判決(自保ジャーナル1665号11頁) 判決は抜粋ですので、症状の経過などの詳細は不明です。 この事案の特徴は、①左胸部のCRPSであること、②神経因性疼痛のメカニズムについて詳細な言及があること、③症状固定時期の認定が詳細であること、④就労と家事労働の逸失利益を区分したこと、⑤心因的素因をきっちり否定したことなどです。
-
- 症状の経過
- 被害者は事故時46歳の美容業兼主婦です。被害者は平成8年7月7日にセンターラインオーバーの対向車との衝突により、多発肋骨骨折等でCRPSを発症します。判決が抜粋のため事故後の症状の経過は不明です。 被害者は、事故により左第6、7、8、肋骨骨折、両膝・両大腿・左肘挫傷、右膝挫創、頚椎捻挫、腰椎捻挫、頭部・右手関節打撲、右手捻挫、右膝蓋靭帯損傷(外傷性関節症)、左肋間神経痛、右膝内部痛(正座不可)、右膝内側知覚異常の傷害を負ったとあり、かなりの重症を負っています。 被害者は左肋骨の多発骨折により早期から左胸部にCRPSの特徴的な症状を生じていたようです。
- 胸部のCRPS(RSD)は判例では少数です。加害者はCRPS(RSD)ではないと争いますが、判決はCRPSの特徴的な症状を多く列記(灼熱痛、痛覚過敏、知覚障害、強い持続痛、アロディニア、皮膚蒼白・冷感・温度差、浮腫、皮膚血流の変化、発汗異常)しており、CRPSであることには問題はありません。左肋骨の多発骨折により同部位にCRPSが生じていることから、因果関係にも問題はありません。
-
- 神経因性疼痛のメカニズム
- 判決は神経因性疼痛の状態、発生機序について、詳細な医学理論を展開しています。この部分は他の判決には見られない特徴的なものです。以下に一部を引用します(丸数字は引用者)。 証拠(略)によれば、①原告には、疼痛障害が強く見られ、神経因性疼痛の要素が強く関与していること、②この神経因性疼痛は、発作的な痛みや刺すような痛み、燃えるような痛みであり、交感神経系の影響を密接に受けるC繊維の自発発火が持続的な灼熱痛を起こし、更に脊髄後角細胞を感化しやすくすること、③知覚神経(Aδ~Aβ)は、末梢の神経受容器から鋭敏な痛みをAδ線維を通して、触覚、振動覚の刺激をAβ線維を通して脊髄後角細胞に伝えるが、このとき損傷部の末梢の侵害受容器が炎症物質などで障害、感作されていくと、侵害刺激を調整することができず、どんどん刺激を脊髄後角細胞に伝えることになり、そこで感作が生じることになるという発生機序であること、すなわち、④正常時には、脊髄後角細胞では交感神経刺激(C線維)と知覚神経(Aδ~Aβ)、そして脳からの下行性抑制系によって、痛みをはじめ、侵害刺激を調整して、それを中枢に伝える機序が働いているが、脊髄後角細胞での調整作用が侵害されると、軽度の刺激に対しても痛覚過敏になったり、Aβ線維を伝わった触覚、振動覚を痛みとして感じるアロディニアが生ずることが認められる。 このように、原告の瘡痛障害は、発生機序が医学的に証明しうるものであり、後記認定のとおり、強度で長期間にわたり持続的に発生している疼痛であって、時には労働に差し支えるものであるから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(後遺障害等級12級12号)に該当するというべきである。
- どうでしょう。これを一読してその意味が理解できる人は、医療関係者以外ではまずいないと思います。何回か読み返すと感覚的なニュアンスとしてスジが見えてくるという程度であると思います。興味のない人にはチンプンカンプンではないかと思います。 この判決の説明は、1986年にロバーツ(Roberts)が交感神経依存性疼痛(SMP)という概念と仮説を導入して、アロディニアを説明したときの理論に基づいていますが、現在ではこの考えは正しくないとされているようです。 RSDについての93年のベルドマン(Veldman)の826症例による大規模研究では、交感神経ブロックの有効例は7%に過ぎず、一時的な有効例も含めて30%程度であり、無効・症状の悪化が66%にも上ったとされ、このことが94年に国際疼痛学会がRSDをCRPSと変更することにつながります(『ペインクリニック』30巻別冊Ⅰ・246頁以下)。 これは神経因性疼痛(今は神経障害性疼痛と呼ぶ方が多いようです)が上記の説明ではおさまらないことを意味します。「CRPSに見られる神経障害性疼痛には、持続性の自発痛のみならず、発作性のもの、誘発性のアロディニアがあり、性質も灼熱様、切り傷様、締め付け様、電撃性と多岐にわたり、一元的な機序で説明することは不可能である」(『ペインクリニック』30巻別冊Ⅱ333頁)とされているようです。 細かい説明は省略しますが、神経障害性疼痛については現在では『神経障害性疼痛診療ガイドブック』13頁以下のように多元性を認める説明が一般的のようです。 なお、上記のようにCRPSにおいては神経ブロックの効果は限定的ですので、「神経ブロックに効果がなかったのでCRPS(RSD)ではない」という加害者側の定番の主張は誤りとなります。
- この判決が医学的な理論を詳細に引用した部分は積極的な認定として評価できるのですが、私が気になったのは、判決が「これで神経因性疼痛のメカニズムが証明されたから、局部の頑固な疼痛がある」との理屈を述べる部分です。ここまでの説明をしないと12級レベルの痛みがあることを認定できないというのは感覚としてちょっとずれている感じがします。 この判決は、次に述べる「メカニズムを因果関係と取り違える誤謬」に陥っているようにも見えます。
- メカニズムを因果関係と取り違える誤謬 因果関係を細かく探究していくと、その結果を生み出すメカニズムが解明されていくことは事実です。メカニズムが解明されたことにより、事実をより深く理解したとの実感が生じて因果性についての心証も強くなるという面も否定できません。 しかし、メカニズムが解明されないと因果関係が証明されたことにならないとすると、ちょっと問題です。 例えば、「壁のスイッチを押して電灯をつけた」という説明に対して、「君はその建物の配電図をみて確認したのかね。していないだろ。なぜその因果関係を認めるのだね。」などと詰問されても困ります。内部のメカニズムの解明と因果関係の有無とは別の問題です。メカニズムの解明にはきりがありません。配電図とおりに配線が組まれていることや、電気信号が電灯の切替えになる仕組みなども解明して理解しないと因果性が認められないとするわけにもいきません。 因果関係の証明は、内部のメカニズムの説明とは異なります。因果関係は事実Aと事実Bに因果性が認められればそれで足ります。内部メカニズムの解明は突き詰めるとキリがありません。 上記のメカニズムを重視する判決の論理に対しては、その理論(SMP仮説)がこの事件に当てはまることの証明があるのかという問題がまず生じます。さらに他のメカニズムを主張する学説による反論も考えられます(本題とは関係ないところで無用な論争が生じます)。 このほかに分子生物学に還元したメカニズムの説明までするべきであるとの反論(実際にも、現在では分子生物学的手法によるより難解な説明がされています)も考えられます(より詳細なメカニズムを解明すべきという形で因果論から後退していきます。) さらに全ての科学法則は経験的に知られているだけで経験からは未来が必然的に導かれることはないという根源的な反論(ヒュームの亡霊。ただしヒュームは恒常的連接ないし規則性で因果関係を肯定すると思いますが)や、ある宇宙の物理定数はその宇宙の偶然でしかないという更なる根源からの反論(因果論を無意味にします)もありうるところです。 本件では、CRPSは激しい疼痛を生じる場合があるとされることに言及すれば、十分ではないかと思います。
- 判決は、CRPSにり患しているとしながらも、被害者の後遺障害等級を12級と低く見積もりました。判決は被害者の就労の労働能力喪失率を50%とみているので、これは奇妙に見えます。9級ないし7級の認定をするべきであったと思います。 判決は、後遺障害等級を認定するためにはメカニズムが解明されていなければならないとの誤謬に陥ったため、後遺障害の認定に用いるハードルが高くなっているように見えます。 判決の認定額は1441万円ですが、さすがに認定額が低すぎると思います。この判決は素因を否定したものの「CRPSという特殊な傷病により生じた損害の全部を加害者に負わせるのは良くない。」というある種の差別的な見方で後遺障害等級を低めに認定して帳尻あわせをしたような印象も受けます。
-
- 症状固定時期
- 被害者は、平成8年7月の事故の後、長期間通院を続けて平成14年に症状固定となったと主張して、平成15年に訴訟を起こしているようです。 これに対して、加害者は平成9年1月(事故半年後)に症状固定となったと主張しています。現実にも被害者は平成9年1月にはいったん症状が軽減したようですが、その後は悪化と改善を繰り返し、平成10年12月には内視鏡的胸部交感神経節焼灼術の手術を受けています。 CRPSの症状には進行性があり、その進行の度合いは個人差が大きく、症状は一進一退を繰り返し、症状が固定したかどうかをその時点で判断する医学的な指標もないことから、症状が固定したかどうかは事後的に判断するほかないと思います。
- 判決では平成11年1月に医師により転地療養を勧められたことや、手術により痛みの性質が明らかに変わったとして、平成11年1月20日が症状固定日とされています。この判決は、症状が一進一退を繰り返すことから、ある時点で改善していてもすぐに症状固定であるとしなかった点は正しいと思います。 判決は、その後の症状の経過について触れていませんが、症状の悪化が止まったかどうかは事後的に判断するほかないことからは、症状が固定したとする平成11年1月20日以降の症状の経過を述べなければ上記の判断が正しかったのかどうかは分かりません。この部分は少し問題があると思います。
- 判決が抜粋のため被害者の主治医が判断した症状固定の時期は不明ですが、おそらく平成11年1月20日よりも後の時期だったのではないかと思います。慢性化した疼痛に対する手術の1か月後に、早々に症状が固定したと医師が判断したとは思えません。 症状が一時的に良くなってもある程度の期間の経過観察を続ける必要があることから、症状固定日は上記の手術後の経過も引用した上で、もう少しあとの時期にした方が良かったのではないかと思います。
-
- 就労と家事労働の逸失利益について
- 判決は、被害者の逸失利益の算定において、少し技巧的な方法を用いています。まず基礎となる収入を、賃金センサスにおける女子労働者の全年齢平均(約335万円)としています。この点は妥当であると思います。算定する期間を短くする場合には被害者と同年齢の平均年収を用いるべきですが、期間が長くなるときは全年齢平均を用いるべきです。 判決は、これを前提として約335万円のうち約116万円は美容師としての就労による所得であるとし、残りが家事労働のよる所得であるとみなし、就労分は50%の労働能力喪失があるとし、家事労働分は14%の労働能力喪失があるとして、両者を区分して労働能力喪失率も異なるとして計算しました。
- この判決の考え方(外での就労と家事労働の区分)は、有職主婦の逸失利益の算定において、1つのありうる方式であると思います。 ただし、両者を分けずに算定するやり方が通常ではないかと思います。判決の考え方に対しては、家事労働も同じ労働であるのに家事労働を低く見ているのではないかという批判もありそうです。 一般的には外での労働の方が厳しい環境で行われ、自宅での家事労働よりも制約が大きく、後遺障害による影響が生じ易いようにも思われるので、判決の考えはそれが被害者の実態に即したものであれば、特に問題ではないと思います。
-
- 心因的素因について
- この判決は、被害者の心因的素因を否定しました。被害者の治療期間が長くなると素因が認められ易い傾向があり、この事例では、さらに被害者に不利な事情があることを判決も引用しています。 判決は①平成8年12月25日(事故から4か月半後)付けの病院の報告書のなかに、被害者には心因的要素もありそうであるとの記載があり、②平成10年3月4日のカルテには自賠責の打ち切りについての記載があり、③同年7月15日の病院の書簡には、被害者が症状を訴えながら涙を流すなどの精神的な面の影響の強さを示唆する事情が書かれており、④同月22日の病院の診療情報提供書には「抑うつ状態疑い」「やや神経症傾向はあるものの、心身症タイプで抑うつもあることから、やはり、末梢性の」神経性の痛みが抑うつ気分で「強められているということかも知れません。」との記載があることを引用しています。
- しかし、判決は、「これらの記載が指摘する原告の心因的要素は、本件事故により発生した原告の疼痛等の症状が長期間慢性化し、そのための入通院治療を繰り返しているにもかかわらず、痛みが消失しないこと等についての原告の心理的不安感、焦り、いらだち、絶望感等によるものであると認めるのが相当であり」としています。 判決は、「前記記載をもってしても、事故により障害を負った患者が陥る通常の心理状態の域を超えて、素因による減額をすべきであるような原告の特異な性格や精神的要因の存在を認めるには足りない」として、素因減額を否定しています。正しい判断であると思います。 (2012年1月27日掲載)
 左胸部CRPSの肯定(H18.1.24)
左胸部CRPSの肯定(H18.1.24)

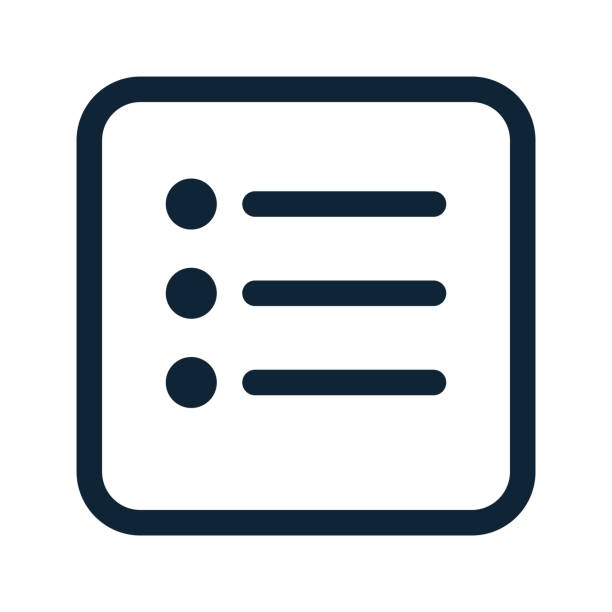 目次へ
目次へ