- さいたま地裁平成23年1月26日判決(自保ジャーナル1863号1頁) 東京高裁23年10月26日判決も同時に掲載されていますが、以下では地裁判決について述べます。 この事案の特徴は、①被害者が20を超える病院に入通院したこと、②3回の鑑定が行われていること、③疑問のある鑑定意見を判決が重視していること、④RSDとの診断が多数回繰り返されてきた右上肢を判決がRSDではないとしたこと、⑤心因的素因により2割の減額をしたことなどです。
-
- 症状の経過
- 被害者は事故時29歳の女子会社員です。被害者は平成11年5月25日に自転車を運転していて交差点内で乗用車との衝突事故で受傷します。 当初は、ごくありふれたむち打ち事案のような治療を受けていますが、1か月半後に右上肢のRSDとの診断を受け、その後に左下肢のRSDも診断され、多数の病院に入通院して治療を受けます。
- 複雑な治療経過をどのように判決文にまとめるべきか? 判決では一般的には「事案の概要」では争いのない部分をまとめ、「争点に対する判断」では裁判所の判断を記載します。この判決は治療の経過が「事案の概要」と「争点に対する判断」の2か所に分散していて散漫な印象を受けます。少なくとも入通院した病院とその時期や治療内容は「事案の概要」で網羅した方が良かったと思います。 本件ではその時期ごとの症状に争いがあったため「争点に対する判断」で分けて書いたとも考えられますが、この場合でも通院した事実や治療内容などは「事案の概要」に記載した方が良いと思います。入通院経過について争いがある場合においても、「被告は~と主張しているが、~の理由で(後記のとおり)採用しない」と付記して「事案の概要」で最低限の骨格は網羅した方が良かったと思います。
- 以下では、判決が分散して記述した治療経過等をまとめて検討します。
- 事故当日・・・平成11年5月25日。B病院に救急搬送される。全身打撲、頭部外傷、左下腿皮下血腫、頚椎捻挫と診断され、翌日まで入院。B病院には1か月通院。 判決の認定によると、事故直後は被害者が首や左下腿などの痛みを訴えるも、レントゲン、CTでは異常はなく、事故4日後には全治約10日間の安静加療を要する見込みとの診断を受けています。当初は後の症状をうかがわせるような診断は受けていません。しかし、のちの経過からは事故後早期からRSDの症状が出ていたと思います。このように初期の病院でRSD(CRPS)の症状が見落とされることは、多くの事案において見られます。
- 18日後・・・6月12日より。C大学附属D病院。頚椎捻挫、左下腿挫傷と診断され、1か月に6回通院。 被害者が早期に大学病院に転院したことから、事故直後の時期からかなり強い痛みを訴えていたと推測できますが、判決では詳細は不明です。被害者は、首と左下腿の痛みを訴え通院し、レントゲン、MRIで異常はないものの、首の痛みや可動域制限が改善しなかったため、E病院への転院となります。
- 1か月半後・・・7月13日より。E病院。外傷性頸部神経根症、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)と診断され、約4か月入院。退院時には、頸部捻挫、RSD(右上肢)との診断を受ける。 被害者はE病院の通院初日に右上肢についてRSDとの診断を受け、そのまま入院します。右上肢はとくに手関節から先の浮腫(むくみ)が顕著で、可動域制限も確認されています。被害者は腕の痛みのため、歩行時には右腕を振らず、体への振動を押さえるために歩行はかかとのみで接地しています。その後のリハビリの中で右手の握力は2.5kgにまで低下しています。 判例の上ではRSD(CRPS)の患者はRSDとの診断を受けるまでに3年やそれ以上を要したものもあり、その過程で症状の原因が分からずに精神科に回される事案も多く、遅れて診断される傾向が明らかにあります。この傾向は診断基準が確立する以前の古い事案ほどよく当てはまります。この事故があった平成11年前後の事故の裁判例では事故の1か月半後という短期間でRSDとの診断を受けた事案はわずかです。 以上から本件ではE病院への通院開始の時点ではっきりしたRSDの症状が右上肢に出ていたことが推測できます。被害者がそのまま4か月(126日)入院したことも、これを裏付けます。 持続性の痛みと知覚過敏、浮腫(むくみ)により、日本版のCRPSの判定指標を満たすことや、右上肢の運動障害なども考え合わせるとこの時点でCRPSを発症していたことに問題はないと思います(判決ではCRPSの発症を否定していますが、誤りです)。 被害者は、4か月に及んだ入院中に浮腫以外はほとんど症状が改善しなかったことから、退院と同時に自宅近くのF大学病院に通院を始めます。
- 半年後・・・11月22日より。F大学病院。2年ほど通院した模様。 F大学病院でもRSDとの診断を受け、平成12年5月12日(事故の約1年後)を症状固定日とする後遺障害診断書が作成される。 被害者は、通院当初に右肩から手までの右上肢全体と左下腿は触っただけでも痛みを感じるアロディニアの症状が確認されています。この症状はこれより以前から生じていたはずです。 左下腿の痛みをかばって足を引きずって歩行していた状況はここでも確認されています。左下腿の痛みは事故直後から続いており、それが悪化して行ったようです。この時点では左下腿にもRSDを発症していたと思います。
- 11か月後・・・平成12年4月11日より。Sクリニックへ通院。 被害者は、右手は握りこんだ状態で指と指の間にカビが生えてきたためSクリニックに通院します。このことから指をグーの状態で握りこむジストニアのタイプのRSDが生じていたことが分かります。 F大学病院での星状神経節ブロックや仙骨硬膜外ブロックで腫脹が改善するなどの効果はあったものの、症状全体としては基本的には改善していません。そのため心因の要素もあるとして、精神科を紹介されます。 1年9か月後・・・平成13年2月21日より。h大学病院精神科へ通院。心理テスト結果には問題はないとされるも、抑うつと診断される。主治医は心因性疼痛の要素もあるとする。
- 2年2か月後・・・平成13年7月12日より。U病院ペインクリニック科へ通院。右上肢、左下肢にアロディニアを伴う疼痛があり、右肩関節、肘関節、左膝関節には疼痛のためか可動域制限があること、右手指には関節拘縮がないこと、右上肢の発汗が減少していること、右手指に腫脹があることが確認されるも、RSDとはっきり診断できないとされる。 現在の判定指標では優にCRPSと判定できる症状が出ているので、この時点でも右上肢、左下肢にRSDの症状が続いていたことが確認できます。この段階までにRSDとの確定診断が繰り返され、症状も悪化しているのですが、U病院は「RSDとはっきり診断できない」としています。平成13年時点では確立した診断基準がなかったため、診断に躊躇する事案がしばしばみられます。 私が気になったのは、U病院で右手指に関節拘縮がないとされていることです。上では右手を握りこむタイプの症状のため指にカビが生えてきてSクリニックに通院したとあるところ、この時点では症状が改善していたのでしょうか。 右手指には腫脹(むくみ)が依然としてあり、アロディニアの症状も出ていたことから、おそらくは自分では(痛みもあって)指をほとんど開くことができない状況ではあるものの、他人が少しの力で指を開くことができるため、関節拘縮とは判断されない状況にあったようです。 患者さんによっては、指が強く握りこまれた状態で拘縮して、力を入れても容易には開かない方もいるようですが、この時点ではそこまでの症状ではなかったようです。
- 2年3か月後・・・平成13年7月16日。F大学病院。右上肢、左下肢について傷病名を反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)として平成12年5月12日を症状固定とする後遺障害診断書が作成される。右手左足に骨萎縮が確認される。 通常は後遺障害診断書を作成した日かその直近の診察日が症状固定日としますが、1年2か月も遡って症状固定日を決めていることから、平成12年5月以降は症状の改善はほとんど見られなかったようです。 しかし、ここまで極端に症状固定日を遡ることには疑問があります。症状が改善しなくとも、平成12年5月12日以降の治療で症状の悪化が防がれた可能性もあることは否定できず、RSDという難病であることに鑑みれば、症状の安定が始まった時期に症状が固定したとすることには疑問があり、腫脹(むくみ)が改善したという程度においては治療の効果もあったと言えます。
- 2年9か月後・・・平成14年2月28日より。Gセンター整形外科。RSDを原因とする右手、肘(右上肢機能障害)、左下肢機能障害との身体障害者診断書・意見書を作成。その後も神経ブロックなどが効果を有せず、RSDとの診断が下される。 原告は、事故の2年9か月後(平成14年2月28日)にGセンターの医師が身体障害者の等級認定の診断をした日が症状固定日であると主張しています。このことからこの時点までには被害者の主張する症状は全て出ていたようです。
- 2年9か月後・・・3月4日より。Jクリニックに通院する。3回の通院のみ。
- 2年11か月後・・・4月15日。Kセンターを受診。右半身麻痺、左下肢麻痺、右拇指屈曲麻痺、右手関節屈曲変形、正中神経麻痺、右肩関節拘縮、右肘関節拘縮、右膝関節拘縮との診断を受ける。
- 2年11か月後・・・4月24日より。L病院への通院を開始するも、M大学病院神経内科を紹介される。
- 3年10か月後・・・平成15年4月2日。N病院を受診。右上肢・左下肢麻痺、右肩・肘・手・指関節拘縮、左股・膝・足関節拘縮、右顔面神経麻痺、右上肢・左下肢知覚異常との診断を受ける。 上記のとおり、事故の1か月半という早期にRSDという診断を受け、事故1年後に症状固定との診断を受けたことからは、早期から強い症状が出ていて、かなり早く症状が進行して重症化した典型的なRSDの症状であると考えられます。 KセンターやN病院での診断などによれば、右上肢は肩、肘、手の関節に強い拘縮が出ているほか、手関節が屈曲した状態となるジストニア様の症状が出るタイプのRSDとして重症化していることが分かります。左下肢についても股、膝、足の関節に拘縮が出ていたことが分かります。
- 4年後・・・平成15年5月12日。O大学病院を受診。顔面神経右不全麻痺。右上肢不全麻痺、左下肢不全麻痺と診断される。
- 5年3か月後・・・平成16年8月9日。P病院を受診。傷病名をRSDとする年金診断書を作成される。翌年にも同様の診断をされる。
-
- 後遺障害認定
- 被害者は事故日(平成11年5月25日)の約1年後(平成12年5月12日)に症状固定とされ、平成14年2月18日に後遺障害認定を受けています。その内容は以下のとおりです。 被害者の右前腕の痛み及び筋力不全等の症状については、本件事故による頚椎捻挫に起因して生じたRSDに起因する症状であり、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級12号とされました。 左下肢痛及び痺れ等の症状については、RSDに起因する症状と捉えることは困難であるとして14級10号に該当するとされ、右上肢と併合して12級とされました。 自賠責の後遺障害認定は以下のとおりですが、右上肢については肩・肘、手関節の可動域制限や疼痛が考慮されておらず、左下肢についても同様です。可動域制限が各関節の後遺障害の等級に該当するかの判断もなされていないようです。また痛みによる日常生活全般への影響も無視されています。
- 上記の症状の経過の中で医師が診断した内容をそのまま受け取ると右上肢は5級6号の「1上肢の用を全廃したもの」に準じたものとなり、少なくとも7級4号の「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない」に該当することは明らかです。 下肢の症状も考慮すれば、後遺障害の認定は異常なほどに低いと思います。RSDの事案ではこのような不可解な後遺障害認定がなされる事案が非常に多く見られます。
-
- 3件の鑑定
- 本件では、3件の鑑定がなされています。鑑定書を書いたとされる医師が被害者を診察した順にA鑑定(平成20年12月12日)、B鑑定(平成21年2月25日)、C鑑定(平成21年8月31日)とします。 A鑑定(加害者側に非常に好ましい結果)は9級7の2「通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの」に相当するとしつつも、被害者の後遺障害には事故による影響は少ないとし、被害者への詐病の疑いを繰り返し述べる内容となっているようです。このため被害者側が再度の鑑定を申立てた結果、B鑑定がなされたようです。 B鑑定(被害者に好ましい結果)は、右上肢、左下肢とも7級の4「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に相当し、両者の併合で5級の2「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に相当するとします。この鑑定は、上記の入通院先の各病院での診断をそのまま鑑定書に反映させたものですが、これに対して加害者側が再度の鑑定を申立てC鑑定がなされたようです。 C鑑定(加害者側に非常に好ましい結果)は、右上肢はRSDないしその可能性が高く、左下肢はRSDであるとして、12級の12に該当するとします。さすがにこれは低すぎると思いますが、判決では軽視されその概要のみしか分かりません。
- 判決はA鑑定を非常に重視します。A鑑定の鑑定人は医療センター長の肩書を持つベテランの医師で年間15ないし25件程度のRSD臨床例を経験し、RSD患者の症例を熟知しているとして高く評価します。 その上で、「鑑定人が、経験上、賠償が絡むと詐病を訴える患者がいるため、常にRSD患者を診る時には目を引いて客観的に見るようにしている旨を述べている点は十分首肯できる」としてかなりの信頼を寄せ、鑑定書の記載や鑑定人質問での回答も肯定的に評価し、「鑑定人の示した理学所見や診断は十分信用に足るものであって」とさらに持ち上げて、この鑑定人にほれ込んだ心情が窺われます。 私はこれまでに華々しい経歴の医師によるとされる医学意見書や鑑定書を安易に信用しないように繰り返し述べてきましたが、この判決では経歴のある人がそれらしい言葉を述べたこと自体を非常に高く評価している点が気に掛かります。 結論から言えば、この判決はA鑑定を重視したと思われる不可解な医学的見解を多数述べることとなっています。
- 以下はあくまでもこの事件のことではなく一般論ですが、これまで検討してきたCRPSの事案のほぼ全てにおいて加害者側から医学意見書が提出されています。私の経験や裁判例などから知りえた知識からは、その意見書の名義人の華々しい経歴の医師であることが少なくないようで、なかには大学医学部の部長レベルの医師やCRPS(RSD)患者を多数経験してきた高名な医師も含まれています。 これら加害者側の提出する意見書は被害者がRSD(CRPS)であることを否定ないし疑い、被害者の詐病を繰り返し強く示唆する内容となっています。被害者の主張を否定するために出されるものなので当然といえば当然ですが、このような医学意見のなかでCRPS(RSD)に必須の症状は1つも存在しないという基礎知識を述べたものは見当たりません。それどころか、必須の症状を多数存在するとするものや、さらには判定要素ですらない骨萎縮や筋萎縮が必要であるのみならず、それが重度でなければならないとの誤った見解を述べる意見が多く見られます。 これと同じ意見が裁判所の選任した鑑定人によって述べられると、裁判所はそれをより信じてしまう傾向があるようです。しかし、これまで見てきた裁判例からは世の中には被害者に格別に不利となる問題のある意見を述べる医師が少なからずいるようにも見えます。裁判所の提示した鑑定人リストを見ても、被害者側の弁護士はこの中の誰が「ハズレ」なのか分からないため、鑑定人を決める作業はあたかも「カードが透けて見える人とのババ抜き」をさせられるような状況となるようにも思われます。実際にもこれまで検討してきた裁判例の上では鑑定書の多くは被害者に格別に不利なものであるようにも見えます。
- アメリカやオランダとの比較では、日本でCRPSを発症する人は年間に1万人~2万人ほどであり、そのうち半数前後が交通事故によるものであると私は推定していますが、専門病院の医師がCRPSとの診断を下した患者については、私は詐病の可能性は高めに見ても1000分の1ほどであると考えています。
-
- 判決の述べる医学的見解について
- 反射 判決は、「右上肢について深部反射はいずれも正常であり、病的反射も認められない」としてこの点を重視します。反射を重視することは、それ自体がちょっと奇異な感じがしますが、「異常な反射がない」、「病的反射がない」と述べて、被害者の詐病を強く示唆する医学意見は加害者側の定番です。判決によればA鑑定にはこの旨の記載があるようです。 CRPSに特有の反射はない(少なくとも知られていない)ため、何ゆえ反射に言及したのか、それ自体が理解し難いところです。ところが、筋反射や腱反射をあたかも「全ての疾患に対する万能な検査」であるかのごとく述べることは加害者側の医学意見の定番とのようです。 仮にCRPSではなく反射が言及される疾患であるとしても、反射を重視することは正しくありません。例えば、頸部神経根障害において筋伸張反射の感度は概ね3%~24%とされています。上腕二頭筋以外は10%以下です(『エビデンスに基づく整形外科徒手検査法』132頁)。つまり検査としての価値が非常に低いこと(価値がないこと)に反射の特徴があります。しかし、問題のある意見書においては、反射が生じる医学的な理由から詳細に説き起こして、反射の重要性を訴えて被害者の反射が不合理であると主張するものは少なくないようです(特に頚椎の不全麻痺の事例では)。 従って、CRPSという特有の反射のない(もしくは知られていない)疾患において、仮に意見書で反射が正常であることをいぶかしむ様な記載があれば、この部分のみにおいて、その意見書の全ての価値を否定して構わないようにも思います。
- MRIに異常はないとの記載について 判決は、右上肢について病的反射がないことに加えて、MRI検査で異常がないことにも言及して、MRI検査で異常が見当たらないのは、他覚所見に乏しいと述べます。 しかし、CRPSにおいて特有のMRI画像はありません。従って、MRIで異常が認められないことは、MRIで検出されるほかの疾患(ヘルニアなど)による症状発生の可能性を否定して、消去法的にCRPSであることを裏付ける事情となります。つまり、MRIで異常が見当たらないことはCRPS(RSD)を肯定する事情です。 ところが、MRI検査で検知できない疾患において、その疾患を否定しようとする医学意見書では、「MRIという高精度の精密検査で異常が見つからないのは、いかなる疾患も生じていないからだ。」とのニュアンスを述べることは定番です。判決はこの主張に惑わされた感じがします。
- 骨萎縮 判決は、右上肢について事故の2年以上後まで骨萎縮を明確に認めた所見はなく、所見を認めた医師がいるものの、鑑定人(A鑑定)は明確に否定しているとして、これをRSDの要件として重視します。CRPS(RSD)において骨萎縮が必須であるとする主張は、RSDを否定すべく提出される医学意見書での鉄板ともいえる定番です。 しかし、CRPSにおいては特有の症状が存在しないことは、世界中の医師が認める定説ですので、必須の症状を認定することは、それだけで重大な誤りです。 また、現在の国際疼痛学会やアメリカ、日本のCRPS判別指標においては、骨萎縮は判定要素の1つにさえ含まれていません。従って、骨萎縮がないことによりCRPS(RSD)であることを否定することは、より強い意味で誤りです。 重症のCRPSには重度の骨萎縮が必須であるとする加害者側の定番の主張(特別基準論)はもとより論外です。そのような相関性は医学的には認められていません。 CRPSにおいてはいったん生じた症状が改善することもあります。このことは骨萎縮に限りません。このように症状が一過性の場合もあるため、日本のCRPSの判別指標においては、症状の経過のなかでの一過性の症状をも対象に含めて検討します。 従って、仮に鑑定時点で骨萎縮が確認されなかったとしても、症状の経過の中で骨萎縮がなかったことを意味するわけではありませんが、判決はこの点についても誤解しています。仮にこれが判決の重視したA鑑定に基づくとすると、本当にこのレベルの医学意見が出たのであろうかと疑われる内容です。 本件では、右上肢について通院中にも骨萎縮の存在は繰り返し確認されており(F大病院の整形外科・麻酔科、G病院など)、自賠責の認定でも確認され、A鑑定の2か月後に行われたB鑑定でも「明らかな骨萎縮」があるとされ、12級との非常に低い等級を述べたC鑑定でさえも、「軽度の骨萎縮」があるとしています。従って、A鑑定のみが正しく画像を読み取ったと考えるべき状況にはないように思います。 なお、高裁判決は、CRPSによる可動域制限が長期間続いていたならば顕著な骨萎縮が生じているはずだという理屈(特別基準論)を付け加えています。「この事件は特別の事情があるからこの要件が特別に必要である。」という特別基準を持ちかける論法です。これを認めたら一般の基準の意味がありませんので、この論理自体に問題があります。一般的な基準でCRPSとされるものを、これを否定するためだけの特別基準を当てはめてCRPSではないとすると矛盾が生じます。可動域制限が長時間続いたならば重度の骨萎縮が生じるという論理ももちろん誤りです(そのような相関はありません。)。しかし、この定番の主張に惑わされた判決は多く見かけます。 あろうことか高裁判決は筋萎縮も重度でなければならないという理屈も付け加えていますが、これも誤りです。筋萎縮を判定要素に含む診断基準は過去においても一度も提唱されたことがないはずです。国際指標や日本の指標では浮腫で腕がむくむこと(判定要素の1つ)を重視していますが、これとは逆に腕が痩せ細ることも同時に要求するのは矛盾となります。まさにその矛盾を高裁判決は述べており、しかも重度の浮腫と重度の筋萎縮が同時に必要であるとしています。
- 浮腫 判決は、被害者が事故後早期に発症した右上肢の浮腫(むくみ)が、その後の神経ブロックなどの治療により改善したとする一方、「浮腫は時間の経過とともに憎悪、拡大するのが一般的である」として、被害者がRSDではないとする方向に向います。 しかし、CRPS(RSD)においては特有の症状は存在しないことは、当然のごとく浮腫についても言えます。従って、この点のみにおいてすでに誤りがあります。 それはおくとしても、判決の述べる「浮腫は時間の経過とともに憎悪、拡大するのが一般的である」という考えは誤りです。上記のとおりCRPSにおいてはいったん生じた症状が改善することもあるため、判定指標においては治療のなかで一時的に存在した症状も検討対象に含めます。従って、治療の経過のなかで浮腫(むくみ)が生じたことはそれ自体が、RSDを肯定する重要な要素となります。 この点をもおくとしても、難病とされるCRPS(RSD)といえども、治療によって症状が改善する患者さんもいるので、浮腫が悪化せずに改善する場合があることは至極当然のことであると思います。現にこの事件では事故の1か月半後にRSDと診断された時点で、右上肢には特に右手関節から先に顕著な浮腫(むくみ)が確認されていたところ、その後の治療で改善したとされています。 仮に万が一、これも鑑定に基づくとすれば、本当にこのようなレベルの医学意見が訴訟で出されたのであろうかと疑いたくなるようなひどい誤りですが、訴訟ではこのレベルのものを頻繁に見かけます。このレベルの意見でも権威のある方の名義の鑑定書・意見書において深遠な口調で「私の長年の経験からは~である」などと自身満々で書かれていると信用してしまう裁判官も少なくないようです。 判決は、A鑑定では鑑定(診察)時には浮腫(むくみ)は一切認められなかったと明確に述べているとして、浮腫は存在しないとしていますが、これも疑問です。A鑑定以前の多数の入通院先やA鑑定の2か月後に診察したB鑑定では、浮腫を認めたとしています。偶然にもA鑑定のときだけ浮腫がなくなっていたとは考えにくい状況があります。
- 程度問題の錯誤 以下はあくまでもこの事件のことではなく一般論ですが、私の経験では被害者の詐病を強く示唆したRSDを専門の1つとする華々しい経歴を有する非常に高名な鑑定人が、軍手を3重にはめたようにはれ上がっていた右手(とくに手の甲の部分は軍手5重位になっていました)を「ごく軽度の腫脹」としてほとんど無視したこともあります。 この種の訴訟の経験のない裁判官が鑑定人を信用しきってしまうと、軍手を7重にはめたような誰が見ても疑うことなく病的であると思えるような腫れ方になってはじめて「普通の腫脹」であると勘違いするかもしれません。そのような典型症例の写真が医学書に載っていることもこの勘違いを後押しするかもしれません。そうなれば、見て分かる程度のむくみが生じている場合であっても「浮腫なし」と断言されると、「医学で疾患として認められるレベルの浮腫(むくみ)はこの程度では足りないのだな。」と納得してしまうようです。 しかし、腫脹とはむくみのことであり、それ以上でもそれ以下でもありません。私のような素人が「少しむくんでいる」と気付く程度のむくみであっても、普通の医師は「腫脹あり」と明確に診断します。 普通の人が「むくんでいる」と気づくレベルであれば、当然に医学的にも「むくみあり(+)」とされます。ましてや軍手を2重にはめたほどであれば、「顕著な腫脹あり(++)」という表現が使われるレベルです。 こんなことは当たり前ではないかと思う方も多いかもしれません。しかし、医学の知識のない人が「かなりむくんでいる」と思うレベルの腫れ方であっても、自分が信用しきった高名な医師が同じ状況を「ごく軽度の腫脹である」とか「病的な浮腫はない」自身満々に明確に断言すると、「ほぅーそれが医学の基準なのか。なるほど、危うく勘違いするところであった。」と納得してしまうことも少なくないようです。 他の症状についてもこのような「程度問題の錯誤」は少なからず生じるようです。筋萎縮など数字が出るものについても、例えば右足大腿部と左足大腿部の周囲の差が1.5cmであるのを筋萎縮によるものと考えていたところ、高名な医師が自身満々に「わずか1.5cmだから誤差の範囲であり筋萎縮と断言できるレベルではない」との趣旨を明言すると、「ほぅこれが医学のスタンダードなのか。なるほど、危うく勘違いするところだった。」と納得する方も少なくないと思います。
- 主観基準のレトリック この「程度問題の錯誤論法」には前フリとして、「主観基準のレトリック」ともいうべき論法が導入されることもあります。 「骨萎縮があるといえるためにはどの程度の骨萎縮があれば良いのか分からない。」、「どこまでの皮膚色の変化があれば良いのか分からない。」と強調して、判断する医師の主観に委ねられる部分が大きいので基準を運用する際には、「誰もが認める一見して明らかな重大な症状のみを採用すべきだ」という結論に誘導します。この結論だけ見れば暴論ですが、素人には知識のない専門分野で権威のある人が前フリから丁寧にこの理屈を述べると信じる人も少なくないようです。 当たり前のことですが、骨萎縮があること自体が分かれば、それは「骨萎縮あり(+)」です。むくみがあることが分かれば「浮腫あり(+)」です。皮膚の温度差(1~2℃の差であっても)や皮膚色の違いなども同様に違いがあること自体が分かれば「あり(+)」です。基準は主観に流されるような曖昧なものではありません。 こんなことは当然のことであると言われるかもしれませんが、C鑑定にこの趣旨の記載がなされていたようであり、高裁判決にはこの論理を大幅に取り入れています。
- 「軽微」という表現そのものについて 以下はあくまでもこの事件のことではなく一般論ですが、目視や写真で見てすぐにそれと分かる腫脹(むくみ)について「軽微な」という形容詞をつけることは重大な誤りです。しかし、加害者側に有利な内容の意見書では「軽微な」、「ごく軽度の」、「わずかな」という形容詞を多用するものは頻繁に見られます。 医師であってもむくみであるかどうかの判別が困難なレベルのごく僅かな腫脹であれば、カルテには「わずかに腫脹が見られる(±)」と記載されると思います。「±」(擬陽性)は「わずかに見られる」、「軽微な」、「ごく軽度の」という意味で、「あり(+)」とは区別されます。 普通に見て腫脹(むくみ)や骨萎縮、筋萎縮、皮膚の変化などがあること自体に疑いがないものに対して、擬陽性(±)の意味となる「ごく僅かな」、「軽微な」、「ごく軽度の」という形容詞を用いることは重大な誤りです。医師がこのような初歩的な言葉使いの間違いをするとは思えないレベルの間違いです。 以上に対して、「軽度」という言葉はどうでしょうか。「軽微な」、「ごく軽度の」、「わずかな」にくらべて症状が少し重い感じがします。「症状が存在するけれども軽度である」の意味ならば、擬陽性とは別の意味とも言えそうです。私も文脈によっては「軽度」という表現には問題がないと思います。 ただし、「軽度の骨萎縮」という表現は問題のある意見書に見られる独特の表現であるように思います。骨萎縮があると分かるものは「骨萎縮あり」と書くだけでよいのに、わざわざ「軽度の」という言葉を追加することには違和感があります。とくに症状を評価する段階ではなく、取り出す段階でこの表現を用いることはおかしいと感じます。 「軽度」という言葉は取りようによっては擬陽性とも取れる言葉です。普通であれば、骨萎縮の内容を説明する表現として、「~骨頭部に骨萎縮あり」という形でその部分を示して書くと思います。部分の限定もなしに「軽度の骨萎縮」という言葉が用いられると、「どこに骨萎縮があるかどうかは別としてとにかく軽度であることが言いたいのであろうか。なぜ場所や範囲を示さないのであろうか。」(この人は画像が読めているのだろうか)という違和感があります。 まして「ごく軽度の骨萎縮」という表現ともなると、それは骨萎縮の有無について擬陽性との見解を示すものとなり、他の複数の医師が「骨萎縮あり」(陽性)としたものについてこのような表現を用いると、そこには見解の相違があり、どちらかが誤りということになります。 問題のある意見書のなかには、「ごく軽度の」という言葉を「陽性(骨萎縮あり)であるけれどもごく軽度である」という意味で用いているものをしばしば見かけます。医師がこのような表現を臨床で用いるとは思えません。私はこのような形容詞の使用法それ自体に強い違和感があります。
- 不自然なレトリック 以下はあくまでもこの事件のことではなく一般論ですが、問題のある医学意見書においては、端的に症状を記述すべき部分で「病的な浮腫はない」、「病的な筋萎縮はない」、「著明な浮腫はない」、「明らかな骨萎縮はない」、「下垂のためか腕がうっ血している」などの余分な形容詞を用いるものをよく目にします。 例えば、浮腫があることが写真でさえも分かる状況において「病的な浮腫はない」という表現が用いられたりします。文字通りに受け止めると、「浮腫(むくみ)があるように見えるけれども、病的なほどのレベルには達していないから、医学的には浮腫はないとすべきものである」という意味に思えますが、これは不可解なことです。 私はカルテの中でこのような形容詞を用いるものは見た記憶がありません。普通のカルテにはそれぞれの症状について、端的に「+」(陽性、症状あり)、「-」(陰性、症状なし)、「±」(擬陽性、症状がわずかに見られる)との外形的事実のみを記載しています。 症状に「病的な」などの形容詞をつけて記載することは、医師が臨床で用いている一般的な症状の表現法とは、根本的な部分で視点が異なります。個々の症状を取り出して記述する際に病的かどうかを述べることはおかしなことです。 臨床ではわずかな症状も洩らすまいとカルテに擬陽性まで記載している医師が、医学意見書では「著明な浮腫はない」として一見して明白で確実なもの以外を無視すべきであるとして、症状の見方を根本から変更した表現法に切り替わるというのも不自然であると思います。 また、症状の有無だけを端的に記載すべき部分で、「下垂のためかうっ血していた。」、「不使用のためか拘縮が生じていた」という余分な形容詞や、「この症状は~に整合しない。」という否定の理屈を付け加える癖のある意見書も、加害者側の意見書ではよく見かけます。臨床ではカルテには端的に症状の有無だけを列挙して、列挙を終えた後にいくつかの傷病の候補を当てはめて検討していくはずです。従って、臨床での検討方法とは根本的に異なる思考法を医学意見書で用いるというのもおかしなことであると思います。 以上のように問題のある医学意見書においては、「症状を端的に取り出す」という症状を検討する前提が成り立っていないものをしばしば見かけます。
- 不使用による症状 判決は根拠とはしませんでしたが、A鑑定は被害者の右手指はRSDではなくて一次性局所ジストニアで、左下肢は軽度のRSDで、これらによる長期間にわたる右上肢および左上肢の不使用が被害者の症状の原因であるとしています。つまり、被害者の「不使用」が症状の最大の原因であるとしています。 一次性(原発性)ジストニアとは、他に原因となる要素が見当たらないジストニアをいい、二次性ジストニアは薬剤や遺伝などにより生じたものを言います。つまり、A鑑定は右上肢の症状は手指のみ(腕にはない)であり、その手指については事故とは関係しないジストニアの発病であるとして、加害者の責任ではないとしていることになります。これによると、ジストニアは局所性のものであって、上肢全体の症状が重く見えるのは被害者の個人的事情であるということになりそうです。 左下肢についても現実に症状が確認できるよりも軽度なRSDであって、症状が重く見えるのは、使えるのに使わなかった「不使用」という被害者の個人的な事情によるとしているようです。 この部分を普通に読むと、この被害者はもともと軽度の傷病(しかも事故と無関係な一次性ジストニア)に過ぎないのに、とんでもない特異な性格のため、格段に重症に見せようとして右上肢・左下肢を数年という長期間にわたって全く使用しないことにより、無理やり重症化したRSDのような症状を作り出したということ述べているように読めます。 さすがにA鑑定のこの部分は「いくらなんでもそんな人がいるわけがない」というのが普通の感覚ではないかと思います。人前でだけ症状を偽装するだけではなく、人の見ていない日常生活でも数年にわたり一度も関節を曲げないというレベルの努力をしていたことになりそうです(私はこれでもRSD類似の症状を作り出せる可能性はないと思います)が、普通であればこのような想定を要求する話は、その前提部分を信じないと思います。 また右上肢については、事故後早期から多くの病院で繰り返しRSDとの診断がなされ、その治療が続けられてきた経緯からは、一次性局所ジストニアという加害者側に非常に都合の良い病名が正しいとすると、被害者は偶然にも事故直前頃に一次性ジストニアを発症し、事故の1か月半後にE病院でRSDと診断されるように人知を越えるレベルの偽装工作をした(私はこの偽装は不可能であると思います)と想定して、当初からの治療経過の全体をつじつま合わせしなければならないこととなりますが、さすがにこれは荒唐無稽なストーリーであると思います。
-
- 出来過ぎストーリー
- 事故により重篤な後遺障害を負ったとして被害者が訴訟を起こしたところ、加害者側は以下のようなストーリーを主張してきました。 それは「本当は軽微である事故をきっかけにそれまで真面目に仕事をしてきた被害者の人格が変わり、何かにとり憑かれたように虚偽の症状を訴えることに人生を賭けるという特異な性格に変質し、どのような偽装を用いたのか想像も付かない特殊な偽装方法を天才的なひらめきによりあみ出して、さらに驚異的な粘り強さでその偽装を根気良く続けて、長期間にわたってウソの病気の治療を受け続け、仕事も休み続け、知人や家族や主治医や弁護士を騙し続けて、重症化した症状の偽装を続けてきた。」というストーリーです。これは加害者側に非常に都合の良い出来過ぎたストーリーです。普通の人は「こんなことはあり得ない」と思うでしょう。
- しかし、このような帰結(世界像)を必然のように導いてしまう医学意見書はCRPSの訴訟においてはむしろ定番とも言えます。なにしろCRPSの訴訟では重症事案であっても症状を否定する医学意見書が出されることが恒例行事のようになっています。 被害者の主張する症状を否定する(詐病とする)ことになれば、長期間の通院や治療や仕事の休業なども最初から最後まで全部がウソに基づくことになります。 ところが詐病を認定する判決においては、その認定を全体として整合するようにつじつまを合わせた世界がどのようなものであるのかについて、考えていないようです。ただ泥縄式(行き当たりばったり)に事実を前から順に決めて行くだけで、その事実を決めてしまうことがどのような帰結(世界像)を導くのかをきちんと想定していないように見えます。「正しいはずの基準(方法論)が導いた結論だから、どんな結論であっても物理的に不可能でない限り、正しいはずである。」という考えで自分が認定した事実の先にある帰結(世界像)を直視していないように思います。 認定した事実の先にある帰結(世界像)を想定してみれば、上記のような「とんでもない」というレベルのストーリー(しかも当事者の一方に非常に都合の良いストーリー)を作り上げる必要があることに気付き、はたと考え直すはずです。 上記の想定は、加害者側に都合のよい結論に至るために全ての事情を最初から完全に作り変える「出来過ぎストーリー」です。この種の「出来過ぎストーリー」を導くもとになる陰謀論(詐病による事実全体の再構成)をどうして信じてしまうのか、私には不思議で仕方ありません。 年間1~2万人ほどと推測されるCRPS患者の症状の経過としての外形を否定して、数千万人に1人いるかどうかという極めて特異な人間により周到に偽装された症状であると考えるには、相当に確実な根拠を必要とすると思います。
-
- すごろく認定
- 上記のような「出来過ぎストーリー」に陥ってしまうのは、事実認定において結論の妥当性の検討が十分になされていないことに原因があるように思います。 結論の妥当性を検討することは、事実認定では不可欠の基本的思考です。認定しようとする事実がその先でどのような帰結(世界像)を導くのかをちくいち検討することは、初歩的かつ基本的なことであると思います。 しかし、事実認定に疑問のある判決の多くは、結論の妥当性の重要性を理解していないように見えます。それどころか、「正しい前提が導いたのであるから、その帰結も正しい。」というところで思考を終えてしまい、その先の検討をまったくしていないようにも見えます。
- とくに要件事実論を過剰に重視しているように思われる判決においてはこの傾向が窺われます。もとより要件事実論は事実認定のための理論ではないと思われるのですが、事案全体のなかからまず要件事実とされる部分に着目してその部分のみの事実認定を先行しようとして、それが自由心証主義でできなければ深く検討せずに直ちに証明責任を適用して、まず要件事実とされる部分を確定させ、これにつじつまが合うようにそれ以外の部分を順次認定していくという、泥縄式(行き当たりばったり)に見える認定はまれに見かけます。この事実認定のやり方は要件事実論の枠組みをはみ出しているように思います。 私はこれを「すごろく認定」と呼んでいます。サイコロを振ってすごろくのように前に進んでいくだけの認定です。証明責任とは真偽不明に陥っても結論を決めなければならない立場にある裁判官に与えられた伝家の宝刀で、証明責任に頼ることは自由心証主義のもとでの理性による合理的な認定をあきらめて、証明責任という「サイコロ勝負」に結果を委ねることを意味します。このサイコロ勝負を局所的に繰り返して事実認定を泥縄式にしていくやり方は、まさに「すごろく認定」というべきものであると思います。 事実認定がすごろく式にならないようにするために、認定しようとしている事実の一つ一つについて、事案の全体像と整合するかどうか、その認定がどのような帰結を導くのか(その帰結は不合理とはならないか)を逐一検討することは基本的なことであると思います。
- 背理法について 以上の検討は、背理法が関係します。背理法は例えば「√2が有理数ではない」を証明するために「√2が有理数である」と仮定して検討するときに用いられたりします。簡単な例では以下のようになります。 <命題:クモは昆虫ではない、を証明せよ> ①「クモは昆虫である」か「クモは昆虫でない」のいずれかである。 ②「クモは昆虫である」と仮定する。昆虫は足が6本である。よって、クモの足は6本である。 ③ クモは足が8本あるので仮定②は誤りである。 ④ ゆえに「クモは昆虫ではない」が正しい。 背理法は、以下の手順を踏みます。 <命題:AならばBを証明せよ> ① 「A→B」か「A→B¬」のいずれかである(排中律)。 * 「→」は「ならば」、「¬」は「ではない(否定)」です。 ② 「A→B¬」と仮定して、矛盾を示す。 ③ ②より「A→B¬」は誤りである。 ④ ゆえに「A→B」である。 これを本件のような事例にあてはめると、以下のとおりとなります。 <命題:患者Xは詐病ではない、を証明せよ> ① 「Xは詐病である」か「Xは詐病ではない」のいずれかである。 ② 「Xは詐病である」と仮定する。すると、上記の出来過ぎストーリーが必然的に必要となる(必然的帰結)。しかし、これは正しいとは考えられない。 ③ ②より、「Xは詐病である」は誤りである。 ④ ゆえに「Xは詐病ではない」が正しい。
- 背理法とすごろく認定 背理法の話を出したのは、すごろく認定には背理法の視点が欠けているのではないかと考えたからです。つまり上記の②の部分で「Xは詐病である」との仮定が導く帰結の妥当性を検討することは、背理法による検討の過程に位置づけられます。 ただし、よくよく考えてみると背理法という言葉をわざわざ用いるまでもないかも知れません。当事者双方の主張がどのような帰結を導くのかを逐一検討することは当然のことであり、背理法を持ち出すまでもないとも言えそうです。 しかし、事実認定を基礎付け主義的に行う傾向のなかでは、「正しい基礎を積み上げて導かれた結論について妥当性を検討するのは良くない。」という思考に陥る可能性もないとは言えないと思います。背理法は思考の一般原則であり、証明責任に頼った認定をする前に自由心証主義のレベルで必ず検討すべきことがらであると思います。 (2012年3月31日掲載)
 3回鑑定が行われた右上肢左下肢RSD(23.1.26)
3回鑑定が行われた右上肢左下肢RSD(23.1.26)

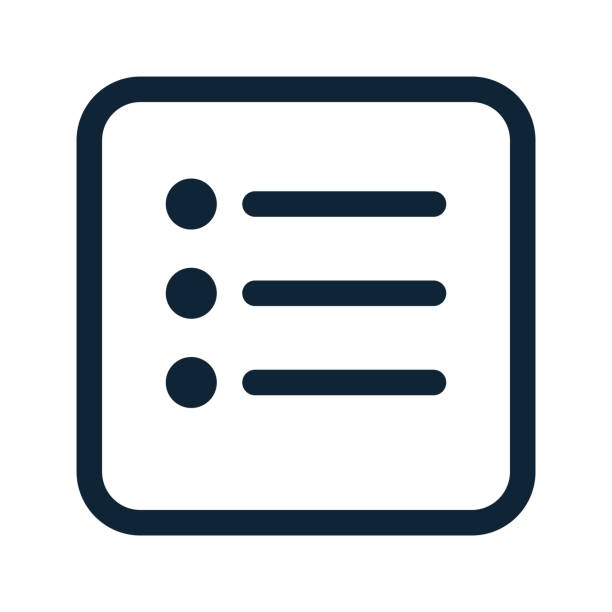 目次へ
目次へ