- 富山地裁平成22年7月15日判決(自保ジャーナル1829号) この事件では、頚髄損傷による後遺症の発生の有無が問題となりました。 本件は、原告の障害等級の大幅な引き下げが注目されているようです。
-
- 本件の概要
- 事故のとき53歳男子の被害者は、事故後1か月半ほどC大学病院に入院し、その後4か月弱D病院に入院し、症状が良くなって退院した後3か月ほど通院したところで症状が悪化して、D病院に再入院して頚椎椎弓形成手術を受けて2か月半後に退院し、その10か月後に再度1か月ほどの入院をしています。
- 原告は、現在は要介護状態にあり、しびれで箸も持てない、ペンを持てても字はかけない、下肢に激痛があるなどの主張をしています。原告は、訴訟前には後遺障害認定への異議申立を経て、障害等級5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当するとされました。このように見ていくと、原告の後遺障害はかなり重いものと思えます。
- しかし、判決では被告側の医学意見をほぼ全部認めて、原告の後遺障害を12級と格段に低くしました。これは原告の詐病を認定したものと言えます。 そこで、私もどのような事件かと思い、さっそく検討しましたが、色々と考えさせられる内容でした。以下に検討します。
-
- MRIのT2強調画像
- 被告は、原告が頚髄損傷を受け、重篤な後遺障害を主張しているにも関わらず、MRIのT2強調画像において頚髄内の輝度変化が認められないなどということはあり得ないと述べます。 本当に輝度変化が描出されていないのか私には確認できませんが、判決はこの前提を事実として認定しています。これは裁判官もMRIの画像を見た上で判断したはずなので、少なくともほとんど変化を確認することができないようなレベルではあったことは、確かでしょう。 たしかに、MRIや頚椎疾患などに関連する医学書には、障害を受けた神経がMRIのT2強調画像で輝度変化により確認できる画像が参考として掲げられています。従って、被告がこの問題を述べたのは、全く理由のないこととは言えないでしょう。
- しかし、問題はこの輝度変化と重症度が相関するかどうかです。証拠に基づく医学では、これは否定されています。例えば、頚椎症性脊髄症診療ガイドライン33頁には、多くの手術例の検討結果から、「MRI上の輝度変化はかならずしも重症度の指標にはなりえないと思われる。」と明記しています。これがガイドライン作成という医学界の一大行事に駆り出されたトップレベルの多人数の医師の検討結果です。 このように輝度変化と重症度の相関関係は、頚椎症性脊髄症においては明確に否定されています。事故による頚椎損傷といっても何らかの頚椎疾患と同様の症状を生じると思われますが、本件の原告の症状が重症化した頚椎症性脊髄症(頚髄症)と類似する面が多いことや、下に述べる事情から、私はこの被害者は事故により頚椎症性脊髄症に類似する状況が生じたのではないかと考えています。もちろんこれは私が判決の検討から得た考えに過ぎません。 いずれにしても、頚椎損傷における輝度変化が常に重症度と相関するというのであれば、そのような主張は誤りというほかないでしょう。 しかし、このような誤解しやすい形で誤った医学的意見を述べる意見書はなかなかの曲者です。医学書は、理系の書物として論理性を重視するので、証明の困難な「~ではない」という否定形の記載はほとんどされないので、被告の主張を否定する部分を探すのに1時間ほど要しました。
-
- 症状の経過
- 原告は、事故の翌日は少し回復して両手、両足の動きが良くなったと自覚して、側臥位で肘をついて上体を起こしてコーヒーを飲んでいて、その翌日には本を持つこともできる状態であったようです。被告は、急性の頚髄損傷患者の場合、最も麻痺がひどいのは受傷翌日であると、批判します。
- 確かに、事故により四肢麻痺を生じるような場合には、直後から最も重い症状が出るので、被告の主張は当てはまるように思います。 しかし、原告の症状の経過が急性の頚髄損傷とは異なるということは、上記の経過のとおりですので、被告の主張は自己矛盾のような感じもします。 被告の主張は、いったん症状が良くなったのに、その後に原告の主張するように重症化するのはおかしいという趣旨でしょう。とすると、その主張は次のものと同じことになります。
-
- いったん症状がよくなったこと
- 原告は、事故の2か月半後にいったん退院する際には、1本杖で歩行できるほどになっていたようです。このようにいったん回復したということが、その後の原告の症状の重症化と相容れないのではないかと被告は主張します。
- 頚椎症性脊髄症(頚髄症)との比較 ここで、原告の症状が頚椎症性脊髄症と類似していることから、頚椎症性脊髄症について検討してみたいと思います。原告が事故による衝撃で頚椎症性脊髄症と同様の状況になった可能性があります。 頚椎症性脊髄症は、男性の発症が女性の2倍で、多くは50代で発症するとされています。加齢による椎間板の変性・狭小化に伴い、靭帯の弛緩や椎体のすべりなどの不安定性を生じ、この不安定性な状況の上での人の活動という動的因子が、静的因子である脊柱管狭窄とあいまって、症状を生じさせるものとされています。 その症状は、四肢のしびれ(上肢のみの場合もある)、手指の巧緻運動障害(箸が不自由、ボタンかけが不自由)、歩行障害などを代表とするものですが、いずれも原告に該当します。 従って、原告が本件事故により何らかの頚椎疾患と同様の状況になり、障害を生じたとすると(何らの頚椎疾患にも全く類似しない症状というのは考えにくいでしょう。)、その何らかの頚椎疾患とは、頚椎症性脊髄症がもっとも良く合うように思います。もちろん、外傷によって生じた症状なので、疾患としての頚椎症性頚髄症の診断はできませんが。
- 頚椎症性脊髄症で特徴的なのは、動的因子が症状に作用することです。症状を生じやすい状況はそれだけでは重症化につながらず、人の活動に伴う頚椎の動きが症状を悪化させる要因になります。 このように、頚椎症性脊髄症の症状は、必ずしも最初が最も重く、次第に症状が良くなるというわけではありません。動きのなかで頚髄の圧迫が悪化するようなことがあれば、症状が悪化します。
- 従って、原告の症状がいったん改善したのち悪化したのも、事故により生じた静的因子や頚椎の不安定な状況がまず存在し、いったん退院したのちに動的因子がこれに作用した結果であると考えれば説明できます。
- 原告が事故により頚椎症性脊髄症と同様の状況になったというのは、私の推測でしかありませんが、静的因子と動的因子の作用する状況は事故によっても生じうるものですので、いったん退院したのちに症状が重症化したことだけを取り出して、不合理とする被告側の主張に対する反例の存在として示すことができます。 また、原告が頚椎椎弓形成手術を受けたことは、私の推測に合致します。この手術は、頚髄圧迫の静的因子や頚椎の不安定な状況を改善するために行われたものではないかと思われます。
-
- 下肢の症状
- 原告は下肢に激痛があると訴えているところ、被告は、頚髄損傷では下肢に痛みは生じないと主張したようです。 これは明確に誤りです。むしろ、頚椎症性脊髄症は下肢にも何らかの症状が出ることの方が多いようです。被告のこの主張は極めて初歩的な誤りですので、本当にこんな初歩的な知識もない医学意見を書いた医師がいるのかと思われるかも知れませんが、訴訟で述べられる医師の意見書ではこのレベルのものは頻繁に見かけます。しかも、その医師の学歴・経歴が華々しいものであることが普通です。
- 医学的なことがらが問題となる交通事故訴訟では、ほとんど全ての場合に被告(損保側)から、原告の主張を否定する医学意見書が提出されます。原告側の主張は、主治医の診断に基づくものですので、素直に考えれば、原告のほぼ全員は実際にも主治医の診断した症状が出ていると考えられます。 しかし、被告から提出される医学意見書のほぼ全部は原告の主張する症状を否定するものとなっています。これらの意見書は、立場上どのような事案でも原告の症状を否定する理屈を述べようとするので、かなり苦しい理屈や荒唐無稽の理屈を述べるものも少なくありません。被告側からは、華やかな経歴を有する医師の名前を冠した意見書が出されることが多いのですが、なぜか内容がそれに合いません。 それでは原告勝訴が大半かというと、そうでもないどころか、被告側の(一部)勝訴例の方が多いと思います。これは訴訟を起こす被害者は、普通の一般人とは異なり、うそをつく悪人が極端に多く、それを見逃す医師も多いということでしょうか。私はそうは思いません。
-
- 筋萎縮の不存在
- 被告は、原告が箸も持てず、字も書けないのに上肢に筋萎縮がないのはおかしいと主張します。しかし、私はそんな主張が出ること自体がおかしいと思います。 例えば頚椎症性脊髄症の診断要件には筋萎縮は含まれていません。そもそも筋萎縮を生じる頚椎疾患としては、頚椎症性筋萎縮症という分類が特に設けられています。『脊椎脊髄ジャーナル』22巻10号(09年10月号)でこの疾患の特集をしています。
- しかし、腕を動かせないとか、動かせる範囲が狭いという患者の事件では、損保側は筋萎縮がないという主張をよくしてきます。たしかに骨折してギプスで腕を固定したあとに、数が月後に腕が細くなっているということは一般人の知識としてあるでしょうし、ギプスをはめなくとも腕がほとんど動かせないのなら筋肉が落ちて腕が細くなるはずだ、というのは一般人の感覚にも合うものでしょう。 しかし、ギプスで長期間固定するような状況でないと、筋萎縮が確実に生じるとは言えません。腕を動かせずにいつも下げたままの状態が続くと、逆にうっ血して腕がむくんだりして太くなることがあります。 例えば、上肢のRSDの重症化事案では、腕の動かせる範囲が極端に狭くなることがありますが、それでもRSDの特徴を10個あてはめるギボンズの診断基準にさえ、筋萎縮は含まれていません。RSDでも筋萎縮が生じる場合がありますが、大抵は生じないか、むしろうっ血でむくんで太くなるので、筋萎縮(腕が細くなる)という要件がないことは当然でしょう。医学書のRSD患者の写真は、腫脹ないしうっ血で太く腫れあがった患者の上肢が写っているものがほぼ全部です。動かせないので筋力は低下しているはずですが、ほとんどの患者さんは逆に腕が太くなっているのです。しかし、RSD(CRPS)の事案では被告側から「筋萎縮がないのはおかしい。」との主張が出るのが通例ではないかと思います。
-
- 上肢の腱反射、圧迫所見との適合
- 被告は原告の上肢の腱反射が原告の主張する症状に合わないと主張します。これとあわせて、原告にMRI上、圧迫所見が認められるのは、5/6、6/7椎間板の高さであり、原告の主張する症状とは合わず、原告の主張は、神経学の常識に反し、完全に説明困難な所見であると、声高々に主張しています。
- 腱反射については面倒なので省略します。圧迫所見との整合性はいやらしい主張ですね。たしかに、椎間板の圧迫所見との整合性の主張は、ヘルニアなどではよく見かけます。そのようなときであれば、相当程度は重視されて良いとは思います。この類推で考えれば、それ以外の頚椎疾患でも椎間板の圧迫所見との整合を要求するのは、もっともらしく見えます。 しかし、例えば頚椎症性脊髄症では、神経学所見からの高位診断の確定は、エビデンスレベルではできなかったようであり、ある程度のものであれば可能とされているにすぎません(『頚椎症性脊髄症診療ガイドライン』31頁)。 しかも、ヘルニアのときのような対応と異なり、個人差や高位のずれもかなりあるようです。ということなので、圧迫所見との整合性を強く主張することはできそうにないですね。
-
- その他に気になったこと
- 頚椎椎弓形成手術 原告は、事故の約10か月後に頚椎椎弓形成手術を受けていますが、判決はこの手術は、既存の5/6、6/7頚椎間の頚髄圧迫に対するもので、この圧迫は本件事故により生じたものとは言えず、手術自体が、今後の圧迫を防止するという意義があるに過ぎないと述べます。これは、被告側の医学意見書に従った見解でしょう。 この理屈によると、原告は本件事故がなくとも手術を必要とする頚髄の圧迫があったこととなりますが、私はそのようには思えません。原告は本件事故の前にはなんらの症状も出ていなかったようですので、本件事故と関係がないというのは、かなり苦しい理屈であると思います。 首の手術をすることは大変に勇気のいることで、かなり重い症状が出ている方でも怖くて手術に踏み切れないという人は多いと思います。私もそのような方の事件を受けたことがあります。全身麻酔をかけられて自発呼吸が停止した状況で、頚部の神経のすぐ近くで技巧を要する手術がされるのですから、普通の人なら重い症状が出ていても最後まで手術は避けたいと思うでしょう。 本件では、頚椎椎弓形成手術を受けたことから、本当に重大な症状が出ていたのだろうという推測が強く働くと思います。
- 詐病を疑うこと 判決は、原告の詐病を疑い、かなり極端な判断に走っています。しかし、実質詐病と認定した判決の結論が極端な方向に向うことはよくあります。なにしろ、被害者の主張がウソということは、理屈の上では被害者は詐欺をしていることになるわけですから。 しかし、患者本人をじかに触って診断した多くの医師の診断書よりも、本人と会ってもいない人の意見書を信じることには、慎重になるべきであると思います。 普通に考えれば、主治医がわざとウソの診断をするわけはなく、ウソの診断をすると犯罪となります。これに対して、損保側の医学意見書にはその立場上常に原告の症状を否定する結論が書かれています。しかも、ただの私文書なので内容がウソでもそれだけでは犯罪となりません。この状況で両者を対等に比較するところから検討するというのもおかしな話だと思います。
- 詐病を主張するということ 裁判では、被告側は原告の主張に反論するのが常です。しかし、本件のように被害者が重症の事件で、これほどまでの主張をしなければならない理由はあったのでしょうか。 あくまでも一般論ですが、被告側は、原告側の主張に反論する権利がありますが、ウソの主張をする権利まではありません。この点に関して、判例の上では不当訴訟の要件が定められています。自らの主張に事実的、法的な根拠がなく、そのことを知りまたは知りうるような場合には、そのような主張は不法行為となります。従って、虚偽と分かっているときには、そのような主張は差し控えるべきでしょう。 本件では、被告側の代理人は私以上に医学的な知見があるようにも見受けられることが気に係ります。 (2010年9月29日掲載)
 頚髄損傷否定判決(22.7.15)
頚髄損傷否定判決(22.7.15)

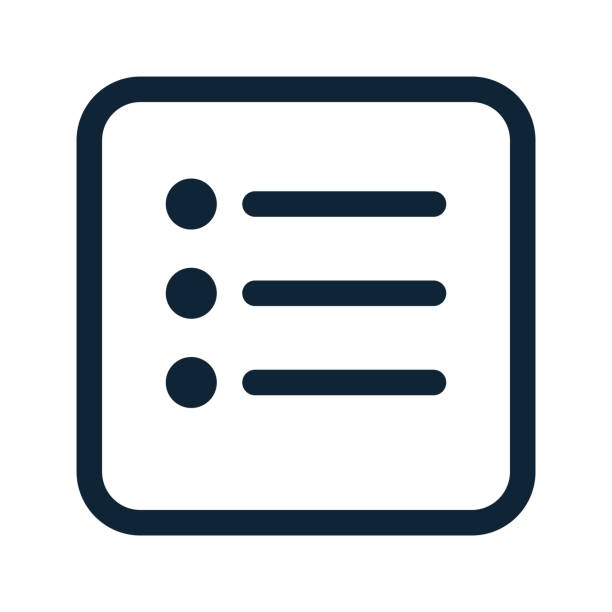 目次へ
目次へ