-
東京地裁平成21年6月23日(交民集42巻3号763頁)
この事件ではカウザルギーが問題となっています。-
カウザルギーとは
カウザルギーはRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)とほぼ同義に使われることもあり、RSDとの区別はややあいまいです。
沿革的には、末梢神経損傷後あるいは神経修復後に生じる難治性の疼痛をカウザルギーと呼び、明らかな神経損傷はないが外傷後カウザルギーと同様の疼痛と自律神経症状を呈する難治性疾患をRSDと呼んで区別してきたとされています(『臨床医のための末梢神経損傷・障害の治療』168頁)。
国際疼痛学会(IASP)は、86年に主要な(末梢)神経の損傷の有無で、損傷があるものをカウザルギー、ないものをRSDと区別することを提唱しました。その後94年にCRPS(複合性局所疼痛症候群)という病名を提唱し、神経損傷の有無による上記の区別を前提にCRPSタイプ1にRSD、CRPSのタイプ2にカウザルギーを位置づけました。 -
臨床での診断名について
CRPSの概念そのものが分かりにくいことや、「主要な」神経損傷の有無という区別基準が明確とはいい難い面があるようで、その後もCRPSという用語を用いずに、RSDやカウザルギーという用語を使用する医療機関が多く存在します。
そのような医療機関においては、国際疼痛学会の定めたRSDとカウザルギーの区別基準(主要な神経の損傷がないこと)を必ずしも前提にしているとは限らないようです。
CRPSという用語が普及する以前の医学書を見ても、RSDのなかにカウザルギーを含めてとくにカウザルギーという用語を用いないものとして、例えば『末梢神経損傷診療マニュアル』があります。この分類ではカウザルギーはRSDのなかに含められ、RSDと診断されます。たしかに、両者の症状は多くの面で共通するため、両者を明確に区別することは困難であるようにも思います。
但し、RSDの名称でカウザルギーを含めている例はあっても、カウザルギーの名称でRSDを含めることはないようです。またカウザルギーとの診断がなされた訴訟でRSDのスコアを当てはめたものもないようです。従って、カウザルギーとの診断がなされた場合は、上記の区別に従って主要な神経の損傷が存在することが前提とされていると考えられます。
-
本件で原告がカウザルギーと診断されたのは、筋電図検査により重度の軸索断裂が確認されたこと(被告は否定)が、主要な神経の損傷というカウザルギーの要件に該当すると判断されたようです。
また、事故(平成18年3月20日)から症状固定(同年10月6日)まで7か月弱というのはかなり短く(RSDの事案では3~7年後ということがよくあります)、これも主要な神経の損傷から直ちに症状の発症が起きたということで、カウザルギーの診断名につながったものと考えられます。
-
カウザルギーとは
-
本件では、原告は多くの病院で治療を受けてきましたが、カウザルギーとの診断を下した医師は1名のみ(以下、A医師といいます)です。
RSD(またはカウザルギー)の事案では、多くの病院で治療を受けていく中で、より専門的な病院に通院するようになり、最終的にRSDとの診断を受けるということはしばしば見られる流れです。
しかし、本件では重度の傷病者の治療を多く受け持っている専門病院ではなく、事故の翌日に通院したクリニックのA医師がその後も治療を続けてカウザルギーとの診断を下したという経過があります。
判決では、この点にこだわっているようにも見受けられます。判決からは「並みいる大病院でカウザルギーとの診断を受けてこなかったのに、町のクリニックのA医師だけがカウザルギーと診断した。」というニュアンスが明らかに読み取れます。
ただ、RSDやカウザルギーのような疼痛を特徴とする疾患は、ペインクリニックで治療を受けることが多いことから、ペインクリニックの医師の方が適しているとも言えるので、むしろA医師の専門分野がペインクリニックであったのかどうかが気に係ります。いずれにせよ、この点にこだわりすぎるのは本筋ではないでしょう。 - カウザルギーとの診断をなした根拠となる神経損傷について
-
右腕神経叢不全麻痺
「右腕神経叢不全麻痺」との診断は、A医師のほかに2名の医師が下しています。そのほかにも「右上肢麻痺」との診断を下した医師もいます。従って、多くの医師が右上肢の麻痺を診断したとの事実があります。現実に患者に触れて確認した医師によるこの判断は重視されて良いと思います。
これに対して、被告は、そのような麻痺がないと主張しています。つまり原告には麻痺などないのに、多くの医師が原告の演技に騙されたか原告に迎合したとの主張をしていることになります。 -
筋電図検査(重度の軸索断裂)
では右腕神経叢麻痺の根拠は何でしょうか。原告は、某大学病院での筋電図検査での結果から、右三角筋に随意収縮が認められなかったことから、第5神経根に重度の軸索断裂があると主張したようです。それ以外に神経伝導検査なども受けているはずですが、判決にはこれ以上の引用はありません。 -
意見書
これに対して被告は医師の意見書で、①「筋電図検査では検者が指示しても被検者が力を入れなければ電気反応なしという結果が導かれる。」、②「原告の三角筋を被検筋とした運動神経誘発電位検査では、三角筋の反応が得られ、受傷後5か月間完全麻痺が続いた筋肉より誘発電位が導出することは医学的にありえず、軸索断裂の診断と医学的に矛盾する部分がある。」などと反論したようです。
上記の①は、明確に誤りであるように思えます。筋電図検査は針電極により刺激を与えてこれに対する人体の生理反応を測定することが基本であるので、被検者が力を入れるかどうかに関わらず、同じ生理反応が測定されるはずです。筋電図検査で被検者の対応で差異が生じる、しかも決定的な差異が生じるという筋電図検査の根本原理を否定する内容の主張には、理解し難いものがあります。しかし、このような理解し難い主張を含む意見書は訴訟では頻繁に見かけます。
上記の②も、誤りであるように思えます。そもそも本件は重度の軸裂断裂ではあっても軸索の完全な断裂ではなく部分断裂であって、それが麻痺の原因であるというのが、筋電図検査の結果のはずです。従って、軸索の完全断裂を前提とした主張は本件とは前提が異なるように思われます。軸索に損傷が生じても、神経軸索の自己修復作用によりある程度の修復がなされます。また、別の経路の軸索が形成される場合があります。この場合には神経伝導速度に反映されます。このように重度の神経損傷であっても、神経のつながりが断ち切れていなければ神経を流れる電位の測定ができるのは当然のことのように思われます。
そもそもこの意見書によれば、筋電図検査の結果を読み取った医師の判断がかなり根本的な部分から大きく誤っていることとなり、普段からその検査をもとに治療しているはずなので、意図的に原告の症状を捻じ曲げた検査結果の報告をしないかぎり、そのような誤りは生じないということになりそうですが、それも疑問です。
-
診療情報提供書
上記に続けて、判決では「右上肢麻痺」と診断した別の医師の書いた診療情報提供書を引用しています。そこには「右上肢は僧帽筋以下麻痺を呈しておりますが、おそらくすべての筋は収縮があり、また、上肢の反射はBRD以外はやや亢進しております。少なくとも肩、肘屈曲、手指の屈曲伸展は効いており、“重度の軸索断裂”(原文は英語)以上の麻痺はないと判断します。このまま回復するものと考えます。」と書かれています。
これは「重度の軸索断裂」が神経の完全な断裂ではないということを当然の前提にしており、意見書とは前提が根本的に異なるのですが、判決は意見書の補強としてこれを引用しています。
判決ではこれを患者の詐病(僧帽筋以下の麻痺)を、患者が見ることのない医師どうしの連絡書である診療情報提供書で他の医師に「本当はすべての筋の収縮があり、麻痺は限定的で、回復見込みである。」とひそかに伝えていたというニュアンスで読み取ったようです。
しかし、診療情報提供書で書かれているのは、「重度の軸索断裂による麻痺が広範囲に生じているけれども、筋の収縮は失われていないことなどから、重度の軸索断裂以上のものではなく、(神経の自己再生機能やリハビリなどにより)このまま徐々に回復するであろう。」という見込みを記載したものにすぎません。
判決のように患者に内緒で患者の詐病を伝え合っていたという謀略的な見方は、その発想からして疑問です。謀略的な見方には、ある種の魔力のようなものがあります。哲学的にも懐疑論のほとんどは論破不能です。懐疑論は避けるしか方法がありません。被告側が詐病を前提とする主張を繰り出したときに、懐疑論の魔力に誘われ、その罠に気付かないうちに懐疑論に囚われる危険があります。
-
以上のとおり、私は筋電図検査によって重度の軸索断裂が確認されたという結果は、肯定してよいと思います。多くの医師がその患者の患部に触れて検査をして、その上で「右腕神経叢不全麻痺」と診断したという事実もこれを裏付けます。もちろん、これは判決を読んだだけの意見にすぎませんが。
これに対して、筋電図検査の読み取りが根本的に誤っていた。その根本的に誤った読み取りをした医師もその診断は本意ではなく、何らかの圧力があったのであろう。右上肢麻痺と診断した他の医師もその診断は本意ではなかったので、患者が見ていないところでは患者の詐病を他の医師に伝えていた。そのほかの「右腕神経叢不全麻痺」の診断をした医師たちはこぞって患者の演技に騙されたか、圧力に屈したに違いない。というような謀略を連鎖的に多発させる見方には賛成できません。結局のところ、このような見方は一つの謀略史観を成立させるために、これに反する事情を全て「やらせ」ないし捏造であるとしているというのが、冷静な見方でしょう。
人間には自分が信じたいと思う仮説に有利な証拠には価値があるように見え、不利な証拠には価値のないように見える傾向があります。これは「確証バイアス」と呼ばれるものです。専門家であってもバイアスから逃れることは困難で、むしろ専門家は専門概念をその有効範囲を超えて重視する傾向に陥りやすいとも言えます。
本件の事実認定は、哲学的には「オッカムの剃刀」の事例ともいえます。オッカムの剃刀とは、簡単にいうとより単純な理屈で説明できるのであればそちらの方が優れた理屈であるというものです。本件に即していえば、1点にこだわって多くの事実に変更を加えて説明するよりも、その1点に変更を加えて他の事実に変更を加えない説明の方が、説明の仕方そのものが優れていると言えます。本件では「詐病」という1点に合わせて、これに反する医師の診断や検査、診療情報報告書などの多数の証拠を本来の意味から読み替える説明と、「詐病」を否定して、これらの読み替えをしない説明の優劣が問われます。
-
右腕神経叢不全麻痺
- 左上肢のカウザルギー
-
既往症
この事件の原告は、平成元年の交通事故で、左上肢にもカウザルギーを有しています。しかもこの後遺障害は右側より格段に重いようです。
判決には、左上肢の激痛に苦しみ18回にわたる手術を受けたことが記されています。しかも、手術では疼痛はある程度低減したようですが、左腕の機能が低下し、肩、肘の関節はほとんど動かず、手関節が少し動き、指は小指などにはほとんど力が入らないようです。これはRSDやカウザルギーが重症化した典型です。 -
矛盾?
判決はこの事情についても、疑問を述べています。即ち、原告の左手の握力が22~26キロと測定されているではないかとして、上記とはかなりの径庭があると述べています。
しかし、判決の引用する原告の左上肢の障害のなかには、握力が記載されていないので、これが矛盾と言い切れるかは、やや疑問です。判決に記載のある部分からは、左手の握力がかなり低下して、薬指、小指はほとんど力が入らないことが読み取れますが、それ以外の指には一定の力が伝わることが読み取れます。
原告の様子を隠し撮りしたビデオにも原告が左腕を動かすところは写っていないようですので、判決からはこの握力以外に原告の左側の症状を疑う根拠はないようです。
-
18回の手術
原告は18回の手術をしたということですが、それは左腕の激痛を低減するために神経や神経腫などを切り取る手術などをしたと推測できます。回数が多いのは、激痛が治まらなかったことと上肢の拘縮が進行していったからでしょう。そのような日常的な激痛と手術の繰り返しのなかで何らかの精神的な問題が生じたことが、その事件で3割の心因的素因を認めたことにつながったのでしょう。日常的な激痛の持続はうつなどの症状を引き起こすことが多いようです。
問題はこの先です。このような手術は当然に全身麻酔のもとで行われます。従って、執刀した医師は原告の左上肢の関節拘縮を確認できます。健康な腕は少しの力で簡単に動かせますが、関節拘縮が生じている腕は少しの力では容易には動かないので、医師はその状況を当然に見たはずです。そうでなければ手術はしません。患者が全身麻酔で無意識にある間にこのような関節拘縮を確認したことが原告の後遺障害認定の裏付になります。
原告が、左上肢の各関節に関節拘縮を訴えているのに、手術のときは関節に拘縮がなく、健康な腕と同じように少しの力で腕の各関節が動かせたのであれば、すぐそのウソはばれてしまいます。事故は平成元年であるのに対して、症状固定は平成8年です。18回もの手術を繰り返す間に関節拘縮は進行していったはずなので、手術の際に関節拘縮が確認されなかったということはありえません。
従って、原告の左上肢の後遺障害は確実なものとして信用できます。
-
既往症
-
特別調査
-
判決は特別調査の結果を引用しています。
原告は左腕が使えないので、右腕だけで車を運転していたところ、その様子を被告側がビデオ撮影して証拠として提出したようです。左腕が使えないので、右腕を使って車を運転するのはやむを得ないことのようにも思えますが、判決は、その様子は原告の訴える症状と合わないと述べます。
-
しかし、判決が記載している内容は、いずれも原告の申告している可動域を超えていないようであり、判決も原告の主張する可動域を超えているとは記載していません。
判決は、制限された可動域の限界まで腕を水平に上げて、ハンドルを回していて、「その動作がいずれもごく自然に行われている。」ことが、原告の主張との矛盾点であるとの趣旨を述べます。右上肢の麻痺があれば、このような自然な動きはできないはずであるとの意味でしょう。
-
この点は、そのビデオを見ていない私としては、評価に苦しみますが、可動域が原告の主張を超えていないのであれば、この点では明確な矛盾はないと思います。
動作が自然であるから「麻痺」というのはおかしい、矛盾しているという判決の言い分もある程度合理性がありますが、原告は右腕1本で生活して食事や着替え、入浴、用便など全てをこなしてきたということに思い至れば、動作が自然だということを決定打にすることは性急に過ぎるように思えます。
-
判決は特別調査の結果を引用しています。
-
カウザルギーの存否
それでは、原告の主張する右上肢のカウザルギーの存在は肯定できるでしょうか。まず、私は筋電図検査の結果から重度の軸索断裂は肯定してよいと思います。従って、これによる上肢の麻痺も説明できます。
重度の軸索断裂、即ち神経の損傷が疼痛を生じることは当たり前のことですが、この神経の損傷がカウザルギーに至るという経過も、医学的には問題はないでしょう。
従って、杓子定規に前提を積み上げていけば、原告の主張は正しいということになります。これを否定する根拠は、「原告は虚偽の症状を申立てている」という方向からしかありませんが、明確に矛盾する行動は確認されていないようです。
-
本件で気になる点
本件でカウザルギーと認定することにまったく支障がないのかといえば、色々と気にかかることがあります。
-
カウザルギーと認定したのが、町のクリニックだけであり、原告の通院した大学病院などではその診断を受けていないことは、やはり気にかかります。
しかし、上で検討したとおり、筋電図検査により重大な軸索損傷という神経の損傷があり、多数の医師が現に原告の患部に触れて麻痺と診断したこと、神経の損傷に対応する疼痛は当然に生じること、神経の損傷が大きい場合にはカウザルギーに発展することは十分にありうることからは、この点にこだわるのは良くないでしょう。この点に拘ると、結局のところ病院の大小という外形だけに囚われた見方になります。
仮に私がこの事件の相談を受けたときは、セカンドオピニオンとして権威のある別の病院にも通院してもらうことを勧めると思います。そこでもカウザルギーとの診断を受ければ証拠が補強されます。裁判では医療機関の権威のようなものは、やはり重要です。しかし、それがないことがカウザルギーを否定する要素になるかといえば、そんなことはありません。肯定する理由が増えるかどうかの問題です。
-
特別調査のビデオの件も気にかかるところです。重度の障害を有しているはずの原告が障害のある右腕だけで車を運転していた(おそらく普段からよく運転をしていたのではないかと思われます)というのでは、その障害はそれほどのものではないような気もします。
しかし、私のかつて担当した事件でも70歳半ばの老人が事故による右肩腱板断裂という障害のため、右腕を上げた状態に保てず、食事のときも肘をテーブルに置いて支点にしていたという状況にありながら、事故以前からの毎日のランニングを続けていたということがあります。
重い障害があっても身体の限界まで活発に動き回る方は多くいるのではないかと思います。パラリンピックに出場される方やそれを目指している方などはその典型でしょう。
このように考えていくと、このビデオの件も「障害者は家でおとなしくしているのが似合っている。」というように、活動的な障害者の姿を否定的にとらえようとするバイアスが基盤となり、その上にある視点からのみ原告の障害の否定が正当化されるという面は否定できません。
-
本件では、事故が原告の主張するような障害を生み出すほどの重大な事故とは思えないことも気にかかります。本件の事故が神経に重大な損傷を及ぼすほどの衝撃が加わったとは考えられないという見方はたしかに説得的です。
しかし、上に見たように、神経の損傷そのものは否定できません。それがこの事故とは無関係に生じた可能性があるかといえば、神経の損傷の規模から見て、事故前に別の原因で生じていて原告がこれを我慢し続けていたというような見方は謀略的に過ぎ、不自然でしょう。
本件事故後に別の原因で神経の損傷が生じたとする可能性も検討する必要がありますが、原告が本件事故後の早期から多くの病院で治療を受けていたということからは、かなり可能性が低いようです。
速度の遅い衝突であっても、そのときに原告が何かにつかまって右手で体を支えようとしたりして、右手が牽引されて神経の損傷が生じた可能性は否定できません。原告のように左腕に大きな障害がある場合には、体のバランスを上手くとれずに右腕に大きな負荷が加わった可能性もあります。
たしかに「普通の人ならこんな怪我をしなかった。」という感覚は重要ですが、現に怪我をした人にそれを言っても仕方のないことです。軽い接触でもバランスを崩して転び、偶然そこに石があり、後頭部に当たって打ち所が悪くて亡くなるということもあり得ますが、この場合に「普通なら」を持ち出すのはナンセンスでしょう。「いかなる状況を想定しても、この怪我はあり得ない。」と断言できるのであれば別ですが、本件ではそこまで言い切れません。
以前テレビで、衝突実験のテストドライバーでかなり頑丈そうに見えたアメリカ人が「時速12キロの衝突実験では首がもげるような思いをしたよ。」と言っていたのを見たことがありますが、低速度でも壁などにぶつかったときの衝撃は我々の想像をはるかに上回るものかもしれません。
- 原告がすでに左腕により重い同種障害を有しているということも気にかかる事情です。しかし、よくよく考えてみると、気にかかるということ以上のことは言えない事情でもあります。「前の事件で味をしめて~」というのは、謀略的な見方なので、良くないでしょう。
-
以上のほかにも、気にかかる点はあります。なぜA医師の勤務先が原告の自宅近くに変わったのだろうかとか、A医師が原告に協力的過ぎるとか、判決がニュアンスとしてにじみ出している事情は色々とあります。
訴訟事件を多く扱うと、人は懐疑的になります。理屈の上でも、対立する証人の一方はウソを言っているという事件がほぼ全部ですから、人はウソをつくものだという見方が染み付いていきます。
この方向に突き進んでいくと、疑うことが知性の証(あかし)であり、ウソを暴くことが知性の勝利であり、人をすぐに信じる朴訥な人間はバカであるという価値観に行きつきます。RSDなどに関連する判例を見ていくと、このような価値観のにじみ出る判決を多く見かけます。悲しいことですね。
疑うに足りる証拠もなく、疑うことから始めてしまっては、懐疑論の罠にはまってしまいます。どのような事件であっても疑いに合わせて事情を再構成すれば、全ての事情が論理矛盾なく説明できます。そこに懐疑論の罠があります。
しかし、素直に考えれば、患者のうちウソの症状を訴えるのは1割以下でしょう。しかし、RSDやカウザルギーの訴訟では患者の半数以上がウソを言っていると判断されてしまっているのが、今の司法の現状です。
-
根本的な問題として、我々は他人の痛みそのものを知りえないという原理的な問題があります。他人の脳と自分の脳をコンセントのようなものでつないで他人の痛みそのものを知ることはできません。
他人が痛がっていても、それが本当なのかウソなのか知ることはできません。サッカー選手はひどく痛がって転げまわっていても、相手にカードが出たとたんに元気にフィールドを駆け回ります。他人の痛みが本当かウソか見分けることは困難です。この点を疑いだしてそのまま突き進んでいくと、懐疑論の魔力に飲み込まれてしまいます。「他人の痛み」はまさに有名な懐疑論そのものです。
本件では、重大な軸索断裂という神経の損傷があるので、その程度においては痛みが存在することは肯定できます。それがカウザルギーという特殊な痛みの状況にまで至ったのかについては、原理的に知りえないことといわざるを得ません。痛みそのものを測定する医学的検査はありません。
しかし、それゆえに常にその痛みを否定して、その先の痛みの訴えはウソであると考えるのは、ちょっとおかしいですね。本件のように重大な神経の損傷という裏づけがちゃんとある場合には、その先の痛みについても否定するよりも肯定する方が真実に近いと思います。
(2010年9月25日掲載)
-
カウザルギーと認定したのが、町のクリニックだけであり、原告の通院した大学病院などではその診断を受けていないことは、やはり気にかかります。
 右上肢カウザルギーの否定(21.6.23)
右上肢カウザルギーの否定(21.6.23)

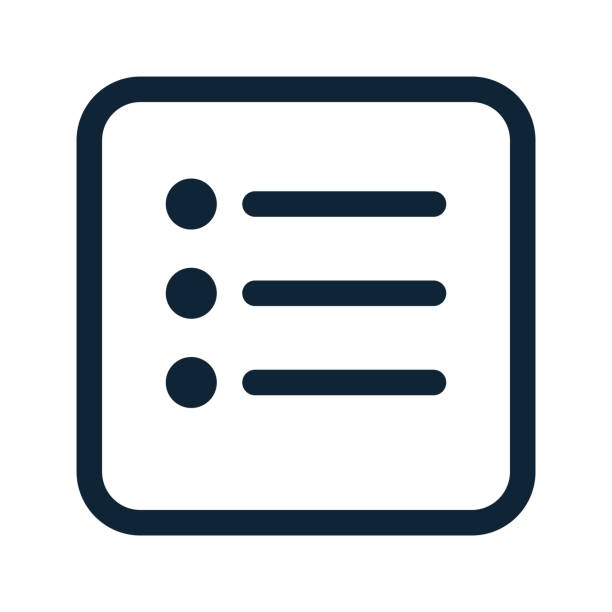 目次へ
目次へ