- 東京地裁平成20年5月21日判決(交民集41巻3号630頁) この事件では、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)が問題となっています。この事件では、被害者側が各種のRSDの診断基準に当てはまることを主張し、裁判所もRSDについていかなる診断基準を採用すべきかについて検討しています。 結論としては、裁判所は被害者がRSDにり患していることを認めました。その結論は私も正しいと思います。損害額の算定はやや低いようにも思いますが、納得できる範囲内です。但し、そこに至る過程において、気になる点がいくつかありましたので、以下に述べます。
- CRPSとRSD
- この事件では、国際疼痛学会がCRPS(複合性局所疼痛症候群)という概念のもとにRSDとカウザルギーを統合したのちもCRPSという病名を用いず、RSDという病名のみを用いています。 その上で、RSDの診断基準として、Gibbonsスコア、Kelmerの基準、Komanの基準、MackinnonとDellonの基準などに言及しています。 CRPSとの病名のもとで判断することになると、上記の基準ではなく、CRPSの診断基準を用いることになるはずです。ところが国際疼痛学会のCRPSの診断基準は、RSDのものに比べると、基準としての具体性が乏しいように見えるので、少なくとも裁判での判断には適していないように見えます。 仮に非典型的なRSDであった場合には、ギボンスのような基準はむしろ有害でCRPSの診断基準のような大まかなものの方が診断に適しているのですが、本件のような典型的なRSD(上肢に特殊な痛みが生じてそれが発展して関節拘縮が上肢全体に及ぶ)の場合には、以前からのRSDの基準の方が判断しやすいという面は否定できないと思います。この訴訟でも原告はRSDとして主張し、裁判所もRSDとして対応して、認定しています。
- しかし、私は、CRPSのタイプ1としてRSDを位置づけた上で、CRPSの基準を主として用いるべきで、かつてのRSDの診断基準は補助的に用いるべきであると思います。 その一番の理由は、かつてのRSDの基準は、適用対象としている「典型的なRSD」の実態把握が実は不正確であるという点にあります。すなわち、かつての基準が作られた時期には今のように臨床の多数の症例報告を積み上げて統計的に検討すること(証拠に基づく医学)が十分になされておらず、最近の報告のなかで以前の考えが否定されているからです。 例えば、病期に従って数か月ごとに症状が進行するというかつての考えは臨床の上では確認されておらず、否定されています。また、骨萎縮も臨床の上では重度のものは少なく、軽度もしくは存在しないものの方が多いとの報告もあり、これに対抗する報告には接していません。 このように最近の証拠に基づく医学の潮流の中では、かつてのステレオタイプ化した理解は有害である場合もあり、交感神経障害としてRSDを考えていた従前の枠組みに収まらない非典型的なRSDが多く報告されたこともあってCRPSという概念が導入されたという経緯からは、CRPSの診断基準を優先的に用いるべきです。 CRPSの診断基準は最近では細かくなってきたので、裁判でも十分に使用できるものになっています。
- RSDの診断基準について
- 骨萎縮 上記のとおり、かつてのRSDの診断基準に関しては、問題が含まれており、その問題は本件においても顕在化しています。 本件では、被害者に骨萎縮が確認されていますが、相手側はこの骨萎縮が軽度に過ぎないと反論しています。実際にも骨萎縮は軽度であったようです。但し、裁判所はこの点にはこだわらずに、RSDとの認定をしています。 なお、自賠責保険の上でのRSDの認定要件としては、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化が定められています(青い本22版317頁)。そこで、損保側は骨萎縮が軽度もしくは存在しないという主張をしてくるのが通常です。なお自賠責保険の認定基準がなぜ作成時の医学的な知見とかけ離れているのか、理解に苦しみます。
- 筋萎縮 RSDは本来的に筋萎縮とは関係しません。むしろ医学書にあるRSD患者の写真は上肢があきらかにむくんでいて太くなっています。一般的にはこれがRSDの特徴とされており、腕が細くなる(筋萎縮)というのはこれとはまったく逆の現象です。筋萎縮であれば目に見えて腕が細くなるはずですが、そのようなRSD患者はかなりの少数派のようです。 しかし、RSDが進行していけば関節の可動域が狭くなり、これに伴い筋肉が少なくなっていくはずで、筋萎縮が生じるようにも思えます。実際にもRSDについて述べた医学書の一部には筋萎縮が生じる場合があると述べています。 このようにRSDの進行に伴い筋肉が少なくなることは、理論上は十分にありうることなのですが、現実のRSD患者の現状は上記のとおり、腕がむくんで太くなるという明確な特徴を示しています。従って、RSDの診断基準に筋萎縮を含ませるのは、明らかな誤りというほかありません。実際にもギボンズのRSDスコアにさえも筋萎縮は含まれていません。 しかし、ほぼ全てのRSD患者に明らかな筋萎縮は生じていないので、訴訟の上では損保側は「そこまで腕が動かせないなら筋萎縮が生じるはずである。」との主張をしてくるのが通常です。 本件では、裁判所はRSDの該当性判断のなかで筋萎縮も重視すべきものとして列挙していますが、おそらくは「腕が動かせないのなら筋萎縮が生じるはずである。」との素人判断で損保側の主張を受け入れてしまったのではないかと思います。但し、この判決では筋萎縮の該当性の判断をせずに、RSDとの認定をしていますので、渡りかけた危ない橋をなんとか回避しています。
- 関節拘縮
- この判決では、被害者の関節拘縮の程度を細かく引用していますが、その数値をそれ自体として重要な証拠としては扱っていないようです。しかし、医師が患者に触れて関節の拘縮を何回も確認したにも関わらず、これを軽視する理由が良く分かりません。 おそらくは、関節の可動域制限は被害者が意識的に力を入れればごまかせるという考えが根底にあると思いますが、普通の医師が患者の上肢の関節拘縮と詐病を見誤ることはあり得ないと思います。裁判では、画像などを重視して医師の徒手検査をことさらに低く見る傾向がありますが、これは根本的に誤っているというほかありません。
- 関節拘縮は、関節部近辺の組織が癒着して伸縮性がなくなったことによるものであるので、患者が力を入れてこの状況をごまかすことはまず不可能です。自称患者がごまかそうとしても医師がこれを見落とすことは、普通ではあり得ません。例えるなら、10分間自由に触れてもぬいぐるみの猫と本物の猫を区別できないと考えるようなものです。 従って、私は医師が徒手検査で確認した関節拘縮の結果から、直ちに関節拘縮を認定すべきであり、これが当たり前のことであると思います。
- この判決は、関節拘縮について医師の判断を重視せず、客観的なものを探そうとする危ない道に進みましたが、なんとかRSDを肯定する認定に至っています。 関節拘縮について画像レベルと同視できる客観的な証拠は、普通は存在しません。関節拘縮を測定する検査が可動域検査であって、これ以外の検査はないので、これは当然のことでしょう。 但し、患者に全身麻酔をかけて可動域を測定して、その状況を撮影するという裁判のためのみの特殊な方法があります。私の知る限りこれをしたのは私だけですが、これは裁判所が患者だけではなく医師の徒手検査をも信用しないという異常な状況でのみ要求されるものです。患者の負担を考えれば、望ましい方法とはとても言えません。
- 重複神経障害(ダブルクラッシュ症候群)
- 本件の事実の流れを見ていくと、これは重複神経障害(ダブルクラッシュ症候群)の事例ではないかとも思えます。重複神経障害とは、抹消部での神経障害に起因して他の部位にも神経障害が波及していくというもので、現在では医学的に問題なく認められている理論です。
- 右拇指(事故直後) 被害者は、事故直後には右拇指の痛みが強く出ています。その理由について、自転車から転んで転倒する際に親指のみがハンドルに残った状態になり、親指が不自然に大きく広がった状態になった(スキーヤーズサム)としています。被害者が親指の痛みのために左手だけで自転車を押して自宅まで歩いたと述べています。これは右拇指の神経の損傷ではなく、靭帯の損傷を疑う話です。 その後も右拇指の痛みが治まらずに被害者は通院を続け、事故2か月後に靭帯再建の手術を受けますが、それでも症状は良くなりません。
- 右手首(1~2か月後) 被害者は、事故約3か月後には右拇指のみではなく右手首に痛みが波及し、右手関節の屈曲痛を訴えています。被害者自身は靭帯の手術以前から手関節の痛みがあったと主張していますが、判決は証拠がないとして認めませんでした。私は、被害者の主張を否定する理由はないと考えます。 むしろ、証拠がないという理由でこれを否定すること自体が根本的に誤っていると思います。自由心証主義による認定が尽きる前に、証明責任を前面に出すことにより、自由心証主義を放棄した形式となっているこの判決の書き方には疑問を感じます。
- 右肩関節(8か月後) 事故8か月後には被害者は、右肩関節に痛みを訴えるようになり、右手や右肩の関節が動かせなくなっていきます。これは「動かすと痛みが生じるので動かさない。」というRSD患者に良く見られる症状です。 無理をして動かすとその反動の痛みがさらに強くなるので、動かさないという選択肢しか残らないのですが、この状況が続くと関節の可動域が狭くなっていきます。この状況が続くなかで関節部の組織が癒着して関節が動かせなくなって行きます。RSD患者の関節可動域の制限はこのようにして進行していきます。
- 以上のように本件は、抹消部(右拇指)の痛みに端を発したタイプのRSDでRSDの典型の1つに含まれます。 私が気になったのは、右拇指の痛みは手根管症候群によるものではないかということです。手根管症候群であるとすると、右手首の痛みや手首の屈曲による痛み(手根管症候群に特徴的)が説明しやすくなり、右手首(手根管)における神経の障害が重複神経障害として右肩に及んだ流れとして、症状の進行も説明しやすくなります。手根管症候群による神経の損傷はRSDの発症を説明しやすくします。靭帯再建の手術後に症状が治まらなかったこともこの推測を裏付けます。
- 以上は私の推測に過ぎませんが、私がこの事件の相談を受けたのであれば、まず右手首や右肩部の神経について筋電図検査を受けることを勧めます。この部位に神経の障害が確認できれば、RSDが認定されやすくなると思います。 もっともこれは裁判上の証明手段のことで、RSDを発症した状況で筋電図検査を受ける医学的な意味はほとんどないかもしれません。本件でも筋電図検査はなされていないようです。
- 素因 この判決は、素因減額の主張を否定しております。これは正しい判断であると思います。まず、体質的素因については、事故前に「疾患」が存在しないので、判例上は当然に否定すべきものといえます。 問題は心因的素因ですが、特定の精神状態がRSDの発症につながるという医学的な証明は存在しません。RSDの悪化に心因的素因が影響するとの考えも医学的には実証されていません。本件では事故前に精神的な問題が生じていたとの証明もありません。 しかし、RSDの事案では、長引く疼痛と重い後遺障害のためにうつ症状を引き起こす患者が多いために、具体的な因果関係を認定することなく、うつ症状等があることから直接に心因的素因を肯定する判決も少なからずあります。しかし、RSDのように疼痛を特徴とする疾患で、安易に心因的素因を認めることは誤りというほかありません。
- その他
- 本件では、被害者のRSDの主張をほぼ認めた点は良かったと思います。そこに至る経路で多少危ないと思うところもありましたが、おそらくこの裁判官は多少の難点はあっても最終的にはこの結論に持っていくという方向性がしっかりしていたのではないかと思います。
- その理由として考えられるのが、まず東京地裁交通部ということです。交通事故を専門的に担当している中で、損保側は常に被害者の症状を否定することを身をもって知っているので、その対応を重く見ないという素地があります。
- そうなると、加害者側の主張を除外した場合に、被害者の言葉がどれだけ信用できるのかを検討することになりますが、本件では、被害者が54歳で仕事も家庭もある男子であったということを重く見ていたのではないかと思います。このような立場の人がウソの症状を訴えて色々な病院を転々としたり、仕事を減らしたり、訴訟に時間を費やしたりする理由があるとは思えません。 裁判ではこのようなことは軽視されがちですが、本人の述べることが信用できるかどうか、その度合いはどれほどかを考慮することは基本的なことではないかと思います。 このような事情はある程度の数量的な推測も可能であって、本当は事実認定のなかでも重要な地位を占めるはずのものなのですが、現実の裁判の中ではこのような事情は考慮されにくい面があります。裁判ではとかく確実な証拠ばかり求める傾向があります。 (2010年10月11日掲載)
 右上肢RSDの肯定(20.5.21)
右上肢RSDの肯定(20.5.21)

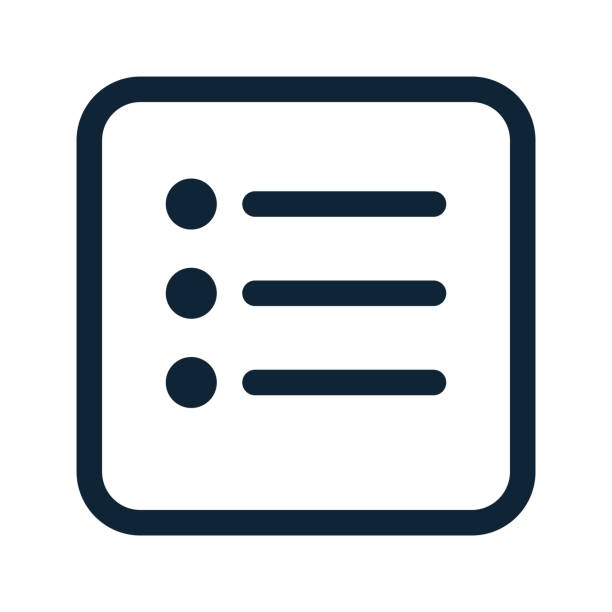 目次へ
目次へ