- 東京地裁平成20年3月18日判決(交民集41巻2号355頁) (自保ジャーナル1747号14頁は抜粋) この事件では、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)、CRPS(複合性局所疼痛症候群)が問題となっています。 被害者は、事故時42歳の有職の主婦で、中国出身で小規模な中華料理店の経営者です。この判決の特徴は自賠責保険のRSDの認定基準を否定して、国際疼痛学会の臨床用基準を用いたことと、CRPS(RSD)と認定しながらも後遺障害は10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい傷害を残すもの)という認定に留まったことです。
- 早期にRSDとの診断を受けたこと
- 被害者は、平成17年7月17日に事故に遭い、同年11月1日には、最初のRSDの診断を受けています。このように約4か月でのRSDとの診断は、かなり早期に診断を受けたものと言えます。 RSD(CRPSタイプⅠ)は、これを確定診断する検査法もなく、各症状のスコアを積み上げる方式で確定診断がなされるため、重症化していない段階では「RSDの疑い」という診断がなされ、確定診断に至らないことが多く見られます。 私の経験や判例の事例では、RSDとの認定を受けるまで1年以上を要することが普通で、3年以上経過した後ということも少なくないと思います。
- 被害者は、事故日(7月17日)からA病院に通院し、10日後(7月27日)にはB大学付属病院に通院を始めています。8月4日からC整形外科に通院し(主治医、11月1日にRSDと診断)、8月26日からDクリニックへの通院を始め、11月11日からはE病院に通院し、12月9日からF病院に通院し、12月16日からG病院に通院し、12月22日からH労災病院(RSDと診断)に通院しています。
- このように色々な病院に次々と通院をしたのは、痛みが酷かったからであると推測できます。RSDによる痛みは、灼熱痛(焼け付くような痛み)やアロディニア(痛覚過敏の酷い状況、風や体の震えでさえも痛みを生じる)という痛みの激化に特徴があります。 痛みが治まらないため、病院を次々と変えて治療を続けるということは、RSD患者ではよくみられます。この事件では、そのペースがかなり急です。
- 治療経過
- 強い痛み RSD(CRPS)にり患すると、患部を動かすと痛みが増すため、患部を動かさない状況が続きます。無理をして動かすとその反動でより強い痛みがさらに続くようです。本件の被害者は、左頚部から左上肢全体にかけて強い疼痛があったようです。
- 神経ブロック 強い痛みに対する普通の治療は神経ブロックです、これは局部への麻酔注射により神経による痛みの連絡を断ち切ろうとするものです。少し古い医学書ではこの神経ブロックにより、RSDの症状が良くなることが多いので積極的に神経ブロックをするべきであるとの記載もありますが、最近の医学書は神経ブロックの効果がない事例も多いという記載もあります。神経ブロックの効果は限定的で、効果のない患者も少なくないというのが現状のようです。 判決では、原告がF病院での星状神経節ブロックによる治療を希望しなかったとあります。星状神経節ブロックは、あおむけになって首に太い注射を打つもので、かなりの恐怖心が生じると聞いたことがあります。この治療を受けなかったのは、そのような事情が影響したのかも知れません。 判決では、どの時点でどの部分に痛みが生じていたと原告が主張しているのかの記載が少ないのですが、疼痛を主とする疾患でこの記載漏れは致命的です。星状神経節ブロックが勧められたということからは、この時点では頚部の痛みが最も大きかったのではないかと思われます。
- 皮膚の変化、腫脹(腫れ) 痛みが生じるとその部位の組織が収縮します。これは収縮により出血を抑え、細菌の侵入を防ぐという自然な生理現象です。RSD(CRPS)では激痛が持続するので患部の組織の収縮がおさまらずに持続し、その結果その部位や周辺部では血流や軸索輸送(神経の栄養分の輸送)の低下が生じます。そうなると患部はうっ血状態になって腫れ上がっていき、皮膚も栄養が不足して低温となり、色も白くなっていき、体毛も薄くなります。これはRSDによる患部の腫脹や皮膚の変化についての一般的な説明です。 本件でも、自発痛や痛覚過敏があり、血管運動障害として皮膚温非対称や、皮膚色変化、皮膚萎縮、腫脹、発汗過多が生じたとあります。
- 関節拘縮 RSD(CRPS)による激痛が続くと、その部分の軟部組織の収縮が持続するため、関節の組織が癒着して伸縮しない状況になり関節が動かせなくなっていくというのが典型的なパターンです。 本件でも、頚部や肩関節に大きな関節拘縮(可動域制限)があり、手関節にも関節拘縮があるとされています。
- RSD、CRPSとの診断
- 原告は17年11月1日にC病院でRSDとの診断を受け、12月22日から通院したH労災病院では、典型的なRSDとまでは言えないが、頚椎捻挫、原因不明の左上肢痛ないし非典型的なRSDとの評価を受けています。 原告は、平成18年2月23日には症状固定とされ、RSDと診断され、4月17日にはI病院からRSD疑いとの診断を受け、平成19年3月から通院したJ病院ではCRPS(国際疼痛学会の臨床基準を満たす)との診断を受けています。
- 自賠責のRSD認定基準 被告は医師の意見書により自賠責保険のRSD認定基準では、①関節拘縮、②骨萎縮、③皮膚の変化の全てが要求されているところ、原告には②骨萎縮がないと主張しています。 RSD患者には骨萎縮は軽度または存在しないものが多いという臨床報告があり、骨萎縮にこだわることは患者の実態に合わないのですが、自賠責の認定基準ではなぜか「明らかな骨萎縮」が必要不可欠な要件とされ、これを要件の1つにさえも入れていない国際疼痛学会や日本の学会の認定基準とは根本的に異なります。 国際疼痛学会や日本の学会の基準でCRPSと認定される患者でも、自賠責の認定基準のように「明らかな骨萎縮」を要求すると、その9割以上がRSD(CRPSタイプ1)ではないとされるおそれがあります。
- 国際疼痛学会の研究目的基準 被告は医師の意見書により、被害者の症状が国際疼痛学会の研究目的基準にも合わないと主張しています。研究目的基準は臨床基準よりも要件が厳しい(感度、特異度の厳格化に応じて項目数が増える)ので、この被害者には該当しにくいようです。 なお、本邦のCRPSの判定指標にも臨床用と研究用がありますが、当てはまる項目が2項目以上(臨床用)か3項目以上(研究用)かで区別されています。 研究用の指標は満たすべき要件が1個増えるだけですが、これにより感度が85%から70%(05年の国際疼痛学会基準の数値)に低下します。感度とは「異常がある患者を検知する検査の能力」を言います。満たすべき要件が増えれば、RSD患者であっても要件を満たさない患者が増えることになるので、感度が低下するという当然の理屈です。 つまり、4主徴のうち2個という要件であってもこれを満たすのはRSD患者群の85%に過ぎないところ、研究用基準で3個の要件を満たすことを要求するとRSD患者群の70%しか捕捉しないこととなります。 どうして感度が低くなる指標を研究用として用いるのかというと、特異度が70%から96%に高くなるからです。特異度とは、「異常がない患者を検知する検査の能力」を言います。研究用指標として特異度が高い指標を用いることにより、「RSD(CRPS)である確実性がより高い患者群」を用いた研究報告が可能となります。 もとより国際疼痛学会の05年の判定指標もわが国の08年の判定指標もあくまでも指標であり、その基準だけでCRPS(RSD)であるかどうかを決めるものではありません。あくまでも指標にすぎません。 このことは4主徴のうち1個しか満たさなくともRSDと診断される患者が存在することや4主徴のうち3個も満たしてもRSDと診断されない患者が存在することを当然の前提としています。 このように判決が診断基準と述べているものは、実際は「指標」であるという基本的な前提が理解できていれば、この判決で述べられている議論は根本的な部分で少しずれたものであると理解できると思います。 なお、国内外の両者の各基準において、筋萎縮は当然のこととして、骨萎縮も判断対象の項目に組み込まれていません。これはCRPSにおいて骨萎縮の発症が必然ではないからです。
- 本件の判決では、国際疼痛学会の臨床基準を用いています。 判決は、「交通事故の被害者の診断において、臨床目的に代えて研究目的の診断基準の適用を論ずることは有益とはいえないことに加え、被害者の迅速な救済のために定型的な基準を必要とする労災ないし自賠責の認定においては、骨萎縮を要件とすることは理解できるものの、訴訟上の判断はそれに拘束されるものではなく」と述べて、J病院の診断を踏襲して国際疼痛学会の臨床基準を使用し、さらにギボンズのRSDスコアにも当てはめています。 研究用の基準を除外することは当然のことですが、骨萎縮を要件とすることは自賠責の認定においてさえも合理性が全くないことをはっきり述べて欲しいところです。
- 障害等級
- 判決は、被害者がCRPSにり患しているとしましたが、その等級は10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)と低く認定しました。即ち、左肩関節の可動域制限だけを後遺症として、それ以外を認めていません。即ち、関節の機能障害のうちの一部だけを後遺障害として認めたにすぎません。
- 上記のとおり、関節拘縮、皮膚の変化、腫脹などが生じるのは、強い痛みの持続が原因であるとするのが、RSD・CRPSでの共通認識ですので、頚部の痛み、肩の痛み、手の痛みを無視してしまっては、CRPSとの認定をしたことと明確に矛盾します。 判決は、被害者にかなり懐疑的な立場から、左肩の極端な可動域制限は信用できてもそこに痛みが生じているのかどうかは確認できないので認めないとしたようであり、「他人の痛みは原理的に知りえない。」ということを最後まで貫徹した形になりましたが、この点はかなり疑問です。 また、頚部の可動域制限や手関節の可動域制限も無視されている点にも疑問があります。頚部の可動域制限は信用できないと考える理由は全くないと思います。 左肩に重大な障害が残っていてそれを治したいと願う患者が、頚部や手のウソの症状を訴えるわけがありません。このような重症の患者で症状の一部についてあえてウソをついて、自らの治療を妨害するような患者は1万人に1人もいないと思います。そのような極めて稀な事情を無条件で前提としている判断には大いに疑問があります。
- 心因的素因 本件の被害者はうつ症状が生じていたようですが、判決は心因的素因となることを否定しました。正しい判断であると思います。 激しい痛みが日常的に続いて、頚部や左上肢に大きな後遺障害を残しているわけですから、普通の人であればうつ病のような症状が出るのが当然とも言えます。 なお、藤村和夫『RSDあるいはCRPSの認定・評価について』(筑波ロージャーナル5号153頁)でも同様に心因的素因の認定には慎重であるべきであるとしています。 (2010年10月22日掲載)
 RPS・RSD肯定事案(20.3.18)
RPS・RSD肯定事案(20.3.18)

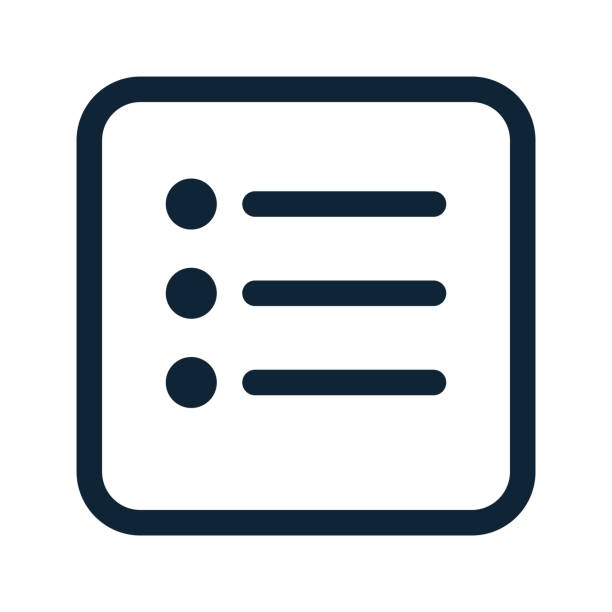 目次へ
目次へ