- 大阪地裁平成21年4月9日判決(交民集42巻2号534頁) この事件では、RSDが問題となっています。 この事件の特徴は、①下肢のRSDであること、②早期(事故4か月後)に左足のRSDが診断され、その後右膝のRSDが後発したこと、③判決が臨床用や研究用のCRPS基準よりも数段厳しい認定基準(二重の絞り)を採用したこと、④判決の認定額が極端に低いこと(既払いとの差額が約121万円)などです。
- 下肢のRSD
- 医学文献に出てくる症例の多くは上肢のRSDで、判決でも上肢のRSDが大半で下肢にRSDが発症する例は上肢に比べて少ないようです(小児CRPSは下肢も多いようですが)。そこで下肢のRSD(CRPSタイプ1)については、まず上肢のRSDと同じ基準で診断してよいのかという問題がまずあります。 この点について私は問題提起をした文献を知りません。通常は上肢も下肢もRSDであるならば、同じ基準を用いるべきであると考えられているようです。CRPSについての国際疼痛学会の基準もわが国の基準も上肢と下肢で区別していません。 従って、原則として上肢も下肢も同じ基準を当てはめるべきことになります。
- ただ下肢の血管や神経の太さや筋肉の量などは上肢とは同じではないので、少し引っかかるところはあります。
- 事故後の経過
- 本件の被害者は、事故時25歳の女性(派遣会社スタッフ)です。平成15年9月24日に自転車に乗っていて事故に遭い、左下腿、左膝などに怪我をします。
- 事故5日後・・・左下腿の鈍痛や左膝内側の圧痛やチクチクする痛み
- 1か月後・・・1本松葉杖で歩行
- 2か月後・・・左大腿内部に痛み。左下腿が下がると拍動性の痛み
- 3か月後・・・左下腿に核のある拍動痛がある。歩き方を誤ると、引き裂かれるような痛みがある。
- 4か月後・・・N大学付属病院で左下肢RSDとの診断を受ける。
- 5か月後・・・右膝の痛みを訴え始める。
- 1年9か月後・・・N大学付属病院で右膝RSDとの診断を受ける。
- 本件では、左下腿RSDや右膝RSDが診断されていますが、足指という末梢部位への症状の波及は述べられていません。上肢であれば、肩の可動域制限が最も重い場合でも手指に症状が出ている事案の方が多いように思います。医学書でも足がRSDでむくんで膨らんだ写真なども載っているので、足でも末梢部に症状が出ることも多いようです。 これに対して、本件では末梢部(足指)に強い症状が出るタイプではないようです。
- RSDの認定基準
- RSD(CRPSタイプ1)は、現在ではCRPSの診断基準のみにより診断されるべきものとされています。従って、RSDの診断基準を当てはめることは、今では医学的には誤りとなります。 医療機関の一部ではかつてのRSDの診断基準がいまだに用いられているようですが、かつての診断基準はそれを裏付ける医学的根拠の集積があまりなされていないことや、各症状に関して臨床での患者群の感度、特異度などとの対応などに欠けるものですので、これを用いることは誤りというほかありません。 従って、本判決がRSDのかつての基準のみを用いたことは、誤りというほかありません。
- 本判決の特徴は、「二重の絞り」という医学基準を超越した非常に厳しい認定基準を用いていることです。すなわち、RSDの4主徴(疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化)と自賠責保険のRSDの3要件である①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化が明らかに認められることの双方が必要としています。 日本のCRPSの認定基準では4主徴のうち、2つを満たせばよいとしているので、4主徴の全てを要求することは、大幅な要件の厳格化で臨床基準と全く整合しません。しかも、自賠責の3要件が明らかに生じていることまで要求するとなると、二重の意味で合理性を失しています。
- 皮膚変化 判決は、皮膚変化もないとして証拠を列挙していますので、皮膚変化がほとんど生じていなかったものと考えられます。 しかし、国際疼痛学会やわが国のCRPSの認定基準では、これは要件の1つにすぎないので、生じていなくともCRPS(RSDはそのタイプ1)との認定の妨げにはなりません。即ち、国際疼痛学会やわが国の認定基準は、CRPS(RSD)の患者であっても、皮膚変化が生じていない例があることを前提にして、これを必須の要件とはしていません。 私の受けた事件でも皮膚変化が軽度であった(抑えられていた)事件がありました。これは患者さん(重度の関節拘縮が生じていました)が、毎日風呂で温水をシャワーで30~40分患部に当てていたと聞いていますが、これによる患部の程よい刺激などに効果があったようです。逆に日中患部にエアコンの冷風などが当たって冷やされると皮膚の状態が悪くなり、上肢のむくみも酷くなる(就労条件のため冷風にさらされてかなり酷くなっていました)ということでしたので、皮膚の変化は患者側の対応である程度は抑制できるようです。
- この事案は日本のCRPSの認定基準に従えばCRPSタイプ1(RSD)と認定できたと思われますが、判決では二重の絞りをかけた結果、RSDと認定されませんでした。 判決は、RSDと認定されると後遺障害等級7級4号か9級10号の認定がなされるので基準を厳しくすべきであるとの趣旨を述べて、二重の絞り(臨床基準より格段に厳しい基準を2重に適用)という極端に厳しい基準を持ち出したのですが、私にはこの感覚は理解できかねます。この基準ではRSD(CRPSタイプ1)と認定できるのはRSD患者の100分の1以下に絞られそうです。 上記のとおり、被害者やその家族がウソの症状を訴えているとはとても考えられません。このような重症事案かつ特殊の傷病の事案で、患者が家族もある若い方である場合に詐病を主張する患者が紛れ込んでいる可能性は1万分の1以下であると私は考えているので、患者の訴えが真実である可能性とウソの可能性を等価値で比較して、厳しい基準にするということには同意できません。 被害者の救済という点からは、医学レベルよりも緩和した要件を用いるべきではないかとも思うのですが、判決のように医学基準よりはるかに厳しい基準をあえて独自に作り出して用いる感覚は理解しがたいものがあります。
- 遅れて生じた右側のRSD
- 本件では、左下腿RSDが事故4か月後という早期に診断されて、事故の1年9か月後に右膝RSDが診断されています。私は実際にもそのような症状が生じていたと考えます。 判決は、事故の1年9か月後に診断されたということで、事故との因果関係を否定しました。私は事故により生じた左下腿RSDとの関連したものである可能性の方が高いと思います。それ以外に原因となりうるものがないからです。判決は、事故1年9か月後に突如発症したかのように述べていますが、右膝の症状は事故5か月後には訴えていたので、その後に悪化してRSDとなったものと考えられます。
- 両側の症状 交通事故により生じる傷病のなかには、左右双方に発症する傾向のある傷病があります。例えば、胸郭出口症候群や手根管症候群です。これらを発症する患者は、両側に発症する患者が多いことがほとんどの医学書で述べられています。中枢神経を介した神経伝達に関連がありそうですが、医学的にはその理由は解明されていないようです。このことは交通事故で発症した場合も変わらないようで、私も両側に症状を訴える患者さんの事件を何件か受けています。 このように考えていくと、当初左側だけに症状が生じていたのに、右側にも症状が生じたことだけを取り出して不合理であるとか、事故とは無関係の持病であるという見方はできないと思います。
- これに対して、加害者側は、RSDというよく分からない傷病が左側だけではなく、右側にも発症したのは本人が意図的に右側にも作り出したからではないかとの疑いを「ヒステリー等の心因反応ではないか」という言葉で述べています。 判決でも、このような疑いを捨て去れなかったようで、それどころか「後発した右側の症状が心因ヒステリーならば先に発症したとする左側も信用できない。」という考えに流れていったようなニュアンスが感じられます。判決は被害者の賠償額(既払いとの差額)を121万円と極めて低く認定しています。 事故により一生車椅子生活を余儀なくされる可能性の高い若い被害者に対する賠償額としては、極端に低いので実質的に差病と認定したものと言わざるを得ません。
- 本件で気になること~原告の請求額 本件では、被害者側は1000万円しか請求していません。これは被害者の訴える症状に比べると、極めて低い金額です。これは「反訴請求」ですので、被害者に対して加害者(損保)側が債務不存在確認の訴えを起こし、これに対して被害者が1000万円を請求する反訴を起こしたという経緯があります。 つまり、損保側が被害者の治療費等を負担できないとして、訴訟を起こしてきたというのが訴訟の発端ですので、被害者側に不利な状況が当初に存在したことが想定できます。 被害者の傷病は、RSDという分かりにくい難病で、しかも被害者にRSDの4主徴が強く出ていなかったことから、RSDと裁判所に認定される可能性が低いと判断した上で1000万円という請求額となったのかもしれませんが、やはり被害者の主張する後遺障害の度合いに比べると低すぎるように思います。 (2010年11月1日掲載)
 両下肢RSDの否定(21.4.9)
両下肢RSDの否定(21.4.9)

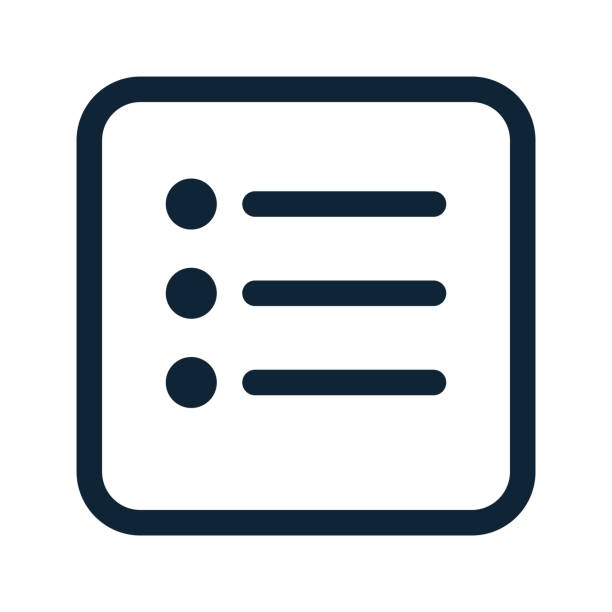 目次へ
目次へ