- 東京地裁平成21年9月18日判決(交民集42巻5号1205頁) この事件では、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)が問題となっています。事案はかなり複雑で論点が多く、平成15年に提訴された事件ですが平成21年に判決が出ています。 この事案の特徴は、①右上肢に生じたRSDが、提訴後に左上肢に波及し、両足にも症状が及んだこと(ミラーペイン)、②右上肢の症状が提訴後に改善したこと、③RSDの病期をRSD判断基準として考慮したこと、④自賠基準により重度の骨萎縮を必要としてRSDを否定したこと、⑤被害者が訴訟中に死亡したこと、⑥身体表現性障害という心因による症状であるという損保側医師の意見を裁判所が採用したことなどです。
-
- RSDの病期
- 病期の意義 この判決ではRSDの病期説に注目しています。RSDは急性期(最初の3か月)、亜急性期(3~9か月)、慢性期(9か月~2年)という疾患特有の進行時期(病期)があり、時期ごとの症状が現れるとの説を判決は引用して、RSDの有無の判断において考慮しています。 この説を引用する医学書は少なくありません。とくに比較的古い医学書で多く、『末梢神経の臨床』(07年)など最近の医学書でも引用しているものは少なくありません。 RSDの病期は臨床の上ではRSDの進行状況に対応した治療をするという視点からある程度重視されてきたようですが、当然のことながら昔も今も病期をRSDの判定指標に用いる医師や学説は存在しません。
- 病期の否定 臨床からの報告では「病期」の存在そのものが確認できなかったとされています。例えば、『複合性局所疼痛症候群CRPS』74頁ではCRPS患者800名以上の大規模研究でこの病期との相関は認められなかったとしています。『整形・災害外科』45巻13号(02年12月)でも同じことが述べられています。『臨床雑誌、整形外科』54巻7号(03年7月)748頁では、臨床との根本的な不一致を指摘して、病期分類は「今日ではまったく意味がないと断言することができる」とします。 このように病期説は印象的な少数の症例が過って普遍化されてしまった古い医学の負の遺産の象徴のようなもので、RSDをCRPSタイプ1として位置づける最近の医学では過去の学説とも言えそうです。 ただ、一部の典型的な症例において治療の参考にする程度であれば問題がないかもしれません。『複合性局所疼痛症候群CRPS』20頁では病期説を「完全に否定することはできない。」というレベルでは肯定しています。
- もとよりRSD判定指標ではないこと 上記のように過去の遺物ともいえる問題のある学説がつい最近の判決で引用されて考慮されていること、それが交通専門部のある東京地裁の訴訟であること、あろうことかRSDの判断基準として考慮されていることにはかなりの違和感があり、驚きました。 被害者にはRSDで特徴的な灼熱痛が生じており、これは普通はRSDを肯定する重症な症候となるはずですが、判決では急性期(当初の3か月)に生じるはずの灼熱痛が半年以上経過した後に生じているとして疑問を呈しています。おそらくこの疑問に同意する医師は1人もいないと思います。訴訟ではこのレベルの医学意見書は頻繁に見かけるので、これは被告側の医学意見書に沿う判断でしょうか。 当然のことながら存在しない病期がRSD患者には生じるはずだとして判定指標として検討されると、患者側には格段に不利になります。
-
- 自賠基準(とくに骨萎縮)の重視
- ほかのところでも何回か述べましたが、RSD(CRPS)で骨萎縮を必須の症状とすることは誤りです。 国内外においてRSD(CRPS)において必ず生じる特有の症状や検査所見はないことに異論はないので、必須の要件を設定すること自体が根本的に誤っていると言わざるを得ません。それを3つも設定することはかなり異常です。 国際疼痛学会のCRPSの判定指標(臨床用、研究用)でも日本での判定指標(臨床用、研究用)でも、骨萎縮は要件の1つにさえ入っていません。このように今日では骨萎縮を要件とすることは国外、国内で否定されています。
- しかし、なぜか自賠責保険の基準では「明らかな骨萎縮」という重度のものを不可欠の要件として要求しています。この基準が作られた当時の医学的知見を無視した基準がなぜ作られたのか不可解です。 他の判決では骨萎縮に拘らないものも少なくないようですが、この判決では骨萎縮をことのほか重視して、本件では骨萎縮は軽度に過ぎないとして、複数の医師によるRSDの診断を覆しています。 以上のようにこの判決では、RSDの病期の考慮や基準決定のレベルですでに問題があるため、現実のRSD(CRPSタイプ1)の患者の大多数(ほぼ全員)がこの基準を満たさないこととなります。このことがもともと複雑難解なこの事件の事案解明から遠ざかった(ように私には見えます)大きな要因となっています。
-
- 症状の経過
- 被害者は、事故時50歳の女性で手作り餃子、ラーメン製造販売会社の代表取締役です。平成13年9月18日に自動車運転中に事故に遭いました。
-
- 事故当日・・・A病院で、後頚部痛、背部痛、吐き気、右胸部痛
- 翌日~3か月・・・B病院で右上肢の痛みを訴え、21回注射(神経ブロックと思われる)を打つ。外傷性頚部症候群、右上腕神経痛との診断を受ける。3か月後のカルテに反射性交感神経性萎縮症、カウザルギーと記載される。
- 3か月後・・・C病院で頚椎捻挫、右上肢RSDとの診断を受け、入院治療(2か月)に入る。星状神経節ブロックを13回受けるなどした。右肩から腕にかけて痛み、触れるだけで痛い、右上肢の痺れ。
- 5か月後・・・C病院を退院してD大学病院に移る予定が空きベッドがなく、C病院に戻って入院。疼痛はアロディニアと判断される。
- 7か月後・・・D大学病院に移り2か月入院。右上肢の知覚不全(遠位優位)、右手指(第3~5指)の屈曲拘縮、手指の強い浮腫・灼熱痛。但し、骨密度は正常で筋萎縮はなく、皮膚温の左右差はない。 脊髄硬膜外刺激電極挿入の手術、脊髄刺激電極の埋め込み手術を受け、右第4、5指の疼痛は緩和した。
- 9か月後・・・C病院に入院(約43日)
- 10か月後・・・C病院に通院。右上肢に疼痛、右手指の浮腫が確認される。
- 1年1か月後・・・C病院に入院(約2か月)。頚部の痛み、右上肢の痛み、可動域制限及び機能低下。星状神経節ブロックを受ける。
- 平成14年12月26日、症状固定とされる。平成15年5月13日に損害保険料率算出機構は後遺障害等級9級相当と判断する。同年6月16日には外傷、疾病による右上肢機能全廃として身体障害2級の認定を受ける。
- 以上のように、現在のCRPSの判定指標ではCRPS(RSD)と診断されることには問題はない事案です。被害者は当初から星状神経節ブッロクなどの局所麻酔を多数回打っていることから、RSDに特有の非常に強い痛みが生じていたことが容易に窺えます。医師は触るだけで痛いという痛覚過敏やアロディニアというRSDに特徴的な痛みを確認しています。3か月後のカルテにRSDと記載されたことから、医師も当初からRSDを疑い、積極的に神経ブロックを施術しています。 この被害者は、手指に強い症状が出るタイプのRSDで、しかも指が曲がった状態で拘縮する症状が出ていたようです。その後に手関節が約70度の角度で曲るジストニアも生じています。なお、指がグーの状態になるのはRSDの要件とされる関節拘縮とは別の原因によるもの(中枢神経または脊髄に由来するもの)ではないかと思います。関節拘縮であれば関節近辺の軟部組織の収縮性がなくなり組織の癒着が生じるので、関節が曲がることを必然としません。ジストニアと考え合わせると中枢神経または脊髄に由来する症状であるように思います。 RSD(CRPS)は局部にのみ症状が出現することが多いので、患部のみに障害が生じていると思いがちですが、現実には中枢神経(脳)や脊髄に由来する部分は少なくないようで、神経学的に関連する部位にRSDの症状が波及する事例もあることからは、中枢神経での障害も考慮に入れる必要があります。 本件で被害者が、脊髄硬膜外刺激電極挿入の手術、脊髄刺激電極の埋め込み手術を受けたのは、中枢神経または脊髄に由来する症状として手指の屈曲が捉えられていたからであると思います。手術の結果、右4、5指の痛みは緩和したようですが、肩関節や手関節に大きな可動域制限が残っています。 平成14年12月の症状固定時点では右上肢RSDにより肩関節と手関節に大きな可動域制限が生じていることが診断され、後遺障害等級9級相当と判断されています。原告は9級では低すぎると納得できず、平成15年に訴訟を起こしています。
-
- RSDの判断
- この時点で医師の診断した症状が生じていたことは、問題なく認めてよいと思います。詐病でこのような多数回の神経ブロックを受ける患者は1000人に1人もいないと思います。さらに脊髄硬膜外刺激電極挿入の手術や脊髄刺激電極の埋め込み手術などの侵襲の大きな治療を詐病で受ける患者は10万人に1人もいないと思います。 しかし、判決は上記のRSD基準のため、RSDを発症していないとしています。判決の基準では現実のRSD患者の大半(ほぼ全員)がRSDと認定されないのでこれは基準設定レベルでの誤りです。基準をめぐる争いが生じた場合には、とかく基準を厳格化しすぎてしまう誤りが生じやすいと言えます。 この患者をRSDと診断した複数の医師だけではなく、医療現場の医師にしてみれば、医学知見を無視したこの判断には納得できないでしょう。本件のようにRSDとの診断が複数の治療機関でなされ、その診断に基づく治療が継続的になされ、侵襲の大きな手術もなされ、現に効果が生じているにもかかわらず、裁判で上記の基準でRSDの診断が誤りだったと判断されたことは、医師としては驚天動地の出来事でしょう。一体裁判所では何が行われているのだろうか、このような裁判官が医療過誤も裁くのか、という裁判不信につながると思います。
- 判決はRSDの発症を否定しながら、この時点では9級相当の症状が症状固定時までは存在し、二度目の症状固定時(平成16年10月13日)には、改善して12級となったとしています。RSDを否定しながら9級相当の症状があったとする理屈はちょっと苦しいと思います。 二度目の症状固定が問題とされているように、この事件ではその後に非常に複雑な問題が生じています。
-
- 提訴後の症状の回復と患部の拡大
-
- 平成15年12月・・・D大学病院で脊髄刺激のペースメーカーの入れ替え手術を受けた後に、それまで見られない左上肢の痛みや腫脹が生じ、手を開くのも難しい状態や、振戦を訴えるようになった。
- 平成16年2月半ば以降・・・両上肢に脱力が見られるようになった。
- 平成16年3月以降・・・バクロフェンの脊髄注入を始めたところ、両下肢に脱力感を訴え、その後しびれも訴える。
- 平成16年10月・・・D大学病院で新たな後遺障害診断を受ける。RSD(全身型)、両上肢麻痺、右上肢振戦、歩行困難、四肢腫脹。但し、右上肢の可能息制限は前回に比べて大幅に改善された。
- 平成17年9月・・・保険料率算定機構は9月10号と判断した。
- このように右上肢だけではなく、左上肢にもRSDが発症して、さらには両下肢にも重い症状が出ていたようです。そこで、バクロフェンの脊髄注入という手法が用いられています。これも身体への侵襲の大きな治療ですので、詐病でこのような治療を受けることはあり得ません。 バクロフェンの効果でしょうか、右上肢の可動域制限などの症状が大幅に改善されています。バクロフェンは中枢性筋弛緩作用があり、髄腔内投与により重度の痙縮に著名な効果が期待できるようですので、両手の拘縮などには効果が期待できます。この被害者は指がグーの状態になるタイプの拘縮が生じていたようであり、このことがバクロフェンの使用の理由になったようです。痙縮とは脳・脊髄に由来する筋の異常な収縮のことで、わずかな筋の刺激でも筋の極端な収縮が生じるとされています。 しかし、バクロフェンには歩行困難などの副作用が生じることもあるとされており、本件でも投与後すぐに両下肢に症状が生じています。もともと中枢神経や脊髄との関連の強いRSDですので、下肢にも症状が出やすい基盤があったのかもしれません。 仮に投薬の副作用であるとすると、事故後の治療により生じた副作用まで事故から生じた障害と言えるのか、しかも事故からかなり経過した時点での症状の発生となると、かなり難しい問題となります。
-
-
- 懐疑論からの負の連鎖
- 判決では、バクロフェン投与後の治療のなかにおける被害者の症状や行動に疑いの目が向けられています。この記載は全てカルテや入院看護記録に基づくはずですが、D大学病院はこの記載を全く問題視せずに全身型のRSDと診断しています。私もこの医師の判断が正しいと思います。 しかし、判決はこの部分の記載を被害者の詐病を認定する方向で実に大量に列挙しています。おそらくは被告側の医学意見書などにより主張された内容に沿うものでしょう。 この部分は、①懐疑論による事実の変換(疑いに合わせた事実の変更)の特徴的な出方で、疑いに都合のよい方向からの解釈を繰り返すというパターンに陥り、②その解釈に対して確証バイアス(自分に都合のよい事実は価値があるように見える)が生じて、疑いが自己増殖していきます。さらに、③反証なき同調事例の列挙(同種の同調事例はいくら列挙しても証明の度合いにはほとんど影響しないのですが)を繰り返すことによる心証の強化という、構造的な負の連鎖に陥っています。
- まず、振戦が睡眠中に出ないとか、会話中に止まるとして、詐病との疑いを抱いています。もともと振戦は24時間常に続くものではなく、痙縮が生じる原理からも間断的に生じたとしても特段に疑う理由にはなりません。しかし、疑いの目で見ると、これは患者がウソの症状を訴えているからであるということになるようです。 拘縮しているはずの手を開いているというのも、バクロフェンの投与の効果と考えれば特に問題視するものでもありません。大学病院の主治医は、手が開くと言っても指でちょっと動く程度であったと述べています。これは指がグーの状態で強く握りこまれる拘縮(爪が皮膚に強く食い込むほどの症状が出る場合もあるようです)が緩くなったということを看護記録などに記したものであると推測できます。バクロフェンを投与した側からは、少し拘縮が緩めば「指が開いた」と看護記録などに記載するのは当然でしょう。 車椅子を使用しながら室内では歩行しているというのも、長距離歩行や立位の持続による疼痛の増強のために車椅子を使用している状況では問題にもなりません。判決では「車椅子は1歩も歩けない人が使う」との誤解から、この部分を疑ったようです。 トイレで手すりにつかまりながら、おろしたズボンを自分で引き上げるというもの、握力が残っている限り、取り立てて疑問視することでもありません。判決はこのほかにもADL(日常生活動作)の改善など実に多くの事情を列挙していますが、私は取り立てて問題に感じません。 しかし、交通事故訴訟では被告側の医学意見書などで、このような事柄への疑問が強く述べられるということは、少なくないと思います。華々しい経歴の医師の意見書でこのような疑問が述べられると、信じてしまうのもやむを得ないような気もします。
- 判決が列挙した多数の事実は、全てカルテや看護記録に書いてあるはずで、当然に大学病院の医師や看護師も当然に見ていますが、医師はこのことを問題視せずにRSDと診断しました。 判決は医師が問題視していないこのような事実を、取り立てて疑いの目で見ることを積み重ねて、疑問を増殖させていったようです。その結果、被害者の行動を詐病という観点から組み立て直す方向に向かいました。 本来問題視すべきではない事柄も、疑いの目で見れば怪しいという見方が可能となります。これは疑いに合わせた解釈を持ち出した結果であって、疑えばどのようなものも疑えるということにすぎません。懐疑論の罠の中からは、疑いに合わせた解釈と普通の事実の認識とが判別しがたくなります。ここに懐疑論の落とし穴があります。 しかし、いったん詐病という観点が出来上がると、その見方を支持する事実に高い価値があるように見えるという確証バイアスが生じます。確証バイアスは人間の認知活動そのものともいえるもので、いかなる人間にも不可避的に生じるものです。 判決は疑い例を多数列挙することにより、その疑いを強化させていきます。反証(医師の判断など)や批判の検討を無視した同調事例の積み重ねをいくら繰り返してもその判断を補強することには繋がらないのですが、同調事例を多く列挙することにより証拠が固められるという錯覚に陥っていきます。自分の推論に有利な証拠を積み重ねようとすることは、確証バイアスに特徴的な認知行動です。正しい推論過程では反証の否定に力点が置かれるのですが、確証バイアスが強くなると同調事例の列挙に向かいます。
- このような負の連鎖に陥る判例は、被害者の詐病を認定する判決ではしばしば見受けられます。ある種のパターンのようなものです。 その原因は色々と考えられます。正しい医学知識が前提とされていないこと、患者の症状を否定する損保側医師の意見に盲従してしまうこと、事案の概要からは患者がウソを述べている確率が極めて低いこと(事前確率の問題)を無視したこと、懐疑論的な論理構造に存在する罠に無頓着であること、確証バイアスについての知識がないこと、現場の複数の医師が患者に騙されたとして自分だけが正しくウソを見抜いたと考えてしまう独善性などが考えられます。この点は詳しくは別に述べます。
-
- 身体表現性障害
- 判決は、被害者の詐病を疑う視点から、損保側の証人となった医師が右上肢以外(左上肢、両下肢)は身体表現性障害(強い暗示によって無意識的に機能障害を呈すること)であると推測したことを重視します。判決は、この医師が精神科を専門としているわけではないとしながらも、精神科医と長年にわたって一緒に仕事をして、心因性の有無を判断して治療方針を検討しているとその医師が述べたとして、重視します。 しかし、普通の医師は、専門外について診断しません。また、診断と受け取られる発言もしないと思います。そもそも、この医師は実際の患者に身体表現性障害と診断したことは一度もないはずです。精神科医ではありませんから。
- 判決によればこの被害者にはとくに既往症はないようです。身体表現性障害であれば、普通は50歳になるまでにこれによる既往症が生じているはずです。50歳まで既往症がない人にここまで重篤な身体表現性障害が生じるというのは、身体表現性障害のなかでも異例のことではないかと思います。 身体表現性障害として、左上肢の疼痛や手指の拘縮が生じるということ自体も、かなりまれな事例ではないかと思います。身体的侵襲の非常に大きな治療を継続的に受け続けるというもの、身体表現性障害とすることへの大きな障害になると思います。 判決のように右上肢の症状が医学的に裏付けられるとする立場で、残りの部分に生じた類似の症状について、身体表現性障害を認めることはかなり困難ではないかと思います。本当の症状にウソの症状を付け加えれば、治療が困難となり、その不利益が自分に戻ってきます。このように本件では身体表現性障害を否定する決定的とも言える事情が目白押しです。
- 被告(損保)は、この種の医学的知見を必要とする訴訟においては、被害者の症状を否定し、その内容に沿う医学意見書を提出してくるのが常であることは裁判所においては公知の事実ではないかと思います。 普通に考えれば複数の医療機関でRSDとの診断を受け、RSDとの診断に基づいて治療を長期間続けてきた患者のほぼ全員がRSDにり患していると思います。本件では治療は極めて身体的侵襲の大きなものですが、詐病でこのような治療を受ける人はまずいません。 しかし、被告側は、このような事案においても、当然のようにRSDを否定してそれに沿う医学意見を出してきます。この状況でその医学意見を重視する感覚は一般の人には理解し難いものでしょう。しかし、裁判ではこのような医学意見書が華々しい経歴の医師の名義で提出されることが少なくないようであり、そのような医師の権威に裁判官が盲従してしまうことも少なくないようです。 身体表現性障害という被告側に極めて都合の良い特殊な疾患を、その適用条件を十分に検討もせず、否定事情が目白押しの状況で安易に認めるというのも医師には理解し難いかも知れません。ことに本件では専門医(精神科医)の診断さえもありません。しかし、被害者の詐病を疑うという視点が強く出てしまうと、それに沿う証拠の価値が高く見えてくるという確証バイアスが避け難くなり、このような判断に至ってしまうようです。 (2010年11月12日掲載)
 全身に波及したRSDの否定(21.9.18)
全身に波及したRSDの否定(21.9.18)

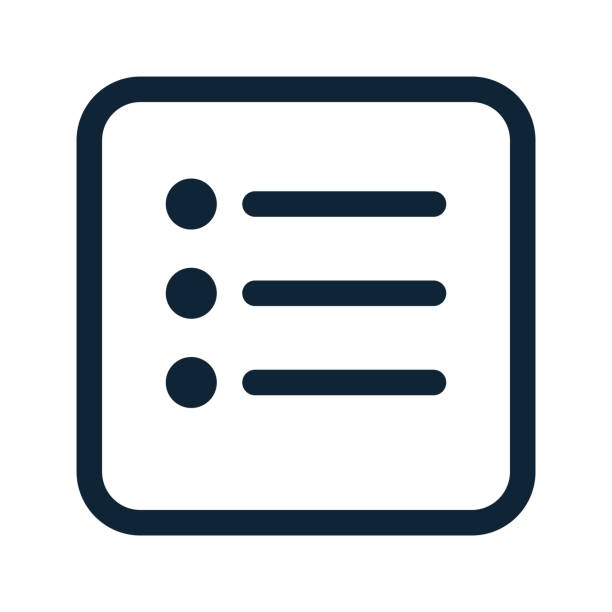 目次へ
目次へ