- 東京地裁平成19年11月7日判決(交民集40巻6号1479頁、交民集40巻の解説索引号284頁も参照) この事件では、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)が問題となっています。この事案の特徴は、①左下肢に「RSD様」の既往症があり、事故により悪化したこと、②事故後に右下肢にもRSDを発症したこと、③ギボンズの基準と自賠基準を併用したこと、④自賠基準によりあきらかな骨萎縮を必要として右下肢のRSDを否定したこと、⑤筋萎縮を重視すべきとしたこと、⑥素因減額を認めたことなどです。
-
- 症状の経過
- 左下肢の既往症 被害者は症状固定時35歳の有職主婦です。被害者は平成9年2月末頃に自宅で階段を踏み外して転倒したことにより、左足の半月板を損傷したことなどがきっかけで、症状が悪化し、平成12年1月には左下肢に「RSD様」との診断を受け、治療の過程で身体障害者等級6級との認定も受けています。 平成12年12月時点では、自発痛はなく、左膝伸展時に運動痛があり、左膝内側関節裂隙に圧痛があるものの、腫れはなく、装具をつけて歩行可能であったとされています。被害者は、この約3か月後に本件事故に遭います。
- 事故は平成13年3月で被害者は停止中の自動車に追突されて両下肢のRSDを発症しました。但し、判決では追突速度は時速10キロを大幅に超えないとされ、車の修理代も10万円弱です。
- 事故当日・・・頚背部、右肩、腰部、両膝の痛みや吐き気を訴えたものの、レントゲンでは異常は発見されません。
- 翌日以降・・・翌日より9日間入院。主訴は頭痛。右下肢痛、左下肢の脱力あるも、CTスキャンでは異常なし。退院時には杖歩行が可能なほどに回復。
- 10日後・・・リハビリ通院(約1年11か月)。事故50日後は両足装具で杖歩行が可能。しかし、両膝に運動痛、皮膚温低下、発汗異常あり。
- 半年後・・・右膝に自発痛、両膝に運動痛、中程度の腫れ、右下肢の皮膚に発赤、左下肢の皮膚に蒼白、チアノーゼあり。
- 10か月後・・・両下肢RSD、既存障害として左下肢RSDとされる。 自覚症状として、両下肢痛、歩行障害、両下肢発汗障害があり、他覚障害として、RSDによる両下肢痛が酷く、歩行障害があり、杖歩行の状態であり、RSD発症中にさらに外傷が加わり、両側難治性として、症状固定となった。事故後に両側の大腿が細くなり、左が特に細くなっている。
- 1年3か月後・・・麻酔科への通院を始めるも、症状改善せず。
- 2年8か月後・・・両下肢CRPS-Ⅰ、左下肢RSDは既存障害と診断される。レントゲンでは左側に著名な骨萎縮あるも、右にはない。
- RSDの発生機序等 判決は、「RSDの発生機序、病態、定義等については現在種々の説があり、未だ現在の医学界においてコンセンサスを得た見解が確立しているとは言いがたい。」と述べます。 この点は判決時も現在も概ねそのとおりですが、このように述べるのであればRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)という用語ではなくCRPSという用語を用いるべきです。コンセンサスのない「交感神経」や「ジストロフィー」を名称に入れるのは適切ではないからです。 また、「RSDに特有の症状がない(不可欠の症状は存在しない)」ことでは、約半世紀ほど前から世界の医学会で異論がないので、このレベルではコンセンサスがあるといえます。
-
- ギボンズの基準
- 判決は「RSDの診断について、臨床的診断基準としてギボンズらの診断基準が最近ではよく用いられていることが認められる。」と述べて、これを考慮するとしています。ギボンズの基準は項目が多く、スコアを数値化するので、厳密な感じがします。
- しかし、医学会ではそれとは逆の評価が一般的なようで、ギボンズの基準は国内外でほとんど用いられたことがないどころか、基準自体が検証も受けていないようです。日本ではペインクリニックの一部でこれが導入され、その後主としてペインクリニックと裁判所でのみ良く用いられているようです。 ギボンズの基準は多くの項目を取り上げているように見えますが、他の基準(指標)では4ないし5に系統分けされた症状のなかに多くの項目を含むのでギボンズの基準は多くの要素のなかの少数のみに着目するものと言えます。ことにギボンズの基準はその要素に偏りがあり、特に発症率の高くない骨萎縮(それゆえ他の基準では軽視されている)をX線と骨シンチで重複して評価する点に問題があります。 ギボンズの基準は、重傷度のスコアとランダムに取り上げられた症状のスコアをそのまま合計するという荒っぽい方法と言えそうです。このやり方は各症状の組合せによる感度・特異度の統計を重視する最近の医学の潮流のなかではかなり異質であると言えます
-
- 自賠基準(とくに骨萎縮)の重視
- ほかのところでも何回か述べましたが、RSD(CRPSタイプ1)で骨萎縮を必須の症状とすることは誤りです。 国内外においてCRPS(RSD)において必ず生じる特有の症状や検査所見はないことに意見の一致をみているので、必須の要件を3つも設定すること自体が根本的に誤っていると言わざるを得ません。自賠基準はこの点でかなり異常です。 国際疼痛学会のCRPSタイプ1(RSD)の判定指標(臨床用、研究用)でも日本での判定指標(臨床用、研究用)でも、骨萎縮は要件の1つにさえ入っていません。このように今日では骨萎縮を要件とすることは国外、国内で否定されています。 アメリカで800名超の患者を対象とした最も有名な大規模調査では、骨萎縮の発生頻度は36%とされています。重度となるとさらに少なくおそらくは10%以下でしょう。自賠責保険基準のように明らかな骨萎縮をRSDの必須の要件とするとそれだけで患者の9割ほどが切り捨てられそうです。 自賠基準は他の2要件も必須として、しかも「明らか」であることを求めるので、統計的に見れば自賠基準ではRSD患者の95%ほどは切り捨てられるのではないかと思います。そこで実際の認定状況が気になるところです。認定機関は、医師がRSDと診断した患者がRSDと認定された比率などを公表するべきです。
- 以上のとおり、この判決がRSDに不可欠の症状を設定していること、骨萎縮を必須としていること、骨萎縮が「明らか」であることを要求していることは、誤りというほかありません。
- 筋萎縮 この判決は筋萎縮を重視するべき症状に加えています。しかし、RSDの判定指標に筋萎縮を含めるなどという学説は、多々提案された基準のなかでも、いまだかつて存在しないはずです。この判決が何ゆえ筋萎縮を重視すべき症状に加えたのかちょっと理解できません。この被害者の左下肢に筋萎縮が生じていたからでしょうか。
- 厳格すぎる基準の適用 以上のように判決は、基準の設定のレベルで極めて厳格にしたのですが、本件の被害者は、左下肢に骨萎縮と筋萎縮があるとして左下肢のRSDのみを認め、右下肢のRSDは否定しました。筋萎縮や骨萎縮を決め手とすることは、この判決の下された時点においても医学的には支持できない考えです。 私は、被害者の症状からは、医師の診断に従い両下肢のRSDで良いと思います。RSDには、特有の症状や検査所見はないので、不可欠の症状を設定することはそれ自体合理的ではないのですが、この判決のように筋萎縮を要件に加えるというのは、いまだかってそのような医学上の学説もないだけにかなり疑問です。 基準をめぐる争いが生じると、基準を厳格にすれば正しい結論が導かれるような錯覚に陥りやすいようです。しかし、RSDは必須の症状を多くすればするほど、多くの患者が切り捨てられます。裁判の目的が「1割の確実な被害者の救済」であれば、これもやむを得ないかもしれませんが、裁判の目的は「全ての被害者の救済」のはずです。
-
- ミラー現象と寄与度
- CRPSには、患部とは別の四肢に症状が拡散するというミラー現象(ミラーペイン)がまれに生じることが報告されています。上肢のCRPSが下肢に拡散することもあるとされています。判例においても、四肢の一方にCRPSを発症している方がもう一方にも発症する例が見られます。 従って、すでにCRPSを発症している方が他の四肢にCRPS様の症状を発症した場合には、それがCRPSである可能性は高まります。
- 判決は、被害者の主治医が、「普通なら症状を出さない程度のものであるが、RSDの既往のある足の感受性が高く、症状を増悪させたと考える。」という意見を取り入れ、これを寄与度としています。 寄与度を認めると、既往症のあった左下肢が事故後に悪化した最終的な症状の全部に対して、既往症が割合的に寄与していることを認めるので、既往症による減額を認める場合と異なる結論が生じます。 これは難しい問題ですが、私は既往症が本人に責められるべき事情がないものである場合には既往症を超えて、寄与度を認めることは抵抗があります。既往症の存在そのものの評価を超えた責任を本人に課す一方で、加害者の負担を軽減することは病者に対する差別となるからです。例えば、血友病のため事故による出血が止まらず、重症となったことが被害者の寄与度になるでしょうか。私はこれを寄与度とすることは単なる病者差別に相違ないと考えます。 本件においても、既往症(すでに生じている損害)として考慮できるレベルを超えて加害者の責任を軽減することには反対です。
-
- 心因的素因
- 判決は、「RSDの発症に精神的素因が影響する場合があることが認められる」と述べますが、このような考えは判決時も現在においても、医学会の通説により、明確に否定されています。 CRPSでは激しい疼痛が続くことや重度の障害が残ることから、発症後に被害者の精神状況が悪化することが少なくないので、これにより事故前からCRPSを発症させる精神状態であったとすることは誤りです。
- 但し、この判決は、被害者の事故前からの精神的傾向を判決で述べているので、「事故前の精神状況が事故後の身体状況に影響した」という判断の基本的枠組みは維持している点は評価できます。 判決は、被害者が完璧主義でストレスをためる性格であり、幼少時の虐待体験や自傷行為があったとして、本件事故後の事情や症状固定後の事情もこれに混ぜて被害者の性格として述べています。しかし、仮にその全てが事故前に存在したとしても、その心的状況がRSDという身体状況に具体的なつながりを有することの説明とはなりません。「ストレスで胃に穴があく」というレベルの関連さえ見えてきません。 結局のところ、心因的素因の具体的な中身は存在せず(心因的素因の空洞化)、精神的な問題が指摘されている被害者に全額の賠償を与えるのは妥当ではないという懲罰的な観点で、心因的素因を認定したというニュアンスが強く出ています。この方向に進むと、病者に対する差別的な感情論と区別しがたいものになっていきます。
- RSD事案における素因の認定は、実際には「このような特殊の疾患は特殊の人にしか生じないはずであり、発症した人には何らかの特殊な素因があるはずである。」という実感に裏付けられたものであると思います。 しかし、今までのところ頚椎後縦靭帯骨化症や血友病のような遺伝的要因は発見されておらず、その他の身体的素因も見つかっていません(もっとも仮に何らかの遺伝的な素因が発見されたとすると、遺伝レベルの差別と言うほかないのですが)。 そこで、「何らかの医学的には未解明の心因的素因があるはずである。」という実質論により、心因的素因を認定するのですが、ここに至ると証明に基づく裁判とは言い難いものとなります。現実の訴訟では「軽微な事故から重大な障害が生じた」という外形があるだけで、「初めに素因ありき」という視点で素因の探索が行われ、被害者の言動に対して懲罰的に素因が適用される例が散見されます。 (2010年11月21日掲載)
 左下肢RSDが両下肢に拡大(H19.11.7)
左下肢RSDが両下肢に拡大(H19.11.7)

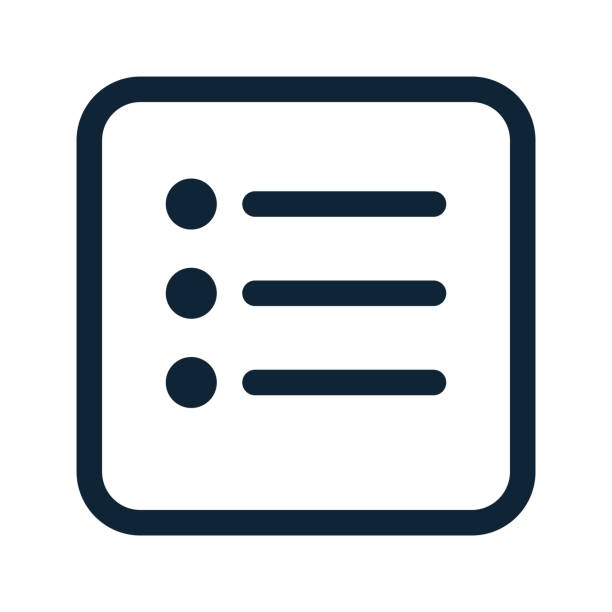 目次へ
目次へ