- 東京地裁平成19年7月23日判決(交民集40巻4号919頁) この事件では、左上肢RSDと左下肢RSDが問題となっています。この事案の特徴は、①左上肢RSDについて加害者側が認めていること、②左下肢にもRSDが波及したこと(ミラーペイン)、③症状固定後の治療費(約2年分)を損害と認めたこと、④加害者側の対応がちぐはぐであること、⑤被害者が平均以上の賃金を得ていたことが無視されたことなどです。
-
- 症状の経過
- 被害者は事故時35歳システムエンジニアの男性です。被害者は平成14年10月5日に追突事故に遭います。 判決によると加害者は被害者の主張を全て認めていますが、加害者の保険会社が独立当事者参加をして争っています。被害者は、加害者の代理人であった者や参加人の担当者の言動等を理由に慰謝料の増額を主張していることからは、加害者の代理人の活動内容が加害者本人の意向に反するとして加害者がその代理人を解任して被害者の主張を認め、保険会社が独自の立場で訴訟参加をしたと思われます。 このように保険会社は参加人という形で急きょ別の代理人(弁護士)を立てて訴訟に加わったようです。そのためでしょうか、参加人は左上肢のRSDの発症を認めているにも関わらず、他のRSD事案と同様にRSDを否定する医学意見書を提出する(当然、判決はこれを主張に反する証拠であるとして切り捨てています)というちぐはぐな対応をしています。参加した当初は左上肢RSDを認めていたのに、その後に争ったということでしょうか。
- 以上の事情により左上肢RSDの存在が前提とされた訴訟であるため、判決は被害者の症状の経過はあまり述べていません。被害者は、左上肢RSDのほかに、外傷性頚部症候群、解離性健忘症、左下肢知覚障害・運動障害・疼痛、胸部交感神経切除後左眼裂狭小、右半身代償性発汗の傷害が認められています。左下肢の症状は被害者がRSDと主張しているとおり、左上肢RSDのミラーペインとして波及したようにも見えます。 被害者は、RSDを発症したのちに、これに伴い解離性健忘症、うつ病などの精神症状を発症し、左難聴、左耳閉感なども生じていたようです。このようにRSD事案では激しい痛みが日常的に続くことにより精神疾患が生じることが少なくないようです。
- 被害者は、事故2日後には大学病院の麻酔科で、星状神経節ブロックや温熱療法を受けています。被害者が高額所得のシステムエンジニアであったことを考えると、事故による激痛がひどいことからすぐに大学病院に移り、本格的な治療を始めた事情がうかがわれます。星状神経節ブロックは痛みがかなり酷くならないと施術されないようですが、本件では早期に的確な対応をしていると思います。 RSD事案では激痛が続いているにも関わらず、何とか我慢して町の総合病院などに通院を続ける方も多いようですが、この我慢強い日本人的な対応が本格的な治療を遅れさせる要因にもなります。 RSDでは早期の神経ブロックには効果があるとされていますが、効果のない症例も少なくなく、むしろ悪化するもの(ABC症候群)もあります。この被害者は早期の神経ブロックにも関わらず、1か月後には痛みが激しいときに健忘が出現するとして、精神神経科で解離性健忘症とされています。RSD事案では激しい痛みの持続のため精神科を受診する方は少なくないようですが、事故1か月内に精神神経科を受診するのはかなり早いと思います。事故後の痛みがかなり激しいものであったことがうかがわれます。
- 被害者は、事故5か月後には左胸部交感神経節を切除する手術を受けています。侵襲の大きな手術を受けたことから激しい痛みが続いていたことが裏付けられます。手術後、激痛はなくなり、健忘症は消失したということで、手術の効果はあったようです。しかし、左上肢の痛みや手の重みは残り、その後も症状の悪化を防ぐために、頚・胸部傍脊椎神経ブロックを施行してきたところ、事故1年後頃から左上肢の激痛が再発しています。 被害者はその後、2箇所の病院で週に3日から5日という頻度で神経ブロックを受け続け、訴訟中にもこれが続き、1回のブロック療法において5か所も局部麻酔薬を注射していたことからは尋常ではない痛みが続いていたようです。上記の加害者本人の行動はこのような被害者の事情によるものであると思います。 この治療により、被害者の左上肢RSDの進行は抑えられ、完全な拘縮肢にはなっていなかったようです。この事情のため、判決では症状固定後の治療費を別個の損害と認め、固定後2年ほどの治療費を認めています。
- 自賠責保険の認定 参加人(保険会社)は、自賠責保険の認定では2回とも12級であったと主張しています。たしかに大学病院等でRSDと診断されても自賠責保険の認定手続でRSDと認定されるのは圧倒的少数であるようです(私の感覚では10%にも満たないと思います。認定機関はこのようなデータを完全に公表すべきです)。その原因は自賠責保険の基準が厳しすぎることに加え、認定機関は瑣末なことに目をつけて無理をしてでも後遺障害該当性を否定する傾向があるからではないかと思います。
- 遅れて生じた左下肢の症状(ミラーペイン) 被害者は、左下肢にもRSDが生じたと主張しています。RSD(CRPS)では、四肢の別の部分にも症状が波及することがある(ミラーペイン)とされているので、この被害者の主張もミラーペインの可能性があります。 主治医は、後遺障害診断書には、知覚鈍磨、脱力を記載するものの、RSDとの確定診断には至らなかったようです。しかし、現在のCRPSの判定指標ではCRPSと診断されると思います。 証人の医師は、「RSDと考えているものの、遅れて生じた症状であることから、医学的にも議論があり、診断する人によっても意見の分かれるところである」(判決文より)と述べたようです。この意見は、RSDを肯定しつつも因果関係について留保するもののようですが、判決ではRSDとの判断を留保したものとして理解されています。判決のこの部分は論理的には誤りであると思います。
- 休業損害 判決は被害者が事故前年に955万の所得があったとしながらも、給与所得者ではないのでそれが続くとは認められないとして、同年齢のシステムエンジニアの平均所得(約667万円)を基準とした休業損害しか認めませんでした。 しかし、「休業損害は実所得により算定する」という実務で広く行われている原則を安易に変更したこの部分には賛成できません。裁判では平均所得より少ないときには実所得に基づいて休業損害が認定されるので、平均所得より多い場合に給与所得ではないからという理由で平均所得とするのでは、偏った判断と言わざるを得ません。休業損害のような比較的短期間の損害の算定において、「給与所得者ではない。」という個別の事件とは無関係な一般論を持ち出してまで実所得の原則を修正することに妥当性はありません。しかも職業別の平均所得という例外的な指標を持ち出してまで、実収入を否定するという方法にはかなりの抵抗があります。
-
- 逸失利益
- 判決は、逸失利益では被害者が症状固定時(36歳)から67歳まで56%の労働能力を喪失したと認定しました。この部分については概ね妥当な判断であると思います。 しかし、被害者の事故前年の所得(955万円)ではなく、平成16年(症状固定年度)の男性システムエンジニアの平均賃金である約546万円を基礎収入として逸失利益を算定しています。 たしかにこの被害者のような給与所得ではない方の収入は不安定であり、高レベルの所得が長期間続くという想定を否定する要素は少なくないと思います。一方で所得が何倍にも増える可能性も十分にあるという見方もできます。将来のことを想定することは困難です。大企業でも国際競争の波に乗り遅れ大幅なリストラがあるかもしれません。一方でベンチャー企業が大躍進するかもしれません。そこで、裁判では以下のように指標が定められています。
- 平成11年の3庁(東京、大阪、名古屋地方裁判所の交通専門部)共同宣言では、それまでの平均所得重視の傾向を変更するべく、実所得重視の方向性が打ち出されています。 それまでは平均所得以下の被害者は平均所得を基準として、平均所得を超える被害者は実所得を基準とする被害者有利の運用が主でしたが、この共同宣言以降は総じて平均所得以下の被害者についても実所得を基準とする方向に大きく舵が切られました。もちろんこの変更は被害者側には不利にしか働きません。 これ以降は、原則として平均賃金は参考とされず、事故前年の実所得が基準として用いられてきました。実所得を基準とすることは、個別の被害者の状況をより正確に反映するので、被害者の差別化を生じる面はあるものの、損害論としては厳密であると言えます。3庁共同宣言は若年(概ね30歳以下)の労働者に対しては平均賃金より少なくとも原則として平均賃金を基準にするべきであるとしているので、被害者の将来の可能性を否定するというマイナス面はこれである程度補えるとも言えます。
- 本件の判決は、事故時35歳の被害者の実所得を否定して、これよりも段違いに低い平均賃金を基準としているのですが、実所得主義を採用した3庁共同宣言により被害者の多くが不利益を蒙った状況で、例外的に不利益を受けない(現状の立場を主張できる)はずの被害者がその立場を安易に否定されたという結果が生じたことは否定できません。被害者としては申告した所得に対応した税金を国に支払っているのに、国の機関である裁判所にその所得を否定されることには納得できないでしょう。 結果的には、一般的な基準を設定したはずの裁判所が一般論を持ち出して安易にその基準の例外を認めたと言わざるを得ないと思います。基準それ自体が一般論であるのに、一般論を持ち出して基準を否定するという論理構造(ダブルスタンダード)となっています。 その一般論も所得が不安定であるというもので、所得が増える可能性があるとの一般論は認めないので、やはりこれは偏った観点からの一般論の導入と言わざるを得ません。どうしてこのような一般論が基準を訂正する要因になるのか理解し難いところです。
- 判決のなかには、平均賃金から何割か割引した所得を基礎所得とするものもあるので、本件のような場合には、例えば平均賃金の3割増を基礎所得にするという解決方法もあり得たところです。しかし、そこまでするのであれば実所得をそのまま基礎所得にするという原則とおりの運用をすれば足りることとなります。実際にも、実所得が平均賃金を上回る方において平均賃金からの割増という認定をした判決はみかけません。 そこで、被害者の事故前年の所得だけではなく、事故前3年間の所得の平均を用いるという方法も考えられるところです。たまたま事故前年だけ特に所得の多かったという年配の個人事業主のような事案ではこのような方法もありうると思います。しかし、事故1年以上前の所得が低いときには被害者側が進んで不利な証拠を出してくることもないと思われるので、裁判所がきちんと説明してその提出を促す必要があると思います。それをせずに実所得よりも格段に低い所得を基準とすることは避けるべきであると思います。 (2010年11月26日掲載)
 争いのない左上肢RSD(H19.7.23)
争いのない左上肢RSD(H19.7.23)

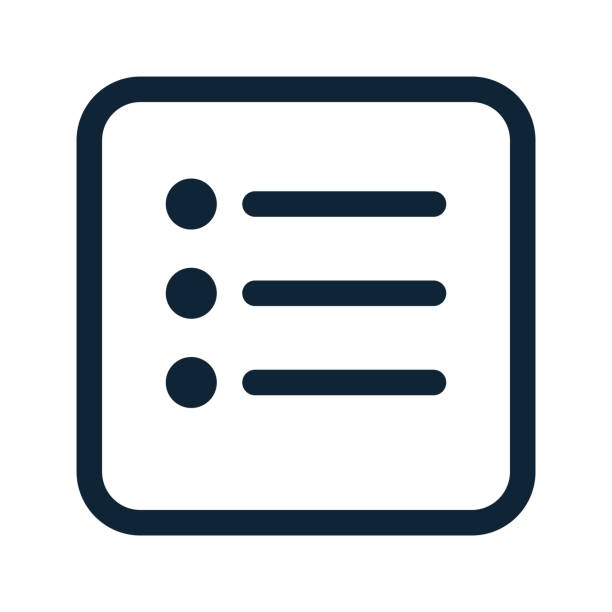 目次へ
目次へ