- 大阪高裁平成18年9月28日判決(交民集39巻5号1227頁、裁判所HPにも掲載されています。「RSD」で検索できます。) 1審は大阪地裁堺支部平成15年12月1日判決です。 この事件では、左上肢RSD(CRPSタイプ1)が問題となっています。この事案の特徴は、①いったん後遺障害診断を受けた後に左上肢RSDと診断されたこと、②複数の医師と鑑定人がRSDを肯定したこと、③加害者側が詐病を主張してビデオを提出したこと、④筋萎縮、骨萎縮を重視せずRSDを認めたこと、⑤判決で各種の判定指標に当てはめたこと、⑥判決が5割もの素因減額を認めたことなどです。
-
- 症状の経過
- 被害者は症状固定時41歳のパート従業員兼主婦です。被害者は平成13年11月16日に本件の事故に遭います。事故は比較的軽微であったようです。
- 事故当日・・・頚部痛、左背部痛、頭痛などがある。左上肢脱力と痺れ、左肩痛があり、左上肢は挙上困難、関節の可動域制限もあり、頚椎捻挫および左肩関節捻挫診断を受ける。X線では異常なし。
- 翌日以降・・・翌日には左上肢は挙上不能となり、左手指に浮腫が生じ、手指の可動性も狭くなり、その後2週間後までに、背中の知覚過敏(なでるだけでも痛い)、頚椎の運動障害と痛み、左肩関節の運動痛及び圧痛、左上肢の脱力感及び痺れ、左前胸部及び左背部の痛みなどが出現し、体動が困難な状況となる。
- 被害者は、いったん症状固定とされた平成14年5月28日からAクリニックに通院しますが、RSDとの診断は受けませんでした。同年10月15日から通院したB記念病院でRSDとの診断を受け、同年12月24日から通院したC病院でもRSDとの診断を受けます。RSDとの診断を受けるまで1年ほどを要しています。このようにRSDを疑いつつも、慎重になりすぎて診断がかなり遅れる事案はしばしば見かけます。 平成14年10月の筋電図検査では異常がなかったので、神経損傷によらないRSD(CRPSタイプ1)であると考えられます。明らかな神経損傷のないCRPSタイプ1のときは、神経損傷のあるカウザルギーに比べると症状が急激に進行しない傾向があるような感じもします。被害者の症状はその後も悪化し続けていきます。 平成15年2月には労災の意見書でRSDとの所見が書かれて、同年10月の2度目の後遺障害診断書ではRSDとされています。2年後の平成17年10月30日に診察した鑑定人もRSDを認めています。この時点では、左上肢等の疼痛、左半身の冷感、左手掌の発汗、左肘関節以下の知覚障害、手関節以下に軽度のアロディニア、左手背・左手指の著名な皮膚萎縮(左手指根元の腫脹先端の先鋭化)、色調の変化、ロウソク表面のような光沢ある皮膚表面が存在し、皺が正常な右に比べてほとんど消失している。左上肢と頚部に大きな可動域制限があります。最初の症状固定のときに比べてかなり症状が進行して重症化しています。 以上のとおり、本件が典型的なCRPSタイプ1(RSD)であることは明らかで、被害者がRSDであることには問題がない事案といえます。但し、7級4号の後遺障害認定は低すぎると思いますが。
- 被害者は症状固定時41歳のパート従業員兼主婦です。被害者は平成13年11月16日に本件の事故に遭います。事故は比較的軽微であったようです。
-
- 加害者側の主張
- このような典型的に重症化したRSDの事案においても、やはり加害者側は積極的にその診断を争い、強硬に詐病の主張をするという典型的な対応をしています。本件でも被害者の後遺障害を否定して医学意見書を提出してかなり積極的に症状を否定する主張をして、被害者の行動を隠し撮りしたと思われるビデオも提出しています。 重症化事案でこれほどまでの主張をするのは、少なくとも道義的には間違っていると思います。しかし、これまで見てきたとおり現実には重症化事案においても加害者側の主張を認めてRSDの診断を否定し、さらには被害者が詐病であると判断した判決も少なくありません。そのため医学知識を必要とする事案においては、加害者側はほぼ全ての事件で積極的に被害者の症状を否定し、多くの場合詐病をも主張します。 あくまでも一般論として述べますが、意図的に虚偽の主張をしてその主張に沿う証拠を意図的に作り出し、裁判所を騙して賠償すべき金額の減額を図ろうとすることは犯罪となります。被害者が重症の場合には悪質な犯罪であると言わざるを得ません。 私は重度のRSD事案で誤診や詐病の可能性は、概ね1万分の1以下と考えていますが、毎回のように誤診や詐病の主張が出てくることは、奇異な感じがします。裁判所は舐められているかもしれません。以下の加害者側の対応は典型例と言えます。
- 基準の厳格化 加害者側は、通常は全てのRSD患者を排除できるほどの厳格化された基準を主張します。本件ではまずRSDの4主徴の全てが必須であるとの主張をしています。この主張に従う判決は少なくないようです。 もとよりRSDに必須の症状や検査所見がないことは学会では異論がないので、必須の症状を主張するこの主張は誤りです。それが4主徴のすべてとなると論外です。なお、本件では被害者はこの厳格化された基準も満たしているようです。
- 交感神経ブロック 加害者側は交感神経遮断(神経ブロック)により、明らかな改善が見られることが必要であると主張します。仮に万が一加害者側の主張とおりであるとするとRSDは全て治癒しそうですが、実際には難治性疾患とされています。 CRPS(RSD)では神経ブロックの効果がない患者は少なくないようで、CRPS(RSD)の中には神経ブロックによりかえって症状が悪化するもの(ABC症候群)もあります。
- 筋萎縮 加害者側は重症化したRSDには重度の筋萎縮が必要と主張します。これも基準厳格化主張の典型です。困ったことにこのレベルの主張さえも認める判決が散見されます。しかし、私の知る限り筋萎縮をRSDの判定指標に含めるものはいまだかつて1つもありません。その筋萎縮が重度である必要性はなおさらありません。
- 骨萎縮 加害者側は、事故後早期に重度の骨萎縮が生じる必要があると主張します。本件ではある程度の骨萎縮があったことから、加害者側は要件をさらに厳しくして「事故後早期の重度の骨萎縮」という主張をしたようです。重度の骨萎縮の主張は自賠責保険の基準を引用して強調することが、加害者側の典型パターンですが、本件では単に重度を要求するだけでは足りないので自賠基準は引用されていないようです。 もとよりCRPS(RSD)に必須の症状や検査所見がないことは、医学的には異論なく認められています。しかも、骨萎縮は重視すべき要素でもありません。この骨萎縮が重度である必要はなおさらありません。 判決は、証拠文献を引用して「骨萎縮については、RSDの場合に骨萎縮が出る場合と出ない場合があるのみならず、その出現する時期にも個体格差があることから、国際的な診断基準(国際疼痛学会の基準等)も骨萎縮を筋萎縮と並んで要件とはしていないところ、骨萎縮は、疼痛のために罹患肢を使用できなかったことから発生することもあり、骨萎縮や筋萎縮の存在しないことが、RSDの存在を否定する根拠となるものではない」としてこれを否定します。正しい論理です。
- 筋電図検査 加害者側は、医学意見書で末梢神経に障害がないことが電気生理学的検査で裏付けられると主張します。これに対して判決は、それはCRPSタイプ1(明らかな神経損傷のないもの)に分類されるとします。 RSD事案では筋電図検査で神経の損傷が発見される場合もありますが、この場合には加害者側から「筋電図はあてにならない。」、「筋電図の読み取りが間違っている。」という主張が出てくることが通常であると思います。困ったことにこのような主張さえも認めた判決もありますが、電気生理学検査は被験者の意思に左右されるものではなく、普段の診断や手術にこの検査結果が用いられるので、その読み取りを誤ることはまずあり得ません。
- 病期説との不一致 加害者側はRSDの「病期」に従った症状が生じていないと主張します。困ったことにこの主張を認めた判決さえも散見されますが、すでに他のところで述べたとおり、臨床での大規模調査の結果、病期の存在そのものが今の学会ではほぼ完全に否定されています。もとより病期は治療の参考程度のものであり、RSDの診断基準ですらありません。
- 医学意見書 以上の加害者側の主張は全て医学意見書に記載されていると思われます。もとよりCRPSの診断を下すような高度医療機関での診断が誤診である可能性はそれ自体低いといえます。私は詐病の可能性を含めて、概ね1万分の1以下であると考えています。これ以上可能性を高くすると、大学病院で年に数名から十数名の患者が診断という基本レベルの重大な過誤を受けることになってしまうので、確率論的に支持できません。 訴訟では医学的な問題が争われる事件のほぼ全部で医学意見書が提出されます。普通に考えればその99%以上が主治医の診断と同じ結論になるはずですが、現実にはほぼ全ての医学意見書で被害者への診断を否定する意見が断定的に切々と述べられるようです。華々しい経歴の医師による意見書も少なくないようです。上記の確率論に従うと、このような医学意見書が正しい可能性は1万分の1以下です。この可能性を考慮に入れるかどうかは、判断の重大な分岐点となります。 多くの医学意見書は、その名義人が異なるにも関わらず、同じような主張をしてくる傾向があります。不思議ですね。
-
- 特別調査
- 加害者側は、被害者の行動を隠し撮りしたと思われるビデオを証拠として提出したようです。これも加害者側の対応でよく見られるものです。被害者は車を運転して、仕事の得意先周りをしていたようで、左肘を曲げてドアを閉めたところなどが撮影されたようです。そのことが被害者の主張する可動域制限に反するとして詐病であると主張したようです。
- 被害者の詐病を認定する判決では、この種のビデオの映像を詐病との認定の根拠にするものが散見されます。この種のビデオは障害者が障害のない部分を最大限使用して日常生活の上で動作を行うという当たり前のことを逆手に取って、被害者の動作を強調することにより、「これだけ動かせるのは、被害者の主張とは食い違う」という方向に持っていく傾向があるようです。 私の見た判決のなかには被害者の主張する可動域に明らかに反するビデオが提出されたものはありません。本来であれば被害者の主張する可動域制限と明確な矛盾がない限りこの種の証拠には意味はないはずですが、現実には「こんなにも活動的であるのはおかしい。」という情緒面に訴える証拠としての意味があり、このようなビデオが提出されることは少なくないように思います。
- 判決ではこの時期の被害者の左肘の可動域と矛盾しないことや、右手のみでハンドル操作可能な障害者用ハンドルグリップを設置していたことなどを指摘して、これを退けています。
-
- RSDの診断基準
- 判決は、細やかな事実認定をして積極的に被害者の症状を分類して認定し、これを4つの診断基準にそれぞれ当てはめていきます。判決は、まず国際疼痛学会(IASP)の94年版の指標にあてはめて、被害者がRSD(CRPSタイプ1)であると認定して、ほかの基準は裏づけとして用いるという論理構造をとっていますが、私もこの時点では最も正しい方法であると思います。私はこの判決の基準の当てはめの部分は他の判決に比べても特に優れていると思います。
- なお現時点では、IASP94年版の指標に加えて、臨床における感度・特異度の裏づけのある日本版のCRPS判定指標(臨床用)が適用されるべきであると思います。 判決は、ギボンズの基準の当てはめもしていますが、医学書によるとギボンズの基準は世界的にはほとんど用いられず、日本ではペインクリニックと裁判で多く用いられているようです。たしかに雑多な項目に重症度も混ぜてスコア化する荒っぽいもので、問題の多い基準であると思います。
-
- 被害者が後発の事故に遭ったこと
- 被害者は、平成13年11月の本件の事故(第1事故)のあとに、平成16年10月に一時停止中に追突事故(第2事故)に遭い、平成17年8月にも追突事故(第3事故)に遭っています。判決によると、第1事故よりも第2、第3事故の方が重い事故だったようです。
- 判決はこのことを減額要素として考慮していますが、かなり疑問です。被害者のRSDは、第2事故よりも前に重症化しているので、これを減額要素とする余地はないと思います。仮に万が一原因競合を認めるとしても、原因競合の場合に連帯責任を広く認める最高裁判例とも整合しにくいので、この部分はかなり不可解です。 判決は、この後発事故と被害者の心因的素因を混ぜて減額要素としたため、どちらも十分な考察がなされていません。この判決はこの部分に至るまではほとんど完璧な流れであっただけに残念です。
-
- 心因的素因
- この判決は、他の部分は優れているのですが、被害者の心因的素因を重視して、5割もの過失相殺を認めている部分は、さすがに同意できません。心因的素因を認めた裁判例は、「特定の心的状況が特定の身体状況を引き起こす蓋然性がある」という素因の結果に対する寄与を具体的に説明せず、その内容を不明確なまま認めたものがほぼ全部ですが、この判決のように不明確なまま5割も認めるのは尋常ではないと思います。 判決は、被害者の心因的素因として、被害者が事故前に心療内科などに長く通院していたなどの特殊の精神状況を認定しているわけではありません。特定の精神状況が特定の疾患の発症につながるという医学的知見を引用して、被害者に当てはめているわけでもありません。従って、「ストレスで胃に穴が開いた」というレベルの関連性さえ判決には書かれていません。 この状況で心因的素因を認めることは証拠に基づく裁判を否定するものであり、尋常ではないと思いますが、心因的素因を認めた裁判例の圧倒的大多数がこのようなものです。判決では心象的なイメージとして心因的素因が用いられています。心因的素因はこのように中身の空洞化した虚像として用いられ、被害者のちょっとした言動に対する懲罰的な用いられ方も多く見られます。それにしても5割というのは、尋常ではありません。
- 判決が心因的素因の認定に際して最も重視したのは、本件事故が軽微であったことです。つまり心因的素因は減額のための方便あるので、空洞化は当然とも言えます。 現実の心因的素因の認定の多くは、このような「軽微の事故から重大な障害が生じた」という状況で、「このような軽微な事故から重大な障害を生じる人は特殊であるから、加害者に全額の賠償を負わせるのは適切ではない」という実感に合わせた結論に向けて帳尻あわせに用いられているため、中身が空洞化しています。 仮に事故が軽微ではなくとも、「このような特殊な疾患を発症するのは本人にそれを生じさせる特殊な素因があったからに違いない」という実感が背景にあり、そこから「加害者に損害の全部を賠償させるのは適切ではない」という実感に近づけるための帳尻あわせにも素因が用いられます。 この判決は、「現在の症状が本件事故のみに起因するとは考え難い」という鑑定人の意見を引用して重視します。たしかに軽微な事故から重大な後遺障害が生じた場合に加害者にその全部の賠償責任を負わせるのは酷であるというのは一つのありうる考えです。
- しかし、原因となる事故からは想定しがたい重症化を生じるのがCRPS(RSD)の特徴でもあるので、この理屈ではCRPSを発症すれば自動的に心因的素因が認定されそうです。事実、CRPS事案では心因的素因を認定するものが少なくありません。 例えば軽微な接触であるのに、転んだ場所にたまたま突起物があって頭を打って運悪く死亡した場合に、心因的素因を持ち出して賠償額を減額することが正しいでしょうか。 これが誤りであることは誰にでも理解できると思います。この判決はこの理屈と区別することが困難です。なぜなら、RSDの発症に関わる身体的素因も心因的素因も医学的には認められていないのですから。 特定の心的状況が特定の疾患を引き起こすという医学的裏付けがなく、むしろ医学的にはこれが否定されている状況で、「軽微な事故から重大な後遺症が生じた」ことを、ほとんど直接的に心因的素因に結びつけることは、明らかな論理の飛躍があります。 もとより、軽微な接触で予期せぬ損害(死亡など)が生じたことそれ自体をもって、加害者の責任を減じる理由とはなりません。被害者にしてみれば、事故に遭うまでは自分がRSDを発症するなどとは想像したこともないでしょう。
- CRPSについては、現在の医学では身体的素因も心因的素因も否定する考えが圧倒的通説です。それはそのような統計的な実態がないことと、怪我の仕方に相関する発症頻度の違いが認められていることによります。このことは全ての人について怪我の仕方が悪ければ「悪魔の当選くじ」を引く可能性があることを意味します。 多くの判例に見られる「このような特殊な疾患は特殊な素因の持ち主にしか生じないはずである」とのニュアンスは、それ自体が差別的であることをひとまず措くとして、その実体的なものの見方にも違和感があります。 例えば、宝くじで1億円を当てた人は、特殊な人でしょうか。霊感が強いとか、生まれつき運が強いとか、当選者に同じ趣味があるといった特殊性は全くありません。くじが売られて当選番号が決められれば、当選者がランダムに決定されるに過ぎません。 CRPSについても現在の医学では、被害者のほぼ全員が「悪魔の当選くじ」を引いたものとされます。このように考えていくと、くじで当選した人に特殊な素因がないように、CRPSにり患したことについて素因がないというのは、現在の医学的知見を前提とすれば当たり前の結論であると思います。
- なお、私は、かりに軽微な事故により重大な結果を引き起こす要因を有していたとしても、これをもって直ちに素因減額することには、より強く反対します。 例えば、血友病のために軽微な接触による出血が止まらず、重大な後遺障害が生じたとして、その責任を血友病のある被害者に負わせることは、病者に対する差別そのものだからです。その疾患が本人に責められないもの(血友病や頚椎後縦靭帯骨化症のように遺伝的なもの)であった場合には、それをもって減額することは単なる差別であることは、誰にでも理解できることであると思います。これに対して、飲酒や喫煙を原因とする疾患が事故による結果の拡大に影響したのであれば、それはその被害者にも責められる事情があるので、この場合には素因として考慮するべきであると思います。 世の中には色々な人がいることにより成り立っているので、責められるべき事情のない病者や障害者が「事故にあったときにはその病気・障害を理由に賠償額が自動的に少なくなる」という劣った地位に位置づけられることは正しくありません。従って、疾患の存在から直接的に身体的素因を認める平成8年の最高裁判決は間違っていると思います。 この判決は、既往疾患の存在が明白である場合には、逆に差別そのものであるということに思い至っていないために、安易に心因的素因を方便として用いたと言えます。それにしても5割もの素因減額は差別に対しての感受性が低すぎると言えます。世の中には多様な人間がいて多様な損害が発生する可能性があることが損害賠償事件の当然の前提ですので、少数者の差別につながるような発想は避けるべきです。 (2010年12月5日掲載)
 遅れて診断された左上肢RSD(H18.9.28)
遅れて診断された左上肢RSD(H18.9.28)

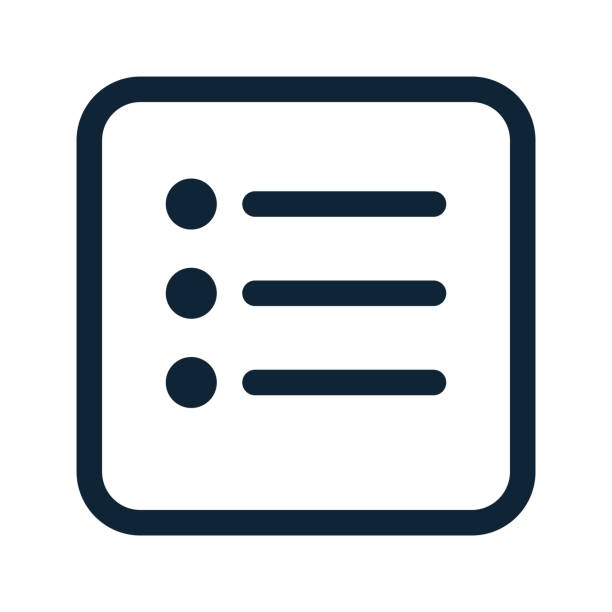 目次へ
目次へ