- 名古屋地裁平成18年9月29日判決(交民集39巻5号1378頁) この事件では、左上肢RSDが問題となっています。この事案の特徴は、①RSD(CRPS)との診断が事故1年半後と遅れたこと、②RSDを認めつつも12級という低い等級となったこと、③局部麻酔がRSDの発症可能性を高めるとする医学意見を判決が採用したこと、④判決が5割もの素因減額を認めたこと、⑤素因を認めるのもやむを得ないと思える事情があることなどです。
-
- 症状の経過
- 被害者は有限会社の代表者の男性(年齢不詳・52歳位と思われる)です。被害者は平成12年11月19日に自動車運転中に出会い頭の衝突事故に遭います。被害者にはこの事故の前に色々な事情があります。 事故前の平成10年3月に肝機能障害、けいれんにより1か月入院治療を受け、平成10年11月には頚肩腕症候群と胃潰瘍で治療を受け、その前後にも急性肝炎(アルコール性)で治療を受けています。 平成11年1月から9月にかけて頚部の低周波や牽引、局部注射の治療を受けています。平成11年6月には、アルコール肝炎や肩腕症候群との診断を受けているようです。 平成12年6月には頚椎第6.第7脊柱管がやや狭小化と診断され、両手のしびれ(ただし時々ゴルフをすることができる程度)もあったようです。被告(加害者)は事故直前の平成12年10月に誤って川のなかに突入する自損事故も起こしていたと主張しています(判決では認定されていません)。以上のように事故前の被害者側の事情はあまり良くありません。
-
- 事故翌日・・・A病院で頭部打撲、頚椎捻挫と診断される。両手の握力低下、しびれが認められ、投薬や頚椎カラーを施行される。
- 8日後・・・MRIで頚椎5/6番の椎間板ヘルニアが認められた。判決は外傷性ではないとするが、その理由は不明。
- 10日後・・・両下肢の浮腫、手のしびれ、頭痛が認められ、横になっても楽にならない状態であった。
- 2週間後・・・約2か月入院。頭部打撲、頚椎捻挫、胃潰瘍、アルコール性肝障害、慢性肝炎、頚椎椎間板ヘルニア、末梢神経炎、下肢浮腫等につき治療を受ける。脳外科で第3~5の頚椎症が認められた。
- 約55日後・・・入院中にB大学付属病院を受診し、外傷性頚部症候群、頚髄損傷(疑)と診断される。両手第4~前腕正中部の痺れを訴える。症状は外傷性頚部症候群に典型的で、少しずつ改善すると思われるが、時間がかかるかもしれないとされる。
- 約80日後・・・右3~5指、左3~5指がビリビリする感覚や頚部痛を訴えた。
- 約5か月後・・・食物等を持つことができず、不眠症、肩部痛に加えて、両母指球の萎縮や右手3~5指全体およびその側の掌部分のしびれ、左手2~5指のしびれを訴えた。以後1年で約40回の硬膜外ブロックを受けた。
- 約7か月後・・・飲酒のみで食事を取らず、意識障害等により搬送されて約1か月入院し、肝機能障害などの治療を受ける。
- 約1年半後・・・C大学病院でRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)との診断を受ける
- 以上のように症状が少しずつ悪化して、事故から1年半後にようやくRSDとの診断を受けます。平成14年6月4日の後遺障害診断書では、頚椎捻挫、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)と診断され、自覚症状は「特に左上肢に強い、四肢のしびれ」とされ、神経症状につき、「左手末梢の冷感、握力低下、知覚鈍磨」とされ、頚椎の運動障害が診断されています。 翌月にD大学病院で神経伝導速度の測定をしていますが、判決には「神経は切れていない」としか記載がなく詳細は全く不明ですが、この検査後にCRPSタイプ1(主要な神経損傷のないもの)と診断されていることからは、筋電図では胸郭出口症候群や手根管症候群などの末梢神経障害は確認されていないはずです。 このときにRSDスコア(ギボンズ)が合計5点(3点以下はRSDではなく、3.5点以上4.5点以下はRSDの可能性があり、5点以上だとRSDの可能性が高い)とされています。アロディニア、痛覚過敏、灼熱痛、浮腫、皮膚色調・体毛も変化、温度の変化につき陽性とされています。現在の指標によってもRSDであることに問題はないと思います。 その後、別の病院で、左交感神経ディスキネジー、胸部交感神経ジスキネジアと診断され、入院、手術を受けています。
- RSDの判定指標 加害者側は、自賠責基準を持ち出してRSDではないと争いましたが、判決は「RSDの症状は多彩であって、これを画一的にとらえることは相当でなく、皮膚の萎縮、骨の萎縮がないことをもって直ちにRSDを否定することはできない。」としています。 骨の萎縮が必須ではないことは、すでに何回か述べたとおりです。そもそもRSDで必ず生じる症状が1つも存在しないことはかなり以前から学会では全く異論がありません。従って、必須の症状を主張すること自体が誤りと言えます。 本件ではCRPS(複合性局所疼痛症候群)のタイプ1とも診断されており、国際疼痛学会がRSDをCRPSのなかに位置づけた以降はCRPSの判定指標によるべきですが、この判決の時点では具体化されたCRPSの判定指標はほとんど知られていない(日本版は未作成)という事情があります。 RSD(CRPS)の最大の特徴は、特有の症状(必須の症状)がないことです。このことは半世紀以上前から言われており、これまで多くの判定指標が前提としてきた基本的なことです。従って、医学意見ではこの点を最重要ポイントとして最初に述べるべきですが、加害者側の医学意見書でこの点を述べたものは一度も見たことがありません。不思議ですね。
-
- 後遺障害等級
- 被害者は、このRSDにより「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(5級)ないし「1上肢の用を全廃したもの」(5級)に該当する可能性もあるが、少なくとも、「1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの」(7級)に該当すると主張します。 労働能力喪失率56%(7級相当)で逸失利益を算定しているので、実質的には7級の主張をしているようです。
- この判決のなかには左上肢の関節可動域制限についての記載がないので、この被害者には左上肢の各関節に関節可動域制限はないようです。とくに手指には強い症状が出ているようですが、機能そのものの障害としては重くないようです。従って、「上肢の用を全廃した」との主張には無理があると思います。また、判決からは「4の手指の用を廃した」と言えるほどの症状を医師が確認していないように見えます。 従って、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(7級)、または「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(9級)を中心に主張すべきであったようにも思えます。 本件では、被害者の主治医の診断からは、左上肢にはかなりの痛みが日常的に持続し、浮腫やしびれも強く、手指のしびれはさらに強いようですので、労務への影響は大きいと考えられるので、現実の就労状況なども考慮に入れながら7級か9級と判断すべきと思います。
- これに対して、判決は、RSDであることを認めながらも、12級12号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」であるとしました。さすがにこれは低すぎると思います。 判決は痛みや痺れによる就労への影響を全く認めなかったのですが、これは「他人の痛みは原理的に知りえない」というドグマを背景にして、「仮に痛みやしびれがあるとして、具体的にどのように就労に影響するのか証明されていない。」という論理を用いたものと推測できます。後半部分の論理は誤りとは言えません。 医師の認めた症状が存在するとした場合には、当然に就労に影響するとも思えるのですが、一般論としてこれを述べるだけでは足りず、個別の動作について「物をつかむと痛みが出るので、強くつかむことができない。」とか、「手指のしびれのため多くの文字を書くことができない。パソコン作業も痛みが強くなるので10分ほどが限界である。」などの具体的な主張をする必要があると思います。
-
- 素因-局部注射
- 判決は、加害者側の証拠を引用して「パンカイン・リノサール、リドカイン・ネオビタカイン、キシロカイン・メチコバールといった薬剤の局部注射の多用がRSDを招来する可能性が高い」と認定しています。 これは加害者側の医学意見をそのまま採用したものです。被害者が事故以前から頚肩腕症候群により局部注射を受けていて、特に事故後はRSDとの診断を受けるまでに神経ブロックを多数回受けていたことから、加害者側は「神経ブロックがRSDを発症させた」と主張したものですが、もちろんこの主張は誤りです。
- 事故後に神経ブロックを多数回受けていたのは、その時点でRSDの発症が始まっていたからであって、これに対する治療として神経ブロックを多数回施行するというのは、至極普通のことです。 私の知る限り、(注射ミスで神経を損傷した場合を除いて)局部注射そのものがRSDを発症させる可能性を高めるという考えは学説としても存在しません。RSDに対する治療の代表的なものは神経ブロックですが、その事実を根本的に否定して、逆に神経ブロックによりRSDが発症するという正反対のことを述べるものですので、とんでもない暴論であることは明らかであると思います。 訴訟戦略上の手法としてもよく恥ずかしげもなくこんな主張を出すものだなあ、ちょっと裁判所を舐め過ぎではないか、いったいこんな医学意見を言う医師が本当にいるのだろうか、という感じもしますが、訴訟ではこのレベルの主張は頻繁に見かけます。 このレベルの主張であれば裁判官は当然に排除すると思われるかもしれませんが、このような主張が有名な大学病院の主任教授並みの華々しい経歴の医師の名を冠した医学意見書で出され、「身体的素因が9割で心因的素因が8割である」などと強硬なことが書かれていると、重視してしまう裁判官も少なくないようです。本件ではどのような医師の医学意見であるのか不明ですが、この主張が判決で採用されてしまっています。
- 判決は事故前から通算して4年間も局部注射を受けてきたことがRSDを発症させた原因の1つであるとして5割(つまり事故と同価値)の素因を認定しています。この理屈が誤りであることを措くとしても、交通事故の治療としてなされた神経ブロックについては、加害者の責任を減じる理由にはならないと思います。 しかし、判決は加害者側の提出した調査報告書(医学意見書)に基づいて、「局部注射が多数回施行されたことについては医師の診療姿勢と原告の心因的なものが相当に影響を及ぼしていると認められる(同調査報告書の意見は入院看護記録を含む診療録に基づいてなされている。)ものであり、医師の診療姿勢の点は格別として、原告の心因的要因によるという点では、訴訟額を減額するのが相当である。」と述べています。 判決には、「このように多数回のブロック注射を長期間続けるというのは異常かつ誤った治療であるに違いない。」という価値判断が出ています。この実感に加害者側の医学意見がうまく入り込んだようです。 しかし、RSDの事案では神経ブロックを繰り返すことは、ごく普通の治療です。RSDでは激しい痛みが持続することが多いので、神経ブロックを繰り返してその痛みを抑えることは当然であるともいえます。
-
- 素因-頚肩腕症候群
- この事件では素因減額がやむを得ないとも思える別の事情があります。まず、被害者が事故前から頚肩腕症候群にり患していて、その治療を事故時まで受け続けてきたという事情です。 この頚肩腕症候群の症状は頚部の痛みや両上肢のしびれとして生じていたので、事故後のRSDによる症状と一部重複しています。従って、この頚肩腕症候群の存在が、RSDを発症させた背景ではないかと疑うことにはそれなりの理由があるようにも思います。
- 頚肩腕症候群の存在がRSDを発症させる可能性を高めるという医学的な統計などがあれば、素因と認めることができると思いますが、そのような統計は訴訟では出されていないようです。私もそのような学説も統計も知りません。従って、RSDの「発症」に頚肩腕症候群が寄与していることの医学的な証明があるとは言えないと思います。頚肩腕症候群の患者にはRSDを発症する患者が特に多いとは思えません。 そこで、RSDの「悪化ないし拡大」の原因として頚肩腕症候群を持ち出すことはあり得ることですが、この点も医学的な証明があるかというと、ないと思います。 従って、頚肩腕症候群については、12級または14級相当の既往疾患とするのが最も穏当な対応ではないかと思います。即ち、RSDによる後遺障害を7級または9級として、頚肩腕症候群による12級(または14級)相当の既往疾患の分を控除するという方法の方が良かったのではないかと思います。
-
- 素因-急性肝炎(アルコール性)、アルコール性肝炎、胃潰瘍
- アルコール性肝炎や胃潰瘍がRSDを発症させる原因となるという理屈は、一見して奇異な感じがします。このため判決でもこれらの既往疾患も含めて、素因を認めたのかどうかはっきりしません。 判決は末尾に被害者の既往疾患や本件事故後の診断の一覧を載せていますが、その分量は3頁にも及びます。この被害者はアルコール性肝炎や胃潰瘍の持病があり、事故後も飲酒をやめずにこれを悪化させていったようです。事故の2年2か月後には糖尿病の疑いという診断もなされています。糖尿病は末梢神経の疾患を悪化させる要因になるので、この点では過量の飲酒がRSDを悪化させる要因となると見ることに理由があるようにも思います。
- 被害者は治療に専念して飲酒を控える状況にはなかったようであり、飲酒を続けたことは事故後の症状悪化の要因の1つになるとも言えそうです。従って被害者にも責められるべき点があると言えそうです。 このように見ていくと、心因的素因として1割程度であれば減額されてもやむを得ない事情があるようにも思います。しかし、判決のように5割もの減額(事故と同価値の事情)を認める素因があるとするのは行き過ぎであると思います。
-
- 素因-頚椎椎間板ヘルニア
- この被害者は、事故8日後に撮影したMRIで頚椎椎間板ヘルニアと診断されています。判決は、上記の局部麻酔がRSDの発症の要因であると述べる加害者側の調査報告書(医学意見書)を引用して、この頚椎椎間板ヘルニアは外傷性ではないと述べます。しかし、判決では外傷性ではないとする理由は述べられていません。 事故後に判明した椎間板ヘルニアが外傷性かどうかを、事故後の画像だけで確実に判断する医学的な指標は存在しないはずですので、この点はちょっと奇異な感じがします。加害者側の意見だけでこれを認定するのは、難があると思います。
- この被害者は、事故5か月前の時点で頚椎第6・7脊柱管がやや狭小化していると診断を受けている一方で、この時点では頚椎椎間板ヘルニアについて診断されていないので、この椎間板ヘルニアは事故によって生じた可能性の方が高いようにも見えます。いずれにせよRSDとは関係しない話です。
- 判決はこれをRSDの素因としますが、この判決は既往疾患と素因とを混同しています。頚椎椎間板ヘルニアがRSDを発症・拡大させるという関連性がない以上、仮に事故前に頚椎椎間板ヘルニアが生じていたとしても、RSDの素因とすることは誤りというほかありません。 (2010年12月30日掲載)
 素因5割とされた左上肢RSD(H18.9.29)
素因5割とされた左上肢RSD(H18.9.29)

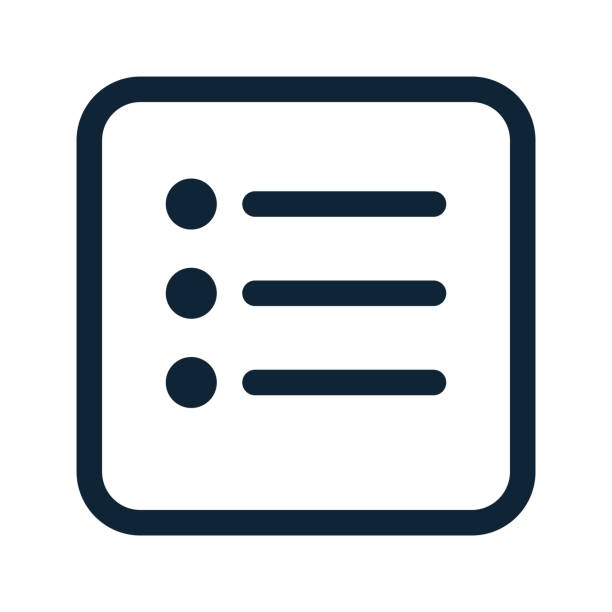 目次へ
目次へ