- 東京地裁平成17年2月15日判決(交民集38巻1号219頁) この事件では、右下肢RSDが問題となっています。 この事案の特徴は、①被害者の症状の詳細が判決で述べられていないこと、②症状固定まで4年9か月を要したこと、③被害者側の鑑定書が出されていること、④判決が後遺障害の存続期間を制限し、かつ症状が将来軽減すると認定していること、⑤判決が疑問のある理由で2割の素因減額を認めていることなどです。
-
- 症状の経過
- 被害者は症状固定時34歳の女性(看護婦)です。被害者は平成10年3月17日に恋愛感情のもつれから加害車両のドアノブをつかんで転倒して、加害車両に右下肢を轢かれる事故に遭います。 判決では、事故後の被害者の症状の経過は全く何も述べられておらず、どこの病院にどれだけ入通院したのかだけが述べられています。被害者の主張する後遺障害の詳細も不明です。被害者側の主張の欠落に依るものであるかも知れませんが、さすがにここまで症状の詳細が欠落している判決は良くないと思います。
- 被害者は、事故後8か月は通院していますが、その後1か月入院し、9か月通院したのち1か月入院して、以後症状固定までかなり長期間の通院を続けています。しかし、上記のとおり、被害者の症状の経過は完全に不明です。判決では一切触れられていません。
- 被害者は入通院のなかで反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)と診断されていますが、どの時点でどの医療機関にどのような症状に対してこの診断が下されたのか、判決には記載されていません。 判決によると、右下肢の感覚障害(知覚異常)、疼痛、皮膚温の低下などが生じていたようです。
- 被害者は、事故後は症状固定となる平成14年12月25日まで4年9か月も仕事に復帰できず休業していたことから、かなり重い症状が長期間続いたことが窺えるのですが、判決にその詳細の記載はありません。 当初の8か月が通院でその後に1か月の入院が2回あることからは、RSDの症状が徐々に悪化して明確になっていき、その結果症状固定が4年9か月後になったものと考えられます。
-
- 被害者の主張する後遺障害の程度
- 被害者は、RSDによる後遺障害を12級12号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると主張しています。休業が4年9か月にも及んだ(おそらくその後も長期間就労に復帰できなかったと思います)ことからは、被害者の主張する12級という後遺障害等級は低すぎるように見えます。 被害者の主張する後遺障害は、右下肢の感覚障害や疼痛が主体のようであり、自賠責の後遺障害認定手続では、関節拘縮、骨萎縮、皮膚の変化が明らかではないことが指摘された(加害者側の主張)ようですので、後遺障害は疼痛や感覚障害(知覚異常)を主体とする症状であったようです。 そこで明確な機能の障害(関節拘縮など)がないことから、被害者は該当する後遺障害を12級12号に絞って主張したものと思われます。
- しかし、被害者が、事故後職場に復帰できず、退職扱いとなったことや症状固定まで長期を要したことからは、12級という主張はやはり低すぎると思います。 就労への影響については、この裁判時の基準においても「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(9級10号)または「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(7級4号)と主張することも可能です。 被害者が休業期間満期で退職扱いとなっていることからは、労務への影響に関するより重い後遺障害を主張しなかったことは、ちょっと奇異な感じもします。 症状固定後に被害者が就労に復帰したという事情があるのかもしれませんが、判決は何も述べていないのでこの点は不明です。就労に復帰していれば、判決で言及されるはずですので、おそらく就労に復帰できていないと思います。そうなると、被害者が12級という後遺障害等級を主張していることは低すぎるようにも思えます。
-
- 被害者側の鑑定書
- この事件では被害者側から、被害者がRSDであるとの鑑定意見書が提出されています。しかし、その詳細は判決では言及されていません。これは被害者が12級という低い等級を主張していたことから、判決では鑑定書の存在に言及すれば、そのレベルの後遺障害を認定するために症状の詳細を述べる必要が低くなっていたという事情が影響しているようにも見えます。 これまで見てきたRSD(CRPS)事案で被害者側から医学意見書が提出されたものはありません。加害者側が損保という巨大組織を背景にして毎回のように被害者はRSD(CRPS)ではないと主張する医学意見書を提出していることに対比すると、被害者側の持つ武器は貧弱です。被害者側はほとんどの場合相談する医師さえいないのが実情で、主治医さえ訴訟には協力的でないことが普通ではないかと思います。このような状況のため被害者側から医学意見書が提出されることは、まれです。
- 本件では、RSDのために4年以上も職場に復帰できずに退職扱いとなったという事情があるので、この鑑定書を武器に7級や9級の後遺障害を主張しても良かったのではないかとも思えます。 ただ、痛みを主体とする後遺障害の場合には、「他人の痛みは知りえない」という根本的なドグマがあるために、訴訟で痛みそのものを後遺障害として7級や9級を主張しても、認められにくいという問題があります。 本件のように痛みと知覚障害を主とする後遺障害の場合には、痛みのため就労できないという事情を理解してもらうのは、かなりの困難を伴うものとなります。
-
- 後遺障害等級
- 判決は、「被害者の右膝痛、右膝の異常知覚等の症状については、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)であると認められること、平成14年12月25日の症状固定時においてRSDの後遺障害が明確に残存しているかという点については判断が分かれるところであるが、少なくとも後遺障害として『局部に頑固な神経症状を残すもの』(自賠等級12級12号)に該当するものと認めることができる。」としています。
- つまり、判決は訴訟になって被害者が鑑定を受けた時点ではRSDであると認めるけれども、その鑑定から2年ほど前と思われる症状固定時(事故から4年9か月後)に、その症状が存在したかどうかははっきりしないとしています。 この点は、鑑定した時点でRSDが確認できるのであれば、症状固定時にも同様にRSDにり患していたと考えるのが素直ではないかと思います。被害者が症状固定まで4年9か月も要したことからは、症状固定時にRSDにり患していたことを否定する特別の事情がない限り、症状固定時にもRSDにり患していたとすべきであると思います。
- 判決からは、「事故から4年9か月も入通院を続けて症状固定になり、RSDであるとする鑑定(国立病院東京医療センターの整形外科医による)も存在し、仕事にも復帰できていないことから、少なくとも12級程度の症状が存在することは間違いないであろう」という実質論を前面に出して判断したというニュアンスが読み取れます。
-
- 後遺障害の存続期間
- この被害者は症状固定時に34歳ですので、本来であれば逸失利益の存続期間は33年(67歳まで)になるはずですが、判決はこれを20年に短縮し、このうち後半の10年の症状は軽くなるとしています。 判決は、「原告の前記後遺障害は、長期化することが予想されるので、10年間は14%、その後の10年間は10%として算定するのが相当である。」とします。
- 判決は、このように期間短縮と症状改善を認定した理由は何も述べていません。おそらくは、12級の後遺障害は存続期間を短くすべきであるというある種の通念のようなものを前提にしていると思われます。 即ち、判例の上では12級の後遺障害の存続期間を5年や10年に制限するものが多く見られます。これは「痛みはそのうち治まるはずだ。痛みに慣れるはずだ。」という感覚的なものを背景にしています。感覚的なものであるため、ある特定の疾患が5年や10年で必ず治癒することが統計上証明されているなどの具体的な根拠を述べる実証的な判決は1つも存在しません。 交通事故の賠償手続のなかで後遺障害等級を認定してもらうことは、かなりの苦労を要することであり、私は12級の後遺障害等級が認定された方の症状が総じて5年や10年で自然に治癒するなどとは決して言えないと思います。 しかし、損保側の長年の主張の甲斐もあって、この20年ほどの間に具体的な根拠もなく12級や14級の後遺障害の存続期間をかなり短期間に制限することが実務に定着したというのが実情です。本件の判決もこの実務上の慣行を当然の前提としているため、何も理由を述べることなく、後遺障害の存続期間を制限しています。従って、判決のこの部分に実務の慣行であるということ以外の根拠はありません。 このような証拠に基づかない認定は、証拠に基づく裁判の否定となるのではないかと思います。仮に認めるとしても、症状が緩和されるとする具体的な根拠をいくつか示し、それに応じた期間の制限のみを認めるべきであると思います。「痛みはそのうち消える」という理由であれば、それを根拠に書くべきです。書いたとたんに根拠薄弱が露呈しますが。
- 難治性とされるRSDにおいては、通常は10年後に自然に症状が改善したり、20年後に自然に治癒したりすることはなく、むしろ症状が悪化する可能性も十分にあります。症状固定後も長期間の通院が続くことが通常であることからは、本件も原則とおり33年間の逸失利益を認めるべきであったと思います。
-
- 素因減額
- CRPS(RSD)事案においては、加害者側から恒例行事のように素因減額の主張が提出されます。この判決は、「心因的素因による減額」という項目において素因減額を認めていますが、その内容は以下のとおり疑問のあるものです。 判決は、①被害者の当初の診断が「右膝挫傷」であったこと、②その後に治療が長期化して4年9か月後の症状固定まで仕事もほとんどできない状態となり、③RSDと診断されたこと、④当初の症状からするとこのような長期化及び後遺障害の残存が通常予想し難いというべきであること、⑤本件では恋愛関係のトラブルが背景にあり、そのことが被害者の治療を長期化させ、症状を重症化させたと考えるのが相当である、などと述べて2割の素因減額を認めています。
- 判決が列挙する内容はどれ1つとっても納得できるものではないでしょう。①の当初の診断がRSDではないことは、RSDと診断された事例の全てに当てはまります。受傷直後にRSDと診断された事案など見たことはありません。これまで見てきたとおり、事故から1~3年後にRSDと診断された事例は良く見られます。RSDという難病の認定は慎重になされるため、むしろ確定診断まで長期間を要することが通常とも言えます。 本件では、被害者がいったん軽快して仕事に復帰したという事情さえも存在しません。被害者が事故後4年9か月も仕事に復帰できなかったことは、当初からかなり重い症状が持続していたと思われます。 ②や③についても、事故によりRSDを発症したために、入通院が長期化したのであって、このこと自体を被害者が責められる事情とするいわれはないように思います。 ところが、RSDに関する多くの判例では「RSDという特殊な疾患にり患するのは、特殊な人に違いない。」、「RSDを発症する人は精神的に問題がある人に違いない。」という差別的な感覚から、それに対応する差別的な待遇を被害者に課すための方便として素因を持ち出しています。 そのため根拠が不明確なまま素因が認定されています。素因認定の根拠の不十分さは、その判断の背景にある感覚、即ち差別意識を際立たせるものとなります。 ④については、本件では当初から仕事に復帰できないほどの症状が生じていてそれが持続していたので、事実認識として誤っていると思います。CRPS(RSD)は当初の症状からは想定し難い症状の悪化をもたらすものなので、そのことを理由に被害者に素因があるというのは、理由のないことであると思います。 ⑤については、事実認識として誤っているというほかありません。本件で入通院が長期化したのはRSDを発症したからであって、恋愛感情のおける不満が入通院を長期化させてRSDを発症させたという論理は成り立つ余地もないでしょう。RSDの発症原因として失恋を挙げる学説など見たこともありません。
- 以上のように判決の列挙する素因認定の根拠は、いずれも誤りであると思いますが、一部の法曹の間ではこのような判断を肯定する見方も根強いのではないかと思います。 それは「RSDを発症しない平均的な被害者」との比較の視点から、A「RSDを発症するのは特殊な被害者であって、特別な扱いが必要である」という見方に帰着します。もちろんこの視点は差別的ですので、判決では法律論の衣をかぶせて論じられます。この視点の問題点は、「RSDを発症しない平均的な被害者」のみを基本的な保護対象にするという出発点が差別的であるところにあります。 Aの視点からB「特殊な傷病を発症することそれ自体が、素因の存在の証明である」という短絡的な結論があり得ます。これをそのまま判決に書くのはさすがに差別的に過ぎて支障があるので、通常は何らかの根拠を述べて、C「被害者に何らかの心因的素因がある」という別のもっともらしい理由が述べられます。 しかし、ある特定の精神疾患がRSD(CRPS)を発症させるとする因果関係は医学の学説の上でも疫学の上でも認められていません。CRPS(RSD)を発症させやすい精神疾患として特定の精神疾患が検討されている状況にもありません。従って、医学の上ではCRPSを発症させる心因的素因の存在を否定する考えが圧倒的通説です。
- ところが、心因的素因を肯定するほぼ全ての判決は、特定の精神疾患ですらない「何らかの精神的な問題がある」という抽象的な事実を心因的素因にして、「それゆえにRSDが発症または拡大した。」とする論理を用いています。 もとより特定の精神疾患として同定することもできない詳細不明の精神状況は、素因となりうる資格さえありません。これを素因とする考えは「なんとなく精神的な何かが影響しているように見える。」というレベルの心証をそのまま裁判に用いるものですので、法律論としても誤りと言うほかありません。 少数説ですが医学書の一部にはこのレベルの抽象的な議論で心因的素因の存在を肯定的に述べるものがあり、注意をする必要があります。特定の精神疾患と切り離された、患者の精神の抽象的な状況の善悪がCRPSの発症につながるという特殊な議論は、それ自体がすでに医学的とは言い難いものです。従って、これを医師が述べるのはかなり奇異なことであると私は思いますが、一部の医学書では現にそのような議論がなされています。 圧倒的通説はこれを否定しますが、裁判においては内容も因果も不明確な抽象的な心因的素因を肯定する見解をもっている裁判官にはこの考えは「渡りに船」となり、このような確証バイアス(自分の考えに都合の良い証拠を正しいとする見方)が抽象的な心因的素因の認定の裏付になっていると思います。 抽象的な心因的素因を認めると、被害者の些細な行動や、不道徳にも受け止められる行動に着目して懲罰的に心因的素因を認定する方向に向かいます。その根底にはAやBで述べた差別意識があります。
- 素因論にはさらに、D「このような特殊な被害の発生は通常予見できない」という損害の予見可能性の面からの補強論もあります。たしかに事故でRSD(CRPS)を発症した被害者も自分がRSDを発症するなどと想像したこともないでしょう。しかし、「予見できなかったので素因がある」とは言えないでしょう。 世の中は様々な人々が存在することで成り立っていることを前提にすれば、事故によりRSDを発症する人がいることは当然のことですので、「予見できない」という考えも実は出発点からして誤っています。 CRPS(RSD)のり患率をアメリカとオランダの中間の数値と見ると、日本では年間1万5000人前後がCRPSにり患していることになります。おそらく年間1~2万人ほどがCRPS(RSD)にり患していると思われます。このなかに事故によりRSDを発症する人が一定数存在することは、判例集に掲載されるものだけでもRSDに関する判決が毎年数件に及ぶことからも裏付けられます。
- 毎年世界中で多数の方にCRPSが発症しているにも関わらず、疫学的に特定の基礎疾患、精神疾患、遺伝子とCRPSの発症が有意な関係にあることは確認されていません。従って、CRPSが特定の素因に基づき発症するという考えを否定するのが現時点では圧倒的通説となっています。ゆえに医学的にはCRPSを発症させる素因の存在は否定すべきであるという結論がすでに出ています。 しかし、これまで見てきたとおり訴訟では、加害者側からはRSD(CRPS)事案での恒例行事のように、素因の主張が医学意見書などを提出してなされます。華々しい経歴の医師により、その主張がなされることも少なくないようです。このため多くの判例が被害者の素因を認定し、その判例に「右に倣え」とばかりに従う新たな判決を生み出しています。 人は異質な存在に対しては差別的な感情が抑えがたくなるようです。人は自分の見方に沿う証拠に高い価値を与える傾向も否定できません。しかし、裁判においては理性的な判断をする必要があります。
- なお、CRPS(RSD)を発症ではなく、維持ないし拡大させる素因を法律論として認めることは可能です。私も治療への意欲があまりにも欠けていると判断できる事案などについては、RSDの症状が拡大したことについての素因を認めるべきであると思います。 また、すでにCRPS(RSD)を四肢の一部に発症している方は、事故により四肢のほかの部分にCRPSが新たに発症する(ミラーペイン)可能性が高くなっていると思います。しかし、これをCRPS発症の素因と考えることには抵抗があります。この場合には病者差別という視点が問題となります。「もともと病気があってそれが拡大しただけだ。」とすることは、病者に対する差別的な見方になると思います。 (2011年1月19日掲載)
 4年9か月後に症状固定の右下肢RSD(H17.2.15)
4年9か月後に症状固定の右下肢RSD(H17.2.15)

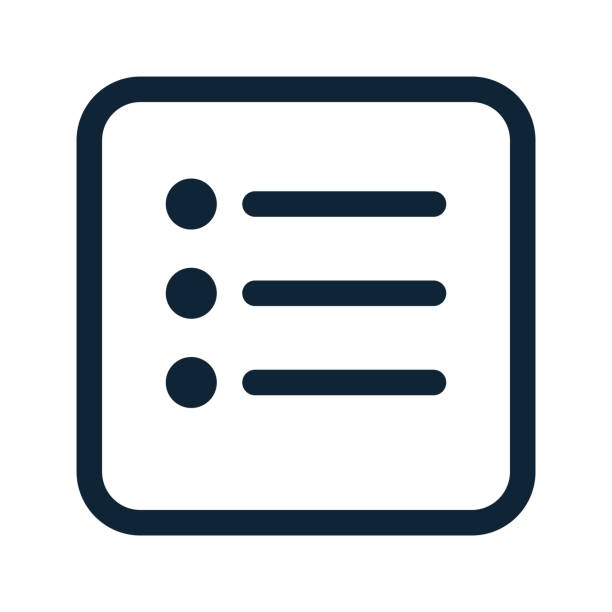 目次へ
目次へ