- 大阪地裁平成21年7月30日判決(交民集42巻4号955頁) この事件では、左下肢RSDが問題となっています。 この事案の特徴は、①RSDとの診断がかなり遅れた(事故から3年後)こと、②症状固定が事故から5年4か月後であること、③被害者が公務員で収入の減少がなかったこと、④7級4号としながらも現実の減収がないとして逸失利益を認めなかったこと、⑤被害者が受け取った地方公務員災害補償基金との損益相殺を否定したことなどです。
-
- 症状の経過
- 被害者は事故時20歳の女性(公務員、幼稚園教諭)です。被害者は平成12年5月6日に原付運転中に自動車と出会い頭に衝突する事故に遭います。 事故後、症状固定となる平成17年9月9日まで5年4か月を要したため、訴訟を提起した平成19年にはカルテの保存期間を過ぎてしまい、当初期の治療のカルテは訴訟には出ていません。このため事故後当初の症状ははっきりしません。判決ではカルテが出された以降の時期を含めて症状の経過を述べていません。 被害者側は、症状固定時に筋力低下、知覚鈍麻、疼痛などの後遺障害があり、軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があり、後遺障害等級7級4号に相当すると主張しています。
- 被害者は、事故後4か月ほど入院しているので、事故による傷害は当初から大きかったようですが、加害者の主張によるとRSDとの診断は3年経過後ですので、当初は外傷性腰髄損傷(第2、3腰髄)として入院したようです。 事故翌年の平成13年には半年ほど入院し、平成14年には1か月、平成15年には5か月、平成16年には2か月半ほど入院し、入院と通院を繰り返しながら治療を受けています。
- 事故の5年4か月後の平成17年9月9日にRSDと外傷性腰髄損傷と左下肢反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)との診断名で症状固定となりますが、その時点でも公務員として給与を支給されているので、入退院を繰り返しながらも仕事を続けていたようです。但し、入通院の経過などから症状固定までの間の就労は形式的なものであるように思われます。
-
- 事故とRSDとの因果関係
- 本件では訴訟に事故後早期のカルテが出されなかったことや、RSDとの診断が事故から3年を経過した時点であることから、事故との因果関係がはっきりしないことから加害者はRSDと事故との因果関係を否定して争っています。 加害者は、被害者に骨の損傷がないので、脊髄損傷の可能性も低いとの主張もしています。ただ、骨の損傷が脊髄損傷に不可欠とは言えないのでこの主張は根拠がないように思います。 加害者側は、被害者が疼痛(痛み)を訴えるようになったのは、事故から3年経過後であると主張しています。これはこの時期のカルテ等が保存期間経過により破棄されて訴訟に提出されていないため、疼痛は存在しないと主張したようです。判決では、関係者の証言により、事故直後から強い疼痛が存在したと認定しています。
- このように判決は、事故直後の症状を認定していますが、これは主として主治医の証言と被害者の供述に基づくもののようです。 判決は、被害者は本件事故前には現在訴えている症状がなかったこと、事故直後に入院した病院では、痛みが強く、全く動けないほどの激痛があったこと(事故後4か月入院しています)、入院翌日には左下肢が動かなくなっていたことに気付き、入院後1週間が経過した後も左腰を中心に強い痛みが残り、入院後1、2か月経過しても左足のむくみが継続していたこと、この症状は1年2月後の平成14年7月に他の病院に入院した際にも継続していたとします。 その上でこのような被害者の症状の原因となりうる事実は、本件事故以外には存在しないと認定しています。当然の認定のようにも思えますが、判決のこの部分は優れていると思います。 古いカルテが破棄された状況では、被害者に対してことさらに懐疑的な見方に至った裁判官であれば、被害者の主張を裏付ける書面が存在しないとし、さらに主治医や被害者の証言を信用できないとして否定する方向に進む可能性もあり(既に見た判決の中にはそのような判決もあります)、被害者側としては、事故直後から4か月も入院していたのにどこにも痛みがなかったなどという不合理な認定をするはずはないだろうと思いつつも一抹の不安を抱えていたのではないかと思います。
- 判決は、(主治医と思われる)証言などから、事故から約1年1か月後の段階では、左下肢の単麻痺様病態、左下肢の膝腱反射・アキレス腱反射の亢進、左下肢全体の感覚障害・知覚低下・軽い知覚過敏状態、左下肢全体の腫脹・皮膚温の低下の異常所見があったと認定しています。 この段階で、MRIで脊髄の実質内に病変が存在すると認められたことと、被害者の症状は脊髄半側に現れていることから、ブラウンセカール症候群と診断され、その治療がされたとします。なお、現在のCRPSの判定指標によれば、この時点でCRPS(RSD)との診断が可能であったと思われます。 その後のRSDとの診断については、被害者には、事故後局所の炎症が蔓延し、疼痛及び腫脹が持続したこと、関節の障害(拘縮)・感覚障害・感覚過敏が存在したこと、皮膚の温度差・浮腫・筋力の低下があり、ジストニア(筋失調症)があったと推測されることから、事故から3年以上経過した平成15年7月3日以降の治療のなかでRSDと判断されて、その治療が行われ、その効果が上がっていたとします。
- 判決は、事故から5年4か月経過した平成17年9月9日に症状固定となった時点では、左下肢優位の両下肢脱力、左下腿部の全体的な腫脹感と疼痛、左下肢全体の筋肉の緊張が認められ、非常に歩行が困難であり、典型的な後記RSDが認められたとしています。また、左下肢に残る痛みのため歩行が困難であり、職務遂行に支障がある状態であり、現在も歩行する際には、必ず左足に装具をつけて行動しなければならない事実が認められるとします。
-
- 後遺障害等級について
- 以上のように判決は、被害者が本件事故によりRSDを発症したと認定し、軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛が残存しているとして、被害者の後遺障害等級を7級4号としました。以上に至る判断は優れていると思います。
- これに対しては、「被害者の後遺障害が具体的にどのように労働に影響するのか不明である。」という観点から、後遺障害を低く見る考えもあり得ます。これまで見てきたRSD事案の判決の中には、RSDであることを認めながらも、局部の頑固な痛みに過ぎないとして12級という低い後遺障害を認定したものも散見されます。 このような判断の根底には、後遺障害等級を認定するためには、具体的な根拠が必要であり、①痛み等により具体的にどのような行動がどの程度制限されるのか、②その行動の制限が証明されているかということについての、程度の高い証明を求める考えがあるように見受けられます。 この点については、「他人の痛みは原理的に直接知ることはできない」というドグマを用いれば、常に証明不可能となります。このようなニュアンスの判決もまれに見られますが、通常は被害者の主張、医師の診断、入院や通院の期間・頻度や治療内容などから、痛みを推測していきます。 痛みがあること自体を認めたとしても、細かな行動形態の全てを列挙して、痛みと結びつけて「この行動はできない」と証明することは困難です。原理的に他人の痛みの程度を直接知ることはできませんので、痛みの程度が行動に関連する度合いを厳密に証明することは困難だからです。 しかし、RSD事案で12級という低い後遺障害を認定する判決には、このような考えが窺われます。もちろん、このような考えを正面から述べる判決はありません。この考えは、被害者側に不可能を要求するものであり、誤っているからです。この考えは、後遺障害等級7級4号の存在意義そのものを否定しかねないと思います。
- 本件の判決は、被害者が左下肢に残る痛みのため歩行が困難であり、職務遂行に支障がある状態であり、現在も歩行する際には装具をつけて行動しなければならない事実があると認定しました。 しかし、被害者側に厳密な証明を求めた場合にはこのような判断が(ほとんど常に)できない可能性もあります。労働への影響は実質的な判断であるので、個別の厳密な立証にもともとなじまない部分があります。 このことへの問題意識の有無が局部の頑固な疼痛であるとして12級にとどめる認定と、労働への影響を認める7級や9級の認定をする判決の分岐点となっていると思います。
-
- 後遺障害による逸失利益について
- 判決は、被害者に7級4号の後遺障害があるとしながらも、後遺障害による逸失利益は否定しました。この被害者は、長期間の通院中も症状固定後も、公務員として市から給与の支払を受けており、減収の事実が存在しないことは原告も被告も争いがなかったようです。 重い後遺障害があっても、公務員であるなどの事情により、退職に至らず収入の減少もないという事案はしばしば見かけます。定年までの期間を考えた場合には、重い後遺障害を抱えながら就労を続けることができる見込みは低いようにも見えますが、一方で、いつ退職するのか予想することはほとんど不可能です。
- 判決は、「将来の就労継続への不安も十分に理解しうるところであるし、現在の職を辞した場合に同等の給与の支払を受けることが困難であるとの主張にも理由があるというべきである。しかし、そのような事実がいつの時点で顕在化するのかについては、未だ明らかではなく、この点からしてもやはり後遺障害逸失利益を算定することは困難であるというべきである。」として、逸失利益を否定しました。 判決では、このことを考慮して後遺障害慰謝料を被害者主張の1000万円から増額して、2500万円としています。
- 以上のような判断に対しては、後遺障害による労働能力喪失率を後遺障害等級7級の通常の場合よりも低く見ることにより、調整する考えもあります。この考えは、形式上は減収がないとしても、残業ができなくなった分の減収や、昇進や昇給に不利に影響することなどを重視して、逸失利益を認めます。 被害者が、潜在的には転職して再就職をすることはほとんど不可能であるという制約があることや、家事労働が大幅に制約されることなども考慮に入れるべきかもしれませんが、この点は慰謝料でも考慮できます。 名古屋地裁平成22年7月2日判決(判例時報2094号87頁)は、被害者(公務員)が残業もして人並みに昇進・昇給している事案において、将来の昇給や昇格に影響が出る可能性もあるとして、11級の後遺障害に対して労働能力喪失率を14%(通常は11級であれば20%)として就労可能年限まで長期間の逸失利益を認定しています。
- なお、慰謝料を増額する考えによっても、本件のように大幅な慰謝料の増額を認めれば、結局はほとんど同じ金額になると思います。本件では被害者の主張する慰謝料(1000万円)を超えて、2500万円の慰謝料を認定しています。 (2011年2月5日掲載)
 5年4か月後に症状固定の左下肢RSD(H21.7.30)
5年4か月後に症状固定の左下肢RSD(H21.7.30)

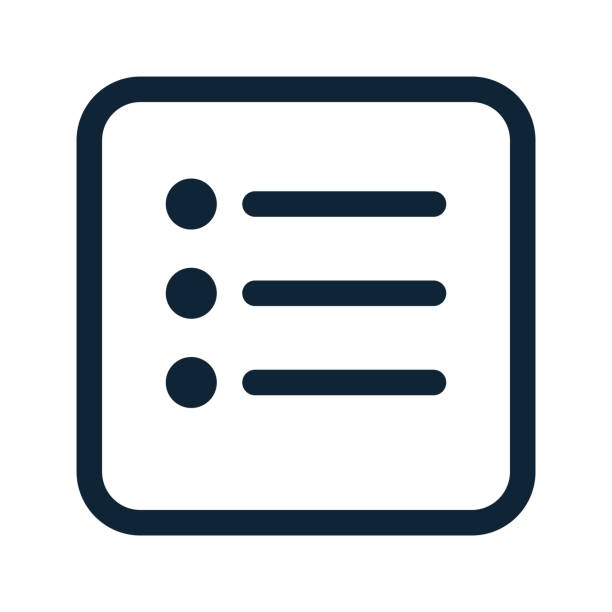 目次へ
目次へ