- 名古屋地裁平成16年7月28日判決(交民集37巻4号1020頁) この事件では、左上肢と左下肢のRSDが問題となっています。 この事案の特徴は、①左上肢RSDとして症状固定となった後に、左下肢RSDを発症したこと、②自賠責保険のRSD認定基準(3要件基準)が制定される前の事案であること、③左上肢・左下肢RSDとして併合5級2号としたこと、④心因的素因の主張を否定した部分の判決の判断が優れていること、⑤事故時27歳アルバイトの女性に女子労働者平均賃金を基準とした逸失利益を認めたことなどです。
-
- 症状の経過
- 被害者は症状固定時27歳の女性(アルバイト、内職、家事従事)です。被害者は平成11年12月28日に自動車を運転していて交差点で左折のため停止中に追突される事故に遭います。 追突した車両は時速50キロで走行していて直前で気付いて急ブレーキをかけたが間に合わず追突し、被害者の車は1.5m押し出されたとされています。 被害者は警察で事情聴取を受けて、車を修理に出したのち4時間後に病院に行きます。この間に背や首の左側の痛みや左腕、左手にしびれが出たと認定されています。担当医師は頚部挫傷、左上肢外傷性末梢神経障害と診断します。
-
- 事故10日後・・・左上肢の痛み、しびれ、浮腫(むくみ)を訴える。左上肢全体の筋力低下、知覚麻痺が認められ、外傷性末梢神経障害と診断される。しかし、その後の治療も効果がなく、症状は悪化し続ける。
- 4か月半後・・・左肩に痛みが出るとともに、左手の指にかけてつっぱり感が出る。その後、麻酔科を受診して星状神経節ブロックを受けるも、効果は30分程度に限られ持続しなかった。
- 5か月後・・・同じ病院の手の専門医に診断してもらったところ、RSDに特徴的な屈曲拘縮、皮膚萎縮、多発汗が認められ、「RSD様」との診断を受ける。
- 6か月後・・・左上肢の痛み、しびれ、浮腫が悪化し、痛みで夜に目が覚めることもあった。
- 7か月後・・・浮腫が認められ、第2指から第4指にかけて少しずつ可動域に制限が見られ、3指には腱癒着が認められた。洗顔、洗髪には右手のみを使用していると医師に述べ、左肩はどの方向に動かしても痛みがあり、しびれは手指末梢部にあり、中枢部は鈍痛となり、特に前腕内側部は重度鈍痛であるとされる。
- 9か月後・・・重度障害者を専門とする別の病院を紹介され筋電図検査などを受け、その後RSDであると診断される。
- 11か月後・・・入院して、疼痛緩和のためのケタミン点滴を受けるが効果は一時的で持続しなかった。その後も入院治療を受けるも改善せず。
- 被害者はその後も症状は改善せず、事故から約1年半後の平成13年6月14日に症状が固定したと診断されます。 傷病名は、頚部挫傷、左上肢外傷性末梢神経障害とされ、自覚症状は、「左上肢しびれ・痛み、筋力・知覚低下著明、著しい左上肢機能障害、廃用手」とされ、他覚症状および検査結果は、「左上肢筋力・知覚低下、左手指拘縮著明」等とされます。この時点でRSDを発症していたことは、現在の判定指標においては問題なく認められます。 しかし、後遺障害診断書では、傷病名が左上肢RSDとはなっていないようです。RSDとの診断は後遺障害診断をした病院とは別の重度傷病者の専門病院でなされています。 この状況に至ってもRSDとの診断に躊躇することは、適切ではないと思いますが、RSDとの判断に慎重になりすぎることは判例の事案の上でも良く見られます。
-
- 後遺障害認定
- 平成14年2月18日に自動車保険料率算定会は、事故によりRSDを発症したとし、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として、7級4号に該当すると認定しました。 主治医は、「左上肢は、日常生活においてほとんど機能不可能な状態をきたしている。」との診断をしています。
- この時点では、現在の後遺障害認定基準が定められていなかったことから、自賠責の後遺障害手続では被害者の症状を実質的に認定して、7級4号と認定しています。 現在の認定基準は、厚生労働基準局長による平成15年8月8日付の基本通達「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等認定基準について」(基発第0808002号)によります。自賠責保険の①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という3要件はこの通達により定められます。この基準が後遺障害認定で用いられるようになるのは、平成16年頃からですので、この事件では用いられず、訴訟でもこの基準による主張はなされていないようです。 この事案で自賠責保険の3要件基準を適用すると、骨萎縮の要件を欠くとして、RSDではないとされて非該当(または14級)とされるおそれがあります。7級4号という判断とは大きな隔たりがありますが、そのような判断が少なくないことは、すでに紹介してきた判決のとおりです。
- 現在の3要件基準については、RSDにおいては必須の症状(必ず生じる症状)が存在しないことが国内外の医学学会で完全に異論のない状況で何ゆえ3つもの要件を必須としたのか、しかも「明らか」な症状が必要であるとしたのか極めて疑問ですが、この事件の当時にはこの問題は生じていません。 自賠責の3要件基準が制定された以後の事案は、それ以前の事案に比べるとRSDの該当性判断の部分で明らかな劣化が見られます。それ以前の判決では、実質的な判断により被害者の救済がなされているものもありますが、3要件基準以後の判決には3要件を無批判で受け入れた形式論理により、実質論を否定する劣化が生じる裁判例が多く見られます。
-
- 左下肢に症状が生じる
- 被害者は、事故から約1年半後の平成13年6月14日に左上肢RSDが症状固定となりますが、その2か月後の8月21日に左頚部に星状神経節ブロックを施術した翌日から、左下肢に症状が出現します。 1か月後の9月26日には、左下肢RSDとの診断を受け、その後も左下肢の症状は悪化し続け、歩行困難(数百メートルまでは松葉杖での歩行ができる)となり、車椅子を使用するようになります。
- このようにRSDでは、患部とは別の四肢に症状が生じることがあるとされ(ミラーペイン)、すでに検討した判例の上でも症状が他の四肢に拡大した事案がいくつかあります。
-
- 事故とRSDとの因果関係
- 裁判では、後れて発症した左下肢RSDと事故との因果関係が問題となりました。判決を読む限り、左上肢RSDについては、加害者(被告)も争っていないようです。 加害者は、左下肢の症状がRSDであるところまでは争っていないので、因果関係のみが争点となっています。現在では自賠責保険の3要件基準の厳格適用を加害者側が主張することが通常で、加害者側は重度の骨萎縮やさらには筋萎縮を必要であるとする医学意見書を提出して争うことが多いようですが、この事件ではRSDの存否そのものは争われていません。
- 判決では、①RSDは交感神経の異常として発症し、外傷を受けた場所とは別の場所に出現する可能性があること、②外傷等の程度に比して驚くほど重篤な後遺症を残すことがあること、③治療経過中に症状が発症したという推移、④本件事故による外傷とその後の治療行為以外にはRSDを発症する事情は窺えないことを述べて、左下肢のRSDも事故をきっかけに生じたものとして因果関係を認めています。 要点を押さえた非常に優れた認定ですが、判決の理由のうち、①については交感神経の異常による説明を普遍化しない現在のCRPSという概念においては、CRPS患者には疫学上ミラーペイン(症状の転移)が見られるという説明になります。
-
- 素因について
- RSDにおいては、加害者側からの素因の主張は定番といえます。本件では加害者側は、遺伝的な素因として心因的素因の存在を主張しています。RSD患者は依存的な性格であり、訴えが多く、恐怖や疑惑に満ちており、情緒不安定であることが多く、これらの患者は痛みに対する感受性が高く、通常では我慢できるような痛みも耐えることができないと訴えるほどであるとして、全てのRSD患者には遺伝的な素因としての心因的素因があるとの主張をします。
- この事件では、主治医の中に被害者の心因的問題を重視した医師がいたという加害者側に有利な特別な事情があります。加害者は、被害者の担当医の1人が「MRIの結果、頭部、頚部とも問題ないと考える。ヒステリーの可能性が高い。神経・精神科を受診するように」と診断していたことを引用します。この医師は、「心因的要因が加わって症状が悪化している。」と判断して、被害者に神経・精神科の受診をすすめます。 被害者は、神経・精神科で「心身症の疑い」、「神経症、不眠症、うつ状態」と診断され、さらに「左下肢および左上肢の症状は、PTSDに伴うヒステリーが疑われ、ICD-10及びDSM-Ⅳの基準に該当する」とも診断されています。 激しい痛みが続き、大きな後遺障害の残るRSDの事案においては、精神状態が悪化する患者が少なくないため、精神科において何らかの精神的問題を診断される患者は少なくないと思われます。RSDをよく知らない医師から見れば、患者に精神的な問題があると感じることの方が自然であるのかも知れません。
- 判決は、まず①「RSDになりやすい遺伝的な素因の存在の証明は必ずしも容易ではなく、また常に存在するものではない」との医学書の記載を引用します。たしかに医学的にはRSD(CRPS)を発症する遺伝的な素因の存在は確認されておらず、これを否定する考えが医学的には圧倒的な通説です。 判決は次に、②被害者の診断をしたほかの医師が、被害者を明るい性格で、不定愁訴がなく、痛みの存在をあまり見せないという性格であると感じ、被害者のような性格の人間はRSDにはり患しにくく、被害者にはRSD発症の精神的な素因は見られないと判断していることを述べます。 この部分は①を前提とすると論理の上では蛇足ですが、①を否定する見解に対する反論に位置づけられます。 判決は、さらに③加害者の指摘する被害者の言動や被害者への診断は、被害者の症状が悪化するなかでの言動を捉えたものであるとします。激しい痛みと重い後遺障害の生じるRSDにおいては、当然の判断とも言えますが、他の判例と比べるとやはり優れた認定であると思います。 判決は、④交通事故の被害者は、治療が長期化し、その補償交渉が進展しない場合には、精神的に不安定な状態に至ることはよく知られていると述べます。この部分は、むしろ賠償交渉に左右されるのは、賠償性の神経症状であるとして、被害者の素因認定に用いる考えもありうるところですが、一般的に生じうる範囲の精神的な状況に関しては、この判決の考えは正しいと思います。 判決は、⑤RSDに対し有効な治療法がないことを、④と併せて考えれば、⑥通常人が被害者と同じ立場に置かれた場合には、被害者と同程度の精神的に不安定な状態になることは容易に推認され、被害者のこの時期の言動を捉えて、被害者のRSDの発症が被害者の精神的素因に起因すると認めることはできない、とします。正しい判断です。
- この判決は、素因を否定したこの部分が特に優れているとして、いくつかの文献でも引用されています。もとより医学的にはRSDについて素因の存在を否定する考えが圧倒的な通説です。 しかし、RSD事案では、精神科医の診断さえない状況で3割以上もの大幅な素因減額を認めたものが散見されます。特定の精神疾患の診断もない状況で被害者の言動に懲罰を与えるような形で素因を認定することには、非常に問題があるといえます。 素因として「特定の精神疾患」を同定し、その「特定の精神疾患」がRSDを引き起こす可能性が高いという医学的統計を示さなければ、素因によりRSDが生じたとは言えないはずです。 しかし、素因を認めたほぼ全ての判決は、そのような論理構造を有せず、被害者の何らかの言動(特定の精神疾患ですらないもの)に懲罰を与えるような形のあいまいな対応関係しか存在しません。しかし、その被害者の精神状況は事故による激痛と重い後遺障害が引き起こしたものであることからは、この考えを支持することはとてもできません。 本件のように、主治医が精神的な問題に原因があると判断して、精神・神経科の受診を勧め、精神・神経科において精神的な問題を診断されている事案においても、その特定の精神疾患が事故前から存在していたことが確実に認定でき、かつその特定の精神疾患がRSDを引き起こす可能性を高めるという医学的統計が示されない限り素因を認めることはできないはずですので、この判決が素因を否定したことは当然であると言えます。
-
- 後遺障害等級について
- 判決は、被害者が本件事故によりRSDを発症したと認定し、左上肢と左下肢の双方について、軽易な労務以外の労務に服することができない後遺障害があるとして後遺障害等級を7級4号とし、これらの併合として後遺障害等級5級2号を認めました。この部分も優れていると思います。この判決は、この時期の判決としては突出して優れた事実認定をしていると思います。
- なお、軽易な労務以外の労務に服することができない後遺障害が左上肢と左下肢に存在することだけでは直ちに5級2号とはなりません。 判決ではこれらの加重の結果、その労働能力は労務遂行の巧緻性や持続力において平均人より著しく劣り、一般平均人の4分の1程度しか残されていないと考えられると述べています。 (2011年2月27日掲載)
 左上肢.左下肢RSDを併合5級と認定(16.7.28)
左上肢.左下肢RSDを併合5級と認定(16.7.28)

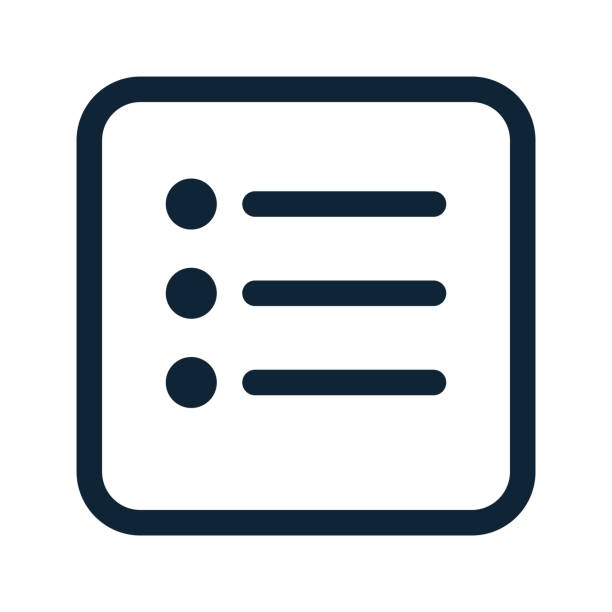 目次へ
目次へ