- 大阪高裁平成21年9月10日判決(自保ジャーナル1818号100頁) この判決は以前に検討した大阪地裁平成21年4月9日判決の控訴審判決です。この判決の特徴は、①被害者側が請求額を増額したこと、②これに対して加害者が時効の主張をしたこと、③医学基準を超越した特別に厳しいRSD認定基準(二重のしぼり)を採用した地裁判決を維持したこと、④他の病院への紹介状(報告書)の記載を重視して心因的な問題の根拠として特に高裁で付け加えたことなどです。
- 請求額の増額 1審の時点での被害者側の請求額は1000万円と低額でしたが、これは加害者(損保)側が債務不存在確認訴訟を提起したのに対応して、被害者側が急きょ対応した結果のようです。 即ち、被害者側は損害額全体をその時点で確定させることはできないとして、損害額のうちの1000万円を請求するという内金請求をしたため、1000万円という低額の請求となったようです。被害者は高裁で4000万円に請求を拡張しています。
-
- 時効の問題
- 民法724条前段は、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定めています。被害者側が「損害及び加害者」を知った時点が時効の起算点となるのは、この両者を知っていればその時点で加害者に請求できるからです。請求できるのに請求しなければ、そのときから時効が進行します。法律ではその期間が3年とされています。
- 簡略化すると交通事故の場合には原則として事故日が時効の起算点で、後遺障害が認められた場合には症状固定日が時効の起算点といえます。 但し、時効の問題は例外を考えると複雑になります。例えば事故後に入通院して治療を続けている間は損害が確定していないので、損害を知っているとはいえないので、「治療終了時点」が起算点になるはずです。 また、加害者の保険会社が治療費を支払っている場合には、その治療費の支払いは損害の全体に対する一部の補填ですので、損害全体に対する確認行為として時効を中断することになるはずです。 このように細かく考えると、時効を中断する可能性のある事柄は色々とあるのですが、必ずしもこれらの事柄で確実に時効が中断するとは言い切れない面があります。従って、後遺障害が認められないときには、事故日から時効が進行すると考えて行動する方が良いと言えます。
- 後遺障害が認められた場合には症状固定日が起算点となるというのは比較的最近の最高裁判例です(最高裁平成16年12月24日判決、判例時報1887号52頁、私法判例リマークス32号64頁)。 この最高裁判決の事案は、被害者が平成8年10月14日に交通事故に遭い、平成9年5月22日に症状固定となり、後遺障害等級には該当しないとの認定を受けたため、平成11年7月30日に異議申立をしたところ、その後12級12号の認定を受け(この認定日は判決では不明です)、平成13年5月2日に訴訟を提起したというものです。 この事件では被害者が後遺障害に該当しないとする判断への異議申立をした時点で症状固定から2年10か月ほど経過しています。従って、後遺障害認定を受けた時点では、症状固定日から3年以上が経過していたと思われる事案です。 そこで1審(地裁)、2審(高裁)は、時効の起算点は、異議申立により12級12号の認定を受けた時点であるとして被害者を救済しましたが、最高裁は症状固定日が時効の起算点になるとしました。
- 後遺障害に該当しないとの判断を受けて異議申立をしたところ、かなり経過してから判断が出ることは私の経験でもしばしばあります。特にCRPS(RSD)のような難解な医学的問題を含む事例では、異議申立をしたあとにかなりの時間が経過してから判断が出ることが少なくないと思います。私の経験でも初回の後遺障害の認定まで1年以上を要していた事案が何件かあります。異議申立による再度の判断となると2年前後を要することはしばしば見られます。 この場合に異議申立の手続に時間がかかっている間に時効になってしまったというのでは、被害者には酷であるように思います。この時点では被害者は弁護士に相談していないことも少なくないので、被害者が気付かない間に時効となる可能性があります。 従って、最高裁判決のように症状固定日から時効が進行すると考えると、被害者が弁護士等に相談せずに後遺障害認定の手続を行っている間に時効が成立してしまうという酷な状況を回避できなくなります。
- これに対して最高裁判決の根拠は「後遺障害認定にこだわらずに訴訟を起こせば、時効にかからなかった。」ということに尽きます。この形式論理は被害者の主観(認識)を基準とする民法724条前段の解釈としては難があります。被害者は後遺障害認定を受けて初めて、例えば「自分は9級である。」などの認識を得ることができるので、この時点でやっと「損害を知った。」というのが実情でしょう。 後遺障害認定手続を経た後遺障害認定には権威があり、後遺障害認定手続で決められた等級は容易には変更されないと言えるので、この手続を経ることによりようやく自分の後遺障害の度合いを認識できる被害者は少なくないと思います。このように社会の現実のあり方を考慮に入れることは、民法166条1項が消滅時効の起算点とする「権利を行使することができる時」について、実質的な面も考慮している判例とも整合しやすいとも言えます。 しかし、後遺障害認定に対して異議申立ができる期間は限定されていないことや、異議申立は何回でもできることから、後遺障害認定手続を基準とすると、被害者側はいつまでも時効にかからなくすることができるというのも事実です。最高裁判決はこの実質論も重視したと思われます。 私は、「訴訟を提起できるほどの特定性をもって損害及び加害者を知ったといえるか。」という被害者の認識についての事実認定の問題は、事案ごとの合理的な判断をするべきで、一律に症状固定日を時効の起算日とする必然性はないと考えています。 この考えは明確な基準が導き出せないと批判されるでしょう。これに対しては、私は被害者の主観を基軸とする民法724条前段は事実認定の問題であり、その事実認定の問題に画一的な基準を求めることが誤りであると反論します。従って、一応は症状固定日を前提としつつも、後遺障害認定手続の実態に応じた例外を柔軟に認めるべきであると思います。しかし、最高裁判例は多数説の支持もあり、容易には変更されないので、注意する必要があります。
- 本件では、被害者側は両下肢RSDを前提として、平成17年12月28日を症状固定日と主張しているのですが、加害者側はRSDを否定して平成15年9月24日が症状固定日であると主張しています。 このように症状固定日を基準とすると、RSDが認められればそれに合わせて症状固定日が遅くなり、RSDが認められなければ症状固定日が早まります。被害者にしてみれば複数の主治医がRSDとの診断を繰り返しているので、最高裁判決を前提としても、被害者が「損害を知った」(民法724条前段)のは、RSDとして症状固定をした日であるとするのが自然でしょう。 民法724条前段によると被害者が損害を知ったという被害者の主観が時効の起算点の基準になるはずで。その認識と後遺障害としてRSDが認められるかどうかとは本来は別次元の話のはずです。 しかし、最高裁判決は被害者の犠牲のもとで「症状固定日が時効の起算日である」という形式論理を採用した判決であることからは、具体的な事情を考慮しない形式論理が貫かれる可能性が高いと言えます。それはもはや「被害者が損害を知った」との事実認定とはいえないのですが。
- 最高裁判決の形式論理を重視すると、本件の高裁判決はRSDを否定したので、被害者が高裁で追加した請求は時効にかかっていることになりますが、判決ではこの点は判断していません。判決は被害者が地裁で主張していた1000万円の範囲内で損害を認めたので、拡張部分の時効の判断をする必要がなかったからです。 そうであれば、そもそも加害者側が時効の主張をしていることを判決文に記載する必要があったのかという疑問も感じます。
-
- RSDの認定基準
- この事件の原審である地裁判決は、RSDの認定基準について、「二重の絞り」という医学基準を超越した非常に厳しい認定基準を用いています。 すなわちRSDの4主徴(疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化)と、自賠責保険のRSDの3要件である①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化が明らかに認められることの双方が必要としています。
- しかし、CRPS(RSD)の基本的かつ最大の特徴は、特有の症状がないこと、つまり必ず生じる症状が1つもないことであるので、必須の症状を非常に多数必要とするこの判決の基準はもとより論外です。CRPSにおいては、必ず生じる症状が1つも存在しないことはかなり古くから定説とされてきたことであり、今現在でもこのことを否定する学者は世界中に1人もいません。 国際疼痛学会(IASP)やアメリカの学会や日本の学会は、4主徴(日本ではこれを5つに分類)のうち、2個を満たせば原則的にCRPSが肯定されるという判定指標を導入しています。 ちなみに日本での判定指標は、4主徴を5項目に分けて、このうち2つが病期のいずれかの時期に自覚症状として該当し、診察時に2つが該当すれば判定指標を原則として満たします。もちろん、5項目のうち1個しか満たさなくとも、鑑別診断で他の疾患の可能性が否定されるなどの状況においてCRPSと診断することも可能です。これは5項目のうち2つを満たす患者はCRPS患者の8割ほどしかいないという統計に基づいています。 このように5項目のうち2つを満たせばよいという緩い基準によっても、CRPS患者の8割ほどしか捕捉できない(感度82.6%)ことが統計上認められています。
- これに対して、この事件の地裁判決は、4主徴の全部と自賠責保険の3要件全部が症状固定時において必須であるという、途方もなく厳しい基準を用いています。この種の訴訟に基本的な医学知識が提出されないまま判決が出されることが多いとは言っても、これはちょっと度が過ぎる感じがします。 この基準では実際のCRPS(RSD)患者のうちの特に重症な1~2%くらいしか捕捉されないのではないかと思います。この基準は加害者側の医学意見に基づくものであると思われます。 これまで紹介してきた判決のなかで、加害者側が提出した医学意見書のなかに、「RSDには特有の症状がない」という初歩的かつ基本的な知識を述べたものは見当たりません。それどころか、必須の症状を多く主張し、ときには「重度の骨萎縮」が必須であるなどという暴論を述べ、さらには筋萎縮も必須である(筋萎縮を判定要素の1つに含ませる医学基準はいままで一度も作られたことがないはずです)という医学意見を述べるものもしばしば見かけます。腹立たしいことに裁判所選任の鑑定人による医学鑑定書でさえこのような意見を述べるものが見られます。
- このような医学意見書は加害者側に迎合したものであると言わざるを得ませんが、既に検討した判例のなかには、そのような医学意見書を書いた医師が有名大学医学部で高い地位にあり、さらには訴訟で証人として出廷して証言していた事案もあります。 私の経験した事案においても、裁判所の選任した鑑定人(有名大学医学部で高い地位にあったRSDを専門とする極めて高名な医師)が、鑑定書において4主徴のほか重度の骨萎縮や筋萎縮の必要性を力説し、身体的素因が8割かつ心因的素因7割と述べ、監視カメラ付きの部屋に長期入院させるべきであるなどと被害者の詐病の可能性を非常に強く述べていたことがありました。 この事案ではこの鑑定書が原因となり地裁で敗訴した後、被害者に全身麻酔下での可動域検査を受けてもらい、患部がガチガチに固まっている状況を私自身も手術室に入ってビデオ撮影した結果、高裁では詐病ではなくRSDであるとの判断を受けています。
- 裁判官が専門的な医学知識を有しない分野において、華々しい経歴の医師の名を冠した医学意見書が出されると、それを妄信してしまうことはやむを得ないのかも知れませんが、本件では被害者を診察した複数の医師がCRPSとの診断をしているという事実を重視すべきであったと思います。また、CRPSにおいて必須の症状が1つもないというレベルの基本的な知識は当然に持っていてしかるべきです。 専門病院の主治医がCRPS(RSD)であるとの診断をした場合において、その診断が誤っている事前確率について私は1000分の1以下(おおよそ1万分の1ほど)であり、複数の医師が診断した場合には、さらにその確率が低くなると考えています。 しかし、これまで見てきたとおり、被害者が医師によりCRPS(RSD)と診断された事案のほとんど全てにおいて、加害社側は条件反射のように「それはRSDではない。詐病である。」という主張をなし、これを裏付ける医学意見書を提出してきます。 この構造においては事案の中身を検討する以前の段階で、加害者の主張が正しい可能性(事前確率)は、おおよそ1万分の1ほどではないかと思います。RSDという事案におけるこのような全体像が見えていれば、専門病院の主治医がRSDと診断した事案において、安易にその診断が誤診(医療過誤)であると認定することはないと思います。 交通事故訴訟は医療過誤訴訟ではありません。難病患者に対して最終的な診断を下した大学病院や専門病院での主治医の診断が誤りである可能性は、概ね1万分の1以下であるという基本構造が見えていれば、問題はシンプルになると思います。
-
- 診療情報提供書
- この事件の高裁判決では、主治医が転院先の他の医師にあてて書いた診療情報報告書を数件引用して、わざわざ地裁判決に付け加えてその判断の根拠としています。 これによるとC病院のP医師が平成16年7月14日付でQ医師にあてて書いた報告書には、「病名:CRPS。いつもお世話になります。前回(平成16年1月19日の診察を指すと解される。高裁判決の注書き)と変わらず、自分の疾患(?)を作っておられます。お手上げ状態です。よろしくお願いします。」との記載があります。
- 同じP医師がD病院の麻酔科Eクリニックから、Q医師にあてて平成16年9月9日に「お返事」と題する書面には、8月30日と9月8日に診察した結果の診断名が左下肢複合性局所疼痛症候群(CRPSタイプ1)であり、「交通事故による傷害部位からは予想もできない範囲まで痛み、しびれ、不快感が及んでいるCRPSと考えます。左下肢の血流低下もありそうで、交感神経ブロックなどが、有効かと考えています。しかし、ご本人は、かなり神経質で、思い込みも強く、治療には難渋しそうです。まずは薬物療法などを行いたいと思います。」との記載があります。
- F病院のR医師がB病院あての診療情報提供書において、傷病名を左下腿RSDとした上で、「平成15年9月受傷でもあり、本人には後遺症として残とMT(ムンテラ=説明)しました。当院では、リハビリは施行しません。また、腰についても事故とは関係なく、保険では診ますが、事故としては当院にて扱いませんと患者に強く説明しました。貴院にて、事故後長期経過しているにもかかわらず面倒をみてくれているならそちらでリハビリを続けなさいと説明させていただきました。また、「心」の病だということ十分に説明させていただきましたが、…納得されていない様子でした。」との記載があります。
- これらの引用ののちに、判決では「いずれの医師も控訴人の症状が心因的要素に基づくものであることを強く示唆している」としています。 私も経験があるのですが、診療情報提供書は診断書のような厳格性が要求されないことから、おおざっぱな記載がなされ、事実に反することや、安易な表現が用いられることが少なくないようです。診療情報提供書は自分ではうまく行かなかった患者を他の病院に紹介するときに作成することが多いので、患者への恨み節が記載される傾向もあります。 このような不確実、不安定な証拠のうち判決の立場に都合の良い部分だけをつまみ食いするということはしばしば見られます。本件では、すべての診療情報提供書がCRPSであることを前提としているという基本部分を無視し、被害者の精神状況を非難する方向にのみ証拠を重視しています。 現場の医師のなかには、CRPSという病態においては心因的な要因によって患者が必要以上に痛みを強く訴えているという感想を抱く方がいるとしても不思議ではなく、むしろ実感としてそのような感想を持つ医師がいる方が自然かもしれません。 CRPSという疾患に不慣れな医師のなかには、「本当は精神的な疾患ではないか」と疑う方は少なくないかも知れません。しかし、そのような感想を医師同士が伝え合う書面を証拠として重視することは、適切ではないと思います。ましてやその感想によって医師が公的にはCRPSと診断していることを否定することは本末転倒です。
- また「患者が重度の後遺障害でナーバスになっていますよ。」ということを他の医師に伝えることが、患者の心因的要素を強調したものとなることは思えません。 CRPSの患者には、激しい痛みが日常的に続いたことや、その結果として重い後遺障害が残ったことなどから、精神的な状況が悪化している方が少なくないというのは事実ではあると思いますが、このこと故に精神的な問題があってそれが原因でCRPSを発症したと言われる筋合いはないと思います。医学会での圧倒的通説は、心因的要因によりCRPSを発症するという論理を否定しています。
- 以上の問題とは別に、判決が3つの報告書を、同列のものとしていることは、もとより誤りではないかと思います。これを同列のものとしたのは、これらを「あるバイアス」から見たことそのものを裏付けるものとなっています。 判決は、「これらの医師は被害者が本当はCRPSではないのに、被害者からの何らかの圧力や、被害者に迎合したことにより、嫌々CRPSという診断をしたのであって、被害者の見ていない医師同士のやり取りのなかでは、被害者の詐病を伝え合っていた。」という解釈を示唆するものとして、これらを並列化して引用しているように見えます。 これは確証バイアスの特徴的な出かたで、自分の考えに都合のよい証拠により高い価値を見つけ出すという人間の自然な認知活動が良くない方向に特徴的に出たものと言えます。その結果、自分の考えに不都合な証拠は誤った証拠(捏造された証拠、迎合して書かされた証拠など)として排除する方向に向います。 被害者の(実質)詐病を認定する判決には、この方向に向うものがしばしばみられます。この場合の確証バイアスの特徴は、同調事例を列挙して自分の考えに沿う部分のみを重視する(もしくは、自分の考えに沿うように証拠を組み立てなおした上で同調事例として列挙する)という点にあります。この場合には不確かな証拠であっても必要以上に重視される傾向があります。 さらに都合の悪い証拠に対しては、それが捏造されたものであるとするための謀略史観が導入されます。詐病を認定する場合には、医師が患者の圧力に屈した(患者に迎合した)結果、本位ではない診断をしてしまったという事情を示唆する方向で認定する傾向があります。 判決が3つの報告書を引用しながら、その報告書の全てがCRPSとの診断を前提としていることを無視したのは、これらの報告書をCRPSとの診断を否定する証拠となると理解しているように見受けられます。それは「医師が患者に迎合して心ならずもCRPSとの診断を下した。」というニュアンスにおいてです。 確証バイアスというと、特殊な理論のように思われるかもしれませんが、家事事件では夫(妻)の浮気を疑う妻(夫)の心理状態として頻繁に見られます。何でもかんでも浮気を疑う方向に解釈してしまうというこの心理状態と、詐病を認める方向に多くの証拠を解釈し直す認知作用とは基本的な構造が同じです。
- 確証バイアスは、ある証拠群から一定の証拠を選択して事実を認定するという訴訟の構造のなかにおいては、不可避に生じるものではないかと思います。「一定の視点から見た場合に整合する証拠」をピックアップすることは、それ自体には問題はありません。問題なのは整合する証拠の価値のみをことさらに高く見ようとすることにあります。 都合のよい部分のみに注目すると、その視点に適した証拠を見つけることはそれほど困難を伴わないため、たいていの場合にその見方を支持する証拠(の部分)を見つけることができます。確証バイアスに囚われると、いくつもの見方が同時に成り立つ状況でたまたま1つの見方だけをして、他の見方を排除してそのまま結論に至る可能性があります。 これを避けるためには、同調事例の列挙ではなく反証の否定を重視すること、証拠の読み替えをしないこと、不都合な証拠を捏造や迎合であるとして排除しないことなどが必要とされます。 もとより個別の証拠に囚われずに事案全体の整合性を常に考慮に入れることや、ある証拠がどこまでの価値を有するのかを正しく見極めることなどの基本的なことが重要であることはいうまでもありません。
- この点に関して注意すべきことは、要件事実論などによって証拠を序列化して考える傾向のなかでは、事案の全体像と整合しない思考に向うおそれがあることです。もとより要件事実論は証拠の序列化を導くものではないはずですが、その傾向は否定できません。証拠をパターン化して序列化していく考えに陥ると、ある証拠がその事案の全体像のなかで本来有する価値を見極めることの重要性が見落とされる面はあると思います。 自由心証主義のもとでは要件事実論における要件の有無とは別次元のものとして一切の事実を考慮した上で事実の有無を判断します。例外的に事実の有無について心証を形成できなかった場合に初めて証明責任に頼った判断を行います。その判断のなかで要件事実の証明責任を考慮した枠組みが用いられるはずですが、自由心証主義レベルの判断と証明責任レベルの判断が混在している判決はしばしば見られます。 この類の判決のなかには、まず要件事実の判断を証明責任により行い、これを基点として自由心証主義による細部の辻褄あわせをするという構造のものさえもあります。自由心証主義で心証が得られない場合に証明責任を用いるべきで、最初に要件事実に証明責任を適用し、その結果を自由心証主義で補強することは誤りと言うほかありません。 このようにして証明責任により結論を導いた判決には、それがいかに不自然、不合理なものでも「証明責任による判断であるから正しい」と考える傾向が窺われます。しかし、証明責任を適用した結果導かれる事実が不合理であることは、その論理が背理法により誤っていることを意味します。もちろんこれは自由心証主義レベルで考察すべきことです。 また、裁判では書面化された証拠を必要以上に重視する傾向にも陥りやすくなります。これは訴訟に特有の利用可能性ヒューリスティックと言えるものです。
- 本件では医師同士の非公式な報告書の価値は、正規の診断書の価値に遠く及ばないという基本構造を、きちんと出発点で認識することが大切です。この構造を変更することが「証拠の読み替え」です。証拠を読み替えは、意識しないと自分が証拠を読み替えていることに気付けないので、注意が必要です。 確証バイアスが強く作用すると、「公には言えない本音がここにある。」という方向に向かい、証拠を本来の意味とは逆の方向に解釈することとなります。たしかに堅苦しい公式見解より軽口の類の方が、本音が出ているという場合もあるのですが、場合によりけりでしょう。軽口はあくまでも軽口であるというのが基本です。軽口は無責任になされます。診療情報提供書は診断書ではないので、その記載について医師は責任を負いません。 (2011年8月2日掲載)
 両下肢RSDの否定(高裁 H21.9.10)
両下肢RSDの否定(高裁 H21.9.10)

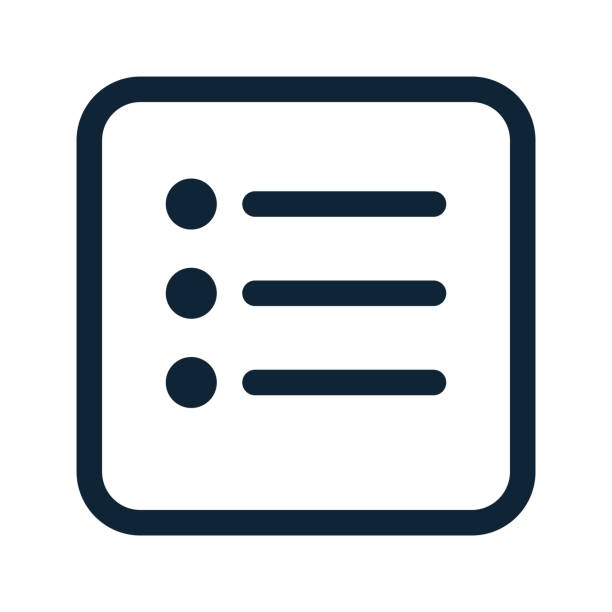 目次へ
目次へ