- 金沢地裁平成21年9月18日判決(自保ジャーナル1848号116頁) この事件では、右手CRPSが問題となっています。この事案の特徴は、①橈骨遠位端骨折に起因する手首のCRPSであること、②症状固定後に悪化したとの主張があり、再度後遺障害診断がなされたこと、③CRPSの診断基準が判決には明示されていないこと、④症状の悪化それ自体の有無を判断せずに事故との因果関係を否定する論理(抱き合せ証明論)を用いたことなどです。
-
- 症状の経過
- 事故当日・・・右橈骨遠位端開放骨折、右遠位橈尺関節脱臼、歯牙破損等の傷害を負いB病院に入院(93日間)。
事故による直接の怪我は手首部分の骨折と脱臼ですが、入院は3か月に及んでいます。入院が長引いたのは骨折に起因した痛みが蔓延化してCRPSの発症につながったとの事情によるようです。 - 1か月後・・・平成17年1月26日頃から、遠位橈尺関節の痛みや、尺骨神経領域の知覚鈍麻が出現するようになった。
- 3か月後・・・3月29日にF病院(2月10日より通院していた)で「RSD様の訴えが始まっているので、星状神経節ブロック等をするように」との指示がB病院麻酔科にされる。指示を受けたB病院で、アロディニア(体の震えですら痛みが生じる、さわるだけで痛みが生じる、という痛覚の過敏)や強い筋萎縮が確認され、神経ブロックが功を奏した。その後にCRPSと診断される。
- 半年後・・・7月4日~8日までB病院に入院(この事情の詳細は判決からは不明ですが、症状の悪化によるものと思われます)。
- 1年3か月後・・・症状固定による最初の後遺障害診断(第1診断・平成18年3月31日)。右手関節の可動域制限について、掌屈55度(左は自動・他動とも90度)、背屈45度(左は自動・他動とも90度)、回内(手首の内側へのひねり)30度、回外50度。握力は6kg(左は22kg)。
- 1年8か月後・・・審査会にて後遺障害等級併合12級との判断がされる。その理由は、①右手関節の可動域が4分の3以下に制限されていることから「関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)に該当すること、②右前腕の回内、回外の制限については上記に含めての判断となること、③右前腕の右手指(母指、示指)、右手関節(尺側)のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)に該当することとした。
- 1年9か月後・・・2度目の後遺障害診断(第2診断・平成18年10月5日)。右手関節の可動域制限が、掌屈40度(他動)ないし30度(自動)。背屈25度(他動)ないし10度(自動)。握力は4kg。
被害者は事故時37歳位(症状固定時39歳)の女子運転代行アルバイトです。被害者は平成16年12月29日に勤務先の社長の運転する車両助手席に搭乗していて、右折してきた対向車との衝突事故により怪我を負います。
- 事故当日・・・右橈骨遠位端開放骨折、右遠位橈尺関節脱臼、歯牙破損等の傷害を負いB病院に入院(93日間)。
-
- 橈骨遠位端骨折について
- 医学書には本件と同じ橈骨遠位端骨折の場合にCRPSの発症率が特に高くなると述べるものがいくつかあります。CRPSは受傷の部位や態様によって発症率に違いがあります。これに対して、特定の身体的・心因的素因によって発症率が高くなることは確認されておらず、医学的には素因の存在を否定する考えがほぼ定説です。
- 本件は橈骨遠位端骨折というCRPSの発症率が最も高いとされる傷害を負い、その部分にCRPSを発症したという典型的なCRPS発症例の外形があります。ただし、この症例は裁判例の中ではかなり少数です。 裁判例で最も多いのは片方の上肢の肩、肘、手関節の可動域が著しく制限される重症例です。判例の事例の大半は重症化したRSDの事案であり、日本では重症化しないとRSDと診断されない傾向があるようにも思われます。ただし、橈骨遠位端骨折が生じる事故が少ないため、この損傷に起因するRSD(CRPS)の事案が少ないのかもしれません。
- CRPSの発症率は国によりかなり異なります。受傷直後からCRPSを疑って積極的な治療をしているとされるオランダではアメリカ(5.5人/10万人)の5倍ほど(26人/10万人)の発症率とされています。 日本は正式な疫学調査はなく発症率は不明です。アメリカと同程度とする意見もあるようですが、私は診断を受ける患者はアメリカよりも少ないと思います。仮に日本のり患率がアメリカ並みとすると年7000人ほど、オランダ並みとすると年3万5000人ほどがCRPSにり患することとなります。 私の経験では、交通事故患者の大半がまずは「町の病院」に行き、リハビリ用に接骨院・クリニックなどに通院し、良くならなければ検査のためだけに専門病院に行きMRIだけを受け、それでも良くならなければ我慢するという流れが良く見られます。この流れの中では手首部分に強い痛みや可動域制限が生じるタイプのCRPSは患者の我慢によって見落とされる可能性が低いとはいえないと思います。
- 本件は緩慢な症状の進行であれば手首の強い痛みとして見落とされた可能性もあったものの、事故直後から激しい痛みがあり3か月もの入院をして、その中でCRPSの発症が確認されたという事情のため、幸いにもCRPSとの診断を受けることができたという印象を受けます。
-
- CRPSの判断基準
- 他の事案と同様に加害者側はCRPSではないと主張しています。判決は、CRPSの診断基準を述べることなく「医師がCRPSの認定基準に従い判断した。」のでCRPSであるとの趣旨を述べます。 被害者の症状について判決が分散して述べていることをまとめると、事故後早期に①右手指(拇指、示指、右手関節尺側)のしびれが、1か月後には②尺骨神経領域の知覚鈍麻が、3か月以内の時期に③アロディニア(触るだけでも強い痛みとなる)や④筋萎縮が、その後に⑤手首の関節拘縮が生じたとされます。 以上のうち、③と⑤からCRPSの判定指標を原則として満たし、その他の症状も考慮してCRPSと診断したと思われます。なお①と②と④は手根管症候群でも生じる症状ですので、鑑別診断が必要であると思います。判決は事故の4か月後頃にCRPSとの診断を受けたとしています。
- 判決は事故の4か月後頃にCRPSと診断されたとしていますが、加害者側は(CRPSの発症を認めるとしても)1年数か月後にCRPSを発症したと主張しています。 加害者側は、主治医は「RSD疑」や「CRPS」としているので、双方につき確定診断が存在しないとの主張をしたようです。つまり、RSDとCRPSは別疾患であり、両方の間でどっちつかずの状況にあり確定診断はないという解釈を展開したようです。この理屈はさすがに無理があると思います。本件では事故後4か月後にCRPSを発症していたと判断した点には特に問題はないと思います。 加害者側は、CRPSであればその病期は3期であるとして3期の症状に合わないと主張します。RSDの病期説はほとんど支持されていない上に、そもそも診断基準ですらないのでこの主張は論外ですが、この主張は加害者側の定番です。病期説のとおりに症状が進行する患者はまずいないので、加害者側は「病期と症状が一致しない(ゆえにCRPSではない。詐病である)」という主張をすることが一般的です。
-
- 症状の悪化について
- CRPS(RSD)の病期説はほとんど支持されていないようですが、「時間とともに症状が悪化する」という進行性は認められています。ただし、症状の進行速度は個人差が大きいようです。 判例においても数ヶ月で重症化して1年以内に症状固定となった事例がある一方で、症状固定まで4、5年を要した事件もあります。このように進行の度合いや、悪化するときの症状の出方に個人差が大きいことから、医学書では病期は臨床では確認できなかったとされています。 従って、どの時点で症状の悪化が止まったと判断するのかは難しく、正確に判定するための指標もないので、悪化がおさまったかどうかは結果から見るほかないと思います。 本件では、事故の1年3か月後にいったん症状固定として後遺障害診断をしたものの、その半年後に症状が悪化したとして再度の後遺障害診断を受けています。主治医は症状悪化の医学的な原因は不明と述べています。
- CRPSの症状はなぜ悪化するのか(進行するのか)についての、医学的に定まった見解はないようです。しかし、CRPSは症状の悪化・進行が存在する疾患ですので、症状が悪化したのはCRPSを発症したからと言うほかありません。 従って、なぜ症状が悪化した(進行した)のかと問われたときに「医学的には不明である」と答えたことが、事故との因果関係を否定する根拠になるわけではありません。
- この問題に対する判決の対応は泥縄的です。判決は、前提となる「被害者の症状の悪化」の存否について判断していません。 通常であればまず症状の悪化が現実に存在するかどうかを確定して、その上で悪化があるとした場合に、それが事故に基づくのかを判断することとなるはずです。症状の悪化が存在しないとなればその先の検討は不要だからです。 これに対して、判決は「主治医が悪化の原因は不明と述べているのだから、仮に悪化があるとしても事故とは因果関係はない」との論理を述べています。上記のとおりこの理屈は誤りです。CRPSは「理由は不明であるけれども症状が悪化する。」という疾患だからです。 仮に症状の悪化があるとした場合、それは事故により生じた症状の進行が尽きる前に症状固定をした可能性がもっとも高く、それ以外の理由を主張するのであればその主張をする側において例外的事情を主張・立証すべきでしょう。
- 従って、まず症状の悪化の有無を認定する必要があります。本件では可動域検査により症状の悪化が認められており、症状の悪化それ自体を肯定することに問題はないと思います。 これに対して、加害者側からは条件反射のように可動域検査の価値を否定する主張がなされます。その結果、「本人がつっぱって抵抗すればごまかせるであろう」という理由で可動域検査を無視する判決が実務ではしばしば見られます。 私は、可動域をごまかすことは困難であり、本当に疾患の存在する人が可動域をごまかすという自分の治療に不利なことをすることは通常ではなく、可動域制限が現実に生じている患者がその制限を大きく見せるごまかしをする可能性は極めて低い(1万分の1以下である)と思います。 例えば、これが訴訟ではなく病院の診察室であれば、可動域制限を訴えている患者のほぼ全員にそのとおりの可動域制限が存在すると考えるのが普通でしょう。 これに対して、1000人に1人であっても可動域をごまかそうとして医師を騙す患者が存在するかもしれないのであれば、全ての患者について可動域検査の価値を否定するべきであるとするのが、加害者側の理屈です。さすがに自由心証主義の範囲内の判断においてこの前提を受け入れるのはおかしいと思います。 本件では現にCRPSにり患してこれによる可動域の制限が生じていることが認められているところ、患者がその可動域制限を大きく見せる虚偽を述べ、主治医がこれを見落とす医療過誤が生じた可能性は1000分の1以下であると考えて差し支えないと思います。従って、特段の事情がなければ症状の悪化を認定して良いと思います。
- 判決の中には「加害者が詐病という疑いを提起した場合には、被害者はその疑いを払拭する証明責任がある」との誤った理解を前提としているものが少なからず見受けられますが、自由心証主義の対象領域のなかにこの種の証明責任を持ち込む考えは誤りと言うほかありません。 通常でないことが起きたと主張する側にはその主張を具体的に裏付けるべきで、それができなかった場合には通常の出来事が起きたと考えるべきです。それが自由心証主義での判断です。 これに対して、詐病との主張に対して詐病で「ないこと」の証明責任を課すことは妥当ではありません。可動域のごまかしと医師の医療過誤という例外的事例の重複を基本にすえて、それへの反証(不可能な証明)の責任を被害者に課す思考は誤っています。 これは証明責任の捉え方に問題があります。訴訟における証明責任は真偽不明に陥った場合に結論を決める手段として機能するはずです。真偽不能になる以前の自由心証主義のレベルでは論理法則に従い合理的に事実を認定するべきで、このレベルでは「通常ではないことが起きたと主張する側はこれを具体的に裏付けるべきである。」という論理法則に従い事実認定をするべきです。
-
- 抱き合わせ証明論
- 本件では、被害者は、①現在の症状(いったん症状固定したのちに悪化した症状)と、②それが本件事故により生じたことを主張しています。通常はまず①の存否を判断し、①の存在が認められた場合にのみ②を判断することとなります。 現在の症状(症状の悪化)について真偽不明に陥ったのであれば、その先(因果関係)を判断するまでもなく、被害者側の主張は認められないはずです。 これに対して判決は、症状の悪化の有無を曖昧にして、「症状の悪化があるかないかは別として、因果関係が不明なので認めない」との論理を述べていますが、私はこの論理は誤りであると思います。
- まず、上記のとおり症状の悪化を否定する理由はなく、CRPSの進行性からは特段の事情のない限りこれを肯定すべきであると思います。症状の悪化という前提が認定できる場合にはそれをなすべきであり、前提が認定できない場合には認定できないことを示し、その先の問題(因果関係)には言及すべきではありません。 このように論理的前提となる事実Aを認定せずに、「Bを満たすAがあるか」として事実Bの有無の判断と一緒に事実Aも判断して、否定の結論を導こうとする証明妨害の論理を、私は「抱き合せ証明論」と呼んでいます。個別にすべき検討を抱き合わせで行う方法です。 この論理には、事実Aの存在を確定させたうえで事実Bの存否を判断するルートを欠落させ、前提事実消去により誤った確率感覚に導こうとする効果があります。 加害者側は否定することが困難な前提事実への対応をあいまいにして、その先の部分を強調して否定することが多く、この場合に抱き合せ証明論という証明妨害の論理が発生します。
- 抱き合せ証明論を用いる判決は、しばしばみられます。その理由はいくつか考えられます。 まず、前提である事実Aの存否の判断に確信がもてないことです。本件では懐疑的思考に陥って可動域検査をごまかす患者がいないとはいえず、これを見落とす過誤をする医師もいるかもしれない、との思考で可動域検査を信頼していないようです。 詐病と医療過誤が二重に起きたという特段の事情については、加害者側でその存在を主張・立証すべきです。しかし、真偽不明の場合の証明責任(結果責任)が被害者側にあることから、真偽不明になる以前においても被害者側に不利に判断すべきであるという誤った理解で証明責任を捉えている判決はこれまでにもいくつか見られたところです。 次に、被害者側は上記の①と②の両方を証明しなければならないのだから、どちらから先に検討しても同じであるという考えから、①が前提であることを重視せず、②の検討において「②を満たす①」の有無を検討しても同じであるとする考えです。しかし、①の存在を確定させた場合と「②を満たす①」との思考では大きな違いが生じます。確定できる前提をあえて確定しないことは、前提事実無視の誤謬となります。
- 抱き合せ証明論の難点は、①論理法則に反している点、②訴訟法における証明責任の位置づけを誤っている点、③前提を確定した場合の証明ルートを最初から遮断する点、④前提を確定した場合と確定しない場合の格差を軽視していることにあります。 このうち①と②は上で述べたとおりです。③は事実A(症状の悪化)が存在することを確定した場合には、その原因を消去法で検討すれば、事故によるCRPSの悪化が続いたとの説明が最も合理的ですが、抱き合せ証明論ではこの消去法的考察の道が最初から断たれています。 上記④についてですが、前提として症状の悪化があることを確定すれば、その理由としてCRPSの症状の進行とする合理性が強まります。前提事実の有無により確率的状況が劇的に変わりうることの理解が必要であると思います。 上記③、④の問題を軽視してしまうのは、因果関係の判断は積極的な認定によりなすべきであるという感覚的な理由が強いと思います。しかし、実際は積極的に因果関係の判断ができる事例は稀有な例外に過ぎません。例えば事故当日に大腿骨骨折が発見された場合にも通常は「他の原因はない」との消去法を用いています。大腿骨に加わった外力の方向や強さ、被害者個人の骨の強度や耐久性などを具体的に証明することなど不可能です。 (2011年10月2日掲載)
 症状固定後に悪化した右手CRPS(H21.9.18)
症状固定後に悪化した右手CRPS(H21.9.18)

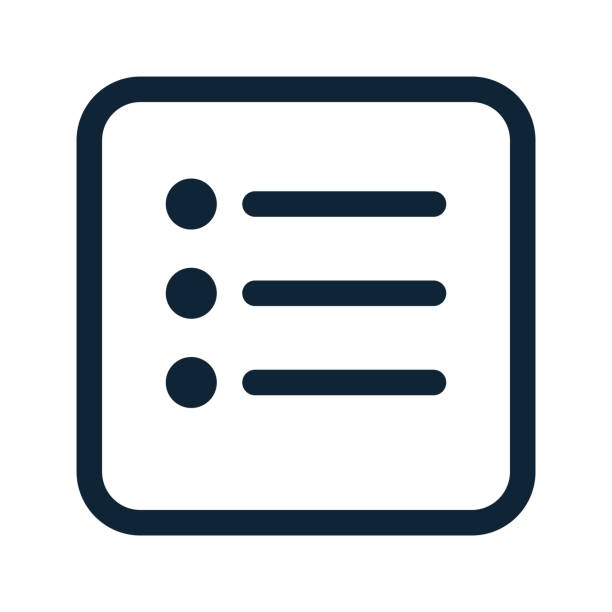 目次へ
目次へ