- 新潟地裁平成23年7月19日判決(自保ジャーナル1859号87頁) この事案の特徴は、①治療長期化事案であるが被害者の症状の経過が判決で触れられていないこと、②被害者がRSD(CRPS)と主張している部位や根拠が不明であること、③加害者がポストポリオ症候群(PPS)と主張したこと、④判決が自賠責の3要件基準をRSDかどうかの基準として誤用したこと、などです。
-
- 症状の経過
- 被害者は事故時53歳位(症状固定時58歳)の女子給与所得者です。被害者は平成16年9月4日にアパート敷地内で携帯電話をかけていたところ、背後からバックで駐車場に入ろうとしていた乗用車に衝突され、以後、被害者が症状固定と主張する平成21年6月12日まで4年9か月通院します。加害者は7か月後の平成17年3月31日が症状固定日であると主張しています。 判決は長期間の通院経過を別表(自保ジャーナルには掲載されていません)に記載し、本文では各通院先での診断名や各時点での症状やその経過などについて触れられていません。おそらく別表にも詳細は書かれていないと思います。各通院先での診断名や症状の経過などは事案の骨格を形成する部分であるので、少なくとも診断名とその時点で医師が確認した症状について触れるべきであると思います。
- 被害者の主張によると、被害者は本件事故により、頚椎捻挫、右膝・右上腕打撲、右膝・右手擦過傷、右肋骨不全骨折、腰部挫傷、右足関節捻挫、右手関節捻挫、左膝靭帯損傷、右下腿痛、右耳痛、身体表現性障害、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD、複合性局所疼痛症候群・CRPS)、身体型疼痛障害(慢性疼痛障害)等の傷害を負い、平成21年6月12日の症状固定まで4年9か月8日間にわたり通院治療したとされています(実通院392日) 判決からはこれ以上の詳細は不明ですが、上記のうち捻挫、打撲、擦過傷、骨折、挫傷の診断は事故直後に診断され、それ以下の診断は治療を続けても症状が改善しない中で下された診断名と考えられます。
- 被害者はこれらの後遺障害は少なくとも9級に該当するけれども、右足変形の既往障害があるので、12級13号「局部に頑固な神経障害を残すもの」に該当するとの主張をしているようです。 後遺障害等級の主張は部分ごとに区別して行う必要があるところ、判決によると被害者側は各部分ごとの後遺障害等級は主張せず、全体としての後遺障害等級のみを主張しているようにも見えます。既往症については「9級の後遺障害から12級相当分(既往症)を控除する」との構成で主張した方が良かったようにも思います。
-
- RSD(CRPS)の主張
- 判決によると、被害者は両下腿、両肩(特に右肩)から上腕の痛みとしびれ、指先のピリピリ感、下肢の痛みとしびれ、膝痛、腰痛、耳の中の痛み、頚部痛、不眠等が事故後、現在(判決時)まで続いており、これらの全てがRSDによるものと主張しているようです。判決のとおりであるとすると、被害者側は各部位ごとにRSDであることの具体的な主張はしていないように見えます。 判決では、被害者の「右足筋萎縮(運動不能)」という症状にも触れており、被害者側としてはこれもRSDによる症状であると主張したようです。「右足」は右の足首以下の部分を指すのですが、足が筋萎縮になったというのはどうにもしっくりしません。被害者は下肢や下腿に痛みとしびれを訴えているので、「右足筋萎縮」は「右下肢(下腿)筋萎縮」の意味で誤用しているようにも見えます。この点も判決からははっきりしません。右下肢の各関節の可動域制限の有無や程度について、被害者から主張がなされているかどうかを含めて、判決では触れられていません。
- 判決によるとRSDは医師の診断によるものであるようですが、どの時期の医師がどの部分についてRSDと診断したのかは、判決には書かれていません。 医師は運動障害や筋萎縮のある右足(右下肢?)をRSDと診断し、上肢については診断していないようにも思われるのですが、判決ではそれも不明です。この判決は全体的に事案の整理がほとんどできていないという印象を受けます。
-
- ポストポリオ症候群(PPS)との主張
- 加害者側は、被害者には後遺障害はなく、仮に後遺障害が残存するとしてもそれはポストポリオ症候群(PPS)であると反論します。 このPPSの主張は主として被害者の右足筋萎縮や運動障害についての主張であると思います。判決も被害者の右足(右下肢?)に筋萎縮があることは前提としており、この筋萎縮は証拠の上で明白に認められるレベルのものであったようです。
- 判決は、被害者の幼少期にポリオの既往があると認めたものの、これに起因する成年後のポストポリオ症候群(PPS)は数ヶ月から1年程度で進行は停止し、かなりの程度に回復する人が多く、ほとんどの人が発症前の日常生活に戻ることができる旨の医学文献や医師の知見があるとして、本件の後遺障害がPPSによるものと「直ちに認めることはでき」ないとして否定しています。 「直ちに認めることができる」というレベルに至らないと事実を認定できないというのも変ですが、判決はPPSの証明責任が加害者側にあるとの前提で加害者側がその証明責任を果たしていないので「PPSであると直ちに認めることはできない(ので本当はPPSかも知れないけれど認めない)。」との論理になっています。 結論的には私もPPSとする積極的な根拠に乏しいことから、被害者の症状はPPSではないと思います。しかし、判決のように自由心証のレベルで判断に至る前に証明責任を先行させて「直ちに認めることはできないので(本当はPPSかもしれないけれど)否定した。」との論理を述べることには引っかかるところがあります。
- 証明責任について 本来であれば、「~の事情からは本件がPPSであるとする積極的な根拠に乏しく、むしろPPSではないと判断すべき事情が~のとおりに存在する。従って、PPSではないと考えられる。」という形で自由心証の範囲内でPPSではないとの心証が形成されたことが分かる書き方にした方が良いと思います。 判決の書き方では証明責任がまず先にあり、「証明責任を満たすかどうかという視点」でのみ自由心証を用いているように見えますが、これでは心証を形成する前から証明責任を負う側に不利なハードルがあるようにも見えます。証明責任はあくまでも心証を形成できなかったとき(真偽不明の場合)に初めて持ち出すものであるはずなので、証明責任を先行させる枠組みに見えるところが気に掛かります。このように証明責任の所在を意識したことを前面に出して、自由心証のレベルで認定したのではなく、「証明責任が果たされなかったので結論は~とする」との枠組みで事実認定を記載する判決は少なからず見られます。 裁判官は証明責任を考慮して、「~ではないと認められる」とは書かずに、「~であると認めることはできない」との表現を用いることを好みます。この表現の方が法律的に厳密な感じもします。かりに「~ではないと認められる。」との心証が形成されていても、証明責任を考慮して「~であると認めることができない。」との書き方ができるのに、それを超えた無駄な心証を形成する必要も開示する必要もないとの考えもありそうです。「~ではないと認められる。」と書いてしまうと、証明責任を知らずに無駄なところまで心証を形成したとの見方もされそうです。 しかし、「~であると認めることはできない」との書き方では、「よく分からなかったので証明責任を満たさなかったことにしますね。」という認定との区別がつきません。自由心証のレベルで「~ではないと認められる」との判断ができたのであれば、「~ではないと認められる。」という書き方をするべきです。ここで「認められる」のレベルに達していなければ「~ではないと考えられる」と書けば良いと思います。
- 当たり前のことですが、証明責任に頼った判断をすることにより、真実に即した認定がなされるわけでも、真実に近づくわけでもありません。証明責任とは、何が正しいのか分からないという特殊な状況においても裁判官が裁判を拒否せずに結論だけは出せるようにするために法が異例の処置として特別に使用を認めた「サイコロ」です。証明責任に結論を委ねることは、要するに「サイコロで決める」ということです。 私も試験のときに五角形の鉛筆を振ってマークシートを埋めたことがありますが、自分で考えて埋めたマークシートと鉛筆が決めたマークシートでは、自分で考えた方が正答率は高いと思います。証明責任に頼るということは、とにもかくにもマークシートを埋めることはできたけれども正答率は保証しないということを意味します。 証明責任は「無知の尺度」です。判決文で「証明責任で決めました。」との論理が書かれていると、「こんな問題も分からずに証明責任に結論を丸投げしたのだろうか?」という印象を受けます。私の経験では平均レベルの法曹が証明責任に頼らなければ事実の骨格が判断できない事件は100件に1件ほどではないかと思います。 弁護士からの評判の良い裁判官は例外なく事件の本質を正確に見抜く力量のある方です。事件の本質を正確に探究できる有能な裁判官であれば証明責任に頼って事件の骨格を決めなければならない状況に陥ることは1000件に1件ほどかも知れません。 それはともかく本来であれば当事者が主張する事実についてどちらの言い分が正しいのかについてきちんと探求して心証を確定させた上で判決を書くべきであり、どちらが正しいのか分からない状況、即ち判決をなす機が熟していない状況で判決を書くことは異例のはずです。 しかし、どこまで審理しても真実が明らかにならない場合もあり、現実の社会では訴訟の迅速化の要請などから時間的制約もあって、例外的に何が正しいのか分からないという特殊な状況が生じることも否定できず、そのような異例の状況においてのみ証明責任に結論を委ねることが正当化されます。 以上の考えには異論があるかもしれませんが、私は証明責任による判断はできるだけ避けて最後に用いる究極の手段にするべきであり、証明責任に頼らずに心証を形成して判決を下すのが原則であると思います。 これとは全く正反対に、自由心証に先行して証明責任の枠組みを設定し、「証明責任を満たすかどうかという視点」で自由心証レベルの判断を行うことは正しくないと思います。例えば、本件では「被害者にはどのような傷病が存在するのであろうか。」との視点で探求すべきであって、「被害者はRSDであることの証明責任を果たせたと言えるほどの証拠を有しているか」との視点で探求することは正しくないと思います。
-
- RSDの診断基準
- 3要件基準 判決は3要件基準をRSDであるかどうかの診断基準とし、「RSDと認定するには、自賠責保険及び労災保険上のRSD認定の3要件である関節拘縮、骨萎縮、皮膚変化(栄養障害、温度)を充足することが必要というべきである。」と述べます。その上で被害者は3要件に該当すると言えず、被害者がRSDであるとした医師は3要件の検討をしていないとします。この部分はいくつもの意味で誤っています。
- 診断基準ではないこと 3要件基準は自賠責保険や労災保険の手続においてさえも、RSDであるかどうかの認定基準(診断基準)ではありません。このことは基準を解説した著書にも書かれています。例えば、『改正障害等級認定基準、上巻』(平成16年3月、厚生労働省労働基準局編集)の45頁では「3要件を満たさないものは、RSDに該当しないという趣旨ではありません」とわざわざ明記しています。 これらの手続では「3要件基準を満たさないRSD」の存在を認め、12級または14級の後遺障害を認定するように指導しているだけで、RSDかどうかを3要件基準で決めるとはされていません。
- RSD(CRPS)には特有の症状がないこと 医学的にはRSD(CRPS)には特有の症状がない(必ず生じる症状が1つもない)ことは世界中の医学者が認めている定説ですので、1つであってもRSDに必須の要件を要求することは重大な誤りです。 現実にも国際疼痛学会、アメリカ、日本のそれぞれのCRPS判定指標においても、必須の症状は1つも要求されていません。これらの基準では4~5の項目(判定指標ごとにその中身は異なります)のうち任意の2つを満たせば、判定指標を満たすとしています。 しかも、これはあくまでも「指標」に過ぎず、各指標の4~5項目のうち任意の2つを満たすCRPS患者は統計上それぞれ8割ほどしかいません。従って、1項目しか満たさない場合にも他の疾患の可能性が排除されるなどの状況においてCRPSと診断されます。もちろん指標の各症状はそれが確認できれば軽度でも構いません。 これに対して、特定の3項目が診断のときに「明らかに生じている」という3要件基準は国内外の診断基準に比べて異常に厳しいものであり、現実のCRPS患者でこの厳しい要件を満たす者は1割以下(おそらく5%以下)であろうことは容易に推断できます。 さらに3要件に含まれている骨萎縮は国際疼痛学会、アメリカ、日本のいずれの基準においても判定の要素にさえ組み込まれていません。発症頻度が低い(統計によると30~50%ほど)からです。その発症頻度が低い骨萎縮が判定時に重度に(明らかに)生じている患者はCRPSの患者の1割以下と推測され、骨萎縮の要件のみにて大多数のRSD患者が洩れ落ちることになります。
- 3要件はRSDの重症度と相関しないので、RSDとして12級を超える等級が認定されるために3要件基準を満たさなければならないとする自賠責や労災の基準は医学的には誤りというほかありません。 後遺障害の重症度については、労務への影響の度合いや可動域制限などを直接検討すれば足りるので、RSDの場合にのみわざわざ重症と認定されるための特別の関門として3要件基準を設ける必要性はありません。同じCRPSであるカウザルギーでは3要件基準は用いられません。 この不合理な3要件基準が制定された政治的な背景はおくとして、これは自賠責や労災の手続内での指標として設けられたものであって、裁判所を拘束するものではありません。従って、裁判でこの基準を用いることは法的な根拠のないことです。
- 本件では日本のCRPSの判定指標を用いるべきです。判決では被害者は全身性のRSDを主張しているようにも読めますが、そうであるとすると各部分について検討する必要があります。判決の述べる事情では、この被害者の各部位に日本の判定指標をあてはめることはできません。 右足筋萎縮が問題となっていることから、医師がRSDと診断したのはこの部分のみであるようにも思われますが、上記のとおり判決からははっきりしません。 判定指標は診断の過程の1つにすぎず、現に存在する症状に何らの傷病名も与えられない不合理な結果は回避すべきですが、判決では「とにかくRSDではない。その先は知らない。」との論理になっています。これは背理法無視の誤謬です。
-
- 既往障害について
- 被害者は幼少期のポリオを原因として脊髄に起因した弛緩性の麻痺が右足にあり、これによる運動障害もあったため平成元年9月に身体障害者手帳2種6級(下肢の足関節の機能の著しい障害)の認定を受けています。 この障害が平成16年9月4日の事故の後の平成16年11月9日に2種3級に変更されており、判決によるとこの変更は右足筋萎縮や運動障害の悪化に基づくものであるようです。 この変更が本件事故後に確認された症状に基づくものであるのか、本件事故前に確認された症状に基づくものであるのか、それが不明であるのか判決には記載されていません。この判決は事案の整理はよくないと思います。疑問に感じたことの釈明もしないまま判決に至ったのでしょうか。
- 判決はこの変更は事故後に確認された症状に基づくものであるというニュアンスを述べて、事故前に症状が生じていて事故後にそれが確認された可能性がある(これに反する被害者本人の供述は信用できない)ので、事故との因果関係はないとしています。 この部分はさすがに荒っぽい理屈だと思います。この理屈を持ち出すとどんな怪我をしても事故前にその怪我が生じていなかったと証明できない場合には(ほとんどの場合に証明不可能であると思います)、事故との因果関係が否定されそうです。
- 判決の論理の流れは、①RSDであるためには3要件基準を満たす必要がある(もちろん誤りです)、②本件は3要件基準を満たさない、③よってRSDではない、④RSDではないとしたので右足筋萎縮や運動障害を説明できる傷病が存在しなくなった、⑤そこで事故後に筋萎縮が生じたとする確実な証明を求めると、案の定それがない、⑥よって筋萎縮と事故との因果関係を認めない、(⑦事故前に筋萎縮が生じた原因については関知しない)、という具合になっていて、この流れの中で⑤の論理がはさみこまれてしまったのは、典型的な泥縄式(いきあたりばったり)の判断ともいえそうです。 筋萎縮が事故前に確認されていないのであれば、事故後に生じたとするのが穏健な判断であると思います。事故前に筋萎縮が生じていたのに、「もうすぐ事故に遭うから病院に行くのはやめよう。」と被害者が特別な予知能力を発揮して我慢し続けてきたとの前提はかなり不合理です。 判決は「事故前に筋萎縮や運動障害の悪化が生じていたけれども痛みはなかった(ので病院にも行っていなかった)。」との事情を想定しているようにも見えますが、その想定自体が奇異であり、特殊な前提に合わせてご都合主義的に特殊な想定をしたと言わざるを得ません。 もとより判決の導く結論に対しては「何ゆえに事故前に筋萎縮が生じたのか。」について説明できませんが、判決は「とにかく事故とは関係ない。その先は知らない。」との形で証明責任に結果を丸投げした形にして、導いた結論の先にあるものを放置しています。 泥縄式の認定は事件の全体を整合させる思考(本来はここから始めるべきであると思います)が欠けていることに原因があると思います。個別のポイントごとに(証明責任を用いるなどして)結論だけを決めていくと泥縄式になります。
-
- 気になったこと
- この判決を読んでいて疑問に感じたのは、「生の事実に迫って事実を認定していこう」という姿勢が感じられないことです。判決をいくら読んでも事件の核心部分が見えてきません。 判決は「3要件基準を満たしていないのでRSDではない、その先は知らない。」、「(本当はPPSかもしれないが)PPSであると直ちに認めることはできないのでPPSではない、その先は知らない。」、「事故前に筋萎縮が生じていなかったと判断できる確実な証拠はないので事故により筋萎縮が生じたとはいえない。なぜ事故前に筋萎縮が生じたのか、事故前に治療を受けなかったのかは知らない。」との論理構成になっています。事実認定を診断基準や証明責任などの形式論に丸投げしているために必然的にこのような論理となっています。 私は自由心証を用いる以前の初期設定に証明責任を配置して「証明責任を満たすほどの証拠があるか」との視点で検討していることが、その原因であると思います。この枠組みは自由心証の尽きたところで証明責任の機能が始まるとする定説とは対極に位置します。この枠組みでは証明責任というハードルを越えたかどうかによって事実を認定することになりますが、このハードルの高さに客観的な基準があるわけではないので、必然的に自在にハードルを上下させる方向に向います。この場合には事件の中身と関係ない形式論理でハードルが上下することになります。 また証拠の序列化を初期設定で行うため、事件のストーリーに合わせた証拠の検討も不十分になりがちです。判決は証拠の序列化を先行させて被害者の言い分(供述)は最初から証拠価値がゼロであるとしているようにも見えます。民事訴訟法が証拠としての能力(適格)を認めているものについて、証拠の中身を検討する以前に価値を序列化することは正しくないと思います。これでは事件の実体が見えてきません。 この判決に従うと被害者はRSDでもPPSでもない正体不明の病と闘って4年9か月もの長期間にわたって通院したことになりそうです。被害者は偶然にも事故と同時期に事故と関係ない正体不明の病により通院を始めたことになり、判決からは特殊な被害者が特殊な主張をしているとのニュアンスが感じられます。「特殊な人による特殊な出来事である」との説明を用いれば、どのような事実認定でもつじつま合わせができますが、それ故にその事実認定はほぼ全ての場合に誤りであると思います。
- この事件の核心は、「この人は一体どのような傷病のために長期間の通院をしたのだろうか。」、「この人にはどのような後遺障害が残っているのだろうか。」という点にあり、この点を脇において要件を満たすかどうかだけに視点を限定して「とにかく要件を満たしていない。その先は知らない。」との論理を述べることは正しくないと思います。この判決は自由心証のレベルで生の事実を探求して事実を認定することをせずに、形式論理に頼って何も認定せずに証明責任で結論だけを決めたように見えます。 証明責任は事実を認定するためのものではなく、事実が認定できなかったときに結論だけを決めるものであり、証明責任に頼って結論だけを決めてしまうとその反作用として空白部分が多く残されてしまいます。この空白部分がいかに不合理であってもそれは「証明責任に従ったのだから仕方ない」、「これは特殊な人による特殊な出来事である」と考えることは、前回に述べた背理法無視の誤謬と言わざるを得ません。
- 通常であれば裁判官は事案の全体像(事件のスジ)を把握することを最初に行い、まず「動かし難い事実」(動かせない事実)を見つけ出し、それを軸にして全体を整合させつつ事実を組み立てていくという形で事件の全体像を把握していると思います。この「動かし難い事実」は要件事実とは無関係に生の事実のなかから見つけ出していきます。 これに対して、この判決のように全体像を把握することなく、いきなり形式論理(要件事実、診断基準)や証明責任に飛びついて、順次必要な部分だけをその都度決めていくという判決もまれに見かけます。しかし、このやり方では上記のような泥縄式の認定にならざるを得ないと思います。 本件では、「この人はどのような傷病のために長期間の通院をしたのだろう。」、「この人にはどのような後遺障害が残っているのだろうか。」という事件の核心部分の全体像を最初につかむ必要があると思います。 この場合に「被害者が実際に通院した事実」、「ある病院である診断を受けたこと。」、「その治療を受けたこと」などの客観的事実は「動かし難い事実」となります。その通院や治療が長期間に及んでいて医師の診断がある場合には、それに相応する症状が存在することも「動かし難い事実」です。動かし難い事実は証拠から直接確定できる事実だけでなく、そこから演繹できる事実をも含みます。しかし、このような「動かし難い事実」は要件事実ではないだけに軽視されがちです。 上記の事実は例えば署名・押印のある抵当権設定契約書と同様の重さがあります。契約書が存在する場合には「何が起きたかは不明であるがとにかくこの契約書は捏造である。」との認定がされることはありませんが、人の傷病の場合には長期間の通院や治療や診断という事実から導かれる「動かし難い事実」であっても、「何が起きたかは不明であるがとにかくRSDではない。RSDとの診断も誤診(医療過誤)である。」との形で否定されやすいようです。 何らの傷病もないのに4年9か月も通院する人はまずいません。形式論理を先行させて「RSDでもPPSでもない、その先は知らない」との理屈で「よく分からない事情で4年9か月も通院した非常に特殊な人がいる」との結論を導くことは正しくないと思います。この判決は全体像の把握や背理法的考察をしないまま証明責任というサイコロで順次結論を決めて前に進むすごろく式の認定になっているように見えます。 また、被害者の現時点(訴訟時)での所見や診断はリアルタイムの医師の判断であり、これも確実性が高い証拠(動かし難い事実)であると思います。被害者の現時点での症状から被害者に「何らかの後遺障害」があるとすれば、それは何であるのかを探求することとなります。このようにして事案の探求をして事実を明らかにしていくことは判決を書くにあたって不可欠であり、仮に不明な点があれば釈明をするべきであると思います。
- 裁判例の中には形式論理に頼った判断を、「高い視点からの客観的な判断」であると考えて、事案の中身に踏み込まない形式的な判断を志向しているように見えるものもあります。その背景には形式論理だけで結論を導き出して中身のごちゃごちゃした問題に入り込むことを避けることは、スマートであるという価値観があるようにも見えます。しかし、私はこのような考えは基本的な部分で間違っていると思います。 (2012年5月28日掲載)
 RSDでもPPSでもないとした右足筋萎縮(23.7.19)
RSDでもPPSでもないとした右足筋萎縮(23.7.19)

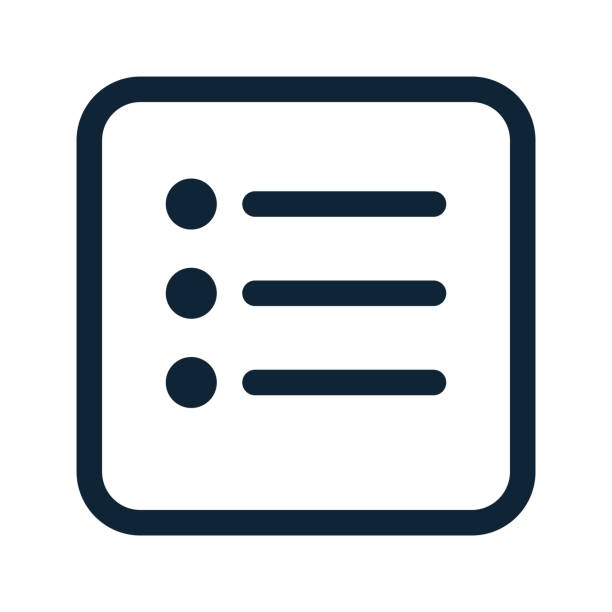 目次へ
目次へ