- 横浜地裁平成24年8月31日判決(自保ジャーナル1883号102頁) この事件では左手指のCRPSが問題となっています。 この事案の特徴は、①車両の損傷が軽微な追突事故であること、②二次性の神経損傷に起因する左手指のCRPSとみられること、③通院先で肘部管症候群の可能性が指摘されていること、④判決がRSDの自賠責3要件基準を診断基準と誤解したことなどです。
- 症状の経過
被害者は56歳女子タクシー乗務員で、平成19年10月17日に停止中に追突される事故に遭います。車両の修理費用は5万円ほどとされていることからは、車両の損傷は比較的軽微なものと思われます。
(*以下では日付は断りのない場合は事故日を基準としたものです)
- 事故当日・・・B病院。左肩に疼痛、左腕にだるさ、左腰部に自発痛と圧痛を訴えるも、頚部CTでは異常なしとされ、むち打ち損傷とされる。
- 事故翌日・・・D整形外科。当初左手が握りづらく、むくみがあり、左手が少し重いとされる。1年9か月通院。 *当初から左上肢の症状を訴え、むち打ち損傷により生じたものとされます。しかし、CRPSが生じたという結果からは、この時点で左上肢の神経損傷の原因が存在したと疑われます。
- 3週間後・・・C診療所。MRI検査を受ける。脊柱管の前後径は生来狭いと思われる、C3/4~6/7レベルで骨棘形成などの脊椎症性変化により脊柱管がさらに狭小化し、硬膜嚢が軽度圧迫されている、C5/6レベルが特に強い、とされる。
- 1か月後・・・E病院。左尺側にしびれと知覚障害を認め、神経根の部分損傷かと思います、2~3か月で改善してくる可能性が高いのではないかと思います、とされる。医師は左肘部管症候群の可能性もあると考えていた。 *医師が肘部管症候群の可能性を疑ったのは、左尺側(小指・環指)にしびれと知覚障害が生じていたことによります。当初の症状からは胸郭出口症候群も含めて検討しても良いと思います。
- 半年後・・・F病院。左手指腫大により小環指近位指節間関節の拘縮が発生したようであるとされる。その後も脹れと左手関節が動きにくい状況が続く。 *被害者が半年の間に多くの医療機関に通院したことや、症状固定までの期間からは、かなり強い痛みが生じていたと思われるのですが、判決にはその記載はありません。
- 1年9か月後・・・平成21年7月31日に症状固定とされ、頚椎捻挫、腰椎捻挫、頚椎脊髄神経根損傷、外傷後反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)とされる。その後、自賠責では後遺障害に該当しないとされ、労災で12級13号の「がん固な神経症状を残すもの」に該当するとされる。 *症状固定のときまでにはRSDとの診断がされているようですが、どの時点でRSDとの診断がされたのかは、判決からは不明です。
-
- 原因は脊髄か、末梢神経か?
- 本件では追突事故で首や腰の捻挫とされますが、最終的に後遺障害が残ったのは、直接衝撃を受けていない左手指です。このように頚部の捻挫(むち打ち)に起因して事故直後から2か月後頃までの間に肩や腕や手指に新たな症状が出てくる事例は頻繁に見かけます。本件では、事故当日から左肩、左腕の症状を訴え、翌日には左手の症状を訴えています。
- 脊椎脊髄疾患と末梢神経疾患の鑑別 左上肢の症状は、頚部の障害(ヘルニア、神経根症など)から生じることもあります。一方で事故に起因した二次性の胸郭出口症候群(外傷性TOS)や手根管症候群などの末梢神経疾患の可能性もあります。医学的にはこの両者の鑑別は重要とされ、『脊椎脊髄ジャーナル』では何回も特集記事が組まれています(21巻9号、25巻2号、25巻12号、26巻1号)。 本件では、被害者には脊柱管の狭窄や脊髄への軽度圧迫があることから脊椎脊髄疾患の可能性があり、症状固定時の「頚椎脊髄神経根損傷」との診断は左手指の症状は事故による頚部での障害が関与しているとの判断を示すことになります。 一方で、左肩の疼痛や左腕のだるさや、第4、5指のしびれなどは胸郭出口症候群で見られる症状です。第4、5指のしびれや知覚障害については肘部管症候群の可能性も疑われています。その後に手指にRSDが生じたことからは、末梢神経の損傷に起因したCRPSであるようにも思われます。 従って、提訴前に電気生理学検査などにより鑑別診断を受けておいた方が良かったと思います。但し、この検査がきちんとできる医療機関を探して検査を受けることは、地域などの事情により容易とは言えないという問題があります。
-
- RSDとの診断について
- 本件では被害者の症状がCRPSであることは特に問題はありません。CRPSの判定指標を満たす上に、左手指の痛み、知覚障害、腫脹、運動制限を説明するほかの疾患が見当たらないからです。しかし、本件のように外形的に明らかにCRPS(RSD)であり、その診断が下されている事案であっても、加害者側は全ての事案で診断を否定する主張をなし、これを裏付ける医学意見書を提出するなどしています。その結果、裁判例の上では初歩的な知識不足から主治医の診断を否定した判決が多く見られます。本件もその1つです。
- 本件ではCRPSを発症した基盤として肘部管症候群、胸郭出口症候群、頚部神経根損傷などによる末梢神経の損傷が存在する可能性があります。これが存在する場合にはCRPSタイプ2となり、存在しない場合にはCRPSタイプ1となります。
- 本件では症状固定時にRSDとの診断を受けていますが、この診断は医学的な分類ではCRPSタイプ1(神経損傷のないタイプ)を意味しますが、本件ではこの意味で「RSD」と診断しているようには見えないという問題があります。 国際疼痛学会がRSDやカウザルギーの上位概念としてCRPS(複合性局所疼痛症候群)という概念を導入した以降も、「RSD」はCRPSタイプ1、「カウザルギー」はCRPSタイプ2としてその傷病名は残されました。 しかし、日本ではこの分類に従っていない医療機関が少なくないようで、CRPSとの病名を用いない医療機関においては明白なカウザルギー以外は全てRSDと診断している例がしばしば見られます。その背景として歴史的にはRSDの中にカウザルギーを含める分類が有力であったことが挙げられます(例えば『末梢神経損傷診療マニュアル』139頁以下)。確かに、この分類の方が納得できる面もあります。 本件では症状固定時の「頚椎脊髄神経根損傷」との診断は神経根損傷に起因した手指のRSDとの意味を有しているはずであり、そうであれば、RSD(CRPSタイプ1)ではなく、CRPSタイプ2(カウザルギーなど神経損傷のあるタイプ)との診断をすべきこととなります。 しかし、本件の症状が昔から「カウザルギー」と呼ばれてきた症状であるかと言われれば、そうではないと考える医師がほとんどでしょう。「カウザルギー」はより重症化した疾患であるとのイメージがあります。そのような事情から本件ではCRPSとの傷病名を用いない医療機関が、CRPSタイプ2について誤ってRSDとの傷病名を用いている事例であるように見えます。 いずれにしても、CRPSであることには変わりはないのですが、RSDとの診断がなされれば、自賠責では3要件基準が適用され、ほとんど全ての患者が著しく低い後遺障害とされる(もしくは非該当とされる)という事情があり、大きな違いとなります。
-
- CRPSについての判決の検討について
- 判決は自賠責や労災の3要件基準(①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化)を診断基準と誤解して、RSDではないとしています。すでに何回も書きましたが、3要件基準は自賠責においても診断基準ではなく、RSDかどうかを認定する基準ですらありません。しかし、なぜかこの点を誤解した判決が多く見られます。 CRPS(RSD)に必須の症状が1つもないことは世界中の医師が認めている初歩的な基礎知識ですので、このレベルの初歩的知識を欠いたまま訴訟が行われることはまずいと思います。日本版のCRPSの判定指標は5項目のうち「いずれか2つ」を満たせばよいという指標(感度約80%)を用いています。この指標からも必須の症状が1つもないことは即座に理解できるはずです。
- CRPS患者であっても3要件基準を満たす方はおそらく1%もおらず、多くみてもせいぜい1~2%でしょう。3要件基準を制定した時点でこのことは理解できていたはずです。 たしかに労災制度には社会福祉的な面があり、労災手続での指標は国による福祉的な保護を受ける方を政策的に制限する側面があり、医学的な合理性とは一線を画するものですが、なぜここまで不合理な基準が作られたのか理解し難い面があります。 この点について、三上容司医師は、3要件のいずれもが必須の所見ではないことを指摘して、「後遺障害認定はあくまでも行政上の作業であり、医学ではない」、「後遺障害認定基準は医学上の診断基準・判定指標とは別物である」と述べています(『複合性局所疼痛症候群CRPS』244頁、『ペインクリニック』33巻8号1109頁、オルソペディクス25巻10号79頁)。
- なお、3要件基準を患者の重症度を判断する指標にすることも誤りです。CRPS患者のうち3要件を満たす方は多めに見積もってもせいぜい1~2%ですので、重症患者のほぼ全員が3要件基準を満たしません。従って、3要件が重症度の指標として機能することは医学的にはあり得ません。もちろん3要件と重症度についての医学的な統計などの裏付も存在しません。 そもそも重症化しているかどうかは、個別の患者の症状をそのまま検討すれば判断できます。これに対して、重症度を判断するために「現実に患者に生じている症状」から目をそらして、重症度と相関しない3要件を満たさなければ重症化を認めないとするのが3要件基準の本来の利用法であり、それ故に3要件基準は著しく合理性を失していると言うほかありません。
- 判決は3要件基準を診断基準と誤解してCRPSを否定し、被害者には他覚的な所見があるとまでは認められないとして、14級としています。これは自賠責の認定基準を訴訟に持ち込むものです。しかし、判決は一方では被害者の訴える症状は存在するであろうと認定しています。 裁判例においては、主治医がRSD(CRPS)と診断し、これに対する治療を行った事案においても、全ての事案で加害者側はその診断を否定し、それを裏付ける医学意見書を提出するなどしています。もとより全てが誤診であるわけがなく、むしろ誤診はごくわずかでしょう(せいぜい1000件に1件でしょう)。従って、外形的には加害者側の主張の全部が誤りと推断できる状況があります。 実際にも裁判例の上では、RSD(CRPS)との診断が誤診であったと思われるものはありませんでした。他の傷病(特に末梢神経障害)との鑑別診断について指摘したものが少なからずありますが、積極的にCRPSではないと推論できる事例は私の見る限りありません。 この特殊な状況の下で、加害者側の医学意見書に騙されるなどして、CRPSに必須の症状が1つたりともないことや、3要件基準は診断基準ではないことや、関節拘縮に骨萎縮が必須ではないことなどの初歩的な知識さえないまま、CRPS(RSD)との診断を否定した判決が多く見られます。裁判所は明らかに舐められています。
- 裁判所が毎回のように騙される原因は、医学的知識の欠如だけではなく、より根本的なものの見方にも問題があると思います。それは主治医がCRPS(RSD)との診断を下したことの重みについてです。 医師が患者に対して難病との診断を下すことは決して軽々に行われるものではありません。CRPSなどの難病の診断が下されると、患者やその家族は大きな精神的ショックを受けます。癌の告知を思い浮かべればこのことは理解できると思います。医師は当然にそのことを知って診断を下しているのであり、十分に調べた上で根拠のある診断を下すことは当然のことです。 裁判例の上ではCRPS(RSD)との診断が遅れている事案が多く見られることは、この難病の診断について医師が慎重になりすぎていることも一因であると思います。もちろん、CRPS(RSD)という疾患についての知識がない医療機関に入通院していたために診断が遅れたと思われる事案も多く見られますが、CRPSとの診断を下した医師に関してはこの理由は当てはまりません。CRPS(RSD)という診断が下されることそれ自体の重みを理解していれば、軽々にその判断を覆すことはできないことに思い至るはずです。 3要件基準は診断基準ではないという初歩的知識がなかったとしても、「仮に3要件基準が診断基準であるとすると、主治医はこれを知らずにRSDとの誤診をしたことになり、それは極めて軽率な医療過誤となる」と思い至るはずです。これに対して、「臨床の医師はこのレベルの基礎知識もない人ばかりである」と軽信して誤解が解けなかったとすると、その判断は医学的知識の欠如にとどまらない、より根本的な問題を抱えていると思います。
-
- 後遺障害等級表について
- 判決は、自賠責の後遺障害等級表が訴訟でどのように位置づけられるのかを理解できていないように見えます。自賠責の後遺障害等級表は後遺障害の重さに応じた賠償額を算定するための尺度(目安)であって、それ以上のものではありません。 原則論から考えれば、被害者はあくまでも事故により生じた「具体的な障害」を主張していることは明らかです。しかし、それを何の目安もなしにそのまま金銭評価することは困難であるため、金銭評価の目安として後遺障害等級表を引用しているに過ぎません。従って、より使い勝手の良い目安が作られればそちらを使うことになります。自賠責の後遺障害等級表は資料のうちの1つに過ぎません。
- しかし、この作業が定型化していくと本末転倒が生じてしまい、あたかも後遺障害等級表が最初にあり、それに具体的な症状をはめ込むことができるかどうかという視点で検討していきます。その結果、はめ込めない部分は切り捨てる(現に存在する障害を無視する)という致命的な誤りに至るものも少なからず見かけます。
- 正しくは「現に存在する具体的な後遺障害を余すところなく適切に評価するためには、後遺障害等級表という資料をどのように利用すれば良いのか(変形させればよいのか)」という視点で見る必要があります。 この視点から裁判例のなかにも12級相当であるとしながら50%の逸失利益を認めるものや、4級相当としながら逸失利益を50%とするものなど、後遺障害等級表という目安を事例に応じて変形させているものが数多くあります。後遺障害等級表はあくまでも損害算定の目安に過ぎません。適宜変形させて構いません。従って、裁判所が自賠責の認定基準に拘束されるとする法律観には根本的な部分で誤りがあります。
-
- 他覚的所見について
- 以上の点をおくとしても、判決が他覚的な所見が「あるとまでは認められない」としていることは疑問です。被害者の左手の腫脹は目で見て分かるものだったはずなので、これは他覚的所見に当ります。 なお、被害者が長期間の通院で痛みを訴えている場合には、それ自体を考慮して12級の「頑固な神経症状」を認める例は自賠責でも労災でもしばしばみられます。労災や自賠責の手続においても一定の裁量的な判断は否定されていません。判決はそれをも否定しています。 また、判決が「他覚的所見があるとまでは認められない」との形で他覚的所見の有無を後遺障害認定の要件であるかのように扱う点にも疑問を感じます。訴訟ではそのような法的拘束はありません。
- 判決はその上で、何をもって他覚的所見とするのかについて独自の見解を採用し、医師の診断や放射線技士によるMRIの読み取りを否定して、自賠責の認定係の意見を優先していますが、この点も疑問です。 判決は自賠責で神経の損傷は認められないとされたことを、神経の損傷を否定する根拠として引用し、神経への圧迫所見がないとする部分でも自賠責の認定を引用して根拠にしています。しかし、自賠責の認定係は医師ではなく、画像を読む能力が保障されていない方が含まれているので、この部分はさすがにまずいと思います。なお、労災においても認定そのものは医師がするものではなく行政官が行うので、その認定の文言を根拠に医師の診断や技師の画像読み取りを否定することは誤りとなります。
- そもそもの問題として、どうして他覚的所見にこだわるのか、何をもって他覚的所見とするのかという問題があります。 臨床では医師が感知した所見の全てを他覚的所見としており、患者の協力を要する徒手筋力検査、関節可動域検査、知覚検査も当然に他覚的所見とされ、後遺障害診断書もこの前提で記載されています。臨床では虚偽の症状を訴えるという少数の特殊な患者を想定して検査結果を除外して診察、治療に当たる医師はいません。当たり前のことですが、参照できる情報を無視することはありえません。以上につき、『臨床リハ』22巻3号234頁を参照しました。 ところが、訴訟では加害者側は画像所見、身体計測所見、電気生理学的所見などの物理的な状況が可視化された(計測された)もののみを他覚的所見であるとして、これをできるだけ狭くする方向で主張します。自賠責の手続も同様の傾向があります。ときには電気生理学検査は患者が意図的にごまかせるなどの難癖(ごまかしは不可能です。患者の意思で神経の伝導速度や運動単位電位が変わることは原理的にあり得ません。)を付けられることもあります。 また、患者の外形的状況(皮膚の変化、末梢の脹れ・むくみなど)は明らかに他覚的所見ですが、訴訟ではこれさえも他覚的所見ではないと主張されることがあります。本件では判決はこの前提に立っているようにも見えます。
- 他覚的所見については、医学での概念をそのまま認めると虚偽の症状を訴える患者がいた場合にその言いなりになってしまうとの考え(性悪説)から、訴訟では独自の観点から変更するべきと主張されます(医学での概念を知らない裁判官を騙す意図がないとも言えませんが)。 もちろん、この考えではごく少数の特殊な人のために大多数(ほぼ全員)が犠牲になります。普通の患者を前提に考えれば臨床と同様の概念で他覚的所見を考えるべきであり、これにより圧倒的大多数の事案で正しい結論を導きます。 しかし、加害者側の主張に惑わされ、「損害の証明は被害者に立証責任がある」との考えから、証明手段をも初期設定で制限するという誤りに至る例はしばしば見られます。自由心証においてそのような縛りはなく、この考えは法的にも(医学的に誤りであることは上記のとおりです)誤りです。 そもそも証明責任は真偽不明になったときに結論(法規の適用)を決めるものであって事実認定の道具ではないので、自由心証の初期設定で証拠を序列化すること自体に誤りがあります。患者本人の関与する検査を否定する方向に向えば、判定者の猜疑心の強さの度合いにより他覚的所見の範囲が決まることとなります。
-
- 結論の妥当性について
- 判決の認定した事実によると、この被害者は事故前にタクシー乗務員として890万円ほどの年収であったのが、事故後は就労に戻れず、収入がなくなっています。被害者にしてみればあと10年はこの仕事を続けるつもりであったのが、事故により仕事ができなくなったので、その損害は3000万円を優に超えると考えていることでしょう。 しかし、判決の認定した逸失利益は340万円ほどで年収の半分にも満たない額です。被害者には全く過失のない追突事故で仕事ができなくなっていることからは、この結論は疑問です。但し、原告が9級ではなく12級を主張していることにも問題はあります。 判決は症状固定までの1年9か月の休業損害についても、タクシー乗務員の仕事ができなくとも他の仕事ができたはず、として1年3か月分の休業損害を半額として570万円としています。しかし、56歳の女性が通院しながら他の仕事で事故前の高収入の半分の収入を得られるとの仮定には無理があります。
- この結論が導かれた原因は、上記のとおりCRPS(RSD)という傷病への無理解が前提にあります。判決は、被害者がRSDであるとする医師の診断や、頚椎脊髄神経根損傷であるとする医師の診断を否定して、MRIの読み取りなども否定しています。 また、現に存在する後遺障害を金銭評価するための目安として後遺障害等級表を用いるべきところを、判決では後遺障害等級表が最初に存在して、これに被害者の後遺障害を当てはめて、はめ込めなかった後遺障害は切り捨てているという構造的な問題もあります。 さらに、判決が被害者は症状固定前に就労に復帰できてかなりの収入を得ることができたはずであると認定していることからは、実質的に被害者の訴える症状の大半について詐病との認定をしたこととなります。 しかし、上記のとおり判決は被害者の主張する後遺障害は存在するであろうとも述べています。被害者の事故前の年収が890万円であったことからは、普通であれば少々の無理をしてでも仕事に復帰しようとしたはずであり、それができなかったことからは相当の痛みやしびれが出ていたことが推測できます。 以上のことからは、判決は3要件基準を診断基準と誤解したことから、被害者の症状を説明できる傷病名が存在しなくなり、後遺障害等級表に後遺障害をはめ込むという方法論で、しかも自賠責の基準を訴訟で厳格化して用いたため14級となり、その結果、逸失利益や休業損害を低く認定するほかなくなり、実質詐病となるほどの低額な賠償額となり、その結果を正当化するための認定も付け加えたという泥縄式の流れに乗ってしまったとも言えそうです。
- しかし、より根本的な原因は「~であると認めるに足りる証拠があるか」という視点で事実認定を行うという誤り、即ち証明責任を事実認定に取り込む誤りにあるように見えます(この点は他でも述べたので、できるだけ繰り返しは避けます)。 この判決からは、被害者の症状や現状についての心証や事件の全体像についての心証はほとんど感じられず、「要件に従って認定した」という淡々とした作業の形跡しか感じられません。その作業とは「~であると認めるに足りる証拠があるか」という判断をポイントごとに繰り返して前に進むことです。まさにこれが泥縄式の認定になった原因でしょう。 事実認定は全ての事情を考慮して、全体として「何が起きたのか」を認定することであって、その視点がなければ一貫した認定とはなりません。全体像も持たずに個別の結論を順番に決めていけば泥縄式(行き当たりばったり)の認定となります。行政官が許認可の書類審査をする場合であれば、ポイントごとに結論を出すことができますが、事実認定は全体として整合する一貫したものとする必要があります。
- 証明責任は真偽不明に至った時点で結論(法規の適用)を決める道具であって事実認定の道具ではないので、自由心証において「~であるとする確実な証拠があるか」との視点を持つことは正しくありません。しかし、泥縄式の認定においては個別の部分ごとの細分化された認定を行うためにこの視点が導入されていきます。 この視点で検討して「~であると認めるに足りる証拠はない」で終えてしまうと「では何が起きたのか」という部分が空白になり、それ故にそれは事実認定とは言いがたいものです。つまり、「確実にAであるとは言えない」という理由で「Aの否定(Aであるとは認められない)」を事実として認定してしまうと、実質的な心証の裏付のない事実認定となります。 しかし、証明責任を自由心証に先取りする誤りに陥ると、これを事実認定と誤解することとなります。この結論を基盤にしてさらに別の結論を「~であると認めるに足りる証拠はあるか」との視点で導いていくと、実質的な心証の裏付のない認定が泥縄式に繰り返されていきます。 本件では主治医の診断(普通であれば長期間患者を診察した主治医の診断の少なくとも95%以上は正しいと考えるでしょう)について、「確実に正しいとは言えない」という理由で否定し、MRIの読み取りも同様に否定していくため、最も可能性の高い事実から乖離した事実が淡々と認定されていく悪循環に陥っています。 本件の全体像を巨視的に見れば、「年収890万円の被害者が事故で働けなくなるほどの後遺障害を残し、医師がそれについてRSDという難病の診断を下した」との外形が見えていて然るべきなのですが、そのような全体的な実体が個別の部分で実質的な心証の裏付を持たない結論に覆されていくという構造になっています。 最近はこの誤りに陥っているように見える裁判例を少なからず見かけるのですが、全体像を持たないまま前から順に結論を決めるやり方は要件事実論が原因でしょうか。要件事実論は事実認定で用いる道具ではないことは自明であると思うのですが。 (2013年3月16日掲載)
 左手指CRPSの否定(24.8.31)
左手指CRPSの否定(24.8.31)

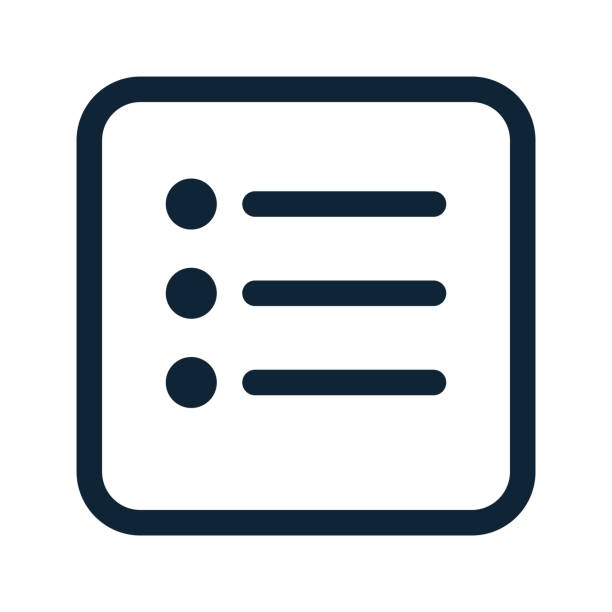 目次へ
目次へ