- 東京地裁平成24年11月27日判決(自保ジャーナル1891号40頁) この事件では右上肢のCRPSが問題となっています。 この事案の特徴は、①判決がCRPSについての初歩的な知見に反することを多々述べていること、②初期に胸郭出口症候群(TOS)と類似する症状が生じていること、③右手指に著しい巧緻運動障害が生じていること、④サーモグラフィー検査の検討に問題があること、⑤判決が自賠責の3要件基準を診断基準と誤解していること、などです。
- 症状の経過
被害者は64歳男子タクシー乗務員で、平成19年1月31日に追突事故に遭います。車両の修理費用は26万円ほどとされていることからは、追突事故としては中程度のものと思われます。
(*以下では日付は断りのない場合は事故日を基準としたものです)
- 事故当日・・・勤務先に戻り、病院に行くことなく帰宅する。 *被害者は、ドアを開けて外に出ようとしたときに追突されて意識を失い、意識を回復して嘔吐したと主張しています。このように少し変わった事情に対しては「本当か?その証拠は?」との視点で検討されるため、疑いのバイアスを持たれやすくなります。 被害者側は、「その傷病が発生する可能性のある事故」であることを証明できれば良く、「その傷病を発生するのにちょうど良い事故」であることを証明する必要はないので、事故状況を必要以上に詳しく主張することは得策ではないと思います。
- 2日後・・・B病院。後頭部痛、右頚部痛、嘔気あるも四肢のしびれなし、徒手筋力検査では4~5とされる。 *事故当日に通院しなかったとの事情は仕事中に事故にあった事例や、末梢神経絞扼障害を後に発症する事例で多く見られます。末梢神経絞扼障害(胸郭出口症候群、手根管症候群、梨状筋症候群など)では、事故による組織の脹れや炎症により徐々に神経が圧迫されて、事故後に症状が悪化するという経過が多く見られます。 *最初の通院で徒手筋力検査が行われていることから、この時点で右上肢の脱力ないし違和感の症状を訴えていたはずです。 *判決はCRPSを否定する根拠として、事故直後の症状が比較的軽微であったこと、一定の筋力が保持されていたことを指摘します。しかし、CRPSの特徴は当初の外傷の結果からは想像できないほどに症状が悪化することであるので、これらは初歩的な誤りです。
- 5日後・・・B病院。後頭部痛、右頚部痛の継続と右上下肢の筋力低下を訴える。
- 6日後・・・B病院。右上下肢の脱力と右上肢のしびれを訴え、以後9日間入院する(頚椎捻挫の病名)。7日後に頚椎MRIで異常なしとされる。 *事故から1週間から2か月ほどの期間をおいて、上肢にしびれと脱力が生じる経過は胸郭出口症候群(TOS)で多く見られます。被害者が6日後から9日間入院していることからは、この時点で相当の症状が出ていたものと考えられます。
- 15日後・・・B病院(以後4か月通院)。右頚部痛、右上肢痛、右上肢のしびれを訴える。20日後には握力が右18kg、左34kgとなり、以後も右手の握力低下が続く。 *この時点の症状(上肢のしびれ、脱力、握力の低下)はTOSで典型的に見られるものですが、最後までTOSは疑われず、その鑑別診断のための検査も受けていないようです。 *判決はCRPSを否定する根拠として、この時点で灼熱痛等の激しい痛みや右上肢の機能障害を訴えた形跡がないこと、関節拘縮や骨萎縮が出ていないことなどを指摘しています。 しかし、CRPSには必須の症状は1つたりともありません(定説)。特定の症状が事故直後の時期に生じる必要はなおさらありません。何ゆえここまでひどい誤りを書いているのか不可解です。 *判決はCRPSを否定する根拠として、B病院の診断名は頚椎捻挫(頚髄損傷の疑い)であることを指摘しています。 しかし、CRPSはその診断が遅れることに特徴があり、実際にも全ての事案で当初は別の病名が診断されています。CRPSの診断が事故の3年後以降になった事例も少なくありません。提訴後の鑑定で初めてCRPS(またはRSD)と判断された事案も何件かあります。CRPSの典型症状が出ていても、診断がなく、その検討もされないまま訴訟が終わっている事案も何件かあります。
- 4か月半後・・・C整形外科(以後9か月ほど通院)。被害者は右肩関節痛、頚部痛を訴え、星状神経節ブロックなどの治療を受ける。右手握力の低下が続く。7か月後ころから箸やペンなどの巧緻運動の障害の記載がカルテに現れる。10か月後頃に痛みによる指関節可動域制限が現れる。 C病院は、当初は外傷性頚椎症性神経根症、右肩腱板損傷と診断するも、半年後に反射性交感神経萎縮症(右上肢)、外傷性肩関節周囲炎の診断名を追加し、1年後に複合性局所疼痛症候群(CRPSタイプⅠ)と診断する。 *半年後にRSDとの診断が下されています。裁判例の上では早期に診断された事案に属します。判決はRSDの診断の根拠が不明であるとしますが、持続する疼痛と関節可動域制限で現時点のCRPSの判定指標を満たし、あとは鑑別診断が問題となるのみです。 *判決はCRPSを否定する根拠として、1年後になるまでCRPSとの診断がされていないと述べます。しかし、半年後に診断された「RSD」と1年後に診断された「CRPSタイプⅠ」は同じ意味です。いくらなんでもさすがにこの間違いはひどすぎます。また、「診断が遅れたのでCRPSではない」という理屈にも無理があります。 *この判決は理解し難い非常に不可解な誤りが多く見られます。そのほぼ全部がほかの事件で加害者側の主張として見たことがあるものです。ここまで特殊なことを独自で多数考え出したとも思えないので、これらは加害者側の主張や医学意見書によるものでしょう。 加害者側が提出する医学意見書は、全ての事件で被害者の主張を否定する結論にするためか、「さすがにこれはふざけすぎだ」というレベルのものが多く見られ、本件のような典型症例になると「ダメでもともと」といった感じのやっつけ仕事のひどいものが出てきます。そのレベルのものでも華々しい経歴の高名な医師の名義がついていると信用してしまう裁判官は少なくないようです。 裁判所はこの種の訴訟で明らかに舐められています。仮にこの判決の記載が医学意見書を元にしているとすれば、その執筆者はこの判決の入れ食い状態には笑いが止まらないでしょう。
- 5か月後・・・D病院(以後1年8か月ほど通院)。頭痛、めまい、右上肢のしびれなどを訴える。
- 1年後・・・被害者が原付に乗っていて猫をよけて転倒して、頭、額、膝を打撲してレントゲンを撮ったことがD病院のカルテに記載される。 *この記述からは被害者はこの時点では原付を運転できる状態にあったようです。被害者は足で蹴っていただけと主張したようですが、この点は信じ難いです。この時点では右手は巧緻運動障害が出ていたものの、原付のハンドルを握ることやアクセルを回すことができる状態にあったようです。 この時点での被害者の主張する症状と矛盾しませんが、怪我人や障害者が活発に動くことに対して良くない評価をする人もいます。
- 1年1か月後・・・C整形外科が平成20年2月29日を症状固定日として、後遺障害診断書を作成する。傷病名は「頚椎捻挫、外傷性頚椎神経根症、右肩腱板炎、複合性局所疼痛症候群(CRPS)」とされ、自覚症状は「右上肢脱力、頭痛、頚部・右肩・肩甲背部痛、右上肢しびれ・疼痛、巧緻運動障害」とされ、他覚所見等は徒手筋力が4~5とされ、握力が右28kg・左36kg、右上肢部分にしびれ・疼痛、手指完全屈曲困難があり、右肩部分に疼痛があるなどとされる。 労災では9級と認定されますが、自賠責では後遺障害に該当しないとされ、異議申立後に14級とされます。 *この時点では右上肢の疼痛・しびれは続いていたものの、右手の握力はかなり回復しています。右上肢の筋力もある程度保持しています。肩・肘・手関節の可動域制限の有無は不明です。痛みのため検査ができない人も少なくないので、検査数値が書かれていないときでも可動域制限がないと決め付けることはできません。 *判決はCRPSを否定する根拠として、右手握力の変動が大きすぎると指摘しています。この種の指摘は加害者側の医学意見書には頻出です。しかし、症状が一進一退を繰り返したことから、症状そのものが全てなかったことにはなるわけがありません。計測値の変動が大きいことは、症状が一進一退を繰り返したことや、日によって症状の変動があって症状が固定していなかったことを意味します。これに対して、詐病であれば握力の計測値に大きな変動を生じさせないように偽装できます。 *握力に限りませんが、計測値のぶれ(ゆらぎ)の大きさを指摘して、「これは私の経験ではありえない。非常に不可解な出来事だ。ここまで変動することはあり得ない。医学的に説明することは極めて困難である。真に症状が存在するならば絶対にあり得ないことだ!」などと強く主張をするのが加害者側の医学意見書の常套手段ですが、これを信じてしまった判決も少なからず見られます。これでは裁判所が舐められてしまうのもやむを得ないのかもしれません。 *巧緻運動障害は7か月後までには生じています。本件では巧緻運動障害の原因として、CRPSと外傷性頚椎神経根症が考えられます。判決からは、頚椎神経根症と診断された根拠は不明です。仮に骨棘による神経根圧迫などの状況が確認されていないのであれば、巧緻運動障害や左上肢の疼痛、しびれの原因として診断された可能性があります。
- 2年2か月後・・・E病院(以後判決時まで通院)。被害者は、巧緻性が低下し、肩関節が硬直していると訴える。外傷性頚椎症性神経根症、CRPSと診断を受ける。右上肢知覚異常、筋力低下のために日常生活動作にも支障を来たしており、右上肢には労働能力がないとされる。 *症状固定後に症状がかなり悪化し、肩関節の硬直も進行しています。その可動域が記載されていないのは、痛みのため検査ができないとの事情があるようです。 *CRPSには症状の悪化が停止したと判断できる医学的な根拠はないので、症状固定の診断(認定)は症状がこれ以上悪化しないことを意味しません。実際にもCRPS(RSD)の裁判例では症状固定後に症状の悪化が生じた(と被害者が主張している)事案がかなりの割合で含まれています。 *労災では、RSD(CRPS)に関しては症状固定後も国費で治療を継続できるアフターケア制度があります。症状固定後も通院で症状の悪化を抑制し続けないと、上肢の硬直などが進行するからです。このように症状固定後に症状の悪化が進行することは国の制度の上でも前提とされています。
- 2年5か月後・・・B病院。身体障害者認定のための診断書が書かれる。外傷性頚椎症性神経根症、CRPS(RSD)を原因とする右上肢の高度の機能障害(右肩、肘、手関節、手指の高度の機能障害)があるため、右上肢での日常生活動作は不可能であるとされる。その約2週間後に3級と認定される(上肢機能障害・右上肢機能の著しい障害)。 *右上肢全体に高度の機能障害があるとされていることから、可動域制限も右上肢全体に及んでいると考えられます。典型的な上肢のCRPS(RSD)の状態に至っています。 *判決には上記の各時点の肩、肘、手関節の可動域が書かれていません。被害者の主張には「右上肢の上げ下ろしを満足にすることができず」とあるので、可動域の制限自体はないようにも見えます。しかし、これは「右上肢の高度の機能障害」という認定には合いません。 おそらくこの被害者は痛みのために可動域検査ができない状況が続いていて、特に症状固定後の悪化で肩・肘・手関節に強い可動域制限が生じていたのではないかと思います。被害者の主張する「右上肢の上げ下ろしを満足にすることができず」というのは症状固定時の状況であって、その後の悪化には対応していないように見えます。
- 5年半後・・・B病院でサーモグラフィー検査を受ける。測定点28対(56か所)のうち、患側(右側)の皮膚温が低かった測定点が21対で、うち2対が1.3度差で、残り19対が0.9度以下の差とされる。 *この結果は、患側に皮膚温低下が存在することを明確に示していますが、判決は有意な差とは言えないとします。 *皮膚温に限らず程度を問題とする場面では、加害者側は、「一見して明らかな差がある場合に限定するべきだ。そうでないと区別があいまいになる。」と主張します。もちろん、これは暴論です。普通に見て差異があることが分かれば差異ありで、それが微妙であれば擬陽性となります。本件の場合は当然に「差がある」(陽性)となります。
-
- 胸郭出口症候群(TOS)について
- 本件で最初に気になったのは、当初の症状が胸郭出口症候群(TOS)の典型症状であることです。TOSはむち打ち損傷により発症する症例が多いことが知られています。しかし、交通事故によりTOSを発症しても、裁判例の上では1年以上経過してからその診断を受けたものが過半数で、TOSには診断が遅れる傾向がはっきり出ています。この事案でもTOSの診断がないことからTOSの発症を否定することはできません。
- 上肢のCRPS(RSD)に関する裁判例ではTOSが悪化してCRPSを発症したとみられる事案が多くみられます。仮にTOSが基盤となってCRPSを発症したとしても、CRPSを発症してからTOSの診断のための検査をすることはほとんどないので、CRPSを発症させた原因となる傷病は分かりにくくなります。
- 本件は、事故後に遅れて症状が出ることが多いというTOSの特徴に合致し、上肢の痛み・しびれ・脱力や握力の低下はTOSの典型症例です。また、TOSによる神経損傷を想定すると、これを基にしたCRPSの発症も理解しやすくなります。従って、この事案は「TOSが基盤となって上肢のCRPSを発症したと思われる事案」と言えますが、それ以上の解析はできません。 ただし、CRPSを発症させたメカニズムを解明しなければ、最終的な症状がCRPSと言えないわけではありません。本件では最終的な症状が上肢のCRPSであることは明らかです。
- 仮にTOSが基盤にあるとすると、CRPSタイプⅠ(RSD、神経損傷ないもの)ではなくタイプⅡ(カウザルギー、神経損傷のあるもの)になります。これにより自賠責ではRSDではなくカウザルギーの主張ができ、自賠責の3要件基準の対象外となります。 また、TOSの検査として血管造影、神経造影、電気生理学検査を受けて所見が得られた場合には、その所見により自賠責の認定が取りやすくなります。
- CRPSについて 本件では最終的な症状がCRPSであることに問題はありません。判決はCRPSを否定していますが、誤りです。判決は自賠責の3要件をRSDの診断基準と勘違いしていますが、3要件基準は自賠責においてもRSDであるかどうかを認定する基準ではありません。そもそもCRPSには必須の症状は1つもありません(定説)。この点は何回も述べてきたのでこれ以上は書きません。 普通に考えれば、本件のようにCRPS(RSD)との診断が繰り返された事案の全ては実際にもCRPSであると考えられます。しかし、訴訟では全ての事件で加害者側はその診断を否定し、ほとんどの場合にそれを裏付ける医学意見書を出してきます。この前提状況が分かっていれば、本件のような典型症例で労災の認定(9級)も出ている事案でCRPSを否定する結論になることはあり得ないと思います。 これは思考のスキームの問題です。例えば、20年前であれば突然の電話で「おじいちゃん(泣)…事故にあって人に大怪我させちゃった(泣)…今すぐ示談のためにお金を(大泣)…」という電話を孫から受ければ、それを信用する祖父が大半であったと思いますが、今では高齢者でも信じる人は少ないでしょう。思考のスキームの中に、これが「振込め詐欺」の典型例として組み込まれているからです。
-
- 診断に対する検討の仕方そのものについて
- 判決はCRPSを否定する根拠として色々と述べているのですが、そのどれもが初歩的な誤りであることは、上に述べたとおりです。それ以前の問題として最も気になったのは、診断を検討するための理屈になっていないことです。 仮にCRPSを否定することが正しいとした場合に「では一体、この症状をどんな傷病名で説明するのか?」(鑑別診断)という問題です。本件では典型的な上肢のCRPSの症状が生じています。ほかの候補は見当たりません。
- 診断とは仮説設定や鑑別診断により、現に存在する症状について多くの候補から正しい傷病名を探し出す作業です。ある診断が誤りであるとしたことにより、現に存在する症状が消えるわけではありません。本件ではCRPSとの診断を否定する場合には、被害者の症状をより合理的に説明できる代替案を挙げる(鑑別診断を行う)必要があります。 しかし、訴訟では加害者側はその傷病とされるためのハードルをひたすら高くするだけで代替案となる傷病名を出さないことが普通です。この方法は出発点に誤りがあるので、検討する価値のない反論です。 この判決も、CRPSと診断するためのハードルを高くする論理のみを述べていますが、「では現に存在する症状をどう説明するのか。この患者の正しい傷病名は何か。」という肝心の部分を置き去りにしています。これは法律的にも誤りで、審理不尽と言わざるを得ません。
- ところが、裁判所は「被害者が主張するのはCRPS(RSD)という傷病名のみである。だからCRPSかどうかのみを検討すればよい。その先は関知しない。」という誤った考え方に誘導されると、その方向に向かいやすいようです。この種の思考は法曹特有のバイアスのようです。 もとより証明責任を事実認定に取り込むことには問題があります。証明責任は真偽不明になったときに結論(法規の適用)を決めるものなのに、それ以前の段階で証明責任を用いて事実を認定するというのは誤りであると思います。
- また被害者が主張する傷病名は要証事実(主要事実)であるのか、という問題もあります。被害者はあくまでも現に存在する具体的な症状や後遺障害を主張しているのであって、その根拠の1つとして傷病名を持ち出しているに過ぎません。ほかの傷病名で後遺障害が裏付けられるのであれば、それでも構いません。傷病名が不明でも検査結果や日常生活の状況などから後遺障害を認定してもらっても構いません。この考えのもとでは傷病名は間接事実であって、証明責任が生じる対象ではありません。
- 損害賠償請求訴訟では「損害に関する被害者の主張には証明責任が課せられる」という素朴な発想のまま、被害者の主張について必要以上に広く証明責任を課す方向に流れやすい面があります。 しかし、例えば被害者側が、加害者の車は時速60キロであったと主張し、加害者側が時速10キロであったと主張した事案において、裁判所が時速30キロであったと認定することもできます。この場合の速度は主要事実ではありません。 仮に主要事実とすると、「時速60キロとの主張が認められない場合に不適用となる法規」があるはずですが、それはありません。時速30キロでも同じ損害(主要事実)が生じることがありえます。また、時速30キロでもわき見などの注意義務違反(主要事実)がありえます。この場合の速度は間接事実であって、過失や損害などの主要事実を基礎付ける背景事情と言えます。 問題は損害賠償請求訴訟で被害者が主張している内容のうち、どこまでが主要事実であるのか、ということですが、それは注意義務違反や損害に直結する事柄として、ケースバイケースで考えるほかないと思います。
- 本件で被害者が主張するCRPSとの傷病名については、被害者が主張する具体的症状や後遺障害(事実的損害)を合理化する事情ではあっても、弁論主義の対象となる主要事実ではありません。 ほかの傷病名で同じ事実的損害が説明できる場合もあり、検査結果などから事実的損害を説明できる場合もあるので、傷病名にまで主要事実を広げる必要はありません。主要事実を広げすぎると、判断が硬直化するという問題が生じます。 従って、加害者側が「とにかくその傷病ではない。その先は知らない。」として診断された傷病名を否定する主張をしても、その主張は医学的にも法的にも、被害者が受けた診断を否定できる構造を有しません。傷病名を否定するためには、加害者側は「本当は、疾患Sである」などの代替候補を主張する(鑑別診断の手順を踏む)必要があります。 要証事実を広くして間接事実についてまで「~であると認めるに足りる証拠はない」との趣旨を述べている判決をしばしば見かけますが、間接事実については「~であろう」などの推論結果を示して、その推論を総合して主要事実の心証につなげるべきです。
-
- 抱き合わせ否定論について
- 判決で気になったのは、判決は最終的な症状として、被害者がCRPSを発症しているのかどうかについて若干あいまいな認定をしていることです。 本件では、被害者側は、①被害者が主張する後遺障害が存在すること、②それが事故により引き起こされたこと、の2点を主張しています。判決は、①を否定する趣旨を述べていますが、同時に「仮に後遺障害が存在する(CRPSを発症した)としても本件事故との因果関係はない」というニュアンスも述べています。 つまり、①と②を別個に検討せずに、抱き合わせで否定する論法を用いています。この抱き合わせ否定論は、加害者側が頻出で用いる特殊の論法です。これは否定するためにのみ効果を発揮する錯誤論法ですが、しばしばこの論法を取り入れてしまった判決を目にします。
- 判決は、CRPSとの診断が繰り返され、労災の認定も出ていることから①についてあいまいな部分を残したまま、仮にCRPSを発症していたとしても、事故は比較的軽微である、事故直後の症状は軽度である、事故後すぐにCRPSと診断されなかった等の多数の理由を述べて、被害者が本件事故によりCRPSを受傷したと直ちに認めることはできないとの論理を述べています。 しかし、「確実に①であるとは認められない」では実質的な認定は何もなされません。これに付け加えて「仮に①であるとしても、②(=事故との因果関係」を満たす①ではない。」としても、実質的な認定はなされないままです。この点は以前に述べましたが、非常にまずいと思います。
- ルンバール事件の最高裁判決では、「ほかに原因は考えられない」との論理で因果関係を肯定しています。メカニズムを解明して正面から因果関係を肯定することができない場合でも、「ほかに原因は考えられない」という理由で因果関係を肯定できます。これは論理としてごく当たり前のこと(背理法)を述べたに過ぎません。 この「ほかに原因は考えられない」という論理の応用形として、概括的認定を認めた最高裁判例も少なからずあります。概括的認定とは、「原因はAかBに絞られる(ほかに原因は考えられない)。AまたはBが結果を生じたメカニズムは不明である。AかBのいずれでも加害者の過失が認められる。ゆえにA、Bのいずれであるかを確定せずに過失と結果との因果関係を認める。」という論理です。 ルンバール事件判決は「原因としてAが疑われる。Aであるとするメカニズムは不明である。しかし、Aのほかに原因は考えられない。ゆえに原因はAである。」という論理です。これは「AまたはA以外のいずれかである(排中律)。A以外のものが考えられない。ゆえにAである。」という単純な論理です。 最高裁判例は、「因果関係を認定するためにはメカニズムを解明しなければならない。」とするドグマを否定しています。従って、原因の側から論理法則による因果の糸を結果に届かせることは必須ではありません。
- 本件では、最終段階の症状からは容易に①(被害者の主張する症状の存在)を認めることができます。事故以外に原因が考えられなければ、因果関係は認められます。事故後に症状が悪化し続けた経過は明らかですので、②の因果関係も当然に認められます。 これに対して、判決は事故が軽微である、事故直後の症状が重症ではない、早期にCRPSと診断されなかった、などと事故の側からしっかりとした因果の糸が伸びていなければならないという形でメカニズム論を取り込んでいます。その結果、「CRPSを生じるような事故であったか」という立証不可能な命題を取り込んでいます。メカニズム論に陥ると、原因の側から論理法則的に因果の糸が伸ばせなければダメであるという発想に陥りがちです。
-
- 証明度について
- 「自由心証が尽きたところで証明責任の機能が始まる」(定説)ことから、私は、「証明責任は真偽不明となった後に結論(法規の適用)を決めるための道具であって、事実を認定する道具ではない」と考えています。これは原理主義であって誤りでしょうか。 私の考えからは、この判決の背後にある考え方は理解し難いのですが、これまで検討してきた判決のなかには、「~であると認めるに足りるだけの証拠はあるか」という視点で、証明責任を有する側に自由心証のレベルで高いハードルを課し、その結果、実質的な心証を形成せずに、否定の事実を認定する判決がいくつかありました。 この論理では自由心証のレベルで証明責任が機能を開始していることになり、しかも、自由心証で証明責任による「認定のためのハードル」を課し、その結果として真偽不明となると再度証明責任を適用するという二重の不利益が生じます。
- しかし、上記の考えを採用しているように見える判決が少なくないように見えます。これは証明度を考慮した結果でしょうか。 証明度を考慮して、「要証事実が高度の蓋然性をもって成り立つこと」を、証明責任を負担する側においてを証明できなければ、その事実は認定できないとして、「~であると認めるに足りるだけの証拠はあるか」を検討するという理屈です。 つまり、要証事実について証明度として「高度の蓋然性」が必要であるとすることは、自由心証において裁判官が得るべき確信の度合いを規定し、自由心証においても証明度を満たしているかどうかという視点で(証明責任を取り込んで)判断できるという論理です。
- この考えに対しては、証明度は自由心証で得た結果としての心証の度合いであり、あらかじめ証明責任を負担する側に厳しい目で判断をするべきであることを意味するものではないと反論できます。 むしろ、裁判官は自由心証ではニュートラルな立場で心証を獲得するべく努めるべきであり、そのために口頭弁論、争点整理、釈明、証拠調べなどの手続が存在すると言えます。 また、「高度の蓋然性」と言っても、一方の主張のみを取り出してそれ自体として確実かどうかを検討するのではなく、相手方の主張との兼ね合いから「こっちの方が正しい」との心証でも構いません。 例えば「原告の主張が正しいと思われるが、確実な根拠はない」という場合であっても、「仮に被告の主張のとおりとすると、~の不都合が生じるから、被告の主張は認められない」という事情から心証を取ることもできます。「高度の蓋然性」を述べたルンバール事件判決でも、「ほかの原因が考えられない」という形で結論を導いています。 また、「原告の主張それ自体では確信が得られない」という場合であっても、「被告の主張との比較では、原告の方が信用できることは間違いない」という場合もあります。この場合も最終的な心証としての「高度の蓋然性」を満たしていると思います。この判断方法を用いるかどうかで結論が異なる事案は少なくないと思います。
- 以上から、仮に「~であると認めるに足りる証拠はあるか」という形で検討するとしても、一方の主張のみを検討するのではなく、対案との兼ね合いも考慮して心証を獲得し、最終的な心証として、要証事実の存在(不存在)について「高度の蓋然性」があるとの認識に至っているかを検討する必要があります。 例えば、CRPSの事件で、被害者がCRPSの判定指標5個のうち1個しか満たさない事例であっても、臨床では「ほかの疾患が考えられない」という理由から医師が確信を持ってCRPSとの診断を下す場合もあり得ます。臨床の統計では、CRPS患者の約2割は5個の判定指標のうち1個しか満たしません。 この場合には、訴訟において「CRPSではない」と主張する側は相応の根拠のある反対仮説を挙げる(鑑別診断を行う)必要があります。例えば、加害者が反論として「CRPSではなく線維筋痛症である」と主張した場合には、線維筋痛症の症状との整合性と、CRPSの症状との整合性で優劣を判断して、心証を得ることになります。 以上に対して、判定指標のうち1個しか満たさないことにより、「直ちにCRPSであるとは認められない」として早々に結論を決める論理が間違っていることは明らかでしょう。心証度は全ての検討を終えた時点で獲得した心証についての問題です。なお、上記のCRPSの例は、それ以前の問題として、それが要証事実に関するものかという問題があります。
- このように考えていくと、「~であると認めるに足りる証拠はあるか」という視点での検討は、言葉の意味それ自体から、部分的な検討のみで結論を出してしまう誤りに流れやすいように思います。 私は判決文にこのような表現を用いることは避けたほうが良いと考えています。特に間接事実に用いることは誤りであり、主要事実についても心証が獲得できたならば端的に「~と認められる」という形で肯定否定を述べるべきであると思います。 「何が起きたのか」について心証が獲得できなかった場合でも、心証が得られた限度において「~であろうと思われる」という形で書いて、その上で証明責任により決めたことが分かるように書いた方が良いと思います。その場合には、「~との心証は得られたものの、それ以上の心証を得ることができなかった。」との表現を用いるべきであり、「~であると認めるに足りる証拠はない」などの表現は論理的にも法的にも適切ではないと思います。この表現では「何が起きたのか」についての心証形成の作業をせずに、直接「~であると認めるに足りる証拠はあるか」を検討したように見えます。 なお、私は民事事件では心証度として「高度の蓋然性」(80%超の心証ともされる)を求めることは適切ではなく「優越的蓋然性」(50%超原則)で良いと考えています。その方が事実に即した認定が増えるからです。裁判所は端的に正しいと考えた事実を認定して判決を書くべきであると考えています。 証明度については、「民事訴訟における証明度論再考」(田村陽子、立命館法学327、328号)が双方の主張を詳しく検討していて参考になります。
- なお、「現実には、裁判官は、主観的確信がない限り、証明があったと判断することはないであろう」(『民事訴訟における事実認定』12頁)という観点からは、高度の蓋然性でも優越的蓋然性でもいずれでも結論はほとんど同じになるようにも思えます。 どちらの主張が正しいのかを検討した結果、「こっちの方が正しい」という結論を出した場合には、たいていの場合は高度の蓋然性の基準を満たすほどの主観的確信を得ていると思います。対案の提起する問題点を克服できていない状態では「こっちの方が正しい」という心証とはならず、どちらが正しいのか分からないという心証になると思います。主観的な「正しさ」の判断は対案よりも十分に優越しているとの内実を含みます。 ところが、「高度の蓋然性」という縛りを満たすために、「確実な証拠の有無を判決文に書かなければならない」というバイアスが導入されると、柔軟な判断ができなくなり、「~であるとする確実な証拠はあるか」を検討してしまう誤りに向かいやすくなると思います。 本来であれば、裁判官は全ての事件についてきちんと心証を取って判決を下すべきであり、証明責任に結論を丸投げするのは100件に1件以下であるべきです。その前提の上で、全ての事件について「優越的蓋然性」を超えた「高度の蓋然性」の心証を得られるように審理を充実させるべく、訴訟制度を整備してきたというのが、理想論から見た民事訴訟制度の発展史でしょう。 しかし、現実には「高度の蓋然性」という縛りのためか、「~であるとする確実な証拠はあるか」というピンポイントの部分のみを簡単に検討して、事件全体に対する実質的心証(何が起きたのかという心証)を取らずに証明責任に結論を丸投げしているように見える判決が増えている感じもします。これは「確実な証拠もなく提訴した方が悪い」との訴訟観とも言えそうです。 全ての検討を終えた時点での証明度を問題にすると、優越的蓋然性が認められるけれども高度の蓋然性が認められないために、正しいと考える結論を認定できない「心証のグレーゾーン」というべき隙間が生じます。 これに対して、最初から「~であるとする確実な証拠はあるか」という視点で検討を始めれば、心証のグレーゾーンは生じません。このため証明責任を自由心証に取り込んで心証のグレーゾーンを消してしまおうとの流れが生じている感じもします。このような弊害が出るのであれば「高度の蓋然性」という目標を取り下げたほうが良いと思います。 伊藤眞教授は、証明度に関する4つの神話の第1として証明度を上げれば上げるほど事実認定は真実に近づくというのは神話であると主張しています(判タ1086号14頁、判タ1098号10頁)。私もそう思います。
- 以上の前提として、証明度の指標としての「高度の蓋然性」という概念と「優越的蓋然性」という概念は同じ土俵にある概念であるのか、という問題もありそうです。 即ち、「~であるとする確実な証拠はあるか」という形で検討する場合には、証明度としての高度の蓋然性は証拠の有する客観的な証明力の度合いについての評価であるようにも見えます。これに対して優越的蓋然性は、裁判官が「どちらの言い分を正しいと考えるか」という主観的な面が強調されます。 証明度は、要証事実の存否についての最終判断としての心証の度合いのはずなので、そこから主観面を取り除いて証拠による証明の度合いとすることは不自然です。ところが、実際には「これはちょっと証拠が弱いなあ」という感覚を持つことはあります。この場合には「誰だってこの証拠では弱いと受け止めるはずだ」という間主観的な形で証拠それ自体の証明力が客観化されています。 しかし、それはやはり個々の証拠の証明力(証拠価値)の問題であって、個々の証拠からの推論を総合して判断した結果としての証明度は評価する人の主観にあると思います。従って、証明度は結局のところは評価する人の主観的な判断であると思います。 むしろ、この証明度を客観化する方向に向うと、対案との検討をしないまま個々の証拠の証明力を最終判断としての証明度と誤解してしまう誤りに向かいやすいと思います。個々の証拠の証明力は、多くの場合間接事実に関するものであるため、間接事実についても証明責任に判断を委ねるという二重に誤りにも陥りやすくなると思います。この二重の誤りに陥ると、動かしがたい事実を軸にした推論の積み重ねにより心証を形成し、それが「高度の蓋然性」に達しているかを検討するという手順を踏まずに、間接事実についても「~であるとする確実な証拠はあるか」を検討してしまい、「何が起きたのか」という検討をしなくなります。 (2013年6月11日掲載)
 労災9級の右上肢CRPS(24.11.27)
労災9級の右上肢CRPS(24.11.27)

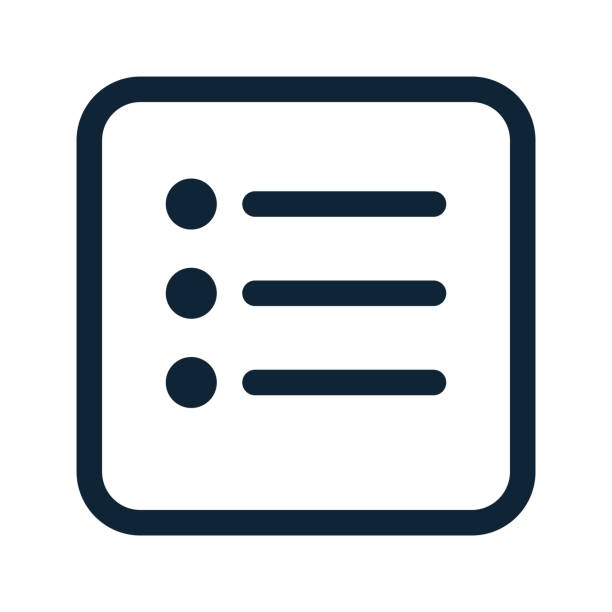 目次へ
目次へ