- 神戸地裁平成25年1月28日判決(自保ジャーナル1895号86頁) この事案の特徴は、①腰背部のCRPSであること、②判決が自賠責の3要件基準を診断基準と誤解していること、③病期説を診断基準と誤解していること、④診断を検討するための論理を用いていないこと、⑤因果関係と抱合わせで結果を否定する論理を用いていること、などです。①以外の論点が前回と同じです。
-
- 症状の経過
- 被害者は事故時32歳の男子公務員(警察官)です。平成20年1月28日に、横断歩道を歩行中に右折乗用車に衝突される事故に遭います。 (*以下では日付は断りのない場合は事故日を基準としたものです)
- 事故当日…H病院。救急搬送され立位、歩行が困難であり入院(56日間)となる。翌日、第11胸椎圧迫骨折、後頭部打撲と診断される。 入院中は体幹ギプスや硬性コルセットで固定され、退院時は独歩可能な状態まで回復。
- 70日後…C病院。1年間通院。背部痛を訴え、鎮痛剤を処方される。
- 1年3か月後…G病院。背部痛が改善しないためセカンドオピニオンとして受診。元の病院で治療を続けるように指示される。
- 1年4か月後…D病院整形外科。背部痛が改善しないためセカンドオピニオンとして受診。体幹筋の萎縮、胸~腰椎部の圧迫痛からRSDと診断し、B病院を紹介した。診断書には「圧迫骨折後の反射性交感神経性ジストロフィー疑い」とされる。
- 1年4か月後…B病院。第11胸椎骨折、慢性複雑難治性疼痛と診断される。投薬内容の見直しやリハビリを行うため44日入院。
- 1年7か月後…C病院。症状固定とされ、後遺障害診断書が作成される。傷病名は第11胸椎圧迫骨折、自覚症状は背部痛、運動時痛、可動域制限、他覚症状は第11胸椎の変形と胸腰部の運動障害で前屈30度、後屈15度、右屈30度、左屈30度、右回旋30度、左回旋30度。常時コルセットの必要ありとされ、症状改善の見込みについて「不変と考える」とされる。
- 2年1か月後…C病院。RSDと診断される。自賠責で11級7号とされる。
-
- CRPS(RSD/カウザルギー)の発症部位について
- 本件では腰背部(背部)のCRPSと診断されています。事故による第11胸椎の圧迫骨折に起因して、腰背部痛み、可動域制限などが生じたものと考えられます。 交通事故の裁判例の上ではCRPSを発症する部位には偏りがあり、上肢全体に生じるものが約6割、手関節以下に生じるものが約1割、下肢が約2割ですが、胸部のCRPS、肘のCRPS、坐骨神経のCRPS、膝のCRPSなどの事案もあります。 CRPSを発症する部位について特に制限はありません。CRPSの症状が生じていて、ほかの傷病では説明できないときには(鑑別診断)、CRPSと診断されます。
- 主治医によれば、①強い腰背部痛、②中程度の腫脹、③皮膚温上昇(サーモグラフィーは行っていない。発赤、蒼白、チアノーゼはない)、④発汗異常(発汗テストは行っていない)、⑤軽度の骨萎縮、⑥腰部の筋力低下、⑧胸腰部の可動域制限からCRPSと判断したようです。 医学的には上記の症状を説明できるほかの傷病がなければ、この診断が正しいものとされます。本件では他に考えられる傷病名がないため、腰背部のCRPSとすることに特に問題はないと思います。
-
- 診断への検討の仕方
- この判決の問題点は、前回検討した東京地裁平成25年1月22日判決とほぼ同じです。診断への検討の仕方は最も基本的なことですが、この点ですでに誤っている判決が非常に多くみられます。これは診断とは何かを知らないことに原因があります。
- 診断の手順 診断の標準的な手順は、主訴からの仮説設定と鑑別診断です。 即ち、①現に存在する症状(および検査結果)を列挙して、②これを最も良く説明できる仮説を設定します(初期の診断)。③その仮説が誤っていたとした場合に次に可能性が高い傷病を鑑別診断としてあげて、④症状・検査結果から両者を比較検討します。⑤その結論により全体が整合性をもって説明できるか確認します。その結果、問題がある場合は③以降を繰り返します。 要するに、その時点ごとに候補となる疾患から最も正しいと思われるものを選び出すのが診断です。それでうまく行かない場合には次の候補を検討します。検査の感度や特異度を考慮して検査結果を尤度比などで検討するEBM(科学的根拠に基づく医学)の方法も上記の枠組みで行われます。この枠組みは事実認定の方法にも通じるものがあります。
- 誤りの典型例 ①典型性の度合いの検討 ある特定の疾患のみを検討対象にして、その疾患から生じるとされる症状の多さや重傷度、その疾患でみられるとする検査結果の多さから、その疾患としての典型性の度合いを検討すること、これが診断に対する誤った検討の典型例です。 ②絶対的基準の設定 ある特定の疾患のみを検討対象にして、例えば疾患RにはA~Cの3つの症状が必須であるとして、その症状が明確に生じているかどうかを検討すること、これも診断に対する誤った検討の典型例です。 ほとんどの疾患には必須の症状や検査結果はありません。症候群との名称の疾患はその傾向がより強くなります。従って、「ある疾患とされるための絶対的指標」は通常は存在しません。存在しない絶対的指標が存在するとの仮定の上に検討をすることは誤りです。
- 「診断基準絶対論」の誤り これらの典型的な誤りに陥っている判決を少なからず見かけます。その発想の根底には、「ある疾患であるかどうかは、その疾患の診断基準を当てはめるだけで判断できる」との誤解(診断基準絶対論)があります。実際には、ほぼ全ての疾患は診断基準へのあてはめのみでは診断することはできません。 ある診断が下されたときにそれを否定することができるのは、「この症状・検査結果を説明できるより適切な傷病がある」との検討(鑑別診断)のみです。訴訟では現に主治医が下した診断がすでに存在します。この場合には鑑別対象となる代替案を出さなければ、その診断を否定することはできません。 CRPSに関しては「診断基準」はなく、「判定指標」が存在するのみです。これは鑑別診断で用いるものさし(指標・目安)です。実は診断基準とされているもののほぼ全部は、その診断基準のみで確定的に正しい結論が導かれるわけではありません。診断基準を当てはめて診断を下しても、どうしても一部の患者はそれでうまくいかず、鑑別診断により新たに診断をする必要が出てきます。 上記の2つの誤りの致命的な問題点は、「疾患Rではない」と判断したときに代替案が存在しないことです。さんざん診察や検査をして、何らの結論も出せない方法は臨床では使えません。
- 本件でのあてはめ 本件では上で列挙した症状を説明できるのはCRPSであり、鑑別診断の対象となる傷病も思いつかないので、CRPS(RSD)との診断に特に問題はありません。 主治医が下した診断に対して、代替案も出さずにこれを否定することはそれ自体が誤りであるので、「RSDではない」とのみ主張することは診断を否定できる理屈ではありません。従って、加害者側の主張は最初から検討する必要がありません。 なお、判決は被害者の背部痛が「RSDに由来する症状であるか」との視点で検討し、RSDに否定的な見解を述べるものの、RSDであるかどうかの結論を明言していません。つまり、判決は「被害者がRSDであるかどうかは別として、少なくとも被害者の背部痛はRSDに由来する症状であると認めることはできない」という特殊な理屈を述べています。
- CRPS(RSD)に必須の症状はない この点は医学的な常識であり、繰り返し述べてきたので詳しくは書きません。日本のCRPSの判定指標からもこの点は一目瞭然です。 判定指標の5項目をA~Eとすると、AB、AC、AD、AE、BC、BD、BE、CD、CE、DEの10通りの組合せのいずれもが陽性(感度約80%)となります。症状がADであってもCEであってもCRPSの可能性があります。ゆえに、必須の症状がないことは自明です。
-
- 3要件基準は診断基準ではない
- この点も上記から自明です。自賠責の手続内の基準が診断基準ではないことも自明です。自賠責の認定係が診断基準を適用してRSDであるかどうかを判断すれば、医師法違反になります。 3要件基準は診断基準と誤解されやすいように作られ、運用されている面がありますが、CRPS患者のうちこの基準を満たすのは高く見積もってもせいぜい1~2%です。
- 3要件基準は①上記の10通り(10通り全部でも患者の80%しか捕捉できない)のうちABの1通りのみに絞込み、②A(皮膚・爪・毛のいずれかの萎縮性変化)のうち皮膚の変化のみに限定し、さらに皮膚温の変化も必要とし、③B(関節可動域制限)をより重度な関節拘縮に限定し、④A~Eに含まれない要件(骨萎縮)を加え、⑤それら3要件が「明らか」であることを要求し(医学的には症状が確認できれば足ります)、⑥これを画像などの資料により確認する(関節拘縮は画像では確認できません)という非常に厳しいしばりを多重に設定しています。 すでにして①のみで捕捉できるCRPS患者は全体の8%となり、②と③で各3分の1以下になるので、これだけで捕捉できるCRPS患者は1~2%となる計算です。 これに加え④~⑥のしばりもあるので、3要件基準をそのまま運用するとCRPS(RSD)にり患している患者でも、10万人のうちの1~2名程度しか捕捉できないはずです。実際にもCRPS(RSD)と診断されて、自賠責で3要件基準を満たすとされた事案は見た記憶がありません。
- 但し、労災の後遺障害認定では3要件基準への当てはめをせずに9級とした事案は少なくないようです。労災では3要件基準を用いずに主治医がCRPS(RSD)と診断した場合にはそのまま認める傾向もあるようです。 ところが、判決は「客観的な証拠に基づいて認定することが可能な①ないし③の症状を重視して判断することとする」(95頁)として自賠責の3要件基準を診断基準と誤解して重視しています。RSDと診断した3つの病院の診断はこれを満たしていないとしています。この点が判決の最大の誤りです。
-
- 抱合わせ否定論について
- 判決は「では、症状固定時に原告に残存する背部痛は、RSDに由来するといえるか」(95頁)とのタイトルで具体的な検討に入っています。即ち、①被害者がRSDにり患しているかの検討と、②被害者の背部痛がRSDによるものか(因果関係)の検討を一体としています。 この種の検討の仕方そのものに問題があることは繰り返し指摘してきたとおりです。
- 普通に考えれば、背部痛は事故以来一貫して訴えてきたものであるので、これが事故による後遺障害ではあることは明白です。また、被害者は長期間疼痛緩和の治療を受け、相当の可動域制限が生じていることから、その疼痛はかなり強いものと認められます。症状の存在や強さについては、治療の実態や医師の判断を尊重して検討するほかありません。 しかし、加害者側はここで特殊な理屈を持ち出してきます。即ち、①被害者は事故によりRSDを発症したと主張し、②そのRSDによる背部痛が存在すると主張をしているのであるから、③「RSDに由来する背部痛」であるとされなければ、強い背部痛ではないという主張です。 この思考の枠組みで、被害者がRSDであれば強い背部痛であり、RSDでなければ強い背部痛ではないという理屈で、判決は「では、症状固定時に原告に残存する背部痛は、RSDに由来するといえるか」との検討を最初に行なっているのです。 この理屈はどこかおかしいと感じなければダメだと思います。ところが、この種の理屈を取り込んでしまった判決をしばしば見かけるようになりました。この理屈は以下に述べる多くの問題を含んでいます。
- 懐疑論への反駁を求める誤り まず、前提事実が未確定の状態で因果関係を判断する点に問題があります。本件では背部痛が存在することは、事故以来多くの病院でそれを訴えて長期間にわたり治療を受けてきたことから明らかです。この治療経過や可動域制限からは被害者の背部痛はかなり強いものであることを認定できます。これは痛みの症状を認定する常識的な方法です。痛みそのものを裏付ける確実な証拠を別のもの求めることはそれ自体が誤りです。 被害者の痛みの強さやこれによる日常生活や就労への影響の度合いは、被害者がRSDであるかどうかに依存するものではありません。 しかし、痛みそのものは他者が直接確認できないことから、「絶対にその痛みは存在するのか。確実な証拠はあるのか」という発想に流れやすく、そこで痛みとは別のもの(例えば、RSDであるかどうか)に判断を委ねようとするようです。
- 証明度を高くしすぎる誤り この発想の根底には、民事訴訟の証明度として「確実に~である」との証明が必要とする誤解があります。しかし、証明度として確実であることは必要ではありません。 例えばアメリカでは証拠の優越の程度で良いとする考え(50%超原則)が採用されていて、どちらの言い分が正しいのかという視点で判断します。これに対して、日本での証明度が確実であること(95%超)とするとあまりにも差が大きくなり、しかも、証明責任を負担する側に酷な結果となります。 私は基本的には最高裁の述べる「高度の蓋然性」は80%程度の証明度であり、「おそらく~であろう」との心証で足り、判断対象によっては証拠の優越の程度(50%超過原則)とする例外を許容していると考えます。最高裁判決は「確実性」という言葉を用いずに「蓋然性」(可能性)という言葉を用いています。 実質的に考えても「何が起きたのか」を認定せずに、「何が起きたのか分からないが、とにかく確実な証拠がないのでその主張は認めない」だけで裁判を終えることは、非常にまずいと思います。 もちろん証明度を高くする場合でも事実認定では「何が起きたのか」を認定するべきであって、獲得した心証をそのまま「事実認定の結果」として判決に書くべきです。即ち、生じた可能性が最も高い事実を推論した結果が事実認定であり、要証事実の証明度(法規適用の問題)は分けて書くべきです。法規適用の局面において「その心証が高度の蓋然性のレベルに達しているか」を検討するべきです。 証明度を高くして事実認定に取り込んでしまうと「おそらくAであると推測できるが、確実にAあるとは言えないので、Aであるとは認められない」との考察に向かいます。これでは、「Aであるとの心証なのに、なぜそれを認定しないのか」と突っ込まれてしまいます。証明度を高くするとこのような「心証のグレーゾーン」が大きくなります。 そこで事実認定に証明責任を取り込み、かつ必要とする証明度を高くして「確実にAではない」とのみ述べる方向に流れ易くなります。心証を空洞化させることによるグレーゾーンの消去です。
- 事実認定に証明責任を取り込む誤り 証明度を高くする誤りの背景には、事実認定に証明責任を取り込む誤りが存在すると考えられます。「~とする(確実な、相当の)証拠はあるか」という見方は事実認定に証明責任を取り込んでいます。 もちろん事実認定は自由心証の領域で行うべきことであり、自由心証が尽きたところで証明責任は機能を開始します(定説)。証明責任は事実を認定するための道具ではなく、事実が認定できなかった場合(真偽不明の場合)に結論(法規の適用)を決める道具です。 しかし、一部の裁判例は、事実を認定するにあたって証明責任はどちらにあるのかを考慮して、その上でその事柄について「~であるとする(確実な)証拠はあるか」との検討をしているように見えます。 証明責任はあたかも問題の解けなかった受験生が振る5角形の鉛筆のようなもの(愚者のサイコロ)であり、とにかく答えは出しますが正答率は保証しません。私は鉛筆の出した答えより自分で考えて出した答えの方が正答率は高いと思います。法曹は自分で考えた答えの方が正答率の高い人であるべきです。従って、できるだけ証明責任に丸投げせずに事実を認定することが望ましいと思います。その意味でも求める証明度を必要以上に高くすることは良くないと思います。
- 間接事実に証明責任を適用する誤り 事実認定に証明責任を取り込んでしまうと、間接事実にも証明責任を適用する誤りに陥り易くなります。 間接事実については、その確実性を求めるのではなく、個々の間接事実から推論できることを積み重ねていく必要があります。従って、確実でないことのみでその間接事実を捨て去ることは誤りとなります。この誤りは個々の間接事実の証拠力と要証事実の証明度を混同する誤りでもあります。 例えば、診断が正しいかどうかは間接事実であって、他の病名でも同じ後遺障害(要証事実)を説明できればその後遺障害は肯定できます。また、 病名が不明であっても長期の入通院や検査結果など(別の間接事実)から後遺障害(要証事実)を認定しても構いません。 従って、①被害者がRSDと主張しているのだから、裁判所はRSDであるかどうかのみを検討すればよいという考えや、②裁判所は被害者の後遺障害がRSDによって生じたものかどうかだけを検討するべきであるとの考えはこの点で誤っています。 また、診断のもとになる個別の症状も間接事実であって、個別の症状の一つ一つについて「確実に存在するか」を検討することも誤りです。間接事実については得られた心証をそのまま述べる必要があります(そうしないと、推論の基礎になりません)。判決にはこれらの誤りが見られます。
-
- 因果関係とメカニズムと取り違える誤り
- 判決は被害者に強い背部痛が存在するかを検討するために、「RSDにより生じた背部痛であるか」を検討しています。即ち、「RSDにより生じた」とのメカニズムが解明できる場合にのみ、強い背部痛であると認められるとする論理です。 しかし、最高裁のルンバール事件判決は、結果が存在し、その結果と原因と目される行為(ルンバールの投与)との間のメカニズムが不明である(4回の鑑定の結果)との前提で、ルンバールの投与以外の原因は考えられないという理由で因果関係を肯定しています。 即ち、詳細なメカニズムが解明できなくとも、「それ以外の原因は考えられない」との心証に至れば因果関係を認めることができます。現実の世の中の事象のほぼ全部は詳細なメカニズムは不明であって、背景事情から絞り込んで「それ以外の原因は考えられない」との理由で因果関係を認めているのが実情です。 非常に厳密に言えば、全ての物理法則、科学法則は経験的に確認された事実に過ぎないので(科学哲学の定説)、メカニズムにより因果関係が肯定できる事案は世の中には存在しません。全ての科学法則は究極的には「それ以外の説明は考えられない」という点に行き着きます。
- 判決は、「RSDに由来する」というメカニズムが肯定できないので、被害者の背部痛は強い背部痛ではなく、脊柱の変形とは独自に評価するレベルには至っていないとします。 一方で判決は被害者がRSDにり患しているかどうかについては、否定的なニュアンスを述べるもののはっきりと結論は述べません。これは複数の医師がRSDとの診断を繰り返しているため、断言できなかったものと考えられます。従って、判決は「被害者がRSDにり患しているかどうかは別にして、被害者の背部痛はRSDに由来するものであることが明らかではないので、強い背部痛ではない。」との特殊な理屈を述べていることになります。
- 被害者の治療経過や可動域制限などからは被害者の背部痛が強いものであることは容易に認定できるはずです。しかし、判決は「強い背部痛があるとするためには強い背部痛が生じたメカニズムが解明されていなければならない」とする理屈でこれを否定しています。 これは構造的には「Aが死亡したという重大な結果を認めるためにはAの死因が明らかにならなければならない」との理屈と同じです。抱合わせ否定論はこの種の誤りに誘導するものです。 この誤りに陥る原因はメカニズムを因果関係と取り違えることにあります。この誤りに陥っている人は、因果関係が存在する場合の大半はそのメカニズムが明らかになるはずであるとの実感があるようです。しかし、実際はその逆であると思います。 例えば、交通事故のあとに大腿骨骨折が判明した場合において、どうしてそれが交通事故により生じたと判断するのでしょうか。普通は、事故前に大腿骨骨折が生じていてがまんしていたはずがないとか、事故以外の原因は考えられないという理由で即座に因果関係を認めます。 これに対して、自動車が衝突した角度、骨の強度、車体の剛性、被害者の姿勢などの全ての事情を明らかにして、大腿骨骨折が生じるべくして生じたと実感できるメカニズムを明らかにすることは不可能です。因果関係が一目瞭然の場合であっても、ほとんどの場合にその具体的なメカニズムは不明です。
-
- 循環論法
- 判決は「では、症状固定時に原告に残存する背部痛は、RSDに由来するといえるか」との表題で単純化すると以下の理屈を述べます。即ち、①被害者はRSDではなかろう、②ゆえに被害者の主張する背部痛はRSDによる背部痛ではない、との理屈です。 私は理屈が循環していると思います。即ち、①の判断のなかで被害者の背部痛をRSDの症状としての背部痛であるのかの検討が必要であり、②でも同じことを述べているに過ぎません。
- 判決は、被害者の訴える強い痛みについて、「遅くともD病院を受診した平成21年5月18日の時点で、灼けたもので内臓をえぐられるような痛みを感じていたというのであるから、原告の主張は採用できない」(96頁)と述べています。 これは21年5月に被害者が強い痛みを訴えていたのに、それを知る医師が平成22年2月になってようやく「RSD様病態を呈している」と診断書に記載したのは遅すぎるので、その主治医の診断は採用できないという流れで述べたものです。判決はその結果として上記の症状の存在も否定しています。 しかし、診断の要素として検討した症状を、診断により確認できる症状として再度述べる構造では循環論法になってしまいます。そもそも「診断により確認できる症状」という概念自体に誤りがあります。
- 循環論法に陥るのは、診断が正しいならば症状の存在が認められるという逆転した発想に原因があります。実は、この誤りはCRPSを否定した多くの裁判例にも見られます。 この発想に陥ってしまうのは、診断に対する検討の仕方に問題があります。正しくは、上記のとおり現実に存在する症状や検査結果に仮説設定や鑑別診断の手順で候補となる傷病名を当てはめ、最もうまく説明できるものを選択するという医学的な手順による必要があります。 ところが、「被害者の主張する症状は虚偽だ。医師の確認した症状や検査結果も被害者の偽装工作にだまされたものだ。」との定番の主張が加害者側から出されると、前提となるはずの症状や検査結果が、そのままでは使えないとの錯覚に陥ることがあるようです。このため「まず、診断が正しいかどうかを検討して、診断が正しいならばその症状が認められる」という方向(循環論法)に向かってしまうのです。
-
- 背景事情からの認定を避ける誤り
- 症状や検査結果の存否は、原則としてそれ自体を直接に認定するほかない事柄です。これは長期間の入通院や医師の診断のほかに、被害者の属性などのすべての事情を総合的に検討して、ときには裁判官が全人格を賭けてでも判断するほかない事柄です。 もともと事実認定の本質はすべての事情を考慮した上での総合的判断という点にあり、個別の事情に対応する証拠の有無をチェックする作業は補助的なものに過ぎません。裁判に現れるほとんどの事情は直接的な証拠を持たないのですが、それゆえに無視したり、軽視したりしていて視野を狭めて行けば正しい判断ができなくなります。むしろ、直接的な証拠を持たない事情をいかにして評価して一貫した全体像を作っていくのかが事実認定の本質であると思います。「動かし難い事実」の積み重ねやこれに基づく推論のなかで、全ての事情を整合させる総合的判断をするというのが、伝統的な事実認定論です。
- 被害者の背部痛の程度について、加害者側の主張に騙されて「ほかの事情で証明するほかない」と安易に考えてしまった誤りの背景には、対応する証拠のチェックという低レベルなものを事実認定のなかで重視していることにあると思います。この誤りの亜種に「一見して重大で確実に存在が認められる症状のみを認める」との誤りがあります。 その根源には、自由心証に証明責任を取り込む誤りがあり、事実の認定にはすべからく確実な証拠が必要であるとの誤解があるようにも見えます。間接事実はもとより、主要事実にもそのようなしばりはありません。
- 判決は被害者に軽度の骨萎縮があるとした医師の診断を、「いかなる画像に基づき骨萎縮の有無及び程度を判断したのか明らかではない」とし、他の病院では骨萎縮への言及がないとして否定しています。 しかし、他の病院は骨萎縮の有無の判断を求められて回答したわけではないので、この部分は理屈になっていません。これは骨萎縮があるとした医師の判断を端的に信用するという普通の判断ができず、ほかの証拠で補強しようとする誤りにより生じています。
- 事実認定の空洞化 判決は、「何が起きたのか」という意味での事実認定をせずに「~であるとする確実な証拠はあるのか」という方向性で「RSDに由来する背部痛はあるのか」を検討しています。 そのため、結論として、「RSDに由来する背部痛ではない。よって、強い背部痛ではない。」として、被害者の背部痛の強さに否定的なニュアンスを述べます。その上で、被害者の背部痛は第11胸椎骨折に伴う疼痛であり、「脊柱の変形と派生関係にあり、11級の評価の中に含まれる」(97頁)と述べます。 抱合わせ否定論のなかで、「~であるとする確実な証拠はない」との判断を繰り返すと、実質的な心証を形成することなく結論を導くことになります。「確実にAとはいえない」との認定はいかなる事実も確定しません。これでは事実認定が空洞化してしまいます。その原因は事実認定に証明責任を取り込む誤り(及び証明度を高くしすぎる誤り)にあると思います。 判決はRSDであるとする要件のみをひたすら厳しくする誤り(診断への検討の仕方の誤り)をしているため、RSDではないとした結果として、「では何であるのか」が空白になっています。被害者について多くの医師が確認した症状・検査結果が説明されずに放置されて、「とにかくRSDではない。 その先は関知しない。」との結論になっています。 事実認定は、「何が起きたのか」(生じた可能性が最も高い事実は何か)を認定するべきであり、この方法では事実認定の空洞化は生じません。事実認定の空洞化が生じてしまうと、空洞化した部分に架空のストーリーを滑り込まされやすくなります。
-
- 劇場型の事実認定
- 消費者事件には劇場型という分類があり、架空会社の社債を購入させる手口や振込め詐欺など多種多様な劇場型の事件があります。劇場型犯罪の特徴は、犯人の用意した架空の舞台設定に被害者をのめり込ませるという点にあります。これに対して、例えば被害者が「お前は本当に息子なのか」などの疑問を述べても、犯人はその場しのぎの言い訳を積み重ね、被害者の認識が架空の舞台設定の中にとどまるように誘導します。 架空の舞台設定ですので、落ち着いて検討すれば矛盾はすぐに見つかるようにも思えるのですが、いったん舞台設定に引きずり込まれてしまうと、その設定自体を疑う思考に向かわなくなります。
- 確証バイアス(反証の軽視) これは事実認定にも当てはまります。誤った前提を正しいものと信じてしまうと、「その前提から導き出される結論は何か」の検討に向かい、その前提を疑うことができなくなります。その結果、不合理な帰結が生じても最初に信じてしまった前提を疑うことが困難となります。 判決は、3要件基準や病期説を診断基準であるとする誤った前提を強く信じてしまったために、不合理な帰結が生じても、その前提を疑うことができなくなっています。 しかし、冷静になって考えてみれば、被害者が事故以来長期間にわたって多数の病院で疼痛緩和の治療を受け、腰部に可動域制限があり腰の動きを制限するためにコルセットを着用してきたことや、複数の医療機関でCRPS(RSD)との診断を受けてきたことは、厳然たる事実です。 また、3要件基準が診断基準であれば、こんな簡単なことさえも知らずに、それに反する診断を複数の医師が繰り返すというのも非常に不合理であると疑うべきでしょう。 ところが、人間はいったん強い思い込みに陥ると、その思い込みに反する思考ができなくなります。その結果、「医者というのは本当にいい加減な人が多いのだなあ。」という安易な考えで診断を否定する方向に向かいます。この発想は、自分が正しいと信じた内容に矛盾する事実を打ち消すための認知的不協和とも言えます。 この発想に至ると、自分の信じた内容に都合の良い証拠の価値を高く見るという確証バイアスも強くなります。被害者の症状経過に対して加害者が少しでも疑義を述べるとそれに飛びついて、「この被害者は大げさに痛みを訴える人だなあ」という見方に流れやすくなります。
- 反証の軽視(不合理な帰結の放置) この判決は被害者の詐病や医師の迎合について正面から述べていません。しかし、判決の結論はこれらの存在を不可欠とします。判決の問題点は導いた帰結の先に存在する不都合に対する無関心です。この無関心も、最初に自分の信じた内容を正しいものとするための認知的不協和であると言えます。 誤った内容を強く信じてしまうと、それに矛盾する事実を安易に否定する発想に流れ易くなり、自分が信じた内容が導く不合理な結果に対しても無関心となります。これは劇場型の事実認定に特徴的です。 仮に、正面から「症状の経過を被害者の詐病として説明できるか」と考えた場合、詐病で長期間の治療経過を説明することは非常に困難であり、客観的な検査結果を作り出すことは不可能であることが即座に帰結できます。また、医師が迎合して骨の萎縮があるとか、発汗が増えているという虚偽内容の報告をする可能性も極めて低いと言えます。 おそらく判決を書いた裁判官も被害者の詐病や医師の迎合については、「その種のこともありうるだろう」、「何か自分には分からない特殊な事情があるのであろう。」という程度のあいまいな認識であると思います。これは劇場型の事実認定に特徴的な認知的不協和ないし保守性バイアスであると言えます。 これまで検討した事案でも被害者が重篤な症状を訴え、長期間の治療を受け、医師がCRPSとの診断をなしている事案で、その診断を否定した判決が少なからずあります。しかし、それらの判決の大半は、被害者の詐病や医師の迎合について正面から検討していません。この思考過程には劇場型の事実認定が存在するように思います。
- 事実認定の空洞化の影響 劇場型の事実認定が生じるのは、事実認定が空洞化してしまったことから、その舞台設定の誤りを見つける手がかりがなくなってしまったことにも原因があると思います。 伝統的な事実認定論に従い、まず動かし難い事実を認定し、次にそこから合理的に推測できる事実を認定していき、これらの作業を積み重ねていき全体の整合性を取れるように事件の骨格を作り上げて行くという手法を用いていけば、基本的な部分で誤った認定に至ることはないと思います。 ここでは論理法則も重要です。本件では、「RSDではないとすれば、どんな疾患であろうか」という点から「RSD以外の候補は見当たらない」という結論に至れば、大筋で正しい認定に至ったと思います。被害者が長期の通院で疼痛緩和の治療を受け続け、RSDとの診断を受けている事実を代替案がないまま否定することも、実は論理法則違反です。 「AもしくはA以外である」(排中律)、「A以外の候補は見当たらない」、「よってAである」は、基本的な論理思考です。これに対して、「Aとする確実な証拠はあるか」という視点で「とにかくAであるとする確実な証拠はないので、Aであると認めることはできない。A以外の候補はないが何が起きたのかは不明である。」とすることは誤りです(事実認定に証明責任を取り込む誤りでもあります)。上の「A以外の候補はない」とは、本件では「CRPS以外の候補はない」を意味します。 1つの事柄のみを検討の対象にして、その対象が「~であるとする証拠はあるか」を検討する仕方では、事実認定が空洞化してしまいます。このやり方では多面的な検討はできず、とくに「ほかの説明は考えられるであろうか」との基本思考(代替案の有無の検討)を欠落させることになります。 (2013年10月16日掲載)
 3要件基準で否定された腰背部CRPS(25.1.28)
3要件基準で否定された腰背部CRPS(25.1.28)

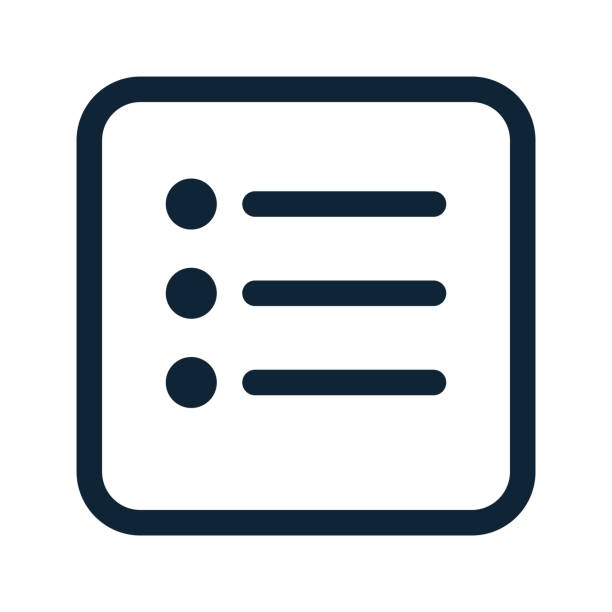 目次へ
目次へ