- 東京高裁平成25年4月11日判決(自保ジャーナル1901号69頁) (1審:前橋地裁大田支部平成24年10月26日判決) この事案の特徴は、①両上下肢のCRPSであること、②最終的な症状の程度を判断せずに因果関係を否定したこと、③ブラッドパッチによる悪化の可能性を述べたこと、④病期説を診断基準と誤解していること、⑤診断を検討するための論理を用いていないこと、⑥鑑定意見に疑問があること、⑦投薬の検討に疑問のあることなどです。
- 症状の経過
被害者は症状固定時(平成17年5月)52歳の有職主婦です。平成16年11月27日に、横断歩道を歩行中に左折乗用車に衝突される事故に遭います。以下では、「判決」は地裁判決を指します。高裁判決は「高裁判決」と書きます。
- 事故当日…E病院。救急搬送され右前腕疼痛・圧痛、下部背部痛を訴える。 以後、左前腕打撲、腰部打撲、頚部捻挫、背部挫傷の診断を受け、半年間、一貫して四肢の痛みとしびれを訴える。 治療経過は判決の別紙一覧表に掲載とありますが、自保ジには載っていないので詳細は不明です。判決には、「21機関の治療費」(83頁)との記載があり、多くの病院に入通院しています。
- 2週間後…B病院。5か月後にRSDの可能性を検討される。
- 半年後……C病院。外傷性低髄液圧症候群と診断され、ブラッドパッチを受ける。
- 時期不明…D病院。詳細は不明。
- 2年半後…F大病院。RSDと診断される。サーモグラフィーで体温の低下みられる。甲医師は、CRPSによる慢性難治性疼痛として、日常生活動作は困難であり、就労も困難とする。 乙医師は、CRPSタイプ1とし、痛覚過敏、皮膚血流の異常、全身痛、下肢のしびれ、振動による知覚過敏、下肢を中心とした皮膚の貧血所見があるとし、自立歩行はできず、座位保持でさえ、疼痛や、しびれを悪化させるとして、後遺障害等級3級3号の「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」に該当するとした。
-
- CRPSの発症部位について
- 本件は被害者が両上下肢にCRPSを発症した事案ですが、その詳しい部位(中枢部と末梢部のいずれが痛みの中心かなど)は不明です。 事故直後に右前腕に痛みを訴え、その後に左前腕の打撲と診断され、下肢は神経伝導速度検査で脛骨神経(損傷を受けると足首以下に症状が出る)に異常が見られた(80頁)ことからは、末梢部が痛みの中心であるようにも見えます。判決ではそれ以上の詳細は不明です。
- 両上下肢の末梢部に痛みを生じてその後にCRPSと診断された事例は「事故2週間後に両手両足に症状発症」の項目で紹介した大阪地裁平成22年11月25日判決があります。 この事案は事故で自転車から転落して後頭部を打ったものの、両手両足には怪我をしていなかったのが、事故2週間後ころから両手両足の痛みが増してきて、両足について後にCRPSと診断されています。本件で痛みの部位が末梢部であるとするとこの事案と似た症状と言えます。
-
- 事実の経過と争点について
- 被害者は事故直後から両上下肢の痛みを訴え、半年後から通院したC病院で外傷性低髄液圧症候群と診断されてブラッドパッチを受け、それでも症状が治まらずにF大学病院に通院しCRPSとの診断を受け、2年4か月後頃(平成19年3月頃)に症状固定となったようです。合計21もの医療機関に入通院したことからは、非常に重い症状が出ていて治療に難儀したと想像できます。 通院先の大学病院の2名の医師が意見書を出し、被害者はCRPSであり3級3号という非常に重い後遺症が残ったとしています。普通に考えれば、この主治医の意見のとおりの症状が存在します。
- これに対して、加害者側は、事故の半年後(平成17年5月)には被害者の症状は固定していて、仮にその後の被害者の症状がCRPS的な症状であるとしても、症状固定の後に受けたブラッドパッチにより発症したものであると主張し、その旨の意見書を出しています。 但し、通院していたときは平成19年3月頃に症状固定となり、そこまでの治療費等も支払われていたと考えられるので、加害者側が事故後半年で症状固定となったと言い出したのは訴訟になってからのようです。 その後に鑑定が行われ、鑑定人は加害者側の主張を支持する意見を述べています。この鑑定意見に疑問のあることは後記のとおりです。
- 以下はあくまでもこの事件のことではなく、一般論として述べるものです。これまで検討した事件にも裁判所の選任した鑑定人が非常に大きな疑問のある意見を述べていたものが多くありました。 ことに複数の鑑定が行なわれた場合には、鑑定人ごとに見解が天と地ほどの違いが出てくることがほとんどであり、このことから非常に問題のある鑑定をしている方が多数いることは明らかです。 ところが、被害者側は裁判所から鑑定人のリストを見せられても、どの鑑定人がまともな意見を述べてくれるのか全く分かりません。これに対して、加害者側(損保側)は被害者側とは桁違いに大きな情報を蓄積しています。従って、被害者側からすると鑑定人選びはあたかも「カードが透けて見える相手とのババ抜き」のような状況になります。これまで検討した裁判例でも鑑定意見は被害者側に極端に不利になるもの(主治医の診断を全否定するもの)が7~8割ほどとなっています。 CRSPの事案では、加害者側は後遺障害を否定してそれを支持する医学意見書を出すことが恒例ですが、主治医が毎回誤診という根本レベルの医療過誤をしているとは思えません。しかし、鑑定人と比べても遜色のない立派な経歴の方がその意見書を書いていることが多いようです。 しかし、この実情を理解している裁判官はほとんどいないようです。むしろ、「裁判所はほぼ無条件で鑑定人の意見に従うべきだ。」との考えの方が多いようです。即ち、双方が意見を出し合って鑑定人を選んだのだから、鑑定人はあたかも当事者が選んだ仲裁人のような立場にあるので、その鑑定人の意見に従うのは当然であるとの考えです。 疑問のある意見を述べた鑑定人が有名大学の医学部の教授やCRPSを専門にしている方であることも少なくないようで、この鑑定手続と医師の権威という舞台装置のなかで劇場効果が生じたように見える裁判例は少なくありません。以上はあくまでも一般論です。
-
- 結果を認定せずに因果関係を判断する誤り
- 被害者は21の医療機関に入通院して3級3号という非常に重い後遺障害等級を主張し、通院先の大学病院の2名の医師がこれを支持する意見を述べています。本件では、加害者側がその後遺障害をそのまま全否定することは難しい状況にあります。 そこで、加害者側は、被害者の症状の否定のみではなく、被害者は実際の症状固定よりも2年近く前(事故半年後)に症状固定となっているので、最終的な症状を判断せずに因果関係を切るべきだと主張をしています。
- これは加害者側に非常に都合の良い理屈ですが、判決はこの理屈を取り入れています。判決は被害者の最終的な後遺障害を認定していません。 判決は、「被害者は平成17年5月(事故半年後)に症状固定となったので、仮にそれ以後にRSD(CRPS)により悪化したとしても因果関係はない。よって、最終的な症状には関知しない。」との理屈になっています。 判決は、「事故によって『RSD的な』症状が生じたとするためには、事故半年後までにRSDと確定診断できる状況にある必要がある。」との理屈で検討しています。
- 加害者側が最終的な症状を否定する主張を強く主張した結果、判決もそれを認定せずに因果関係だけを検討することはしばしば見られます。この場合は常に因果関係を否定する結論になります。 事実認定では確実なものだけを認定するべきだという方向性の強い方はこの誤りに陥りやすいようです。この方法では、「最終的な症状は確実ではないから認定しない」、「因果関係も確実ではないから認めない」という形で事実認定が空洞化していきます。これでは「何が起きたのか」は分かりません。 事実認定は「何が起きたのか」の視点で「動かし難い証拠」から認定できるものを積み上げていくべきです。これに対して、「証明責任を満たしているか」の視点で「満たさない」を積み上げていくやり方をしている判決もしばしば見かけますが、この方法は良くないと思います。
- 因果判断の対象である結果を不確定にしたまま因果関係を判断できるとする理屈には無理があます。「どのような症状であるのかははっきりしないが、とにかくそれと因果関係はない」という理屈はおかしいと思います。 本件では、結果を認定すれば事故からの一貫した症状であると即断できるのにも関わらず、結果をあいまいにして因果関係だけを判断しようとすることは誤りというほかありません。 因果関係の判断は、結果を認定したのちに「この結果を生み出した原因としてはそれ以外には考えられない」との判断によっても行なわれる(ルンバール事件最高裁判決など)ので、このルートを削除することは誤りとなります。この点は何回か述べてきました。
-
- 「~と診断できないので症状が存在しない」の誤り
- 判決は、CRPSの診断基準について述べ、「まず、C病院を受診する平成17年5月まで原告の症状を、上記RSD及びCRPSの診断基準に当てはめて検討する。」(80頁)と述べて、その結果、この時点ではCRPSとは認められないとします。その上でこの時点で症状が固定していたので、因果関係が切れるとします。
- 判決は、①被害者が事故によりCRPSを発症していたならば、事故半年後までにCRPSと診断できる症状が絶対に存在したはずである、との前提に立っています。 その上で、②事故半年後にCRPSと判断(診断)できるかを検討し、③CRPSと判断できなければ、その時点では「CRPSによる症状」ではない、④この場合には、その後にCRPSの症状が出たとしても連続しない。⑤よって、最終的な症状がCRPSであるかどうかを判断せずに、因果関係を否定できる。という理屈を述べています。 出発点の①からしてそのような前提が成り立たないことは明白であると思います。②以下も奇妙な理屈です。診断は症状や検査結果を元にして下されます。従って、「CRPSと診断できないのでその症状は存在しない」という理屈は成り立ちません。症状の存在は常に大前提であって、診断の有無に左右されません。この点は前回も述べました。
- 最終的な症状は両上下肢の強い痛みですので、事故直後から訴えてきた両上下肢の痛みとは連続することは明白です。症状のレベルで考えればこれは自明です。しかし、判決は「CRPSと診断できるほどの症状」という特殊なしばりでこの連続性を否定する理屈を述べています。
-
- 1つの疾患のみを検討する誤り
- 診断とは現に存在する症状に対して複数の候補から正しい傷病名を選び出す作業であって、最初から候補を1つに絞って「ある特定の傷病の診断基準に当てはめた結果、その傷病ではなかった」との検討をすることは、誤りです。その疾患の典型的な症状が出ていなくとも、他の疾患である可能性が除外できれば、その疾患と診断できます。1つの疾患のみを候補として検討することは誤りとなります。
- 判決は同じ疾患(CRPS)の診断基準をいくつも並べて検討することで判断の精度が向上するとの錯覚に陥っています。具体的な代替案との比較の視点がないため無意味な検討となっています。この点はこれまでに何回も述べました。 この判決は、Lankfordの病期説を診断基準と勘違いしています。病期説は疾患のイメージをつかむプロトタイプとしては意味があるという類のもので診断基準ではありません。しかし、病期説に従う症状経過の人は皆無に近い(そもそもCRPSには必須の症状が存在しない)ので今日では全く意味がないとも評されています。
-
- 症状の悪化を考慮しない誤り
- CRPSの症状の進行速度は人によって大きな違いがあります。これまで検討したCRPSの裁判例では、事故後半年ほどで急激に症状が悪化して症状固定になった事案もあれば、徐々に症状が悪化して3年以上経過してから症状固定となった事案もあります。 症状の進行がゆるやかな場合には、当初はCRPSによる症状がはっきりとは出ていないことが多いようです。CRPSの診断基準や判定指標はある程度症状が進行して重症化しないとCRPSと診断されにくいという問題があります。 重症化しないと診断できないという問題は他の多くの疾患でも生じる問題です。この問題に対して、例えば関節リウマチ(RA)では早期治療という視点から、2010年に診断基準が改定され、新たな分類基準が作成されました。CRPSには早期治療のための診断基準は存在しません。 もちろん、CRPSでも早期に治療を開始することは重要です。CRPSを疑った場合には早期から積極的に色々な治療を試してみるべきであるとされています。 判決は、発症後の早い時期の症状を見分けるという視点で検討しているわけではありません。むしろ、発症直後にCRPSの症状が明確に出ているはずだという前提に立っています。これは致命的な誤りです。
- 本件では、その後に被害者がCRPSと診断されたという結論が出ています。従って、当初の症状がその後に悪化して、CRPSとしての症状が明確になっていったと考えることが最も自然で合理的です。 ところが、判決は初期症状の検討において、症状の悪化という視点さえも取り入れていません。逆に、判決は事故の半年後に症状が固定していて、その後の症状の悪化とは無関係であるとしています。
- CRPSの裁判例では症状固定後に悪化したと被害者が主張している事案がしばしば見られます。CRPSには症状の悪化が止まったと判断できる指標はありません。ある一時期の症状が安定していたとしても、その時点での症状固定の判断が正しかったのかどうかは結果から判断するほかありません。 CRPSでは疼痛緩和の治療などを止めてしまえば症状の悪化が進行するために、労災においてはアフターケア制度により症状固定後も3年間(その後も継続可能)は治療が続けられるようになっています。CRPSにおいては治療の継続により症状が安定した時期があっても、そこで症状が固定したとは言えません。
- 裁判例では事故後半年以内にCRPSと診断されるのは2割程度で、当初から大学病院などに入通院していた場合などに限定されます。 ほとんどの場合に初期の通院先ではCRPSと診断されません。この場合にはその病院の診断書やカルテにはCRPSを疑うべき症状はほとんど記載されません。このため、CRPSを知っている病院に転院した直後にCRPSを疑う症状がいきなり複数出てくるという事情は多くの裁判例で見られます。 判決のようにCRPSと診断しなかった初期の通院先のカルテ等で確認できる症状だけを取り出して、「この時点ではCRPSではなかった。」と断言できるはずもありません。しかも、その検討によって半年で早々に症状固定に至っていたとすることは誤りというほかありません。
- なお、判決は平成17年5月以降に受けたブラッドパッチによりCRPSを発症した可能性がある(判決は結果を認定していないので、仮にRSDを発症したとしたらそれはブラッドパッチの影響だろうという理屈で述べています)。しかし、ブラッドパッチでCRPSを発症したとする理屈は奇異であり、事故直後からの症状の連続性を否定できる理屈でもありません。
-
- 鑑定意見について
- 本件では被害者の症状などへの医師の意見として、①被害者の主張する内容を述べる通院先の大学病院の2名の医師の意見書、②加害者側から出された意見書、③鑑定人の鑑定書が出されています。 被害者の後遺障害について、①は3級3号と非常に重いものとし、②と③は平成17年5月時点で症状固定となり14級9号(一番低い等級)であるとします。主治医の意見と鑑定意見では天と地ほどの隔たりがあります。
- 判決は鑑定意見に沿った内容となっていますが、判決の引用(80頁)する鑑定意見は疑問があります。 まず、被害者の各種の筋反射の異常所見は頚髄症で説明できるとする部分は、被害者が頚髄症の診断を受けていないので前提に難があります。この反射を根拠に頚髄症とする趣旨であれば誤りです。事故による頚椎損傷の病態が頚髄症に類似するもので、それを基盤にCRPSを発症したという考えであれば、なるほどと思う面もあります。しかし、鑑定は既往症としての頚髄症の症状が事故と無関係に出ているとの趣旨のようで、これでは事故後の症状経過の説明はできません。 また、神経伝導速度検査で検知された脛骨神経の障害を変形性腰椎症で説明するのも疑問です。普通は逆です。現に末梢神経に損傷が確認されたのですから、腰椎由来ではなく末梢神経の損傷による症状と考えます。 下肢の体温低下については腰椎症に伴う自律神経症状としますが、痛みを訴えている部位に体温の低下があれば、普通は痛みとの関係を認めます。痛みの場所とは異なる腰椎にその原因を求めて、さらに中枢の自律神経を通して、さらに例外的に局所にのみ出現した部分的な自律神経障害の症状とするのは、合理的な思考ではありません。 事故から平成17年5月までの腰部・背部痛、手足のしびれについて、事故前からの変形性頚椎症による症状が一時的に強まった状態で心理的ストレスが加わり回復を遅らせたものというのも、まれな症例の連続による無理のある説明です。主治医の診断のとおりにCRPSによる症状と考えればすっきりと説明できます。
- 鑑定書は被害者の最終的な症状について、RSD又は骨髄障害に罹患している可能性は否定できないとします。しかし、何をもって「骨髄障害」の症状としたのか意味不明です。 鑑定書は、被害者の症状の悪化はブラッドパッチの影響であるとして、「少なくとも下肢の症状については、ブラッドパッチがRSD的な血管運動異常を含めた自律神経症状の契機となった可能性がある。」としています。しかし、ブラッドパッチで「RSD的な」というあいまいな症状を説明する理屈には無理があります。この部分で述べるメカニズムそれ自体が一般的ではなく奇異です。 鑑定は被害者がCRPS(RSD)であることを否定的ですが、この部分では「RSD的な」という形でこれを認めるという矛盾が存在します。要するに、「CRPSを認めるとすればブラッドパッチにより発症したという形で認める。」と述べています。 結局、鑑定書は被害者の最終的な症状の内容や、それがRSDであるかどうかはあいまいにしつつ、とにかく事故との因果関係はない、心因的なものであると主張しているようです。判決はこれを取り入れています。
- 判決が引用した鑑定意見の抜粋はすべてが疑問のある内容です。判決が引用した部分だけをみると、あくまで個人的な感想ですが「これはちょっとふざけすぎ。悪乗りしすぎ。」という感じもします。 これまで検討した裁判例においても、このレベルのものは多く見られました。このレベルのものでも、裁判所の選任した鑑定人という舞台設定で述べられると劇場効果で信じてしまう人が少なくないようです。裁判所は舐められています。判決は鑑定書のこの部分を「詳細で信用性のある意見」として引用したように見えます。
-
- 抗不安薬の投与について
- 高裁判決は事情を少し付け加えてこの地裁判決を支持しています。高裁判決も「平成17年5月の時点でCRPSを発症したと認められなければ(確実に発症したとする強い証拠がなければ)、その後にCRPSを発症したのかどうかに関わらず、そこで因果関係が切れる」との理屈を用いています。 ところが、平成17年4月23日のB病院のカルテに「RSDか。神経科へコンサルタント」との記載があり、これはこの時点でRSDを疑う症状が存在した証拠となります。 しかし、高裁判決は地裁判決同様にこの半年後の時点で確定的にCRPSであったと認められなければ、その後の症状悪化とのつながりは切れるという前提で検討しています。その上で判決は、「この時点において控訴人がRSDを発症していたと認めることはできない」(72頁)としています。私は前提が論外であると思います。
- 判決はその理由として、抗不安薬のセルシンを処方されたことに着目し、RSDの可能性を検討したけれども、むしろ心因反応の可能性を重視してセルシンを投与したとします。つまり、高裁判決はセルシンという精神疾患への適応とされる薬を処方されたのは、痛みの種類が心因性疼痛であるからだという理解に至ったようです。これも医学意見書か鑑定書に基づくものでしょうか。 しかし、これではRSDを疑ったと記載しつつ、RSDではない心因性疼痛として治療したことになり矛盾します。 そもそも神経障害性疼痛に対して精神疾患への適応とされている薬を処方することはごく普通のことで、むしろ国際疼痛学会などで第1選択薬とされているのは抗うつ薬や抗てんかん薬などです(『ペインクリニック』30巻別冊春号216頁)。
- 例えば、抗うつ薬では三環系、四環系、SSRI、SNRIなどほとんどの薬が神経障害性疼痛の治療に鎮痛薬として用いられています(『神経障害性疼痛診療ガイドブック』57頁)。 抗うつ薬だけではなく、抗てんかん薬にも古くから鎮痛効果が認められ、ガバベンチンはCRPSで多く用いられています。その効果を改良したプレガバリン(リリカ)は鎮痛剤として広く使われています。神経障害性疼痛に対してオピオイドのような副作用の強い薬をいきなり処方することはありません。 事故による痛みを訴える患者に対してはNSAIDs(エヌセイド。非ステロイド性抗炎症薬)を投与する事案が良く見られますが、NSAIDsは炎症を生じるような侵害性疼痛が本来の対象であるので、神経障害性疼痛に対しては推奨されていないようです。実際には投与されている例をしばしば見ますが、神経損傷による炎症防止でしょうか。 そこで、抗炎症作用のないアセトアミノフェンも選択肢に入りそうですが、単品では推奨されていないようであり、トラマドール塩酸塩(オピオイド)と合体させたトラムセットが推奨されています。ただし、オピオイドは最初に投与される薬ではありません。対象となる症状に対して、選択すべき薬が段階的に決められています。
- 本件でも、被害者は最初のうちは交通事故による痛みということで、ロキソニンなどのNSAIDsが処方されていたと思われます。しかし、その痛みがRSDによる神経障害性疼痛の疑いがでたことから、次の薬として何を選択するのかという問題が生じます。 神経障害性疼痛に関しては、国際疼痛学会や欧州・カナダでは抗うつ薬では第1世代の三環系を推奨しています(『ペインクリニック』30巻別冊春号215頁)。三環系は副作用の強い古い薬という面もあるので、本件では最初に選択する薬としては避けられたのかもしれません。 抗てんかん薬のガバベンチンはGABAを増強する作用を期待されて作られたのですが、「驚くべきことにGABA受容体に作用しているのではない」(『ラング・デール薬理学』567頁)と判明し、Caチャネルα2δリガンドであるとされています。これを改良したのがプレガバリンです。これらは副作用が心配であるとして、最初は別の薬を試してみることもあるかと思います。 そこでまずセルシン(ベンゾジアゼピン系。ジアゼパム。GABAの作用を増強する)を最初に試してみたというのは選択手順として合理的に説明できます。 セルシンの適応を見てみると「神経症、うつ病、心身症(更年期障害、消化器疾患、循環器疾患、自律神経疾患、腰痛症、頸肩腕症候群)の不安・緊張・抗うつ」(『今日の治療薬2013』848頁)とされています。神経性の痛みの鎮痛効果と痛みによる不安増加を抑える目的で投与されたと理解できます。実際にも効果があったことが高裁判決に書かれているので、選択として結果的にも正しかったと思われます。 ただし、併用した薬などを見てみないとこの点ははっきりしません。当初から強い痛みの訴えがあり、早い時期から各種の鎮痛薬が試みられ、セルシンはその鎮痛薬の補助薬として処方された可能性もあります。いずれにしても、被害者が心因性の痛みを訴えていると考えてセルシンを投与したという話ではありません。 以上に対して、高裁判決ではそれまでに投与された薬や併用された薬の有無にも触れずに、セルシンは抗不安薬なので被害者の痛みは心因性であって、その効果が出たのでやはり心因性であったとの趣旨が述べられていますが、検討のレベルがあまりにも低すぎて話になりません。 (2013年12月15日掲載)
 症状固定後とされた両上下肢CRPS(25.4.11)
症状固定後とされた両上下肢CRPS(25.4.11)

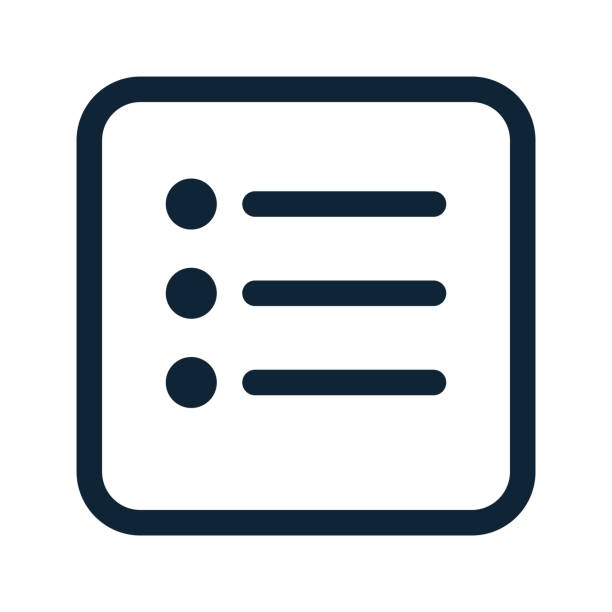 目次へ
目次へ