- 仙台高裁平成24年7月26日判決(自保ジャーナル1881号24頁) (1審:福島地裁いわき支部平成23年11月24日判決) この事案の特徴は、①腕神経叢損傷の事案であること、②両側に症状が出ていて片側のみが診断されたと思われること、③筋萎縮必須論が出されていること、④筋電図検査を否定する意見が出されていること、⑤問題のある医学的知見が多く出されていること、⑥胸郭出口症候群の検討がされていないことなどです。
- 症状の経過
被害者は事故時19歳の契約社員(郵便局に採用されてまもなく事故に遭った)です。平成18年5月15日に後退してきた自動車が被害者の乗っていた原付に衝突するという事故に遭います。
- 事故当日…F病院。救急搬送され頚部痛及び右手のしびれを訴えたため、中心性脊髄損傷が疑われ、11日間入院。事故当日の握力は右が13kgで左が16kgであった。MRIでは右肩に明らかな腱板損傷は認められなかった。
- 12日後…B病院。中心性脊髄損傷は否定され、右腕神経叢損傷とされる。後頸部痛、右肩、上肢しびれ、脱力の主訴。頸椎運動制限及び運動時頸部痛、右上肢橈骨側・遠位側優位の知覚障害・運動麻痺が認められる。9か月ほどの通院の間、左右の握力の低下が認められる。
- 8か月後…症状固定とされる。これに基づき14級9号との認定を受けた。被害者はその後も通院を続ける。
- 11か月後…C診療所。右肩痛、右上肢挙上制限を訴える。レントゲン、MRIでは異常なし。頚椎椎間板損傷、右腕神経叢まひ、右肩関節周囲炎とされる。
- 11か月後…D病院。右肩痛を訴える。握力右5.1kg、左20.6kg。医師は上腕、前腕の周径に左右差がなく、右腕神経叢損傷と合致しないとC病院への書面に記載した。右肩関節唇損傷、右腕神経叢損傷と診断した。
- 1年8か月後…C診療所。右腕神経叢まひ、右肩腱板疎部損傷とされ、再度症状固定とされる。
- 2年7か月後…F病院。筋電図検査で遠位筋ほど多相性の神経原性電位を認めるとして、腕神経叢損傷(全型節後損傷)と診断される。
- 2年10か月後…再度後遺障害診断書が作成される。これに基づき12級13号との認定を受けた。
-
- 片側だけ(一部だけ)の診断について
- 被害者は事故当日から両手の握力が低下し、その状況が少なくとも1年以上続いています。判決からは両上肢に同じような症状(痛み、しびれ、脱力等)が出ていて、左側よりも右側の症状が強いように見えます。しかし、通院先の診断は終始一貫して右側のみに限定されています。 私の経験でも被害者が事故直後から両側の症状を訴えていたにもかかわらず、片側だけが診断されていた事案が数件あります。もちろん両側に症状が出ていると診断された事例の方が多いのですが、症状の重い側だけを取り出して診断する医師も少なくないようです。 片側だけを診断をした医師は、「事故により神経に損傷が生じたとすれば、両方同時ではなく一方のみのはずだ。従って、症状の弱い側は反射的な症状が出ているだけである。」との見方により、片側の症状だけを取り出して診断したとも考えられます。 これと似たような話で、上肢に強い痛みを訴えている場合に、相対的に弱い痛みや違和感を訴えている腰や下肢の症状が無視されていた事案も数件経験したことがあります。 事故に遭われた方の多くは事故直後には頚部や腰部だけではなく全身に痛みが出ていたと言われますが、多くの場合カルテには一番強く訴えた症状だけが記載され、その後のカルテはその症状を重視した記載になる傾向があります。
- 胸郭出口症候群や手根管症候群のように事故の場合にも両側に症状が出ることが多い疾患もあるので、両側に症状が出た場合には両側について診断した方が良いと思います。その方が事実に即しています。 症状固定のときに突如として両側の診断となると、追加された症状がいつ出てきたのかが問題になります。このような場合では、なぜかカルテの記載が非常に少ないことが多く、問題が複雑になります。
- 本件と類似の事案で、左側にも同様の症状が生じていた場合でも、左側の症状の裏づけが少ない場合には、訴訟戦略の上で左側の症状を主張しないとの判断もありえます。 即ち、「左側の症状を裏付ける証拠はわずかで、主治医も診断していないのだから裁判所も認めるはずがなく、主張しても逆に不利に働くだけである。」という考えです。事情によっては、この考えに至るのもやむを得ないと思います。 本件ではそのような事情から右側のみが主張されているように見えます。 被害者側は主治医の診断した右腕神経叢傷害により自賠責の認定した12級相当の後遺障害が残存すると主張しています。実際には両上肢に痛み、しびれ、脱力等の症状が出ていて、9級相当の後遺障害が残っているとも思えます。
-
- 被害者の最終的な症状の程度について
- 全体的な見方 事案をおおまかに眺めてみると、①被害者は事故により救急搬送され、①中心性脊髄損傷が疑われて11日間入院し、③右上肢の痛み、しびれ、脱力について早期に右腕神経叢損傷と診断をされ、④8か月後にいったん症状固定とされるも症状が改善せず通院を続け、⑤2年7か月後は筋電図検査で腕神経叢損傷が裏付けられたとの経過が存在します。 つまり、事故直後から一貫した症状の訴えがあり、それに対応した治療を受け、症状が続くため通院が長期に及び、精密検査でその診断が裏付けられています。従って、最終的に右上肢に痛み、しびれ、脱力(及び握力の低下)が残っていて、その程度は決して軽くはないことが十分に推測できます。この見方は一般人の常識的な考えにも合うと思います。 このような「全体的な見方」は物事を考える上で軸となるべきものです。細部での問題は随時この思考の軸(全体像)にフィードバックさせて整合性を検討する必要があります。
- 頭でっかちな見方 訴訟ではこの全体的な見方を軽視して、部分ごとに切り離して検討した結果、全く異なる結論に至ることが多く見られます。これまで検討してきた裁判例のほぼ全部は「全体的な見方」からすれば被害者の主張する症状が最終的に残っていると判断できる事案ですが、細分化した検討の結果、その結論に至っていないものがほとんどです。 毎回のように部分での検討で全体像が否定されてしまうのでは、世間一般からは「裁判官は頭でっかちだ(細かい理屈ばっかりで結果が伴わない)」と言われるかも知れません。要件事実論に証明責任を取り込んで事実認定をしてしまうと、この傾向に陥りやすくなります。
- 部分での検討で行なうべき判断 被害者の症状を否定した裁判例では、部分ごとに切り離した検討で部分ごとに越えるべき「証明のハードル」が設置され、そのハードルを越えていないとして全体像が否定される形のものが多く見られます。 細部での検討を厳密に行なうと正しい結論が導かれるようにも思えますが、実際には部分ごとの検討で「何が起きたのか」を検討せずに「証明責任をみたすほどの証拠があるのか」を検討している判決が少なくありません。細部にまで確実な証拠を求めると、事案を細分化すればするほど被害者に不利になります。 もちろん、証明責任の対象は主要事実のみですので、間接事実に証明責任を適用することは誤りですが(私は主要事実であっても事実認定に証明責任を取り込むことは誤りと考えますが)、この誤りに陥っているように見える裁判例を多く見かけます。 部分(間接事実)の検討においては「何が起きたのか」を検討して「~と推測できる」との結論を導くべきですが、「~であると認めるに足りる証拠はない」という法的に誤った書き方をしている判決を少なからず見かけます。「Aであると認めるに足りる証拠はない」との判断は、Aではないことを意味するわけではなく、推論の度合いが示されないため判断が空洞化しています。 部分での検討は最終的に認定する主要事実を導く際の推論の元になるものであるので、獲得した心証をそのまま記載するべきであると思います。証明責任に頼ると判断の空洞化(実質的心証の裏づけのない認定)を導きますが、この点への意識が低い判決を少なからず見かけます。
- 新様式判決の功罪 判決には旧様式判決と新様式判決があり、おおざっぱに言えば旧様式判決は当事者の主張を法的に細かく区分して記載したのちに、法的な序列に従って事実を認定していくものです。新様式判決は、当事者の主張の序列化は大まかな把握に留めて、争点の抽出とその判断に力点を置く書き方をするものです。 旧様式判決では当事者の主張を整理する段階で、事件記録を一通り検討する必要があるため、この段階で事案の概略をつかみ、争点に集中しすぎない全体のバランスの取れた判断になるとも言えます。 これに対して、新様式判決では事案の概略を述べた後にいきなり争点の検討を始めるため、上記の「全体的な見方」を意識することがないまま細部での判断が全体を決する流れに向かいやすくなります。 新様式判決で争点に対する検討が厚くなった点は良いと思うのですが、その検討の中身が「証明責任を満たすほどの証拠はあるか」という形で空洞化し、間接事実を証明責任で判断する誤りに陥っていると思われるものが少なくありません。このため、全体像の欠落が目立つものも少なからずあります。 全体像の欠落というのは、細部での検討で導かれる結論について「仮にAではないとすると、何が考えられるか」を事案の全体像に戻って検討する作業の欠落です。Aではないとした場合の代替案が存在しないにも関わらず、「Aであるとする確実な証拠はない」との思考で、細部の検討のみで結論を確定させることは誤りであると思います。
-
- 裁判に至る過程での選別
- この事案では地裁判決は12級と認定し、高裁判決は14級と認定しています。判断が分かれたのは、「この事故によって被害者の主張する後遺障害が生じるであろうか」という点の考え方に大きな影響を受けています(後述の点も影響していますが)。 事故は停止後に後退した車が被害者の乗っていた原付に衝突して、被害者の乗った原付が転んだというもので、おおまかな外形からは被害者が腕神経叢を損傷するほどの事故であるとは考えにくい状況があります。
- 地裁判決 地裁判決は「確かに、前示のとおり、本件事故によって生じた原告車両及び被告車両の損傷の程度は軽微であり、本件事故による衝撃の程度がそれほど大きなものではなかったことがうかがわれるものの」(41頁)として、事故の衝撃は大きなものではないとします。 しかし、「事故により傷害が生じるか否かは、衝撃を受ける者の個体差や衝突時の身体的条件、車両及び道路条件等によっても違いが生じ得るものであることからすると、上記各証拠をもって直ちに本件事故により原告に右腕神経叢損傷が発症したことを否定することはできない」とします。 即ち、地裁判決は被害者に腕神経叢損傷が生じる可能性があれば足りるとしています。私もこの考え方を支持します。
- 高裁判決 高裁判決は、①原付が転倒して被害者がしりもちをついたとの事故状況、②被害者の体に強い衝撃を与えるような衝突ではなかったこと、③被害者の右腕神経叢に牽引力が働く状況ではないことから、被害者の主張する腕神経叢損傷が生じるような事故ではなかったとします(30頁)。 私も同様の事故に遭った方が100人いた場合に原告と同様の怪我(障害)を生じる方は1人ほどであると思います。しかし、裁判に訴え出るのはまさにその1人です。後遺障害がない人は裁判に至る過程の選別で除外されます。 なお、地裁判決は上記のほかに、被害者が転倒した際に頭部が傍らのフェンスに衝突したことを認定しています(40頁)が、私はこの事情が不可欠とは考えません。
- 裁判に至る過程での選別 むち打ち損傷を検討した有名な工学実験では時速10キロ以下の衝突によっても一部の人には頚部痛が生じることが確認されています(『検証むち打ち損傷』)。有志で実験に参加された方で衝撃が来ることが抽象的には予見で来ていた方であってもこの結果なのです。時速10キロで追突された衝撃でも頚部は最大可動域まで屈曲・伸展しますが、衝撃を感知して頚部の筋の収縮が始まるのはその後のことであるので、この結果はある意味当然と言えます。 例えば、時速15キロで追突された人が100人いるとして、そのうち40人は何らかの首の痛みを訴え、うち10人は首の痛みが持続し、うち2人は頑固な首の痛みになると仮定します。後遺障害があるとして訴訟に訴え出るのは最後の2人です。この「裁判に至る過程での選別」という思考は、およそ裁判官であるならば備えていなければいけません。 これに対して、訴訟の場において、「その事故で頑固な首の痛みが残る可能性は2%であるから、その被害者の主張する障害が生じた可能性は小さい。」と考えることは誤りです。後遺障害がないのに訴訟に訴え出るという特殊な想定で、原則となる思考を否定することは正しくありません。
- 他の原因が考えられないこと 地裁判決が述べるように、事故態様は被害者がその怪我をする可能性が認められれば足り、「被害者の主張するような障害が生じるほどの事故」である必要はありません。 それ以前の問題として、高裁判決はこれが因果関係の問題であるという認識をほとんど持っていないようにも見受けられます。高裁判決は、「被害者の主張するような障害が生じるほどの事故」ではなかったとして、この部分だけで結論を決めているように見えます。 しかし、事故の程度としてはその傷病を生じさせる可能性が認められれば足ります。その可能性すら否定できるのはよほど特殊な事情が必要であると思います。 従って、因果関係を検討する場合には、現実に被害者に生じている後遺障害の有無・程度を確定して、事故以外の原因によりその結果が生じたと考えられるかとの検討が必要です。事故による衝撃が不明であっても現にその怪我をしていることが明らかであって、事故以外の原因が考えられなければ事故との因果関係が認められます。ルンバール事件最高裁判決はこの趣旨を述べています。
-
- 胸郭出口症候群の検討
- 交通事故のあとに上肢の痛み、しびれ、脱力(及び握力の低下)を訴える事案は多く、この症状は頚椎の損傷に由来することもあれば、上肢の神経の損傷に由来することもあります。 上肢の神経の損傷は、例えば衝突時にハンドルを握っていた手が牽引されたことによる一次的な損傷もあれば、頚部から肩部にかけての筋や軟部組織の損傷に由来する二次的なものであることもあります。 衝突の衝撃が伝わると頚部は最大可動域まで一気に振られますが、人体が衝撃を感知して筋を緊張させ始めるのはこれより遅れます。頚部が急に大きく動かされると、多くの場合に頭部を支える各種の筋や軟部組織に炎症や断裂が生じます。むち打ち損傷と呼ばれるものです。痛みや張りは頚部から肩甲部・肩部にまで広く及びます。頚部の動きに関連する筋や軟部組織は広範囲に及ぶからです。 このときに損傷を受けた筋や軟部組織が神経を圧迫することがあり、それが胸郭出口部などの狭い部位で持続的に生じると神経損傷に至ります。これが事故による胸郭出口症候群(二次性TOS)の発生原因です。アメリカでは胸郭出口症候群の大半が事故による二次性TOSであると報告されています。 胸郭出口症候群はさまざまな要因から生じる症状の寄せ集め(症候群)ですが、基本的には上肢の痛み、しびれ、脱力が主たる症状です。医学的には胸郭出口症候群は両側に症状が出る事案が多いとされ、私の経験でもほとんどの方が両側に症状を訴えていました。
- 本件では、事故後に被害者が主張していた症状は、胸郭出口症候群の主たる症状そのものですので、胸郭出口症候群との鑑別診断が必要となります。胸郭出口症候群の診断のためには、徒手テストのほか、血管造影、神経造影などの検査が行なわれることが多いのですが、本件では筋電図検査のみしか行なわれていません。 胸郭出口症候群であるとすれば、治療内容も変わってきます。第一肋骨切除術などの手術(あまり治療成績は良くないようですが)も検討対象になります。
-
- 「問題のある医学的知見」について
- ほぼ全ての傷病について、加害者側が被害者の症状や医師の診断を根底から否定する医学意見書を出すことは多く見られます。しかし、主治医の診断ミス(医療過誤)や被害者の詐病は少数に過ぎないと考えられます。 また、訴訟では対立する鑑定や医学意見が根本から異なる内容を述べていることは少なくありません。双方が誠実に意見を述べたのであれば、ほとんどの事案で似通った意見になるはずです。この場合、一方の医学意見は意図的に誤った内容を述べていると考えるのが自然であると思います。訴訟においては、「問題のある医学的知見」が多く見られます。
- 「問題のある医学的知見」に対しては合理的な疑問を述べることができますが、その多くは絶対に誤りであると断定することは困難です。 医学は自然科学の一部であって基本的に経験主義により記述され、医学書には経験により確認できる事実が記載されています。経験により確認できた事実からは、経験により確認できないことが誤りであると断言することはできません。 「問題のある医学的知見」の大半は何らかの前提からの強引な推論であり、その推論には医学的に明確な根拠はありません。しかし、それが誤りであると断定することは困難です。いまだ確認されていない推論の当否を断言することはできないからです。 「問題のある医学的知見」の特徴は、過度の断定にあります。それは全称命題(全てのPはQである)によることが通常です。しかし、医学では全称命題が述べられることはまずありません。経験により確認できないことの断言になるからです。
 地裁と高裁で評価の分かれた腕神経叢損傷(24.7.26)
地裁と高裁で評価の分かれた腕神経叢損傷(24.7.26)

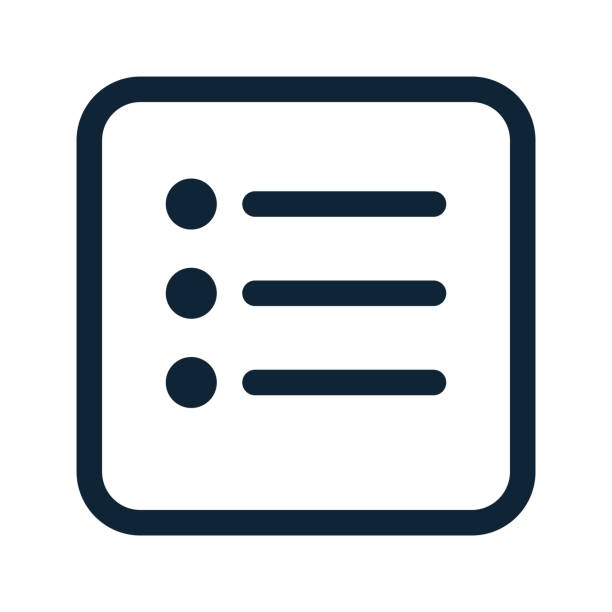 目次へ
目次へ